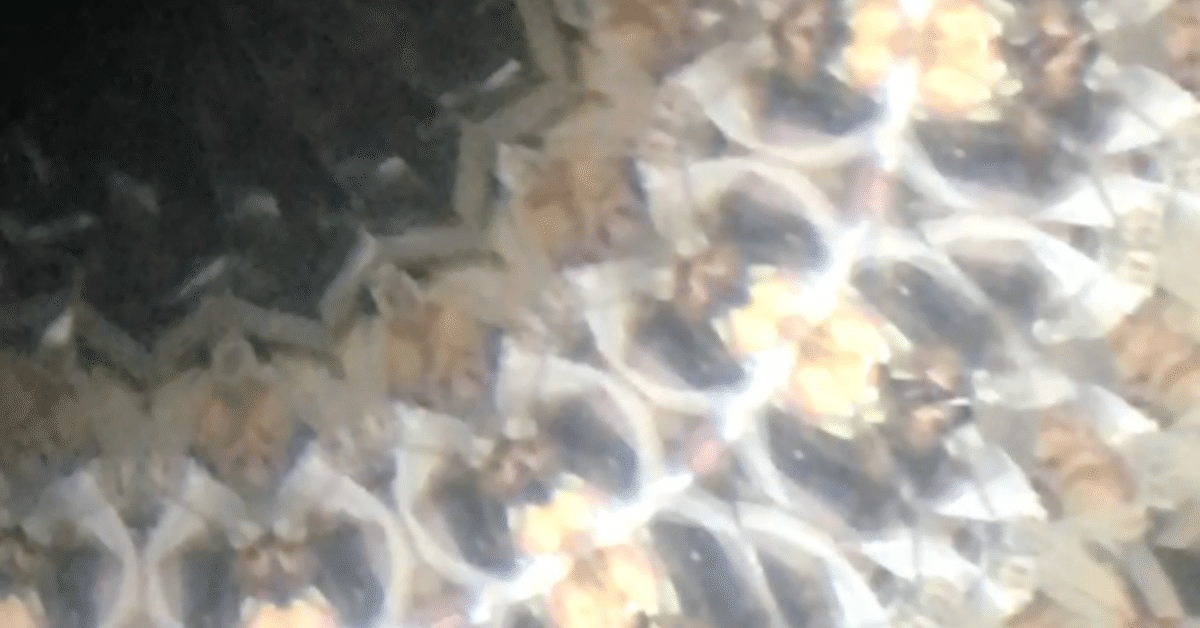
はじまりのはなし…贖罪⑭
霰が霙に変わった…小窓の格子に溜まった氷の粒も、直に溶けるだろう。
不本意ではあるが、霙とは霰や雹と違って、雪に分類される様で…今夜雪になるという天気予報は、雪らしい雪が降っていないのにも関わらず、外れたという事にはならないらしい。
これを初雪と呼ぶには淋し過ぎる…
彼女と一緒に、今年は初雪を見ようと約束していたが…こんな霙ならば、一緒に眺める事が出来なくても惜しくはない。
今は彼女が夢中になって語っている…はじまりの話を一言一句でも、聞き逃してしまう事の方が…よっぽど惜しいと思える。
「愛は私を癒し、愛は私に力を与えました。愛は私を解き放ち、愛は私を満たしました。愛は私を楽しませ、愛は私に勇気をくれました。愛は希望であり…愛は答えであり…愛は私の居場所となりました」
彼女のお母さんには、てんかんの持病があった…基本的に症状は軽度で、若い頃に2、3度倒れた事があるらしいが、彼女の目の前で気を失った事は勿論…発作を起こした事も一度も無かったらしい…
それでも、車の運転や激しい運動は控えていると聞いていたし、薬も毎日ちゃんと服用していたみたいで…彼女も余り心配していないと言っていた。
それが突然こんなタイミングで…彼女が妊娠を伝えようとしていた…そんな時に限って、起こって欲しくないという事は起こってしまうのだろうか?
彼女が病院に到着した時には、既に集中治療室でお母さんの治療が始まっていた。てんかん発作だけではなく、倒れた時に頭を強く打っており…出血は少なかったようだが、意識が戻らない状態が続いていたらしい…
しかし、彼女のお母さんは…彼女が現れると、まるでそれに気がついたかのように意識を取り戻し、何度も何度もお母さんと呼ぶ彼女にごめんね…ごめんねと言って、彼女の手をギュッと握り…彼女への人生最後となるメッセージを、その命の灯火が消えるまで...残った僅かな力を振り絞って伝えたらしい。
僕が到着した頃にはもう…母親の最後を看取った彼女は抜け殻のようになっていた。
そんな彼女の隣で、彼女のお母さんの上司らしき男の人が…自分の所為だと…自分が悪かったと…自分の不注意だったと頭を何度も下げていた。
僕は大人の…それも自分の父親と同じくらいの男の人が、此処まで必死に…涙ながらに謝っている姿を初めて見た。
僕はその男性に圧倒されて、彼女に気の利いた言葉のひとつも掛ける事が出来なかった。
放心状態のままの彼女を、助手席に乗せて帰る途中、突然彼女が走行中の車のドアを開け、強引に飛び降りようとした...
幸い深夜で後続車はなかったが、外は土砂降りで、冷たい空気と一緒に大粒の雨が車内に流れ込んできた。僕は彼女の衣服の袖を引っ張りながら、速度を落として路肩に停車した。それでも彼女は僕の手を振り払い、ガードレールの脇に置かれた何かを指差して、あれを見て、あれを見てと繰り返す。
彼女が指差す先を目掛けてヘッドライトを上向きにしたが、雨が強くて良く見えない。僕はサイドブレーキを強く引き、彼女を掴みながら車を這い出て確認すると、それは事故現場に置かれた献花だった。そして、彼女が無理矢理...僕を振り切って、ガードレールにしがみ付きながら声高に叫び出した。
「これが証拠よ...ここでも誰かが車に轢かれて死んだのよ。これがね...神様なんて居ない証拠なのよ...私は神様なんて...神様が居るだなんて一生信じない...信じられない。もしも、それでも居るって言うんだったら...絶対に、絶対に私の事が嫌いなのよ...お母さんが死んだのも...お父さんが死んだのも...全部、私が嫌いだからよ」
彼女は泣き崩れ...嗚咽しながらボソボソと小さな声でお母さんに会いたい...お母さんに会いたいと連呼していた。
僕は発狂してしまった彼女に...初めて見る彼女の姿に戸惑いながらも、急いで車の後部座席に置いてあった傘を取りに戻り、自分が着ていたズブ濡れの上着を彼女の肩に掛け、戻ろう...戻ろうと何度も言った。どれだけ大きな声で怒鳴っても、彼女には届かなかった。
気が付くと...首元から胸の辺りを苦しそうに掻き毟っていた彼女の左手が、脇腹の辺りを摩っていた...ふと彼女の膝下に目を遣ると白のロングスカートが赤く染まっている。慌てて訳も分からず救急車を呼び、パニックになりながら...心の中で幾度となく、彼女が信じないと言った神様に...僕は助けを求めていた。
神様に届いたのかは分からないが、僕達二人には容赦なく雨が降り続き、救急車が到着した頃には、既に子宮内容物が全て身体の外に出てしまっていた。その後、産婦人科の先生が、早期流産の原因は殆どが染色体異常だと説明してくれたのだが、彼女は雨で身体を冷やした事と、母親の死による精神的なショックが原因であると思い込み、誰の言葉にも耳を傾けず、自分の事を責め続けた。
そんな失意の中彼女には追い討ちを掛けるように、その後の検査で子宮頸癌が見つかり...子宮を全摘出する手術をする事となって、彼女は母親を亡くして間もなく...母親になれない身体になってしまった。
「愛が全てを救ってくれると思いました。しかし、愛は残念ながら万能ではございませんでした。愛には欠点があったのです。
愛は生まれた時から悲しみと同居しており、悲しみから離れる事が出来ず、常に表と裏の関係であり続けました。愛が深ければ深い程、悲しみも深くなり...愛が強ければ強い程悲しみも強くなってしまいました。人々はその悲しみを放棄したくても、同時に愛を手放す事を拒み、醜く縋り付いてしまう様になったのです。
全ては私の責任です。全ては私の罪なのです。私はこの罪を償いたい。自ら罰を受け入れたい。そう願う様になりました。どう償えば良いのか...悲しみを消し去る為の方法はあるのか...この罪を消し去る為の名案はないかと考えた末に...私は一つの策へと辿り着いたのです」
「その...策とは?」
「記憶を消去する...忘れるという事を思い付いたのです。それは、革新的な結果を生みました。悲劇的な思い出も、抱え切れない問題も...いずれ訪れる〝死〟への恐怖も、全てを忘れてしまえば...何も知らない純真無垢な幼子に戻る事が出来るのです。
ただ、それは私の託した宿題も目的も、愛も喜びも、万物の親である筈の私の事さえも...全て忘れ去るという事でした。
忘れ去られてしまうという事は、寂しい事ではありますが、それで皆が苦しみから救われるのであれば、これはもう自業自得だと...忘却こそが私の受けるべき罰であると...
私も私自身の事を忘れて...忘れて...忘れて
忘れ...忘れ...忘れ...」
雨音はどんな曲にも寄り添う伴奏の様に思える。人によってはショパンの調べであると言ったりするが、それは人それぞれに好みがあり、人それぞれに思い出があるのだろう。
彼女はいつも雨が降ると...洗い物や掃除などの家事をこなしながら、バッハの『G線上のアリア』を聴いていた。クラシック音楽が好きという訳ではないし、それ以外の曲を聴いている所は見た事がないが、彼女のお母さんの習慣だったらしく、彼女はそれを大事に受け継いだみたいだった。
「なんでこの曲好きなのって聞くとね...お母さんが、顔を真っ赤にして黙っちゃうの。いつもは余計な事までベラベラ喋るのに...でもまぁ、どうやらお父さんがプロポーズをした時に、レストランの中で流れていた思い出の曲らしくて...折角のハレの日に、生憎のお天気の中、二人で聴いたんだろうね...なんか私の両親らしいでしょ。
未だにどんなプロポーズだったかは教えてくれないけど、嬉しかったんだろうなぁ~...雨が降ると必ずこの曲を聴いてたから...雨が降る度に憂鬱な気持ちになるんじゃなくて、幸せな気持ちになってたんだと思うと、なんか羨ましいよ...それにね、お父さんも幸せだと思うの、だって雨が降る度にお母さんに思い出して貰って...それってお母さんの中で、お父さんはずっと生きてるって事だと思うし...」
「じゃあ、僕も雨の日にプロポーズしようかな...」
「やめてよ...雨が降る度にそわそわしちゃう...」
僕はなぜか...一本の弦で演奏する曲だからなのか?
彼女と一緒に『G線上のアリア』を聴く度に、イギリスのワッツという画家の『希望』という絵画を思い出した。小さな球体の上で、行き場もなく...目隠しをした女性が、竪琴に残る一本の弦を爪弾いている。それは正に、絶望の中に残る一縷の希望であると言えるだろう...
彼女は今...壊れたおしゃべり人形の様に同じ言葉を繰り返し始めて二十分間は経過している。声は痛々しく掠れ...時々息を詰まらせている。彼女を止めたくても、機械のように停止のスイッチはないし、無闇に中断させようとすれば、発作を起こす可能性も充分に考えられる。
僕のこんな一つの閃きが...些細な思い付きが、一縷の希望になるのかどうかは分からないが...彼女の耳元にそっと携帯電話の小さなスピーカーを寄せて、ダウンロードしてあった『G線上のアリア』を再生し聞かせる事にした。
得体の知れない何かに取り憑かれた様な...そんな彼女の中に、まだお母さんが生きていると信じて...
「忘れました...忘れました...忘れました...」
「お母さんの最後の言葉を覚えてる?」
「忘れました...忘れてしまいました...忘れて...忘れ...わ...す...」
彼女は小刻みに震えていた唇を閉じて、鼻からスーッと一息吐き、目尻から流れた一筋の涙は耳の穴へと吸い込まれていった。
携帯電話の僅かな明かりに照らされた彼女の顔には、漸く安堵の色が蘇っている。僕は薄明かりの中、一人掛けソファーの上に置いた大学ノートを手に取り、真っ新なままのページを閉じて、鞄へと戻し、静かに病室を後にした。
どうしてだろう?
なぜだか、今日は...守衛さんにも怒られない気がする。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
