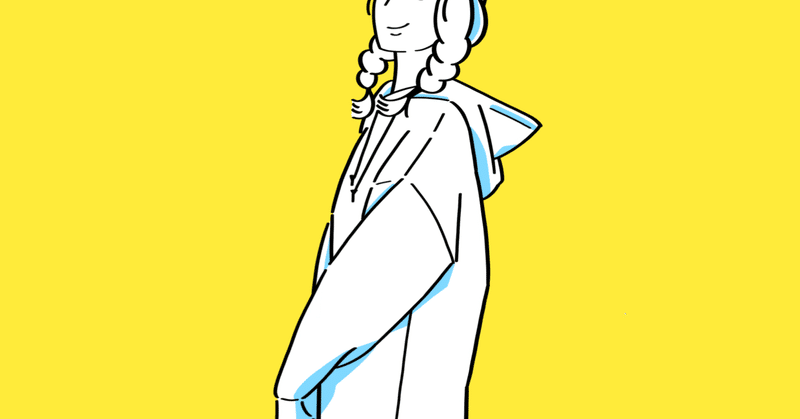
「きっと良い奥さんになるね」と言ってしまったあの頃の私へ
これは私自身のジェンダーについての、取りかえしのつかない失敗談のはなし。
*
私はこれまでいくつかの、多くはないにせよいくつかの性差による偏見や役割を押しつけられてきた。
学生のころ、運転免許を取ることにした私に、母はこう言った。「男の子だからマニュアルを取らないとね」。私はなにも疑問を抱くことなく、ドライビングスクールの申込書の欄に、「AT(オートマ)車」ではなく「MT(マニュアル)車」にチェックをいれていた。ちなみに今日、免許を取って長い年月も経つが、スクールを卒業してから一度もマニュアル車に乗ったことはない。
初めてのバイト先はレストランだった。子どものころから通っていた地元のステーキレストラン。そこではたらくホールスタッフに憧れていたのだ。
面接では店長に「ホールスタッフ希望です」と伝えた。しかし店長は「今キッチンは人手不足だからキッチンに入ってほしい」と。当時、私は包丁さえろくに握ったことがなかった。すると店長は「大丈夫、誰でもすぐに出来るようになるから」と言った。そうして私はキッチンで修行を積むことになったのだ。
レストランのキッチンは完全なる男社会だった。なかなか血の気が多い人も多く、取っ組みあいのような喧嘩も起こった。私は店長に何度も「ホールに移動したい」とお願いしたが、取りあってもらえなかった。しかし、新しく入ってきた未経験の学生(女性)は、ホールスタッフとして採用が決まっていた。
「男/女だから◯◯」「男/女なのに◯◯」。そんなあまりにありふれたあたりまえの言葉を浴びながら、私はひっそり息をしてきた。そして社会はそのあたりまえを疑う余地すらくれなかったのだ。まるでスポーツのルールのように、そのルールに則って試合することが前提だった。従わなければ、反則やペナルティーを課される。そんな“現実”を何度も突きつけられ、私はすこしずつ、自分でも気づかないうちに、けれど着実に擦り減っていた。
*
今でこそ、私はそのルールに反旗を翻すことができる。性差による差別や役割の押しつけ。それを昨今では『ジェンダー・バイアス』と呼ぶそうだ。その言葉を知ったとき、ああそうだったのかと、腹落ちしたような気がした。なるほど、どおりでこれまで息をするのが苦しいときがあったんだ、と。そこには納得感があり、絶望があり、静寂があった。一種の安堵感と言ってもいいかもしれない。長年苦しんできた“病名”が判明して、ふと肩のちからが抜けた患者が抱くような。
私は彼らに──これまで私にジェンダー・バイアスを押しつけてきた母やバイト先の店長、その他の人々に──、反撃の狼煙をあげるつもりはさらさらない。というより、ジェンダー・バイアスという言葉を知ったとき、私にはそんなことをする資格なんて、どこにもないのだとわかったのだ。
なぜなら私にも、決定的なジェンダー・バイアスの失敗があるからだ。
/////
私はいやなこと、辛いことがあっても、海外という逃げ道を知っていた。『ジェンダー・バイアス』を知らなかった数年前の私でも、その陰鬱な気分を言語化できないながらに、どこか日本での生活は息苦しく感じられ、海外にひとり旅に行くことがあった。外の空気を吸うと、私はどこまでも自由になれたのだ。
そんな日々のなか、欧州を旅していたときだった。東欧にむけて歩みを進め、オーストリア・ウィーンに来ていた。巨匠クリムトやシーレを生んだ都の文化に惹かれていたのだ。

私はゲストハウスに宿泊した。そこで同じく旅をしていた、あるドイツ人女性のことを今でも鮮明に思い出す。
「なにを作っているの?」
私はゲストハウスのキッチンで料理を作っていた彼女に声をかけた。バジェットトラベラー(低予算の旅行者)が集まるゲストハウスではたいてい共同のキッチンがある。そこで彼女はもくもくと湯気をたたせて料理をしていた。
「これはアイントプフ(農夫のスープ)よ。日本にはない?」
「初めて見た。めちゃくちゃおいしそう!」
「どう、食べてみる?」
実際にその料理はとてもおいしそうだったし、食べさせてもらったら味も気にいった。ソーセージやジャガイモ、レンズ豆などを入れたドイツ定番の家庭料理。純粋に感動したし、彼女の料理の腕前を、気のきいた言葉で褒めたいと思った。そして私はこう言った。
「あなたはきっと良い奥さんになるね」
そのときのことは今でもよく覚えている。それまでずっと和気あいあいと話をしていたが、彼女の表情が一瞬だけ、曇ったのだ。
「あれ、どうしたの?」と問う私に、彼女は一度なにかを言おうとしたが、言葉を呑みこんだのがわかった。怒り、そして諦め。そんな感情が渦巻いていたように見えた。そして表情を切りかえて、彼女はこう説明する。
「ううん、なんでもない。あなたはアジア人だし、大丈夫。でも、もしあなたがドイツ人だったら私はI’m gonna kill you(すぐにでも殺すわ)」
そう言って冗談めいたニュアンスで彼女は微笑んだのだ。「え、ごめんどういうこと??」と私はとっさに尋ねたが、彼女は「ううんなんでもない」と優しく微笑んだ。
/////
それから何年も月日が経ち、今なら私にもその彼女の微笑みの理由が、すこしはわかるような気がする。なにを言っても仕方ない。あなたにはあなたのあたりまえが存在するし、そのルールに則っている以上、私にはなにも言えないの。だからI'm gonna kill you、なんちゃって。
「きっと良い奥さんになるね」。その言葉は当初、だれも傷つける予定のなかった、咄嗟に出てきた「褒め言葉」だった。無垢な言葉として飛び出てきたはずだし、瞬時に彼女もわかってくれたようだった。
それから何年も経ち、私も当時よりは大人になれたのかなと思うし、思いたい。それでも当時のことを思うと、私には性別の役割を誰かに押しつけるような発言をする人のことを糾弾して、はたまた社会的制裁を与えようとSNSに投稿して炎上を狙うなんてことをする資格はない。私だってそうだったし、そう思っている現在の私にだって、きっと知らないところで心ない発言をして、もしかしたらいまこの瞬間も、だれかのことを傷つけてしまっているかもしれない。
だから私は、私に対してこう言ってやりたい。私よ、知らないうちにあなたはだれかを「傷つけているかもしれない」し、「自分だって加害者になりうる」。言葉はすぐにカタチを変えて凶器にだってなる可能性を、はらんでいるのだ。
これって“ちょっと”偏見かも? 男らしく、女らしく生きなくちゃいけない? 意識を”ちょっと”ずらしてみるだけで、周りのひとも、もしかしたら自分自身も、ずいぶん救われることがある。救われてはじめて、あぁこんなに重たい荷物を背負っていたんだと、はじめて気づいたりするのだ。
きっとその“ちょっと”が自分を変えてくれる。社会はなかなか変わらなくても、いまちかくにいるだれかの世界を、はたまた自分自身の世界を、180度変えることができるかもしれない。そう願って。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
