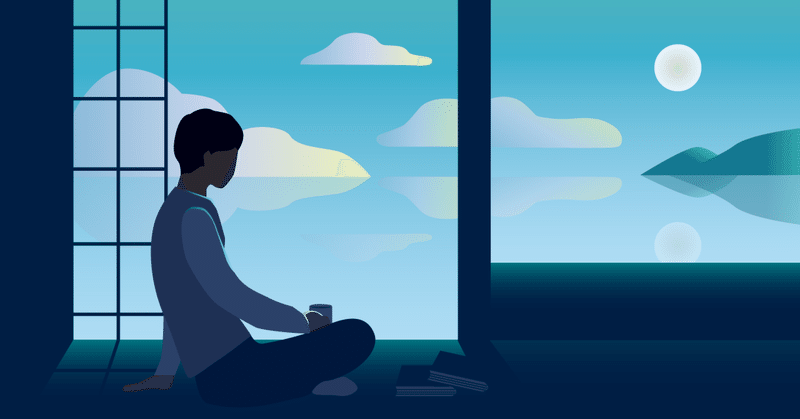
《第2ステージ》国と家庭と教育と-1年かけて考えたこと-
こんにちは!タノ🦒です。
秩父の自然とムーミンパークの北欧感に癒されてきました。
#スナフキンってかっこいいですよね

今回は、
この1年のこと、最近のこと、
少し先のこと、将来のことについて、
徒然に書いていきたいと思います。
教育者・社会人としての第2ステージの話に
なるかと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.ステージが変わった
1年少し前は、
小学校の先生として現場で働いていました。
コロナ等の大変なこともありましたが、
先生として働くことはとても楽しかったです。
ただ、コロナ+GIGAスクールを経て、
それまで何となく感じていた
「学校システムの違和感」がはっきりし、
一度退職するという決断をしました。
長く書きませんが、その違和感は、
「管理型」と「先生達の自己犠牲で成立する」に集約されます。
学ぶ子供も、教える大人も、
どちらも自分を削りながら過ごす部分が必ずあります。
誰が悪いというわけではなく、
明治以前の日本や諸外国を比べてみると、
見えてくるものがあります。
と、いっても、
在職中にはっきりと認識していたわけではなく、
退職してから、勉強し、
NPOや海外の先生、団体、民間の方々と話す中で分かったことでした。
また、「日本教育の次の未来が始まっている」と確信したのは、
5月に行われた教育総合展でした。
今年もあります。
最大規模のイベントで、国内の教育企業が集結します。
そこで見た技術や考え方は、描いていた多くのことを実現するものでした。
「今、日本は新しい教育を描くための途上で、
ここから始まっていくんだ」と感じました。
一方で、根本の問題も大きいと感じました。
それは、明治維新と戦後の政策によって
「150年間かけて築かれてきた教育の常識」です。
江戸・大正時代の
元々の日本の教育スタイルと聞かれた時、
思い浮かべるのは、寺子屋や藩校のようなものではないでしょうか?
または、松下村塾のような私塾もあったかしれません。
あの時代の教育は「地域密着」の教育です。
そのため、商売や経済と深く関わっていました。
「和算」と呼ばれる日本独自の算数は今から見てもレベルが高いですし、
読み書き、儒教や論語などの生き方も説かれていました。
分かりやすい例を一つ挙げると、
算数の計算では、
俵(たわら)を元に蔵の米の量をはかったりしていました。
また、面白い話で、
町民の中で算数問題を出し合う文化があり、
優れたものは神社に奉納されました。
そんな教育が変わった原因は、明治維新以降。
国力を高めるために、一律に労働力が必要になりました。
その結果、基礎学力や時間、集団規律を教える方向に進みました。
当時は戦争色が強かったようですが、
今でも軍隊が基本になった文化は受け継がれています。
※それが必ずしも悪いというわけではないです
※合理的なのも大切
そして、現在。
公教育による歪みや対応できない部分も出てきました。
それは、不登校問題にも現れています。
でも、日本の教師や子どもの学力は世界的にもトップレベルです。
そのあたりは、この本が教えてくれます。
色々な俗説を数字で検証しています。
日本は「国家レベルで教育を抜本的に変えた」経験が少ない。
明治維新・戦後以降ありません。
どの時代も「戦争」によって必要に迫られて変えました。
もう戦争は起こしたくない。
違った方法で変える必要があります。
それは何か?
制度改革とテクノロジーです。
少し、その背景を話します。
元文部科学大臣の方に数ヶ月前にお会いしまいた。
実際問題、
「文部科学省が主導に立って国を変えていく」
ことは難しいと、おっしゃっておりました。
その方だけでなく、経産省・内閣府・実業家、
みなさん口を揃えていいます。
「文部科学省では国は変わらない」
なぜか、
発言力と経済力がないからです。
国政策は、内閣府が進めます。
内閣府のバックアップや後押しがあるかないかで、
その省庁の力は変わります。
もしくは、強く推進する力や改革のビジョンです。
文部科学省には現状、そのあたりがないと言います。
現場の教師目線でもそれは思います。
となると、個人が頑張るか?
個人の頑張りは大切ですが、
社会の波や全体には勝てません。
よく聞く言葉ですが、
「あの人だからできるんだよね」という言葉はよく聞きます。
次の未来の教育者が戦っているのは、
個人ではなく、
「150年かけて固まった文化や伝統、常識」です。
個人が実践をする、本を出す、発信するだけでは、
その人が力尽きた時に終わってしまいます。
受け継ぐ人がいて、そして国を変えていく必要があります。
国はどうしたら変わるでしょうか?
それが「制度を変える」ことです。
優れた取り組みが「力尽きて終わる」なら、
力尽きないように支援する制度があればいい。
もしくは、優れた取り組みをモデルケースとして広めるケースがあればいいということになります。
口で言うのは簡単ですが、これが上手くいかない原因は、
「教育業界に事業のノウハウが不足しているから」です。
先生達は優秀です。
でも、事業計画を作れる人は1%もいないはずです。
KPI。KGI。収支報告。経理。労務。集客。広報。損益分岐点。
事業には自走のための考えが必要ですが、
そこと教育の噛み合わせが非常に難しいです。
理由の1つは、公教育の風潮です。
「学校でお金のことを教えるなんてもってのほか」
「儲けよりも個性や道徳心を大切にしよう」
というような風潮です。
結果として、よく分からない曖昧なものを追うことになり、
数値でのPDCAが回せない点があります。
また、塾のように進めようとしても、
「偏差値や点数よりも大切なものがある」
「学校では社会的なスキルや集団生活を学ぶ」
というような反対意見が出るかと思います。
受験=学校ではよくないですから、
この点についてはよく分かります。
では、どうしたらよいのか?
それは、
「最上位目標として教育理念を言語化して示す」
「その教育理念を達成のための数値目標を掲げる」
の2つです。
新しい教育事業を公教育としてスタートさせるなら、
※1条校、オルタナティブのように
教育理念が必要です。
もちろん、
国際バカロレア(IB)、モンテッソーリのように、
諸外国の教育を輸入するのも良いと思います。
ただ、一点必要なことは、
国際、日本、地域、日本人の特性の
4点それぞれの視野が必要な点です。
根本でいうと、教育方法はなんだって良いと思います。
※極端ですが
必要なのは、
「社会に出て自分らしく生きていけるか」です。
例えば、新しい学校をモデルケースとして作る。
その時に、
「社会に出て自分らしく生きていける子の育成」を掲げる。
そのための手段は何でも良いです。
ですが、ここで重要なのが、
「数値目標」を示し、分析ができることです。
この数値目標がないことが教育政策では多いです。
地域活性のための
文部科学省の政策で300億円投入しているものがありますが、
そのサイトに成果事例や報告のデータはありませんでした。
「予算を確保して、申請され、交付する」だけということです。
もしかしたら、報告会はあったのかもしれません。
ですが、どこの自治体がどんな取り組みをしたか、
後世に残ることはありません。
ですが、教育事業を数値で語るのは難しいですよね。
有名大学への進学率?倍率?そうなってしまうと、
世の中は変わりません。
そうではなく、
「入学希望者数」「不登校の数」「指標を定めたアンケート実施」
事業として行う場合は、その事業自体に価値がありますから、
「講演会を行う」「助成金だけでなく支援金を集める」
「賛同してくれる企業の数」
などが考えられます。
興味深い例として、
岐阜県草潤中学校の事例はとても先駆的です。
全国21校の不登校特例校です。
https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/904/annai.pdf
このような学校が増え、スタンダードになれば、
日本中の公立学校が少しずつさらに良くなる未来があると思います。
この学校の資料で面白いのは、
オンラインでの参加率が数字になっているところです。
「学校に行く=出席」の考え方が変わります。
学校に行くことが目的ではなく、
「社会に出た時に自分らしく生きること」が目標です。
それは「1人きりで生きる」ことではありません。
自分の意思で決めて、できないことは頼り、
できることを増やして誰かのために立つことです。
その誰かの役に立ったことの対価が「お金」です。
どんな方法でも誰かの役に立って
「お金」を稼ぐことができれば、生きていけます。
それを可能にするのが、もう1つの国を変える方法。
テクノロジーです。
漫画の好きな言葉に、
「科学は全ての者を平等にする」という言葉あります。

今の時代家にいても仕事はできます。
それだけでなく、個人の力が企業を凌駕することもあります。
知り合いにフリーランスのチームがありますが、
1人1人が際立った能力を備え、集まっている集合体です。
何でもできる満遍なくジェネラリストを育てるのが旧来の価値観なら、
次の未来は特化した力を持ったスペシャリストの時代になります。
最も、最低限のスキルやコミュニケーションが必要な部分はありますが、
マストではありません。
それはテクノロジーがあるからです。
SNSの文面でもコミュニケーションはとれますし、
ツールを使えばデザイン、経理計算などもできます。
私はこの1年で、
ホームページ、デザイン、イラスト、ラジオ配信
確定申告、動画編集、SNS発信、オンライン授業等を
1人行いました。
あらゆることは、1人でもできる時代です。
※その上でチームは重要
制度を変えるには前例やモデルケースがいります。
それにはテクノロジーの力が生きてきます。
その時に数字で語ることで、
制度が再現性をもって広がっていきます。
私が今参加している
教育立国推進協議会の活動が、
そこに寄与する部分かと思います。
私はここで第二分科会の書記を担っています。
2022年5月11日には、分科会の幹事の方が、
国会に資料/政策を提言します。
それがどのように国制度に影響するか
注意深く見ていきたいです。
この教育立国推進協議会は、
180名の国会議員や百数十名の民間事業家が集まり、
各分科会ごとに話し合い、提言を行います。
私の分科会も1月から十数回話し合いをしてきました。
1回につき2時間程度。
資料作りは深夜までかかることもありました。
元文部科学大臣・元文部科学副大臣が発起人と幹事長でありながら、
超党派という異色の分科会のため、
文部科学省以上に国全体に対する影響力が期待できます。
1人1人への支援という観点も、
国全体の抜本的な改革という観点からも考えています。
ちなみに、なぜ私がここに参加できたのは、
所属する保育園の理事長先生とのつながりです。
私一人の力では決してありません。
けれど、とても嬉しかったことがあります。
日本が世界に誇るフェラーリのデザイナーである、
KEN OKUYAMAさんから、
「我が社にも1人は欲しい人材」と言っていただいたこと。
「素晴らしい記録だね。本当に助かるよ」
と幹事の大久保さんに言っていただいたこと。
他にも、多くの方からお言葉をいただきました。
私がもつ「記録の力」「見える化の力」や
「教育における知識や勉強」は、
国のトップレベルの分科会でも通用しました。
スキルは身につきました。
国家レベルの話し合いに参加することもできました。
そこで、次の話に移ります。
2.これからのビジョン
教育者を志してから20年。
教育の仕事をしてからは12年。
本気で「日本の教育システムを抜本から変えたい」と
思ってからの活動は2年目。
ここまでを振り返ると、
予想以上の成果が得られました。
でも、私は一言で言うと、
「運が良かった」に尽きます。
多くの人に運よく助けてもらってきました。
それはきっと、
「何もない中で手探りで頑張っている人を応援しよう」
と思ってくださった方々のおかげです。
私は、多くの方々のおかげで、
「戦いの土俵」にあげてもらいました。
戦い方も戦い方も分からない私に、
武器や戦略、土俵まで案内をしてくださいました。
けれど、そろそろその「応援ブースト」は終わりです。
その理由の一端が「家族」のことです。
ステージの変化は、仕事だけでなく、家庭もそうです。
自分一人の家庭ではなく、親族も増えました。
子供が生まれることも視野に入れる必要があります。
私は以前のように、
24時間を教育活動に費やすことは難しいです。
私は大体いつも教育について考えているのですが、
一般的には普通ではないようです。
でも変人には変人が集まる法則で、
私の周りにはそんな人がたくさんいます。
「24時間無我夢中に活動を進めることで応援してもらう」
という自分から、
「長期的な計画を持ち、得た武器を最大限使う」
という自分に切り替えないといけません。
それは、何ももたない私を応援してくださった方々に対しての
期待に応えるという意味でもあります。
1人での戦いでは限界があります。
私に必要なことは、やはり、
「個人の能力を最大化すること」
「仲間を作り進んでいくこと」です。
今は、事業ノウハウや個人の力を伸ばしています。
連携の仕方、事業の進め方を覚えます。
そして「組織に必要なレアな人材」になります。
私は、1人では戦えません。
でも、私の代わりはいないと思わせるようになります。
そうすれば、いつでも声がかかるようになる。
自分から応援してもらえるように、
応援しやすいような人間になりたいと思います。
あとは、単純に時間と金銭面です。
急に現実的な話ですが、退職してやはり年収は落ちました。
年収をカバーする必要があるため、
個人での活動はマストになります。
価値あるものを伝えながらも、
対価を十分に得られるような
先生にもなりたいと思います。
そうすれば、お金のことを考えずに、
思いっきり教育に舵を切ることができます。
理想は、
「自分がやりたい教育事業に全振りできる環境」です。
スキルはある程度身につきました。
仲間もいます。
時間と資金は少し足りません。
これを可能にするには、「実績」です。
まず「実績」を作ろうと思います。
叶えたい教育現場を実現し、
願わくばそこで先生として働きたいと思います。
また、教育の世界でプレイヤーとして働けるように、
今を頑張りたいと思います。
今の仕事は授業論ではなく、
事業や経理、決済、システム、マニュアルなどです。
裏方の仕事です。
正直苦手な分野でもあります。
でも、きっと必要なことだと思っています。
なんとか踏ん張って頑張りたいと思います。
そして、国家試験。
国家資格を手に入れて、伝える力を高めていと思います。
自信をもって、これからも生きていけるように。
少しずつ教育の未来は変わってきています。
今があるのは、今もなお1人1人が頑張っているからです。
その頑張りが、ちょっと楽に、
報われて、循環して、多くの人が笑顔になりますように。
変わったステージの上で、
次のステージに向けて頑張りたいと思います。
タノ🦒でした。またね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
