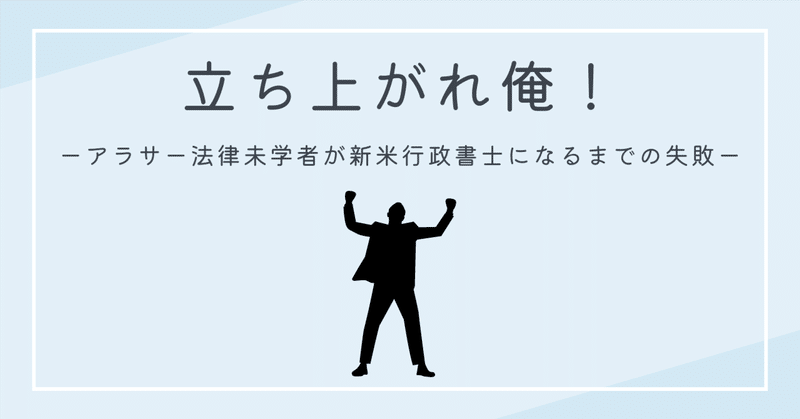
【行政書士試験失敗記】10話 資格試験初心者のくせに生意気だ(体験談)
初めから負け戦と知りながら戦うことほど虚しいものは無い。
行政書士試験失敗記も節目の10話を迎えることができた。
ここまでお付き合いいただいた皆様には最大限の感謝を送りたい。
総ビュー数も現時点で800を超え、各話ごとに平均して50ビューを超えているということで読者諸賢の皆々様にそれなりに価値のあるものを提供できているのではないかと生意気にも思ってしまう私だ。
そう、現時点でも生意気な私ではあるが、過去の私は軽くその上を行っていた。
本題に入ろう。
今回は行政書士試験における捨て科目についてのお話である。
ご存じの通り、この失敗記のタイトルの通り、私は行政書士試験の勉強を始める前は法律という学問には全く触れてこない人生を送っていた。
唯一、私が法律に触れたのは、大学進学について考え始めたころである。文系であった私はどの道を進むか検討している中に「法学部」なるものがあった。
興味本位で近所の古本屋に足を運び、中古の六法全書を手に取り、さっと開いてすぐに棚に戻した。
うん、これは私の手に負えない。
あまりの難解さに恐れおののき、金輪際、法律の勉強などするものかと心に誓ったほどである。
それから数年の時を経て、最近では法律条文を見るとニヨニヨと不気味な笑みがこぼれてくる変態になってしまったのだから人生というのは分からないものだ。
行政書士試験を勉強していると、よく言われることの中に「捨て科目」、「捨て問」の話題が上がる。
試験問題の中には、範囲が膨大でありながら、出題数が少ない科目がある。
それらを無理して勉強するくらいなら出題数の多い行政法や民法を集中的に勉強するのが最短合格のルートなのだと主張する人もいる。
時間は有限なので、科目を絞って戦うのは戦略として間違いではない。むしろスマートな考え方だろう。
やり玉に挙げられるのは会社法、次に基礎法学だろうか。一般知識についても分野によっては対策のしようがなく、問題の取捨選択に迫られる。
これらは範囲が広い上にどこが出るのか予測を立て辛いのだ。
各科目別に考えてみると
会社法は例年必ずと言ってもいいほど出題される範囲もあるが、それでも全ての問題を完答するのは極めて難しい。
基礎法学は行政書士試験における一発目、そこで試験センターは受験生の心を折りにかかる難問をぶつけてくる。これも完璧な対策は難しいだろう。
一般知識に至っては、様々な人が問題を予想し、ありがたいことに「今年はこれが出る!」と胸を張って言ってくれるたりする。
しかし、そういう問題に限って本番では出ない。全くでない。なぜか出ない。なぜだ。
出なかったことは仕方ない。その人を責めても責任を取ってくれるはずがないのであきらめるしかないのだ。
結論としてどれも対策がし辛く、全てを勉強しようとするのであれば膨大な時間がかかる。そういった理由から捨て問、捨て科目の話が出てくるのだ。
もちろん私はその話を真に受けた。
それもしっかり真に受けたのである。
もとより勉強嫌いであった私は、しなくてもいい科目があるのであれば絶対に勉強などしたくなかった。
資格試験勉強をし始めた頃の私はもちろん会社法を捨て科目にしていたし、基礎法学も一般知識も
「出たとこ勝負! 文脈を見ればなんとなくわかるっしょ!」
なんて考えていた。愚かである。
「どうしても分からなければ全ての選択肢ウを塗りつぶせ」
と先人のありがたい教えをきっちりと守った私の試験結果は案の定、不合格であった。
先人の教えを守ったとしても、それがそのまま合格に直結するわけではない。人生は甘くないのだと私はここにきてようやく学習できたのだ。ありがたい。
さて、ここで我々が考えなければならないのは捨て科目・捨て問との付き合い方だろう。
本番では難問・奇問が毎年、どこかしらで出題される。これらの問題は合格率を下げる目的で出題され、受験生の時間を使わせたり、そもそも解くこと自体が難しいものである。
そういった難問・奇問を世間では「捨て問」と呼び、それらとは戦わずに他の問題を倒してから余った時間で回答する、という対応が一般的だ。
しかしこの捨て問、どこの科目で出てくるのかは決まってない。
なんとなくの肌感覚では民法に多い気がする。逆に行政法は少ない気がする。いや、地方自治法では結構出るか……?
このように、いまだにしっかりとした意見を持てないほど謎な部分なのである。だが、毎年「なんじゃこりゃ!?」みたいな問題は必ず出ている。これは間違いない。
一生懸命勉強した行政法で出ることもあれば、昔の私のように全く勉強していない科目から出ることもある。
ではその捨て問が出てしまった場合、私はどうするのか。
当然戦わない。この問題は捨てる。
そう心に決めていた。
そう決意して模試を受けている最中、いつものように捨て問であると見切りをつけた問題を飛ばそうとしたとき、耳元で私のなにかが囁いた。
『科目ごと捨てているところがあるのに、問題を解くのをあきらめてもいいのか?』
その囁きに私はこう答えた。
「問題ない。正解できる問題を確実に正解するために知識の精度を上げていく。それが行政書士試験における攻略法だ。わからないものはわからない。難易度の高い問題は解いても時間の無駄。だってこの問題を見てみろよ。なにを言っているのかさっぱりわからないんだぜ?」
『本当にそのままでいいのか?』
1回目の試験に落ち、2回目の挑戦を始める際、その囁く声はさらに大きくなっていった。
行政書士試験は合格率が平均10~11%の試験だ。10人受けて9人が不合格の試験。
『おい、鈴木駿生。お前は、お前の他に9人並んでて、「自分が一番能力高いです!」と声高に叫べるような人間か?』
もちろん、「はい」と答えられるわけがなかった。しかし、自分が受けようとする試験はそういう試験なのだ。そういった試験はあの手この手で受験生を振るい落とそうとする。
ここで考えてみて欲しい。
先ほどやり玉に挙がった会社法は試験において5問出題される。得点にして20点。基礎法学は2問で10点。
私はこれらを「別に取れなくていい問題」として扱った。そして、模試でも本番でもこの7問のうち、1問でも解けたらラッキーくらいに考えていた。
どういうことかわかるだろうか。
私は試験が始まる前から300点満点の試験を受けていたのではない。試験が始まる前から30点を失い、270点満点の試験を受けていたのだ。この差は大きい。既に10%失った状態で戦い始めていたということになる。
おいおい、と。私の耳元でまたなにかが笑った。
『お前みたいな人間がそんなんで合格できるのか』と。
私の別の部分が言い訳をする。
「選択問題なんだから適当に書いても当たるときは当たるでしょ、1、2問くらい」
愚かだ。極めつけの愚か者だ。
逆に当時の私に聞きたい。
『お前は自分の人生がかかっている試験でそんなことが言えるのか。愚か者』
私が世の中の成功者のような出来の良い人間ではないことは、今までの人生を歩んできた結果を見れば、分かり切っていることである。それも嫌と言うほど。
出来の良い人間であれば正解したい問題だけ正解し、スマートに合格していくだろう。
しかし、私は違うのである。
私がやるべきことはスマートに効率よく合格することではなかった。
最初から30点分をドブに投げ捨てるのではなく、どの問題も泥臭く検討し、試験時間の3時間をフルで使って正解を導き出し、300点の中から自分が解ける問題をかき集めてかき集めて180点にする、という作戦を練らなければならなかったのである。
そんな気づきを得て、ようやく私は自分がかつて捨て科目としてきた法律たちに立ち向かった。嫌々ながら。
ここでまだ目を覚まさないあたり、私も中々であるが、それでも立ち向かった。
立ち向かって気が付いた。
かつて無駄だと切り捨てた科目が「面白い」のだ。
会社法は会社を設立しようとする一連の流れが見えて面白い。民法や行政法とは違い、「会社」のことなので想像しやすい。特に大企業に関する法律は、一見とっつき辛いが、社会派系ドラマ(「倍返しだ!」っぽいもの)が好きな人はよりニヤニヤできる。
基礎法学は歴史好きであればより面白いと感じるかもしれない。
法律とは究極的なことを言えば、人類の歴史の積み重ねだと私は思う。法律の成り立ちについては中世から続く歴史的な背景があるように見える……なんて考えるとちょっと見え方が違ってくるだろう。
特に日本の法律の成り立ちは特殊で戦前と戦後の考え方の変遷は読んでて面白いなと感じた。
一般知識も面白い。現在と過去それぞれの世界情勢を知ることができる。
特に行政書士試験の問題を作るとき、予備校も本試験も体感ではあるが、日本の歴代総理大臣に関連する問題を出してくることが多い気がする。総理大臣と自民党の歴史をざっと振り返っておくと近代史が面白く感じるのだ。
最新の技術についても勉強することができる。雑談でIT関係の話が出たとしても「なんとなく知ってますよー」という顔ができるのでお勧めだ。
なんだ、面白いじゃないか。なんでちゃんと勉強してこなかったんだろう。
それが率直な感想だった。
対策し辛いというのは本当ではある。模試でも本試験でも「なんだこの問題!? 知るか!!」と吐き捨てようとしたことも1度や2度ではない(現に私は本試験で「知るか!」と叫びそうになった)。
しかし、それでも。
勉強しなかった方が良かったとは決して思わない。勉強した時間が無駄であったとは思わない。
勉強しなかった時の私とは試験に対するアプローチがまるで変ったからだ。
なにを言っているのか全く分からなかった問題文も違って見える。
部分的に理解できる箇所が見える。であれば無抵抗で終わらずに最後まであがくことができる。
真剣に考えて爪痕を残すこともできるのだ。たとえ間違えていたとしても次につながる一歩となるかもしれない。
初めから負け戦と知りながら戦うことほど虚しいものは無い。
戦うからにはなにか手に入れなければならない。
だからこそ真剣に敵と相対することになる。対策を考える。勝てなかったときに悔しさが生まれる。次に活かせる。
私は効率良く、スマートに合格するためと言い訳して、捨て科目や捨て問を気軽に作る、なんともまぁ、生意気な受験生だった。
それができる人は世の中には沢山いる。それは間違いない。
しかし、私はそうではない。
私は全ての問題を検討し、必死になり、目を血走らせ、脳みそを沸騰させながら考え、与えられた時間をフルに使って身をよじりながら知識を絞り出す。
その絞り出した知識をかき集めて何とか合格点を獲得できる、そんな人間だったのだ。
私はスマートな人間ではなかった。だから失敗したのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
