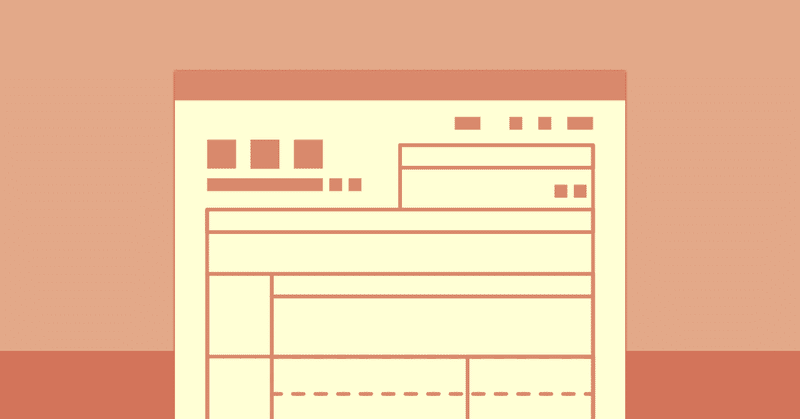
新人社労士としての手続き業務の覚え方
社労士資格は取った。事務指定講習も終わった。開業登録もした。
さあこれから営業だ。
そういう時に、強烈な不安感が襲うことがあります。
「依頼を受けて、その業務ができなかったどうしよう」
これが実務経験がある人との大きな違いです。
不安の根幹はどこにある
事務指定講習を受けたとしても、完璧な回答をすらすらできた方はごく一部です。なんとか完璧な回答ができたところで、1回ぐらいの経験で実際の経験があるレベルまで到達できるわけがありません。
しかも社労士実務の現実には、事務指定講習で一切触れない業務の話がいくらでもあります。現実世界は、あまりにも想定を超えており、「いくらやっても知らない業務がある」と感じます。それをなんとなく感じているからこそ、不安感が出てくるのでしょう。
それを払拭するには、実は
・経験を積む
・強靭なメンタルを備える
ぐらいしか対策がありません。なんて意味のないアドバイス。
手続き業務の根幹から考える
そもそも手続き業務とは何でしょう。
社労士の関連するものに限らず、様々な法令によって、一定の条件下にある人や企業は義務を課され、時には権利を得ます。こうした課された義務の報告や登録と、得た権利の行使をするために手続き業務はあります。
それらのほとんどは、行政手続法や各省庁の通達やガイドライン等で定められた手順や判断基準で、受付され、審査され、決定されているのです。一部は例外もありますが。
社労士に関しては、取得喪失も労災も年金裁定請求も全て法令に基づいて行われます。社会保険労務士が社会保険労働保険等に関する手続き業務の代行を独占業務として認められている理由は、労働社会保険行政に関する法令について、十分な知識があるものだと思われているからです。
正確には社労士に関連する行政から、全員がそう思われているわけではありませんが、社労士資格の性質上で十分な知識があることにしていないと、社労士側の方が都合が悪いことになります。
手続きは、法令に基づいた審査のために、欄を埋めていく作業
社労士として申請書類を作成する場合に、単純に空欄を埋めるだけでは不十分です。法令に基づいたものの一部の例を挙げましょう。
①氏名や生年月日は、個人を特定するために記入します。
雇用保険は前職の経験によって、失業等給付の受給期間が異なったりするので、被保険者番号が無い場合は、前職を聞いて個人を特定させます。
年金では基礎年金番号もマイナンバーも不明だと、個人特定ができないから申請できません(H24の通知で両方不明時は手続き禁止となっています)。
②取得日や喪失日は被保険者となった日を特定するため。
雇用保険の喪失日は当日、社会保険の喪失日が翌日なのは、試験でも覚えるはずです。日付特定の理由が、出勤簿、雇用契約書、解雇通知、退職届等と様々あります。何をもって事実と判断したかも重要です。
③離職票の書き方は失業等給付の要件を満たしているかが、ハローワークの職員が分かりやすいような書式になっている。
離職票はこれらが顕著な例で、過去2年以内に12か月(ひと月11日以上)の要件を離職日から遡った日付で記載、受給額を決定する欄の記載方法、特定理由資格者・特定受給資格者を判別する離職理由等、法令に基づく記載が満載です。
こうした申請書等は、原則的に審査に必要な情報だけを記入するようになっており、それで不足する情報のうち、転記が困難なもの(出勤簿等)や、真実性を担保するもの(登記簿や契約書等)について「添付書類」として求めています。
申請書類作成において考えること
申請書は、企業の職員のように書き方をマスターして、その通り行うことではなく、記載内容が問うていることが何なのかに答えるように記載します。
これは取得・喪失だけでなく、労災も助成金も裁定請求も同じです。
そうした面を考慮して記載してみると、この記載内容では事実関係が伝わらない事項が出てくるでしょう。そうした場合は、問われる前に添付してあると、行政の業務がスムーズに進むのです(ちなみに私は行政経験がほとんど無いので行政の業務手順は推測です)。
これらを意識しないで、書き方だけを学ぶと、書式が変わっただけで、腹が立ちます。多くは書式が変わるということは、法令が変わったことによるものなので、法改正情報と照らせば「当然」のものがほとんどです。
特に効率化のために電子申請が主流になりつつありますが、専用ソフトを利用するとある程度を意識しないで自動的に書いてくれるので、結果的に行政が何を見て審査しているのかが、非常に見えずらくなっています。
何を求められているのかは、試験問題と同じだと思って
近年の社労士試験では、長文だらけの論点が何かが曖昧な文章から、正解を導くことができた人しか、受かっていないはずです。
実務の書類作成は、見本もあるし、書き方の指南書もあります。そのため単純な書き方だけ理解すれば、数をこなせばできるようになります。しかし、その方法は企業の社会保険実務担当者の覚え方であり、社労士の覚え方ではありません。
私は、実務経験を会社役員経験で登録したために、実は実務経験0の事務指定講習無しで開業登録しました。実は自分の離職票も見たことがありませんでした。そのためこの視点に立てるまでに2年以上かかりました。
手続きに自信が持てない状態で2年費やしたのは、非常に無駄な時間です(その間に就業規則とか助成金とか勉強してましたけど)。
申請書が理解できれば、怖がるものはありません。障害者雇用納付金とか、介護処遇加算とか別に学ばないと最初はできないものも多数ありますが、取り組み姿勢が理解できていれば、必ず分かるようになります。
ショートカットで聞ける先輩がいると便利ですし、どうしても理解不能な場合は行政に聞いてもいいのですが、
「全部教えて」と言われると、多くの人は萎えるので注意しましょう。
面白いとか、役に立ったとか、ちょっと違うかもとか思って頂けたら、ハートをお願いします。ツイートやFBで拡散して頂けると、とってもうれしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

