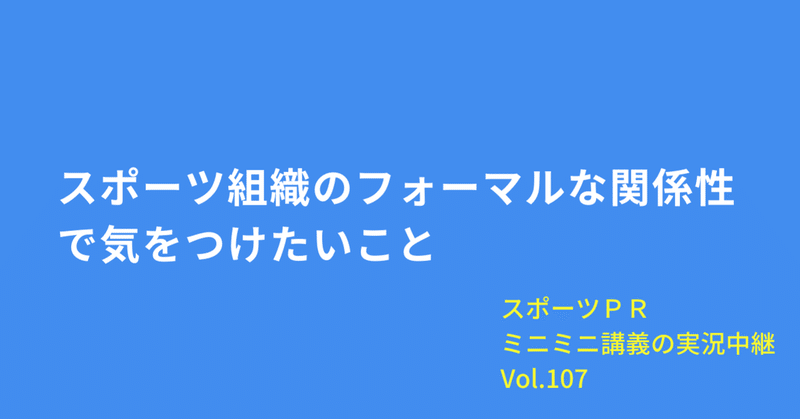
スポーツ組織のフォーマルな関係性で気をつけたいこと
「スポーツに関わる“常識破り”の価値を広めて、常識にする」を胸に、仕事をしています。
この「スポーツPR ミニミニ講義の実況中継」は
-------------------------------------------------------------------------------
「前例がない」「できるわけがない」「それはきれいごとだ」
などの声に負けずに挑戦している方に、ヒントになる考え方を伝えること
-------------------------------------------------------------------------------
を目的として、週に2,3本のペースで更新する
・スポーツ関連事業を行っている企業・組織で働く方
・スポーツ関連ビジネスの個人事業主
・現役アスリート、元アスリート
向けの短い講義です。
スポーツとは関係のない広報担当者から「スキ」をもらうこともあります。
なぜ、スポーツに関わる“常識破り”の価値を広めて、常識にしたいのか。
私はスポーツ記者を13年、その後、PR業に立場を変えて8年と、伝える仕事を20年以上続けています。その中で、言語化や仕組みづくりを進め、組織や個人が大切にしている理念が広まれば、“常識的にはありえない”ことも実現する場に立ち会ってきたからです。
例えば、私がかつて広報担当を務めた日本ブラインドサッカー協会は、前例のないスポンサーシップを行ったり、競技の価値を活かした教育プログラムや企業研修を開発し、言語化と仕組みづくりで、それらの価値が広まって、何万人もの人の心を動かすものとなりました。
この連載は、忙しいあなたが、3分以内で手軽に読んで変われるよう、ギュッと凝縮しています。価格以上の大きな効果につながる内容にしています。
移動中に読んでもいいですし、定期的な学びの時間として使って頂いてもいいです。あなたに合うスタイルでお楽しみください。
今回のテーマは「スポーツ組織のフォーマルな関係性で気をつけたいこと」です。
スポーツ組織内にあるフォーマルな関係性において、働く人、特にマネジャークラスの人は何を気をつければいいのでしょうか?
まず、大事なことは、組織の構造が、目的や目標を達成するのに最適な形になっているかということを考えましょう。部門の分け方ですとか、上下の階層がその対象です。自分が入っている部門の中で変えられることもなります。
また、部署とその役割を理解することが大切です。マーケティング、営業、総務、何々事業部などいろいろありますが、自分が入っていないところも含めて、その中身が分かっていないといけません。
次に、命令系統を理解することも大事です。
自分の上には誰がいて、指示や許可をもらわないといけないのか。自分の部下は誰で、どんなことを伝えないといけないのか。いわゆるレポートラインというものですね。自分が企画したものを通していく手順、大事な決定があった時にどのように伝わっていくのかなどを把握しておく必要があります。
また、それぞれのマネージャーが、どこまでを管理しているのかという範疇も理解しなければいけません。
これらのことを考えていると、大事になってくるのは、権力を集中させるのか、分散させるのかというところです。
ワンマン社長のように、トップに立つ人が何でも口を出す形なのか、権限を現場に近いところに移譲をして、それぞれに任せる形なのか。どちらか一方に振り切れてることは少ないと思いますが、その間の目盛りの調整は何らか行われています。
これも組織が達成したい目標によって、構造が変わってくるということです。
また、組織で働く人は皆さんが、日々取り組んでいることの一つが、調整です。それぞれの働き手の間だったり、それぞれの部門の間の調整が、うまくやっていけるのかの鍵になってきます。非常に難しいことではありますが、調整なくして組織内で物事は進んでいきません。
まとめますと、部門、管理する範囲などをしっかり理解すること、命令系統にしたがって話を上に上げたり、下におろしたりすることがきちんとできるかということになります。言われてみれば当たり前で、スポーツ組織だからと言って、特殊なことがあるわけではありません。
よろしければ、サポートをお願いします。新しいことを学んで、ここにまた書くために使わせていただきます。
