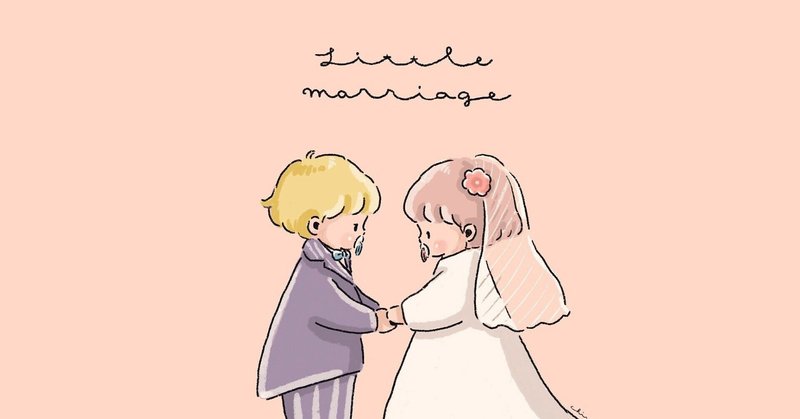
第66話:結婚式スピーチ
もう「今は昔」のこと、僕らは三島大社の神殿で結婚式を挙げた。外から丸見えなので人がゴソゴソ集まって「あっ、見て-。結婚式!」などという声も聞こえるし、時々チャリンと賽銭が投げられたりもしていた。
台風が抜けた10月のよく晴れた日で、爽やかな日であったことを覚えている。
自分が結婚するという実感は乏しく、人生の大事であることは疑いようもないのだが、着慣れないものを着、皆におめでとうと言われることを照れ臭く思ったりはしたが、その日が特に昨日と違う一日のようには思われずにいた。
不精な僕はヒゲも剃らず、頭もボサボサのまま式に出掛け、披露宴でお色直しに退室するとき、兄に怒られてヒゲ剃りを渡された光景がビデオに映されて残っていたりもする。
実は大切な花婿のこと、それなりに式場で手当てをしてくれるものと思っていたのだが、そんなことはなく、かえって更衣室で係のオバサンに言われるままに服を脱いだら、オバサンはゴソゴソ辺りを探し始め「花婿さんの衣装がないわ」と裸の僕を置き去りにしたまま慌てて飛び出して行ってしまった。
あっちこっちで「花婿さんの衣装がない!」という叫び声がしたから結構苦労はしたのだろう、結局5分ほど経って何とかオバサンは発見して来てくれたが、その間何とも間の抜けたパンツ一枚の姿で、花婿である僕は大鏡の前に一人ポツンと座っていたのである。
僕は披露宴というものが嫌で、日が近付くに従って憂欝だった。自分が雛壇にいてみんなの視線を受けたり、ケーキにナイフを入れてポーズを取ったり、赤や青のスポットを当てられたり、ドライアイスの中を登場したり…、そういう諸々のことが何とも恥ずかしかったのである。
最初は何とか披露宴を簡素にしようと考えてはみたが、結局式場の人の「披露宴というのは、お二人のためだけのものではありませんから…」という殺し文句に従うしかなかった。
今の若い人達が友達だけを呼んで式を挙げるとか、外国で二人だけで挙式するとか、そういう気持ちもよくわかる。むしろ、ゴンドラに乗って登場とか、お色直し5回とか、そういうことの方があまり理解できない。
ほんの子供のころ、向かいの家に嫁入りがあり、嫁入り行列の中に白無垢姿で馬の背に揺られてやってきた花嫁の姿を見て、子供ながらに感動を覚えたことがあった。商業主義的演出が、そういう淡い憧れを抱かせる結婚式を消してしまうのはいかにも残念なことではある。
披露宴も千差万別。少人数のパーティー形式のものもあれば、200人を超える披露宴もある。地区の公民館での挙式もあった。和やかなのもあれば、うるさくて「いいかげんにせえー」というのもある。新婚旅行の旅費の補助だと言ってバナナの叩き売りが登場したり、酔っ払って大声をあげ顰蹙を買う人がいたり。
概して東京の式は静かだが、田舎の式はパワフルである。オジサン達が赤ら顔で歌いまくり、親族対抗カラオケ大会のようになってしまうのもあった。乾杯前の主賓の挨拶が長くて2時間も御馳走に箸を付けられなかったとか、乾杯の発声をするのにちょっと一言と言って15分も話を続けたためにみんながグラスをもったままの姿勢で立ちすくんでいたとか、そんなことも起こる。
スピーチもとりどりで、聞いていると「よく言えるよ」という歯の浮くようなのがあるかと思えば、「そこまで言っていいの」というキワドイのもある。
ちなみに、かつて知人の結婚式では新郎が友人達のスピーチで徹底的にやっつけられていた。
友人達に悪意はないのだが、
「学生時代に酒を飲みそのまま外に出てバイクに乗り、電柱にぶつかって救急車で運ばれた」とか、
就職後も「遅刻ばかりするのでモーニングコールの当番を決めていた」とか、
「酔って誰かの土産の提灯に火をつけたまま寝てしまいボヤを起こした」とか、そんな暴露話が延々と続いた。
新婦はほめ、新郎は裏話も登場するのが披露宴のスピーチの多いパターンではあるが、これだけ次から次へと裏話ばかり出て来るのは珍しい。皆が皆「誰かがまじめないい話をするだろうから」と思った結果なのかもしれないが、とうとう最初から最後まで誰もまともなスピーチをしなかった。
かわいそうなのは新郎で、親には怒られ、新婦の親戚からは「しっかりお願いしますよ」と声をかけられたそうで、披露宴後、つくづくと「俺は人選を間違えた」と嘆いていた。
もうひとつ、その直後に出た披露宴の事を書いておきたい。これは大学の同期で、高校の教員をしながら大学でも講師として教え、国語学の論文を精力的に書いていた。後に大学の学長になる、かなり優秀な奴だったのだが、そんな関係で出て来る人、出て来る人、一様にいいことしか言わない。
学生時代をそれなりに知っている僕らは何となく歯の浮くような思いでいたりしたのだが彼は「人選に成功した」ということになるのだろう。
ちょっとしたことが人生の明暗を分けるものだと僕はくだらぬ感慨に浸っていたりしたのだが、そんな中で、大学時代の教授がこんな内容の話をしたのが非常に印象深かったので紹介しておきたい。
本来ならば二人楽しくお幸せにと言うべきなのでしょうが、彼は今、研究者としての道を歩き出しています。研究者には土曜日も日曜日もありません。毎日が勉強に明け暮れなければならない生活になるでしょう。日曜だから遊びに行きたいとか、のんびりと二人で夜を過ごしたいと思っても、それは普通の若い夫婦のようには行きません。
厳しく聞こえるかも知れませんが、新婦はそれを理解して彼を支えてやって下さい。彼と一緒に時を過ごすことを望むのではなく、ご自分も没頭できる何かを自身でお持ちになって、ご自分で充実した時を過ごす術をお考えいただきたい。
そんな話の内容だった。学問的に非常に厳しい姿勢を貫いて来た女の先生で、だからこそ言えることなのだろう。歯に衣着せぬスピーチは結婚式としては異例のものに違いないが、一同、感動して聞き終わった。
昨今ではなかなか聞かれなくなった、道の厳しさとか、自分自身の人生の時間の使い方とか、夫婦関係を含めた本来的な人と人の在り方とか、そんなことを改めて考え、何だかちょっと快い気持ちになって家路についたのであった。
だいぶ趣は異なるが、どちらの結婚式も「教訓」にしていただければと思う。
(土竜のひとりごと:第66話)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
