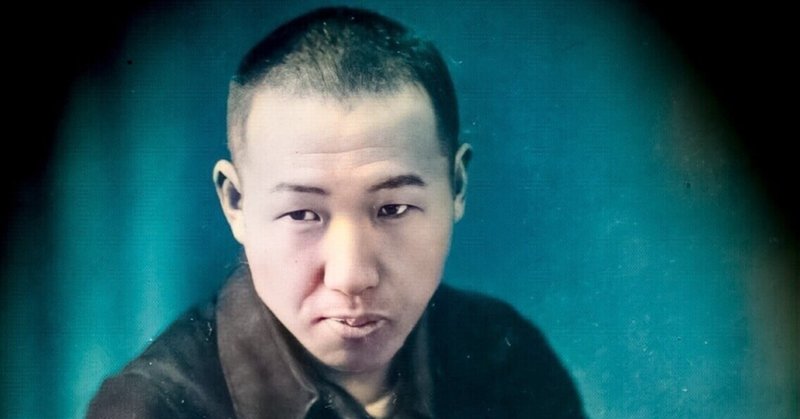
高校の国語から文学が消える?
一般の方はご興味がないかもしれませんが、ちょっと柄にもなく真面目な国語の話をしてみたいと思います。
学校によって違いがあるので僕の現在の経験で書きますが、一般的に大学進学を前提とした科目の置き方は現在はこんな感じになります。
1年生
旧課程
■国語総合→現代文中心に週2時間、古典中心に週3時間、計週5時間。
新課程が今の一年生から導入されていますが、新課程ではこんなふうに科目が変わりました。
新課程
■現代の国語 と■言語文化 をそれぞれ週2時間と週3時間、計週5時間。
同じではないかと思われるかもしれませんが、文学的文章と古典の両方が■言語文化に組み入れられ、■現代の国語は論理のみということになっています。
現代の国語は論理的思考、言語文化は言語文化的な思考ということで、それはそれで結構なことですが、文科省の理念はともかくとして、現場で大学受験を考えた場合、ほとんど高校生から学習が始まる古典にどうしても比重をかけなければならず、詩や短歌、俳句、小説などに時間が取れなくなっているのが現状です。
それでもまだ1年生はいいのですが、2・3年生は
旧課程
■現代文B ■古典B→現代文を3時間(理系は2時間)、古典を3時間。これを2、3年生で2年間継続。
であったのが、
新課程
■論理国語・■文学国語・■国語表現・■古典探求 (いずれも標準時間は週4時間)から選択
という形になりました。
何が問題かというと、先程書いたように、受験を考えた場合、■古典探求を放り出すわけにはいかず、そうすると、■論理国語と■文学国語のどちらかを選ばなければいけないということになります。
全部ちゃんとやれば国語で週12時間使うということになるので、それは30~35時間しかない週の授業コマ数から言えば無理な話です。
単位数を少し削って両方を組み込むという対応が許されている県もあるけれど、東京などではまったくそうした対応は許されないそうです。
そうすると■論理国語と■文学国語を天秤にかけなければなりません。当然と言ったら叱られるかもしれませんが、これも現実的な受験を考えると■論理国語を取らざるを得ないということになるわけです。
したがって、タイトルに書いたように「高校の国語から文学が消える」という状態が生まれつつあるわけです。
随分前から、小説を中心にした文学が入試から消えていくという傾向はありました。新しく導入された共通テストも、これまで2回行われた試験ではそんなに大きな変更はありませんが、試行調査(試験問題のサンプル?)では著作権法の条文やらグラフやらの、いわゆる実用的な文章が出され、激震が走りました。一括採点不可能な「記述問題」は撤退されましたが、まだまだ実用的文章が出される可能性はあります。
恐らく、いわゆるピサショックで、日本人は複数の資料を見比べる読解力に欠けているという反省が根っこにあるのだと思います。
それは「情報処理能力の不足」だとエライ方々は理解しているようですが、だからと言ってそれが、契約書や規約の文章を読解することではないでしょうし、人生の入り口に立っている若い世代が、哲学的な思考や文学的感性を磨くために、ひとつの文章、一人の著作者とじっくり向き合うことは大切なことだと思います。
情報(データ)処理として読まれる文学や思想書は、もはやノウハウでしかありません。心に響かない。
現場は翻弄されています。何か変わるたびに。
今回の教育課程の変更も、抽象的な文言は示されても、何の具体性も示されない中で、2年前に現在の1年生が卒業するまでの教育課程を組むことが求められ、全く「そんなの無理」状態でした。
翻弄。
ゆとり教育失敗。知識は大事?
総合学習って?探求学習って?
ipadを全生徒に。でも、個人で買わせて。
評価の仕方も観点別に改めなさい!
18歳成人のために主権者教育もしなさい!
投資やお金の増やし方も欧米では教えられている!
マナーや礼儀、思いやり、交通安全、防災教育、情報処理能力、部活動で運動も、健康管理、心の教育・・。
・・でも、残業手当ないし勤務時間もブラックだから頑張って働いて!
思わず語気が荒くなりました。申し訳ありません。現場の努力が足りないんだと一般の方から言われれば、それは甘んじて受けなくてはならないのだと思います。税金で働いていますし、リストラもありません。兄貴にはいつも「公務員は生ぬるい」と言われ続けてきました。
とりあえず、一国語教員としては、それでもかつては、「一時間外に出て短歌を作って、みんなで批評したり、クラスで歌集を作ったりした、そういう日々があったよなあ」と、ちょっと懐かしく思ってみたりするわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
