吉田健一「文学の楽しみ」
坂本龍一さんが「婦人画報」で連載している、本についてのエッセイ「坂本図書」の最新の寄稿で吉田健一と石川淳について触れられているということを友人から教えてもらいました。メインとなっていたのは石川淳の紀行文「西游日録」でしたが、坂本さんがこれを知ったのは、吉田健一「文学の楽しみ」を通してとのことでしたので、今回はこちらを取り上げることにしました(石川の紀行文も名品なのですが、現在は入手困難なので・・・)。本書はこれまで比較的地味な扱いだったと思うのですが、池澤夏樹さんが個人編集した日本文学全集に収録されたことで、改めて注目を集めたのかもしれません。
ところで、合気道の伝説的な達人に、潮田剛三という人がいます。今でもYouTubeで往年の演武を見ることができるのですが、見る度に感嘆を禁じ得ません。一見無造作にも見える立ち姿なのですが、いざ相手がかかってくると無駄な力みを全く感じさせないで技をかけ、倒してゆきます。この境地に至るには相当の修練があったと想像できますが、そうした修練の跡を感じさせない、自然な体さばきなのです。私はそこに吉田健一が説く文学との接し方と共通するものを感じます。文学に接する際、その言葉のもつ響きや、外国文学であるならその国についての歴史や文化的背景を知っておくのは吉田にとっては当然のことで、それを求めるために文学を読むというのがおかしいのだ、ということになります。そうしたことを通過した上で、言葉に向かうことで読者の精神も自在に働き、楽しみを得ることができる。それは吉田健一が終生語り続けたことでした。本書でもそれは変わりません。
酒や友人、文学をこよなく愛した吉田健一にとって、「文学の楽しみ」というテーマはまさに格好のものと思われるし、実際そうなのですが、本書を読んで私がまず感じたのは当時の日本の文学を巡る状況についての怒り、いらだちでした。では吉田健一は何にいらだっているのでしょうか。それは「文学」に対して鹿爪らしい、硬直した態度で向かうことであり、何かを教わるためや役立てようとして読むことであり、自分の頭で考えず古典の権威に盲従することであり、表面的な目新しさに囚われることであり、みじめさ、怒り、悲しみこそが文学であるといった思い込み・・・つまりは先述した、精神の自在な働きを阻害するものに対するいらだちでした。日本がヨーロッパの近代文学に接してから、いつのまにか蔓延るようになったこうした思い込みの数々を本書で吉田は批判していき、本来の「文学の楽しみ」に立ち返ることを説いています。生きることは喜びであり、生きた言葉に接することで読者の精神はその響きを受け止め、その喜びを知る。吉田健一にとって文学とはそういうものであったのです。評論「ヨオロツパの世紀末」と小説「瓦礫の中」から始まる、吉田健一晩年の実り豊かな作品の数々は、まさしく本書で描かれた「文学の楽しみ」を具体的に読者に提供したものでした。
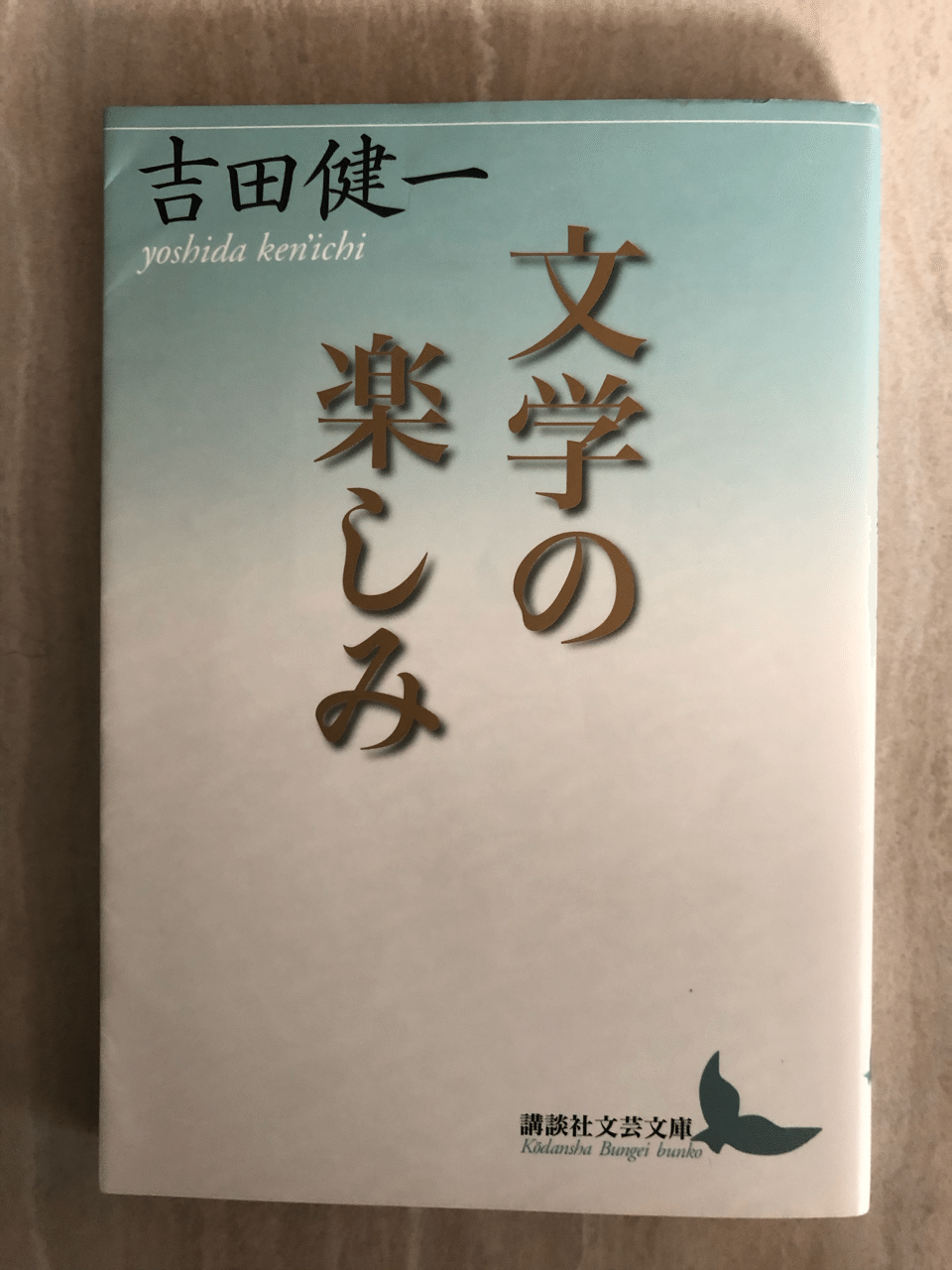
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
