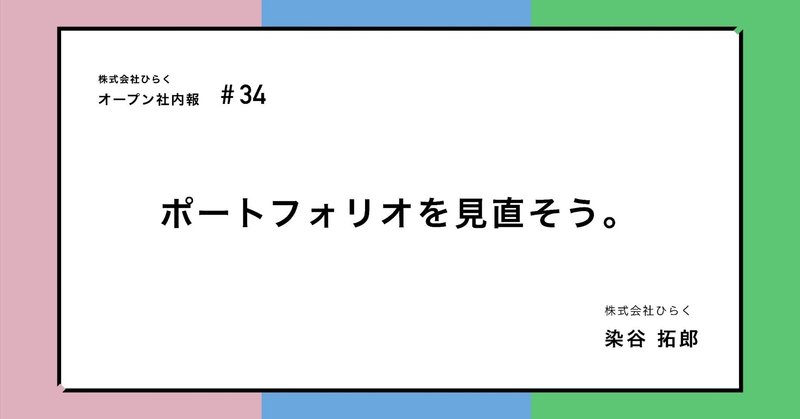
【オープン社内報#34】ポートフォリオを見直そう。
こんにちは。株式会社ひらくの染谷拓郎です。
ここ数日、21時に寝て午前3時に起きるというサイクルが定着しつつあります。朝型の集中力は目を見張るものがある(と自分で言っちゃう)のですが、日中の眠気といったらありません。このままこのサイクルで行くべきかちょっと悩んでいます。「朝3時クラブ」の同志がいましたら、一緒におはようを言い合いましょう。おはようございます。
さて、あっという間に上半期も終わってしまいますね。下半期は、いよいよ常総市のまちなか再生事業が本格稼動します。また、福岡県八女市の新図書館構想や11月には大型コンペがあったりと、プロジェクトが目白押し。放っておくととにかく眼前のプロジェクトばかり見てしまうので、意識的に振り返りの機会をつくっていこうと思います。
今日のテーマは、その振り返りの方法について「ポートフォリオ」をつかって書いてみます。このポートフォリオにはふたつの意味があって、ひとつは資産形成で使われる「保有資産の組み合わせ」のこと。預金と株式と不動産でポートフォリオを構成している、とかそういう使い方。もう一つは、自己PRのための作品集もポートフォリオを呼びます。デザイン会社などの採用欄には「自身のポートフォリオを提出すること」が要件に入っていたりします。振り返りには、このふたつのポートフォリオがとても大切になります。
まず、「保有資産の組み合わせ」としてのポートフォリオの見直しから考えてみましょう。いま、手元に持っているものを整理すること。例えばひらくは、文喫事業・プロデュース事業・公共プレイス事業の3つの柱を掲げてスタートしました。その3つの事業は、現在それぞれかけている人員に対して、売上と利益は適正な状態にあるだろうか。3つのバランスは適正だろうか。4つ目の事業が必要なのか、もっと絞っていった方が良いのか。大きく伸びている事業があれば、そこにリソースを集めていく方がいいし、どれも可能性とリスクを持っているのでれば、やはり分散しておいたほうがよいと判断します。
文喫事業は六本木と天神の2店舗の運営に加え、文喫プロデュース案件も多数進行。プロデュース事業は安定的なエスコート案件に加え、2025年、26年に向けた大きなプロジェクトもいくつか進行中。公共プレイス事業は先ほどの常総市や八女市など、確実に手がける場所が増えています。
課題はどの事業も労働集約型で属人的であることです。パッケージでスケールするモデルとしてそもそもつくってないところがあるので、ひらく単体では良いかもしれませんが、グループの売り上げを牽引するようなモデルにはなり得ていません。今後ひらくの事業を安定的に成長させていくためには、そういったモデルの開発を急がねばと感じています。マニュアルを見てシステムを入れれば簡単に稼働できるパッケージではなく、人の手が入ってはじめて価値が出てくるようなめんどくさいパッケージ。僕たちなりの方法で新しい領域をつくっていきたい。
このように、いま自分が関わっている領域で、どの事業がどれほどの割合で構成されているかを整理するのはとても大切です。最初に組んだものを再配分する「リバランス」をするタイミングとして、下半期に入るこの時期はちょうどよさそうです。
つぎに、「作品集」としてのポートフォリオの見直しを考えてみましょう。作品集=過去事例。僕の場合であれば、いままでこんなプロジェクトを手掛けてきました。こんな人と対談してきました。という内容をまとめたものがポートフォリオになります。
前にどこかでも書きましたが、基本、依頼をいただける仕事は過去に起因します。Aの仕事をすれば、AかA’の仕事がきます。自分がいくらBの仕事をしたいからと言って、「あの人はAのプロ」と思われている限り、Bの仕事はきません。プロデューサーや編集者が「あの人はAの仕事をしているが、実はBもいけるはずだ」と目をかけてくれることもままあるでしょうが、それは「Bができそう」と思われるだけの何かがあったからでしょう。
ひらくを主語にすると、「場と機会をつくり、うれしい時間を提供する」ことを標榜し、3つの事業と担当領域を明確化したことによって、シンプルな選書仕事は明らかに減りました。これはとても良い傾向で、ブックディレクション単体ではなく、プロジェクト全体の設計やクリエイティブディレクションをした先に本が登場することは設立当初から意識してきました。「本から始めず、本から逃げない。」ということばです。
また、僕個人としては、まちづくり系のプロジェクトができるようになってきて、幅が少し広がってきた感があります。30代があと3年半で終わるので、40代からの過ごし方も見越しながらポートフォリオを考え、これからの名刺になるようなものをつくらねばいけません。ひらくのあり方や仕事のつくりかたもその一つになればとも思っていますし、もうちょっと突飛な方向性のことをやって「すぐにはわかってもらえないこと」もやらないとなあ。面白いものや残っていくものって、やっぱりすごく「変」なので。もっと真剣にふざけないといけない。
ということで、「保有資産の組み合わせ」と「作品集」の二つを見直すことで、認知や印象を整理していきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。今日もがんばりましょう。
染谷
ーー
今週の「うれしい」
川村記念美術館で開催中の「ジョセフ・アルバースの授業」を観てきました。最近僕が気になっていた「ブラック・マウンテン・カレッジ」で彼は教鞭を取っていたそうで、関心が行動につながったことがうれしい。観るだけでなく、体験が重視された良い展示でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
