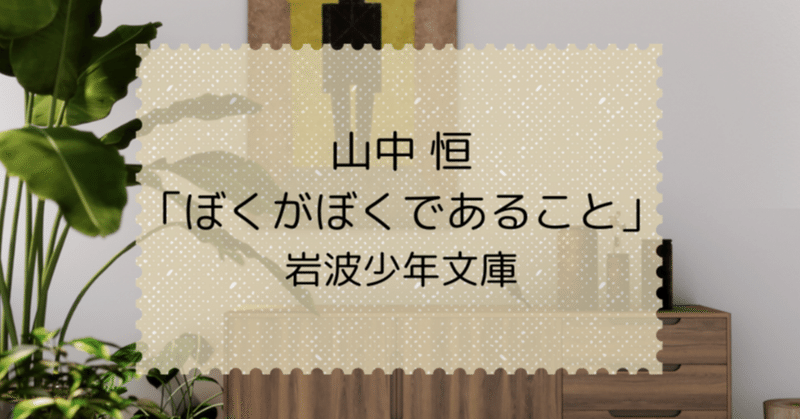
山中恒「ぼくがぼくであること」
名作揃いの岩波少年文庫です。初版は1969年なのでもう50年以上前!
岩波のこのシリーズでの第1刷は2001年ですが、私が読んだのは2013年の第13刷。現在は角川から今風の表紙になって発売されているみたいです。
尾崎豊に似たような名前の曲がありますが、このタイトルをつけるあたり作者はセンスは悪くないなと思って手に取ったという次第です。アマゾンとかで調べてみると、他にも似たようなタイトルの曲がたくさん存在するみたいですね・・・個人的になんとなく語感というかリズムがいい気がするのですが、同じように感じる人が多いのでしょうか。
そして読む直前に知ったのですが、作者の山中恒はかの有名な子供向けドラマ「あばれはっちゃく」の原作者とのこと。あばれはっちゃくのドタバタ要素に、主人公が成長していく教養小説の要素が加わった小説だろうなと思って読み始めたら、やっぱりその通りでした・・・が、思った以上にシリアスな要素もあり、しっかりドタバタもあり、楽しい読書体験となりました。また、「あっちへいっちめえ!」などモロに昭和を感じる表現とか、切手の値段が15円だったりとか、時代の流れを感じる部分もありますが、そういった部分も含めて楽しむことができました。
ストーリーは主人公の秀一という少年が息苦しい家を飛び出してから(少々危険な人物も含めて)多くの人と出会い、ピンチを乗り越え、きれいごとでは済まない大人の世界も垣間見て、葛藤を繰り返しながら自分なりの生き方を模索してくというものです。特に最後の秀一の独白にその成長ぶりが集約されていて、ちょっと感動もしてみたり。
ただこのストーリーが、そんな都合いいことあるか?と突っ込みたくなるようなところもあったり、母親の暴君ぶりが目に余るというか、そんな嫌な人間いるか?と思うほどデフォルメして書かれてあったり、気になる人は気になるところかもしれません。
考えてみたら、平成になったあたりから小説は「矛盾のない自然な人物造形であること」「無理なく自然に流れるようなストーリーであること」「物語の辻褄は最初から最後まで一貫していること」「伏線はすべて回収されること」みたいな暗黙の了解みたいなのが出来上がってきた気がしています。
小説スクールや小説の書き方みたいな本が世にあふれた結果なのかもしれません。それはそれで読みやすくていいのですが、世に流通する作品がどれもこういった暗黙のルールに従ってしまっているために、作品のスケールが年々小さくなってきているのではなかろうか、ということを個人的に感じ続けていて、どうしたものかと(私がそんなこと思ってもどうにもならなのですが)思っていたところです。
一方でこの作品では、作者の山中恒はそういった予定調和から明らかに自由であり、「抑圧する大人たちの中で成長する子供の姿を描く」という明確な目標を持って、人物造形やストーリーが多少不自然ではあるにせよ、思い通りに書くことができているなと感じました。60年代や70年代の作家に言わせるとあたりまえのことなのかもしれませんが、今の小説をどこか息苦しく感じていた私からしたら、50年以上前のこの小説がものすごく清々しく思えたのでした。
そもそも世界的に有名な文学作品を読むと、前後の辻褄が合わなかったり、登場人物の設定に明らかに無理があったり、所々で明らかに破綻しているような作品は全く珍しくなくて、それでも物語はものすごいエネルギーで爆進して、読み終わる頃には小さな矛盾や不自然な点はどうでもよくなってしまう。で、読んでいて楽しかったり、心に残ったり、「人生の糧」になるのはどちらかというのは言うまでもない。
現代の日本小説をすべて否定するわけでは全くありませんが、そういった意味でいろいろ考えさせられた読書となりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
