
2022年を振り返る! 本屋大賞ベスト30を大予想〜!
まえがき
ごきげんよう、あわいゆきです。
年末年始、いかがお過ごしでしょうか?
もしかしたら実家に顔を出しておせちをつっついたり、仕事始めまでコタツで足を伸ばしたり、のんびり過ごされるかたもいるかもしれません。あるいは初詣に行ったり、初売りのために長蛇の列を並んだり。慌ただしい日々を過ごされる方もいるのではないかと思います。
私は三が日が過ぎるまで、腰を落ち着かせる余裕のない毎日になりそうです。やるべきことがしんしん積もりすぎて、ひとつずつ確認していかないとうっかり忘れてしまいそうなものがあまりにも多すぎます。
しかし!忙しい日々の渦中にいても決して忘れてはいけないものがあるのをご存知でしょうか?
それは……もちろん!本屋大賞の一次投票〆切日(1月4日まで)です!
本屋大賞はいま現在、芥川賞&直木賞を上回るほどの注目を集める文学賞です。
そして本屋大賞のノミネート作、受賞作を投票によって決めるのは、全国の書店員さんとなっています。
私は書店員として働いていないので直接関与はできません。これはルールなので(それはそう)です。
しかし!noteで本屋大賞の記事を書いて投票を呼びかけることならできます!本屋大賞の一次投票〆切は1月4日!
というわけで今回は、本屋大賞にノミネートしそうな10作を予想する記事を書いて、本屋大賞を2022年のうちから盛り上げていこうと思います!
……いや、でも、しかし……本当にそれだけでいいのでしょうか?
本屋大賞は書店員さんが有志で結成している「本屋大賞実行委員会」によって運営されています。そして運営には「本の雑誌社」さんが全面的にバックアップと協力をしているのです。
そのため例年、4月ごろになると「本の雑誌」増刊として本屋大賞の結果を発表する雑誌が刊行されます。そこにはノミネートされた10作品だけではなく、票を1票でも集めたすべての作品がコメントと共に紹介されているのです。なかでも一次投票ベスト30に入った作品は、「一次投票全結果」としてランキング表示がされます。なのに10作品予想するだけで……私は満足してもいいのでしょうか……。
……いや、だめです。普段から文学賞の予想ばかり考えて生きているのだから、10作品で満足できるわけがありません!
というわけで今年は10作品だけでなく、どかんと投票上位に入りそうな30作品をまとめて予想し、紹介していきます!全力で30作品全的中を狙っていくぞ!
なお、本屋大賞は書店員さんが独自に好きな本を3冊選んで投票するのを一次投票、その上位10冊をすべて呼んでよかった本に投票するのを二次投票としています。
投票対象は2021年12月〜2022年11月に刊行された国内小説すべてです。単行本に限らず文庫でもライトノベルでも児童小説でもなんでもOKなので、もし書店員で働かれている方がいればぜひ!3冊選んで投票をしましょう!!!
投票システムのログインフォームはこちら!!!
おさらい
まず、本屋大賞でノミネートされやすい(一次投票で上位になりやすい)作品を簡単におさらいします。
詳しくは昨年のノミネート作予想記事に記したのですが、端的に言うと重要なのは「読んでいる人数」と「作家の人気」。全員が同じ10冊を読んで投票する二次投票と異なり、一次投票は1000冊以上ある対象作から選ばれるため、読まれている母数が多ければ多いほど必然的に投票数は多くなるのです。100人読んでいて100人が絶賛している本よりも、1000人読んでいてうち500人絶賛している本のほうが有利というわけですね。
そして投票している書店員さんの好みによっても左右されるので、一部の人気がある作家さんは毎年立て続けにノミネートされやすい傾向。実際、人気の高い知念実希人さんは『硝子の塔の殺人』で一次投票3位でした。
以上の二つを気にしながら、1位〜10位、11位〜20位、21位〜30位の予想ブロックにそれぞれわけて、作品を簡単に紹介していきます!
なお、私がすでに読んでいる作品から紹介・予想をしています。
そのため、未読作は含んでいないのでご理解いただければ幸いです。
もし「これがないのはおかしい!」という作品があればぜひ教えていただけるとうれしいです!もれなく読みます。
予想 : 1位〜10位
凪良ゆうさん『汝、星のごとく』(講談社)

『流浪の月』で本屋大賞に輝いたこともある凪良ゆうさんの最新作。
「月に一度、わたしの夫は恋人に会いにいく」と、ただならぬ予感を抱かせながらはじまるのは、瀬戸内の島で出会った二人、櫂と暁海の恋愛劇です。幸せな将来を夢見ながらも都会と田舎に分断された二人は、大人になるにつれて旧態依然な社会に呑み込まれていってしまいます。
社会から押し付けられる「正しさ」の抑圧に抗いながら、私たちはどう手を取り合って生きていけばいいのでしょうか? 愛を見失いそうになりながらも必死に生きていこうとする人々の生きざまが、丁寧かつ緻密に描かれていました。
凪良さんらしい、当事者同士の意思を重んじる「愛」を貫いた一級品の恋愛小説。おそらく今年最も多くの人に読まれたであろう新作小説でもあり、一次投票の1位はぶっちぎりでこの作品ではないかと思います。
青山美智子さん『月の立つ林で』(ポプラ社)

2年連続で本屋大賞2位となっている青山さんの最新作。
今回はそれぞれ異なる場所を生きている人々が、ポッドキャストから流される「月」にまつわるトークを聴くことで救済されていく話になっていました。
どこに立っていても見上げれば浮かんでいる「月」と、どこにいても聴けるポッドキャストがうまく結びつけられて、疎外感を抱いている登場人物たちが「一人じゃない」と前向きになれるまでの道のりにとても説得力がありました。随所に挟まれる「月」に関する豆知識も面白いものが多く、その言葉に耳を傾けているうち、しぜんと人との関わり合いに希望を見出せるようなやさしい世界観が作者の手によって広がっていきます。
感傷的でありながら感傷的になりすぎず、前を向かせてくれる力強さも備わった、読んでいて心地のよい小説です。今年も一定の人気を集めることは必至かと思います。
高瀬隼子さん『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)

第167回の芥川賞受賞作。
とある職場を題材にしたこの物語では、三人の登場人物を中心にして、あらゆる場面で形成される「空気」への違和感が明らかにされていきます。それはたとえば周りが「おいしい」と口にしているとき合わせなければいけないような空気や、強い人が弱い人のケアをしなければいけないような空気。軋轢をうまないために強いられる負担を「強い」とされる人間の側から描こうとすることで、普段感じていても言い出せなかったような違和感をひとつずつ指摘していくのです。
また、メインとなる三人が記憶に残りやすいのも特徴でした。強くあろうとする現代的な価値観を持ち、つい無理して真面目に働こうとしてしまう「自分に対するケアが不得手」な押尾さん、弱者の立場を受け入れて献身的になることで生き抜こうとする「自分に対するケアが得意」な芦川さん、弱者をコントロールすることで優位に立とうとする「ケアのいらない」二谷。人間をしっかり描けており、それの活かし方も巧みでした。
仕事、料理、恋愛、いろんな視点から現代の「空気」を切り取っており、共感を抱く読者も多いのではないでしょうか。芥川賞受賞作のなかでは読みやすい作品なのも、幅広い層からの支持を集めそうです。
結城真一郎さん『#真相をお話しします』(新潮社)

今年最も話題を集めたミステリ短編集。
特徴的なのは、ミステリの仕掛けに使われている題材がいずれも現代的であること。Youtuberやマッチングアプリ、リモート飲み会など、いまを生きている読者にとって馴染みを覚えやすいものばかり。そこから物語を展開していくので、読者も共感しやすいものとなっていました。
それでいてミステリの仕掛けも複雑すぎるほどではなく、一読してわかりやすいのも「読みやすさ」に拍車をかけています。もちろん、仕掛けが単調でつまらないなんてことはありません。
特殊設定ものが増え、年々複雑になっているミステリ作品群のなかでも、この「読みやすさ」は後述する『方舟』とあわせてある種の原点回帰として特筆されるべきでしょう。
ミステリの入門にうってつけ、幅広い層に支持を集めやすい作品なので、本屋大賞と相性はいいと思います。
夕木春央さん『方舟』(講談社)

下半期に話題を集めたミステリ長編。
とある山奥の地下建築に訪れた主人公たちが、地震によって施設に閉じ込められるところから物語は始まります。やがて地下から誰かがひとり犠牲になれば脱出できる極限の状態に追い込まれた主人公たち。地下から浸水がはじまるなか、登場人物たちの生存を賭けた駆け引きが始まります。
近年のミステリにしては珍しく、キャラクターの個性やドラマがほとんど描かれないのがこの作品の特徴。探偵としての自意識や地下建築の背後にある謎には紙面を割かず、そのぶん「ミステリとしての完成度」に全力投球をする姿勢は、「新本格」流行初期に原点回帰したような感覚があります。実際「トロッコ問題」を題材にしたミステリとしてはこれ以上ない「衝撃」を味わえるようになっており、怒涛の種明かしには目を見張ること間違いありません。
散りばめられた伏線とトリックの驚きを楽しむ、まさにミステリ小説の醍醐味を味わえる作品。事前に読んだ方の口コミ経由で広まった作品なのもあって、書店員からの支持は集めそうです。
知念実希人さん『機械仕掛けの太陽』(文藝春秋)

本屋大賞ノミネート常連となっている知念さんの最新作。
いつもはミステリを利用したエンターテイメント性重視の作品を描いている知念さんですが、今回はミステリ要素がありません。COVID-19が流行してからの2年間を医療現場に携わった当事者たちの視点から順に追っていく、ドキュメンタリー要素の強い作品となっていました。コロナ禍における医療体制の逼迫をを臨場感たっぷりに描きながら、慣れによって薄れはじめてている「コロナウイルスの恐ろしさ」を改めて示します。
また、コロナ禍における「敵」はウイルスなのだと主張が一貫しており、人間同士で連帯していくことの重要性が終始描かれるのも特徴です。これによって希望を示す人間ドラマをうみだしており、終盤にはエンターテイメント的な物語の盛り上げにも貢献していました。
現代を生きる私たちにとって、コロナウイルスは切っても切り離せないものになっています。
これまで「コロナ禍の日本」を舞台にした作品は本屋大賞にノミネートされていないのですが、この2年間を丁寧に振り返った作品として要注目です。
一穂ミチさん『光のとこにいてね』(文藝春秋)

第168回直木賞候補作。
昨年『スモールワールズ』で数々の賞を受賞し、本屋大賞にもノミネートされた一穂さんの最新作。異なる家庭に育った二人の女性、結珠と果遠の四半世紀を交互に描いていきながら、シスターフッドとも異なる名前のつけられない関係性を紡ぎ上げていきます。
離別と再会を繰り返しながら「彼女しかいない」と再実感していく感情があまりに澄み渡っていて、誰からの干渉をも跳ね除けるような眩しさを抱かせます。
そして同時に、四半世紀を丁寧に描いていくからこそ、子どもと大人の違いを示しながら「選択権」の有無について触れていく点も目をひきました。子どもの頃は母親から正確に愛情を注がれず、かといって自由にもなれなかった二人は、大人になって人生の選択権を手に入れると、今度は子ども世代にどう「選択権」を与えるか悩みます。いまこの瞬間を生きている子どもの自由意志を尊重しながら大人としてどう振る舞えばいいのか、彼女たちの成長に重ね合わせながら語られていくのです。
また、「選択権」を手に入れた二人がたどり着いた「二人だけの」ラストも見逃せません。大切な人の存在と、大切に思う気持ちの大きさを実感させてくれる小説です。直木賞候補に選ばれた勢いのまま、ここでも注目を浴びるのではないでしょうか。
呉勝浩さん『爆弾』(講談社)

第167回の直木賞候補作。
些細な傷害事件を起こして取調を受けていた謎の男「タゴサク」が、秋葉原で起きる「爆発」を予言したところから物語は始まります。爆破テロを未然に防ぐべく、警察はタゴサクと駆け引きを繰り広げながら爆破事件を未然に防ごうと苦心します。狭い取調室から始まった物語が東京中を揺るがす事件に発展していく、2022年を代表するエンタメミステリ。
物語の力を利用しながら、積極的に読者を巻き込んでいこうとする姿勢がすばらしい作品でした。物語の鍵を握るタゴサクは「爆弾」の設置されている場所をさりげない雑談から徐々に誘導していく形で、「謎」として語りかけていきます。これにより読者に油断させる隙を与えず、知らず知らずタゴサクの長台詞に引き込まれていく、没入感を味わえます。
そしてタゴサクの放つ「他人の命にランクを付ける」理屈は一見して詭弁のようで、しかし確実に登場人物を翻弄していきます。次第にその理屈は「人間が等しく有している感情なのではないか」と思わせる説得力を帯びはじめ、読者に自分の価値観を見つめさせることをナチュラルに強要します。
エンタメミステリとしての楽しさだけではなく、自らに潜んでいる「いやなところ」を物語のほうから見つめさせようとする野心にあふれていました。
ただ読者として物語を読むのではなく、物語への「参加」を促してくる、エンターテイメント性をどこまでも追求した作品です。ランキングでの高評価を見る限り、支持を集める可能性も十分考えられます。
寺地はるなさん『川のほとりに立つ者は』(双葉社)

『水を縫う』『ガラスの海を渡る舟』と2年連続で人気の作品を刊行している寺地さんの最新作。
物語は、カフェで働いている原田が病院から連絡を受けるところから始まります。恋人の松木が喧嘩沙汰を起こして怪我してしまい、意識が戻らないと聞いた原田は身元を偽って松木の面倒を見ることに。その過程で松木の部屋に行くと、彼が書いていた日記を見つけました。その日記を読み解いていくことで、原田は自らが当たり前に認識していた「普通」の脆さと向き合っていきます。
いくつものテーマを並行しながら取り扱っている本作ですが、なかでもケアをする際に当事者を「普通」の枠組みに当てはめることで個人の差異を無視して寄り添っていないか、と問いかけてくるのが特徴です。
そして恋人が「意識不明」であるため、なにも語らない松木の心情を想像して喧嘩の原因を探っていくことは、これまで当然のように思い込んできた「松木」像の打破にもつながるようになっていました。
「手を差し伸べる行為は当事者の感情を無視した一方的な偽善なのか」と葛藤する作品は多くありますが、この作品ではそれを自覚したうえで、それでも相手の幸福を願おうとします。その前向きさは固定観念的な「普通」にとらわれず、「知ろうとすること」の大切さを私たちに伝えてきます。
寺地さんは2年連続で12位、11位と惜しい順位が続いているので、今度こそ。
安壇美緒『ラブカは静かに弓を持つ』(集英社)

第25回大藪春彦賞の候補作。
あるとき、全日本音楽著作権連盟に勤めている橘は音楽教室で「演奏権」が侵害されている証拠を手に入れるため、上司からの命令で音楽教室にスパイとして潜入することになりました。
橘は任務を遂行しようとしながらも、講師をしていた浅葉との交流を経て、「この場所を潰してしまっていいのか」「みんなを裏切っていいのか」と次第に感情を揺らがせるようになっていきます。
上に記したあらすじの前半部分は、現実にあったJASRACとヤマハ音楽教室の演奏権をめぐる裁判をモデルとしています。そして本作では裁判だと一顧だにせず切り捨てられてしまう「個人」の感情に着眼点を置くことで、スパイとして潜入していた人間個人のくるしみに目を向けようとしていました。
実際、スパイとして音楽教室に潜入する橘がそこにいる人間と交流関係を築き、信頼関係とのあいだで葛藤していくドラマは読みごたえたっぷりです。上から言われて仕事をやるしかないサラリーマンの視点を通すことで、正しさと個人的な感情の狭間でもがく橘の姿も、働いているひとの多くが共感できるはず。
現実に起きた騒動をエンターテインメント小説としてうまく成り立たせた、「スパイ×音楽」という面白いキャッチコピーに恥じない物語です。刊行から時間は経っていますが、12月に入ってから受賞や候補入りの報が続いているのでその勢いで。
予想 : 11位〜20位
佐原ひかりさん『人間みたいに生きている』(朝日新聞出版)

昨年『ブラザーズ・ブラジャー』でデビューした佐原さんの最新作。
食べることを幸せだと思えず、「食事」に嫌悪感を抱いていた高校生の三橋は、ある日食べ物の匂いがしない吸血鬼の館に辿り着きます。そこで出会った泉は「血しか飲めない病気」に患っており、彼に好感を抱いた三橋は吸血鬼の館に居着くようになりました。
食事に対する違和感の表明は『おいしいごはんが食べられますように』と共通。また、「拒食症」とラベリングを貼られることに抵抗を覚えながら、同時に泉の心境を汲み取らずに「同類」として共感してしまう三橋のすがたは、後述する『N/A』のような、安易なラベリングと上辺のコミュニケーションによる被害⇄加害の表裏一体性を示します。
一方、『おいしいごはんが食べられますように』『N/A』とは異なり本作では「泉さん」がフィクション的なキャラクターとして設定されているため、よりエンターテイメント的。読みやすい作品となっているので、テーマにも取っ付きやすくなっていました。考えさせられながら、すいすいと面白く読めます。リーチの広さは見逃せません。
窪美澄さん『夜に星を放つ』(文藝春秋)

第167回直木賞の受賞作。かつて『ふがいない僕は空を見た』で本屋大賞2位にもなっている窪さんの短編集。
世界観のつながりこそないものの、収録されている短編の筋書きは最初から最後まで一貫していました。まず何らかの暗さを抱えた語り手が、救済してくれる他者と出会い、明るさを取り戻していく。そして語り手が立ち直ったとき、救済相手は語り手の前から姿を消す。
その際、救済してくれる相手にはそれぞれ星座のモチーフが割り振られており、作品ごとのテーマと密接に絡み合っています。
真新しさには欠ける短編集ですが、そのぶん基礎部分の造りが極めて丁寧。人物造形、物語の構成、リーダビリティ、いずれもよくまとまっており、小説の上手さを感じさせます。また、安易な救済や感傷に走っていないのも物語の強度を確かなものにしていました。現実をしっかり捉えた筆致になっているのも、好印象です。
原点に立ち返ったようなつくりによって、小説を読む歓びのようなものを再確認させてくれる、地力がないとできない直木賞に相応しい小説です。
小川哲さん『君のクイズ』(朝日新聞出版)

「クイズ大会の対戦相手が問題を読まれる前にクイズに正答した」謎を追いかけながら、そのクイズ大会の様子を振り返っていくエンタメミステリ。
「ゼロ文字押しでクイズに正答した」謎自体をクイズのように配置しながらクイズについてひたすら語っていくので、「クイズ小説」というこれまでになかったジャンルを確立することに成功しています。
また、謎を解かずにはいられない真実/知識への追求が人間の在り方のような哲学的問いかけにもつながっていくため、非常にスケールを感じさせる内容となっていました。
クイズ大会の結果は最初からわかっているにもかかわらず、読む手を止めることができない、魅力にあふれているエンターテイメント小説です。後述する『地図の拳』とはまったく路線の違う二作ながら、より手軽に読まれやすいほうを上に。
年森瑛さん『N/A』(文藝春秋)

第167回芥川賞の候補作。
物語の語り手となるまどかは高校2年生。安直なラベリングをする / される ことを拒み、かけがえのない唯一無二の関係性や、自分だけの言葉を探そうと懸命にもがいています。
しかし周囲の人間は、そしてまどか自身の感情はそれを許しません。安易な理解による加害と被害が表裏一体となって襲い掛かってくる現代社会を背景に、「集団」に属する / 括りつける ことで軋轢をなくして円滑な関係性を築ける気楽さと、そこに流れ着いてしまう「個」の脆弱性が描かれます。
それに巻き込まれ、逃れようとしていた「女」の型に当て嵌まってしまったまどかが直面する限界は、ままならなさを抱かせるものでした。
多様性が声高らかに叫ばれる現代で、「個」で在り続けることの限界を突きつけてくる、まさに2022年読まれるべき小説でしょう。文學界新人賞受賞作では異例ともいえるプッシュをされているのもあり、本屋大賞でも一定の票は入ると思います。
ブレイディみかこさん『両手にトカレフ』(講談社)

本屋大賞のノンフィクション大賞を受賞しているブレイディさんのフィクション(初となる小説)本。
ネグレクトを受けている14歳のミアは、図書館で「金子文子」の刑務所回顧録と出会います。「違う世界」を生きている彼女の境遇に共感を覚える一方、当事者性の有無を気にして自らが貧困とネグレクトに苦しんでいることを言い出せないミア。ところがある日、学校で同級生からラップのリリックを書いて欲しいと言われてから、ミアがいまいる「世界」は変わっていきます。
貧困やネグレクト、あるいはそれを取り巻く無理解や差別を正面から描き、まだ自立していないがゆえにどうしようもならない現実を突きつけてきます。その際に音楽や本などの芸術分野から「別の世界」を見出し、救いにつながっていくのは、この作品が一冊の本であるからこそ、一層効果的になるアプローチでしょう。
ミアが金子文子の自伝から「新しい世界」を見つけられたように、この本を読んだ誰かがくるしみから抜け出して「新しい世界」を見つけられるように物語が仕組まれていました。
ヤングアダルトに分類されそうなので票数がどこまで入るかはわかりませんが、幅広い層に読まれている小説なのは確かです。
今村夏子さん『とんこつQ&A』(講談社)

『むらさきのスカートの女』がtiktok経由で売れ行きを伸ばしてからは初となる、今村さんの単行本。
「群像」で掲載された作品をまとめて収録した短編集ですが、すっとぼけたような語り口は今作も健在。中華屋で働き始めた女性がQ&Aのマニュアルを自作して受け答えしていくうち、歪な関係性を構築していく表題作をはじめ、「おかしい」とされる他人の表面だけに触れていくことで、自らが抱える「おかしさ」を露呈していく構造が取られています。有害さをシュールな語りに落とし込んでいるので独特の味わいをうみだしており、ありがちなテーマを作者ふうに調理していく過程も見逃せません。
まさに今村夏子さんらしさ全開の、人気を集めそうな短編集です。
上橋菜穂子さん『香君』(文藝春秋)
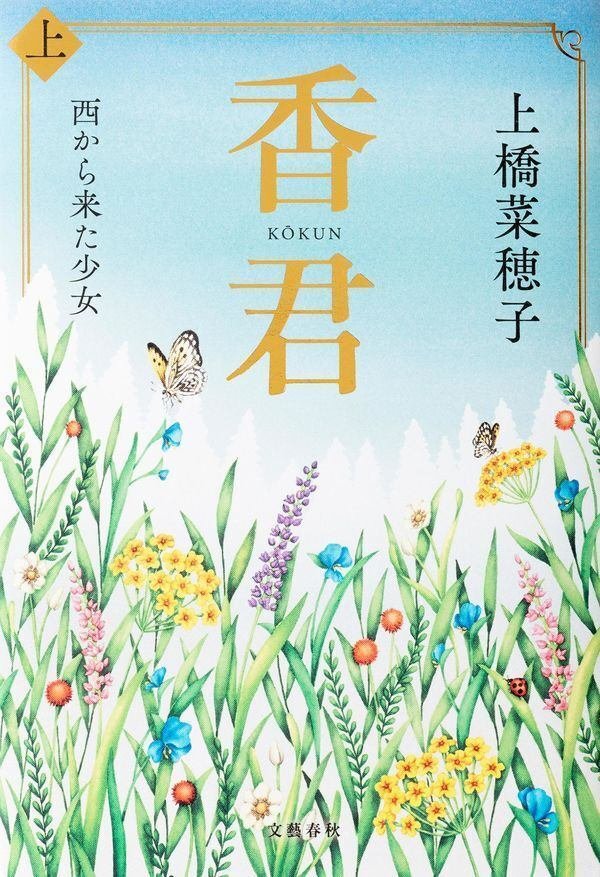
『鹿の王』で本屋大賞を受賞したこともある上橋さんの最新長編。
稲を年貢として納める⇄種籾を普及する、という関係で成立している、江戸時代における幕府基盤を連想させる大きな帝国と各地方の藩王国が舞台。その関係の根幹を成している「オアレ稲」の生態を紐解いていくことで、歴史の真実を浮かび上がらせます。
生活インフラをひとつのものに依存することの脆弱性、未曾有の事態に陥ったとき信仰に縋ろうとする人心、あるいは危機に直面したとき楽観視することで眼前の不安から逃れようとする本能。 現代情勢と明確に重ね合わせられながら紡がれていくため、コロナ禍に対する人々の意識のシミュレーション、としても興味深いです。
もちろんファンタジーとしての世界観の練り込まれ方、先の読めなさも面白く、上下巻の文量にふさわしい壮大なスケールの作品です。上橋さんのファンは書店員さんにも多いはず。
荒木あかねさん『此の世の果ての殺人』(講談社)

第68回江戸川乱歩賞の受賞作。
数ヶ月後に隕石が熊本県に衝突すると判明し、未曾有のパニックに陥った世界が舞台。
誰もいなくなった太宰府で淡々と教習所に通っていた小春は、教習車のトランクに滅多刺しの死体が詰め込まれているのを発見します。もうすぐ皆死ぬのに、なぜ殺人を犯してわざわざ隠蔽までしたのだろう? 教官のイサガワ先生とともに、その謎を解き明かそうとします。
ポストアポカリプス的な世界観、エンターテイメントとして手に汗握る展開に惹きつけられながらも、変化した世界で「どこまで日常を守れるか」を考えていくのも特徴です。
非日常な「殺人事件」と荒廃した世界を重ね合わせることで、教習所に淡々と通うことで演じてきた日常の脆さを指し示し、変化した世界でどう日常を維持していくかを問いかけていく姿勢は巧みでした。
世界が変わってしまっても、捻じ曲げるわけにはいかない倫理観や信念があるのだと、現代を生きる私たちにいま一度気づかせてくれます。今年のエンタメ系新人賞受賞作では、この作品がいちばん支持を集めそうです。
浅倉秋成さん『俺ではない炎上』(双葉社)

昨年『嘘つきな六人の大学生』で本屋大賞にノミネートされた浅倉さんの最新作。
何者かに「女子大生殺害事件」の冤罪を被せられてSNS上で大炎上した山縣が、冤罪を晴らそうとするべく逃げ惑いながら奔走するお話です。
SNS炎上への加担、刑事捜査、社会派サークルの活動など、あらゆる面を通して、「自分は悪くない」と責任転嫁する(それによって正義を正当化しようとする)感情が描かれていきます。責任の押し付け合いによって回っている醜い現代社会を浮かばせつつも、一方で責任転嫁してしまう弱さを認めて、それを少しずつ改善していこうと促す作りになっているので、決して醜いばかりではありません。
炎上に巻き込まれた男性と無理解な周囲、という構図の不快さが上回らないように、爽やかやとやさしさを取り入れているのがエンターテイメントとして絶妙なバランス感覚です。
前作同様、人間のいやな感情をとことん炙り出しながら、それでも善性を信じようとする前向きな物語でした。共感を覚えるひとも多いでしょう。
町田そのこさん『宙ごはん』(小学館)

『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞している町田さんの新作。
育ててくれている『ママ』によって育てられた子どもの宙が、産んでくれた『お母さん』と出会うことで始まる物語。どうやって愛せばいいのか、どうやって甘えればいいのかわからないまま生活をともにするようになる二人の、徐々に心を通わせていく過程が描かれます。
衝撃的なエピソードがいくつも繰り出されながら、それぞれが抱える家庭的な事情をあたたかみのある「ごはん」によって絆していくところにやさしさがありました。シングルマザーや容疑者家族が晒される周囲からの視線についても言及され、拗らせた大人たちの言動を受け止めようとする宙のすがたには、胸を締め付けられるものがあります。
これまでの作品と同様、新たな家族のかたちを必死に模索していく一冊です。『52ヘルツのクジラたち』『星を掬う』が続いてノミネートしている流れで、この作品も見過ごせません。
予想 : 21位〜30位
永井みみさん『ミシンと金魚』(集英社)

第45回すばる文学賞の受賞作。認知症を患って既に記憶も曖昧になっている老婆カケイの一人称で、彼女の辿ってきた壮絶な一生が語られます。
老婆カケイの語りは支離滅裂で、あらゆることを忘れては思い出し、その曖昧さは物語の輪郭すらも壊しかねないものです。しかしこの作品は構成を緻密に練られており、繰り返す夏からの移ろいや「みっちゃん」の存在、息子の妻が来訪するデイ・サービスに、同じ介護施設にいる人たち。それらを適切なタイミングで読者に提示していくことで物語を綺麗に縫い合わせ、先を読ませるための推進力にしています。
読んでいくうち、カケイの放つ一つひとつの言葉が手元を離れて泳いでいき、奔放に跳ね回る光景を思い浮かべずにはいられません。老いの果てにある諦観と叫びを描く、渾身の一冊。刊行から時間が経っているのがややネック。
白井智之さん『名探偵のいけにえ―人民教会殺人事件―』(新潮社)

2022年のミステリランキングで上位を席巻した多重解決ミステリ。
物語のモチーフとなっているのは実際に発生した人民寺院による集団自殺。そこから独自の解釈を加えていって、カルト宗教が支配するコミューン下における連続殺人事件を解決していきます。
多重解決を軸にしたミステリのなかでは、登場人物たちが試行錯誤してひとつの真相に辿り着くのではなく、宗教信仰による「みている世界の違い」を踏まえて複数の真相を示す点に新鮮さがあります。探偵のたどり着いたものが真実であろうと、相手の知覚する世界にとっての真実とは限りません。
多重解決に対する新しいアプローチと、カルト的な宗教に対する見識とフィクション要素の埋め込み方が光る、高評価も納得の小説です。
伊予原新さん『オオルリ流星群』(KADOKAWA)

45歳を迎えた種村が、かつての高校の同級生、山際との再会をきっかけとして太陽系を観測する天文台を建てようとするお話です。
「45歳定年制」を冒頭に掲げて時代の輝きを振り返りながら「普通」になってしまったいまを振り返る構造により、全体通して煌めきを懐かしむようなノスタルジーが漂っています。ドラッグストアと薬局の競合や中年層の引きこもりなど、時代を感じさせるトピックがいくつか積まれているのも拍車をかけていました。
そしてかつての同級生の「死」の真相にも迫っていくので、ミステリとしての読み応えも十分です。
加齢により見失ってしまったものをいま一度思い出させ、懐かしい気持ちにさせてくれる小説です。本屋大賞の主な投票層と題材は噛み合っています。
瀬尾まいこさん『掬えば手には』(講談社)

かつて『そして、バトンは渡された』で本屋大賞を受賞した瀬尾さんの新作。
他人の心を読める大学生の梨木は、バイト先で新しく入ってきた女性の常盤と知り合います。しかし梨木は、常盤の心だけが唯一読めませんでした。梨木は心の読めない相手と出会うことで、能動的に「知ろうとしていく」ようになります。
王道的な設定を活かしながら、知ろうとするだけではなく「知ってもらおうとする」ことにも重きが置かれ、それによって救い救われる関係性を構築していくのが印象的でした。
そして知る/知られるのコミュニケーションによって得られるアイデンティティは、登場人物が個別に抱えている劣等感やトラウマの回復につながっていきます。人とのつながりによって救われていくものを、確かに実感できます。
余談ですが、オムライスがとても美味しそうなので、個人的にオムライスをとても食べたくなる小説でもありました。
小川哲さん『地図と拳』(集英社)

第13回山田風太郎賞の受賞作、および第168回直木賞の候補作。
日本から満州に渡った若者・細川が、人工都市〈李家鎮〉を満州につくりあげていくことではじまる群像劇です。この〈李家鎮〉に関係する登場人物たちがいずれも魅力的で、それぞれ面白いエピソードを引っ提げながら水滸伝のように集っていくさまはエンターテイメントのスケールをどんどん膨らませていきます。
また、国を「建築」する着想のもと、個人の生きざまをミクロな視点で掘り下げながら、それら人間を「構成要素のひとつ」として小さく扱う二つの概念、〈地図と拳〉(≒国家と戦争)をマクロな視点で掘り下げていきます。
どうして私たちの国が戦争を起こしてきてしまったのか、国家が戦争を起こす原因を多角的な視点で徹底的に分析・シミュレートしていきながら、その結果を〈李家鎮〉の存亡に反映させるのです。
小説を通してひとつの都市をつくりあげるだけでなく、滅びるまでを計算して描き切る、非常にスケールの大きい作品でした。今年の重厚なエンターテイメントといえばこれ、となる人も多いはず。
宇佐見りんさん『くるまの娘』(河出書房新社)

前作『推し、燃ゆ』が本屋大賞にノミネートされた宇佐見さんの最新作。
17歳を迎えたかんこが、亡くなった祖母の葬式に参列するために父、母、弟と車中泊の旅にでます。かつての思い出をなぞるように始まった旅は、次第に家族の抱える歪さを浮き彫りにしていきました。そして加害と被害の連鎖と二つの境界線の曖昧さ、そして曖昧なまま日常に溶けていくことで可視化できなくなるままならなさを徹底的に言語化していきます。
モチーフとメタファーの扱い方が上手いのももちろん、エピソードの一つひとつから切実さが滲んでおり、光(白)と闇(黒)を交互に映すことで物語の起伏を作り出していました。そして母親や父親が一番断ち切りたい存在でありながら、一番断ち切れない存在でもあることを言葉の説明以上に描写で伝えてくるのは、小説だからできる感情の揺さぶりでしょう。
破綻しかけている家族が織りなす痛みを、光から遮られた小さな車のなかに詰め込んだとても濃い作品です。
村田沙耶香さん『信仰』(文藝春秋)

『コンビニ人間』で本屋大賞にノミネートされたこともある村田さんの新作。
さまざまな媒体から短編、エッセイを収録している短編集。
二者間における価値観の断絶を描いた物語が多く、ひとつ前の作品で対に置かれていたテーマを新たな視点で回収するようになっているので、それぞれ独立していてもひとまとまりの作品のように読めます。
テーマ自体の掘り下げも多面的かつ読者に驚きを与えるものが多く、読んでいるうちに村田さんの構築する世界観に引き摺り込まれるような感覚を味わえる一冊です。
古谷田奈月さん『フィールダー』(集英社)

「すばる」で短期集中連載されていた作品の書籍化。
出版社に勤める橘が仕事や趣味のオンラインゲームを通じて、さまざまな問題と直面していきます。そして彼に投げかけられる「問題」の数々が、私たちがいま生きている現実を揺らがせるようになっていました。児童虐待、小児性愛、ルッキズム、ソシャゲ中毒、ネット炎上と現代的なトピックだけでなく、物語中に登場するあらゆる二項対立、理念と欲望、現実と空想、マジョリティとマイノリティ、当事者と非当事者、人間とペット、大人と子ども。すべてが渦を巻いて橘と私たちを混沌に陥れます。
そして二項の関係性を複雑にする「矛盾」をすべて炙り出そうとすることで、矛盾をきたさないまま正しさの「筋を通すこと」の難しさと限界を語っていきます。
また、現代社会の先端にある問題を詰め込みまくった『フィールダー』という物語自体が「筋を通さない」構成をとっているのも見過ごせません。これによって、この『フィールダー』自体がそのまま社会の歪みの縮図として位置付けられるようになっています。
複雑なものを簡単に説明しようとしてしまうことへの抵抗も示されており、noteでは到底語りきれないほどの歪みを詰め込んだ、「矛盾」を体現する作品です。
阿部暁子さん『金環日蝕』(東京創元社)

ある日大学生の春風が、ひったくりに遭っている知り合いの老婆を偶然見つけるところから物語は始まります。春風はそこに居合わせていた高校生の錬と協力して、犯人を捜索していくことになりました。やがて手がかりを掴んでいくうち、親子関係がうみだす現代社会の問題が顔を覗かせていきます。
焦点があたるのは、親の影響を受けて育った子どもたちがたとえば特殊詐欺や貧困、性被害に直面したとき、どう「正しさ」を見失わずに生きていけるかです。「正しさ」の通用しない世界に沈まないためには、はたしてどうすればいいのでしょう?
春風が現代的な視点と考えからいわゆる「正論」を放つなか、その正論では決して救えない人たちにスポットライトが当たるので、「正しさ」は次第に複雑さを帯びていきます。
キャラクターに癖があり、コミカルな会話劇も挟まれるので読みやすい作品となっていました。だからといって軽過ぎることはなく、巧みな文章によって社会問題と真摯に向き合っていく、ミステリー要素も兼ね備えた家族小説です。口コミ経由で広がった作品なので、本屋大賞向きの印象は強いです。
住野よるさん『腹を割ったら血が出るだけさ』(双葉社)

『店長がバカすぎる』シリーズで有名な早見さんの長編。
物語を二章構成に区切りながら、母娘三代の二代目にあたる「エリカ」を中心に、母から娘に引き継がれていく鎖のように縛られた被害と加害の歴史を綴っていきます。
一章は加害性を秘めた男性の視点から、「エリカ」の造形をひたすら細かく描いていきます。男性優位社会におけるさまざまな女性搾取を通して、男性に対する絶望を抱くようになっていくエリカ。街を出ていこうとするたびに〈出られなかった〉母親に妨害をされ、芯があったはずの女性がゆるやかに人生を蹂躙されてレールを外れていく流れには切実なものがあります。
そして二章で描かれるのは、エリカが苦難のすえにようやく手に入れた根城である「団地」。社会からはぐれた人間が人生を他人のせいにしながら慰めあって堕落していくその場所で発生する事件は、実際に起きた事件をベースに綴られており、あまりに壮絶な描写で満ちていました。
そしてエリカの娘である陽向は、これまでに引き継がれてきた鎖を引きちぎろうとします。親子三代に続く生きづらさを描いた作品のなかでもストレートにメッセージが投げかけられるので、受け止めやすいのは間違いありません。
非常に重たい題材を取り扱いながら、読んだ後には清々しさと力強さを与えてくれる作品です。
まとめ
30作品を一気にばばーっと振り返っていきました。
改めて、紹介した作品を羅列していきます。
予想 : 1位〜10位
凪良ゆうさん『汝、星のごとく』(講談社)
青山美智子さん『月の立つ林で』(ポプラ社)
高瀬隼子さん『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)
結城真一郎さん『#真相をお話しします』(新潮社)
夕木春央さん『方舟』(講談社)
知念実希人さん『機械仕掛けの太陽』(文藝春秋)
一穂ミチさん『光のとこにいてね』(文藝春秋)
呉勝浩さん『爆弾』(講談社)
寺地はるなさん『川のほとりに立つ者は』(双葉社)
安壇美緒『ラブカは静かに弓を持つ』(集英社)
予想 : 11位〜20位
佐原ひかりさん『人間みたいに生きている』(朝日新聞出版)
窪美澄さん『夜に星を放つ』(文藝春秋)
小川哲さん『君のクイズ』(朝日新聞出版)
年森瑛さん『N/A』(文藝春秋)
ブレイディみかこさん『両手にトカレフ』(講談社)
今村夏子さん『とんこつQ&A』(講談社)
上橋菜穂子さん『香君』(文藝春秋)
荒木あかねさん『此の世の果ての殺人』(講談社)
浅倉秋成さん『俺ではない炎上』(双葉社)
町田そのこさん『宙ごはん』(小学館)
予想 : 21位〜30位
永井みみさん『ミシンと金魚』(集英社)
白井智之さん『名探偵のいけにえ―人民教会殺人事件―』(新潮社)
伊予原新さん『オオルリ流星群』(KADOKAWA)
瀬尾まいこさん『掬えば手には』(講談社)
小川哲さん『地図と拳』(集英社)
宇佐見りんさん『くるまの娘』(河出書房新社)
村田沙耶香さん『信仰』(文藝春秋)
古谷田奈月さん『フィールダー』(集英社)
阿部暁子さん『金環日蝕』(東京創元社)
早見和真さん『八月の母』(KADOKAWA)
また、私の手が回らずに読めなかった作品などのなかから、上位30作品に入る可能性がかなり高い作品にも触れておきます。
有力作(未読)
辻村深月さん『嘘つきジェンガ』(文藝春秋)
岩井圭也さん『生者のポエトリー』(集英社)
米澤穂信さん『本と栞の季節』(集英社)
伊坂幸太郎さん『マイクロスパイ・アンサンブル』(幻冬社)
奥田英朗さん『リバー』(集英社)
村山由佳さん『星屑』(幻冬社)
綾崎隼さん『ぼくらに嘘がひとつだけ』(文藝春秋)
そのほか注目(既読)
住野よるさん『腹を割ったら血が出るだけさ』(双葉社)
又吉直樹さん・ヨシタケシンスケさん『その本は』(ポプラ社)
原田ひ香さん『財布は踊る』(新潮社)
芦沢央さん『夜の道標』(中央公論新社)
相沢沙呼さん『invertⅡ 覗き窓の死角』(講談社)
ほかにも確認漏れしている作品はあると思うのですが、とりあえずはこの辺りで。
確実なのは『汝、星のごとく』『おいしいごはんが食べられますように』『#真相をお話しします』『方舟』、次いで『月の立つ林で』『光のとこにいてね』、漏れるかもしれないのは『爆弾』『ラブカは静かに弓を持つ』、入れ替わりがあるとするなら『機械仕掛けの太陽』『川のほとりに立つ者は』だと思います。
いずれにせよ、本屋大賞のノミネート作発表は1月の下旬です。それまで楽しみにしていましょう!
余談
ちなみに、私が仮に投票するならこの三作品にしていました。
遠野遥さん『教育』(河出書房新社)
四季大雅さん『わたしはあなたの涙になりたい』(ガガガ文庫)
年森瑛さん『N/A』(文藝春秋)
そしてTwitterにも載せた、今年のMy本屋大賞ノミネート作は以下の10作。

いずれも自信を持って勧められる作品ばかりなので、ぜひ読んでみてください。
2022年もいくつか記事を書いていきましたが、こうして目を通してくださりありがとうございました。
2023年もぜひ読んでいただけるとうれしいです。そして、文学賞に興味を持つ方が少しでも増えれば幸いです。
それでは、ごきげんよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
