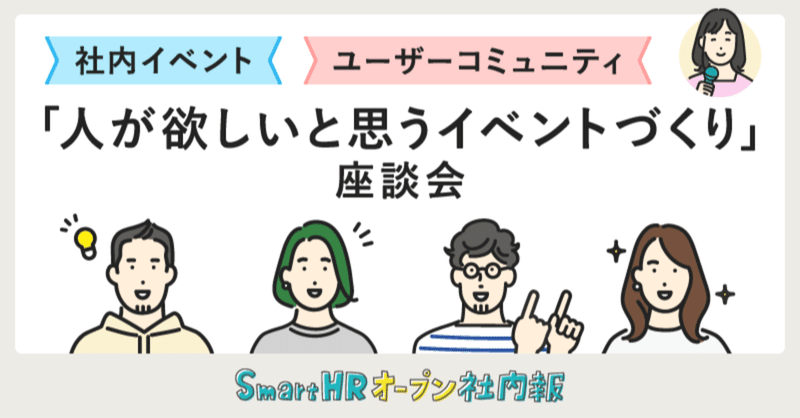
社内イベント、ユーザーコミュニティ。「人が欲しいと思うイベントづくり」座談会
こんにちは、広報の山王(さんのう / @chisa )です!
2021年8月入社でまだ入社から間もないのですが、今後全社キックオフをはじめ、さまざまな社内イベントの運営に携わることになり、「人が欲しいと思うもの」にしていくにはどうすべきかとドキドキワクワクしています。
そこで今回は、締め会や全社キックオフ、ユーザーコミュニティなど多様な切り口でイベント運営に関わっているメンバーの皆さんから学びつつ、社員の皆さんにもそのこだわりを知っていただくべく、座談会を開催しました!
登場いただいたのはこちらの方々です!ジャジャン!

写真左から、
● 人事グループ Inotaさん( @Inota ) / 月次開催の社内イベント「締め会」を担当
● 人事グループ rokumeguさん( @rokumegu ) / 半期毎に開催の社内イベント「全社キックオフ」を担当
● マーケティンググループ secchin_maruさん( @secchin_maru ) / ユーザーコミュニティ『PARK』を担当
● マーケティンググループ rikoさん( @riko ) / ユーザーコミュニティ『PARK』を担当
※ 以下Slackネームでお届けします!
ニーズや企画のアイデアはどう拾っている?
chisa:最初の質問です! イベント開催にあたって、どのように参加者ニーズや企画のアイデアを拾っていますか?
Inota【締め会担当(以下、締)】:締め会は、定期的なアンケートでニーズを拾いつつ、社内メンバーからの持ち込み企画も随時受付中です!
rokumegu【全社キックオフ担当(以下、キ)】:キックオフでも、前回実施時のアンケートを運営メンバーで確認し、次回のカイゼンに活かしたり注力したりすることを考えています。また、CxOやVP、マネージャー陣へヒアリングしつつ、一緒に企画しています。ちなみに、組織サーベイの結果も参考にして企画に反映させていますね。
chisa:ユーザーコミュニティ領域ではいかがですか?
secchin_maru【ユーザーコミュニティ担当(以下、コ)】:コミュニティでもやはりアンケートをユーザーさんに回答してもらっています。イベント後の参加者アンケートのほか、イベント前にも「どのようなテーマに興味がありますか?」と要望を集めることもあります。
riko【コ】:アンケート以外にもユーザーさんに個別ヒアリングさせていただくことも増えています。これはコミュニティイベントはもちろん、これからオンラインコミュニティなども立ち上げていくにあたって、ユーザーニーズを聞くだけでなく、私たちからも「一緒にコミュニティをつくっていきたいです!」と伝える場にしています。
secchin_maru【コ】:そのほか労務実務を担う社内労務ユニットのメンバーや、お客さまとの接点の多いカスタマーサクセス・PMMのメンバーからヒアリングすることもあります。
chisa:ユーザーヒアリングではどのようなことを聞いていますか?
riko【コ】:「コミュニティの場でどんなことを話したいですか?」と聞いています。私はもともとカスタマーサクセスだったのですが、その経験を活かし、お客さまの困りごとを、登壇コンテンツやユーザー間の交流によって課題解決につながるよう企画に落とし込んでいます。

▲ マーケティンググループ rikoさん
イベントをいかに「共創」するか?
Inota【締】:そのヒアリング対象のお客さまは、どうやってお声がけしているんですか?
riko【コ】:コミュニティイベントでの事後アンケートに「機会があれば登壇してみたいか」、「運営に携わってみたいか」などを質問しているんですが、そこで携わる意思を表明してくれた方をメインにお声がけしています。
secchin_maru【コ】:それ以外にも、関係値の深まってきたユーザーさんをカスタマーサクセスのメンバーから紹介いただいたり、導入事例の取材の場で「コミュニティに興味を持っていただいた人」を取材担当メンバーから共有してもらってアプローチしたりすることもありますね。一緒にコミュニティをつくっていくにあたって、これまで30社近いユーザーさんにヒアリングしつつ、関係構築をしてきました。
Inota【締】:運営サイドからの一方通行ではなく「一緒につくっていく」って感覚はすごく大事だと感じますね。実は締め会でも「運営に関わってみたいですか」、「ヒアリングなら協力できます」、などを聞きつつ社員を巻き込んでいくよう徐々に取り組んでいます。
chisa:コミュニティでも締め会でも「共創」がキーワードになっていますね! キックオフも同様ですか?
rokumegu【キ】:キックオフもポイントは近しいかもしれませんね。たとえば運営メンバーが自律駆動で企画案を持ち込んでくれることがあります。そのほかSlackで盛り上がっている部活のチャンネルをのぞいて、「こんなことができるんじゃないか?」とアイデアとして活かすこともありますね。
chisa:部活チャンネルなどから着想するって斬新ですね〜。
スムーズに運営し盛り上げるために心がけていることは?
chisa:続いての質問です。スムーズなイベント運営のために心がけていることはありますか?
rokumegu【キ】:キックオフは関係者が多いので、アサインの明確化とスケジュール管理に気を配っています。
具体的には、実施の2ヶ月くらい前から運営メンバーを中心に定例ミーティングを開いて全体の進捗確認をしつつ、運営内でも役割分担をして、非同期でタスクを準備を進めてもらっています。ミーティングは人数が多いと定例参加時の30分間何も話さないことも出てくるんですよね。疎外感ややりづらさが生まれないよう、関係者全員が関われることをミーティングでも運営の進行においても配慮しています。
また、運営メンバーの自律駆動なしにはできない企画なので、できるだけ盛り上がるようなミーティングにしたり、誰か1人に負担が集中しないように全体をフォローしたりしています。
secchin_maru【コ】:コミュニティイベントは、主催者だけでなく関係者や参加者みんなでつくるものです。社内の当日スタッフ向けにも事前に説明会を開催し、事前にどんな動きをしてほしいかを明示しています。
riko【コ】:現在コミュニティイベントはZoomを使ってオンラインで開催していますが、ブレイクアウトルームでのユーザー交流タイムは、労務の課題感を共有しやすいよう業界や従業員規模が近しくなるよう部屋割りを決めています。
次回以降のスムーズな運営のために、イベント規模を問わず毎回KPT(Keep・Problem・Tryの検討)を実施しています。
chisa:イベントに向けて雰囲気を盛り上げていくために、心がけていることはありますか?
Inota【締】:全社キックオフって助走期間が長いので色々難しいポイントがありそうですし、rokumeguさんにぜひ聞いてみたいです。
rokumegu【キ】:早めのタイミングにSlackやSKJ(週イチで経営会議内容をシェアする場)で全社告知をすることで、全社的な盛り上がりを当日までの間につくることがポイントだと感じますね。
あとは「大喜利文化」はSmartHRの代表的なカルチャーのひとつですよね。企画を考えるとき、みんなでワイワイ考えるのは、みんなで楽しくイベントをつくる効果的な手段だと感じます。
riko【コ】:全社キックオフはいつも祭感あってSlackもめちゃくちゃ盛りあがりますよね。以前盛り上がりすぎてスレッドが追えなくなった記憶があります(笑)。
rokumegu【キ】:実際にアンケートで「スレ内の投稿数が増えた結果、重くてスレッドが開けなくなる」という声をもらったことがありました……(笑)。その意見をふまえて、スレッドが重くならないようセッションごとにスレッドを分ける運用に変えたんです。

▲ 人事グループ rokumeguさん
トラブルシューティングで大事なことは?
chisa:皆さんはイベントでトラブルが発生した際の、トラブルシューティングで大事なことは何だと思いますか?
riko【コ】:「トラブルはつきもの」と肝に銘じて、前もって準備しておくのが大切だと思いますね。トラブルの予防策として、幹事メンバーで必ずリハーサルを実施し、テクニカルな部分やオペレーションに不備がないか、懸念点はないかを確認しています。
Inota【締】:同じく予防的な観点ですがちょっと切り口が異なることとして、「期待値が必要以上に高まりすぎない」ように気をつけています。また、トラブルが発生した際には「いま何が起きているのか」をオープンにするよう心がけています。
secchin_maru【コ】:期待値が高まりすぎないようにしている理由ってありますか?
Inota【締】:理由としては2つあります。まず「うまくいかないこと」も想定しているからです。背景として、締め会は毎月開催している頻度の高いイベントで、準備期間は約2週間。さらにメイン業務ではないため、リソース不足や準備不足になってしまうこともあります。毎回うまくいくとは限らないため、「乞うご期待」という言葉は使わないよう意識してきました。
2つめの理由は、運営体制の観点で、属人化させずいつでも誰でも運営メンバーになれるよう、ハードルがあがりすぎないようにしたいからです。
secchin_maru【コ】:なるほど〜、めちゃくちゃ共感しますね。コミュニティでも期待値コントロールを誤ると、参加者が「お客さまモード」になってしまう懸念があるんです。本来、ユーザーさんが主体となってユーザー同士の交流を生み、共に盛り上げていくのがユーザーコミュニティの「場」としての役割です。
でもこちらが一方的なおもてなしをしてしまうことで「お客さまモード」になってしまうと、「SmartHR⇔ユーザー」の場になってしまいかねないんですよね。ユーザーさんも含めて、“みんなで”コミュニティをつくっていけるよう心がけていきたいです。
chisa:いい意味で「ハードルをあげすぎない」って大事そうですね。具体的に心がけていることはありますか?
riko【コ】:「いまこういう状態です、助けてください!」「一緒にやりたいです!」と素直にユーザーさんに伝えていますよね。
secchin_maru【コ】:そうですね、一緒につくっていくという意味で「応援したくなる余白」って大事なんでしょうね。デビューしたてのアイドル的な、というか。

▲ アイドルのライブ会場をイメージしたポーズをとるsecchin_maruさん。
rokumegu【キ】:……アイドルからトラブルシューティングの話に戻しますが、当日のトラブルシューティング要員を事前にアサインするようにしています。予防策としてはコミュニティ領域でrikoさんがおっしゃっていたのと同様に、事前の配信準備やリハーサルを実施するようにしています。
secchin_maru【コ】:話を戻してくれてありがとう。なるべくスムーズにトラブルシューティングできるよう「何かが発生したとき、hogehogeについてはdaredareに聞く」とスタッフのアサイン時にあらかじめ決めています。また、オンライン参加される登壇者の方々には電波環境に気をつけてもらい、不安があれば事前に相談いただくようにしています。
これはコミュニケーション的な観点ですが、もしイベント中にエラーやトラブルがあっても、参加者の方々から応援してもらえる、応援しあえる関係性を築くことも大切だと感じます。
riko【コ】:実際に、PARKで音声トラブルが発生したときに、ユーザーさんが「頑張ってください!」「音聞こえるようになりましたよ!」とリアクションがあり、場をつないでくれたんです。参加者の皆さんにとても助けられましたね。
一同:いい話〜!
chisa:先ほど話題にあった「一緒にコミュニティを盛り上げていきたいです!」と巻き込むことの大切さにもつながる話ですね。何かトラブルがあったとしても、イベントに参加する方々と助け合って一緒に場を盛り上げていけたらとても素敵です。
Inotaさんから「どんな状況であるかをオープンに説明する」というコメントがありましたが、「いいことも、悪いこともオープンにする」というのがとてもSmartHRらしい考え方だなと感じました。Inotaさんはどうして大事だと思いますか?
Inota【締】:期待値を下げておきたい話と似ているかもしれませんが、巻き込んで当事者になってもらうのが狙いです。締め会ではトラブルシューティングに人員を割けておらず、どれくらい会が止まってしまうのかもその場ではパッとわからない分、少しでも不安を解消するためにも最低限「何が起きているのか」をなるべく具体的に伝えるようにしていますね。参加者の中に、その手の解決に詳しい人もいるかもしれないですしね。
chisa:社内イベントもコミュニティイベントも「参加者みんなでつくっていくもの」。「運営だけで完璧にするもの」ではないんですね。参加者が「お客さま感覚」ではなく、みんなで助け合ってつくっていく空気感が大事なんですね。
secchin_maru【コ】:お店でだしてくれるプロのつくるカレーだけでなく、キャンプの飯ごう炊さんでつくる少しお焦げも入ったカレーがそれと同じくらい美味しく感じるのは、みんなでつくる過程も含めての「美味しい〜」なんでしょうね。アレと同じなんだろうな。
Inota【締】:なるほど?
どうやって振り返りをして、カイゼンにつなげている?
chisa:次の質問です! どうやって振り返りをして、カイゼンにつなげていますか? あわせてKPI(Key Performance Indicator;重要業績評価指標)があれば教えてください。
Inota【締】:参加者の定性的な声をもとにカイゼンしています。毎月定期開催するという特性もあって、仰々しくならないよう「改善点」ではなく「もっとよくするには」の観点で聞いていますね。
KPIとしては、初めて参加する社員・数回参加した社員・常連社員でセグメントを分けてコミュニティを可視化し、なるべく1:1:1のバランスになるよう目指しています。
rokumegu【キ】:キックオフでは、参加者アンケートの満足度などの推移をみたり、夜の部は参加者数の推移をみています。アンケートでもらった意見のなかでも、重要度や緊急度に応じて「マストでカイゼンする」「このような声があることを認識する」などの優先順位づけをしています。
そのほか、参考までに組織サーベイの変化やSlackの当日の盛り上がり、投稿数もウォッチしています。
全社キックオフは、任意ではなく基本必須参加イベントなので、マンネリ化しないよう「毎回同じことをやるのではなく、なにか新しいチャレンジをする」などの方針は意識しているかも。
chisa:新しいチャレンジといえば……! 7月に開催した下期キックオフでは本番前の0次会的な立ち位置で社内ラジオを流したり、チーム分けをしてクイズ大会を開催したりで盛り上がったと聞きました。今後も全社キックオフを楽しんで貰えるよう、私も運営として色々挑戦していきたいです!
コミュニティ領域では、どのようにカイゼンにつなげていますか?
secchin_maru【コ】:社内イベント同様に、参加者アンケートをもとにカイゼンしています。KPIとしてみている参加者満足度はもちろん「導入事例を打診したら許諾いただけるか」「コミュニティの企画側になってみたいか」なども設問として入れています。コミュニティイベントを通じて関係値の深まったユーザーさんには、個別にアプローチして、「中の人」になってもらえるようアクションしていますね。
chisa:参加者満足度を重視されている方が多いんですね。アンケートに集まる意見には、ものによって少数の声もあると思いますし、どこまで反映させていくのかは頭を悩ませるポイントなんじゃないかと思います。皆さん、どんなステップや基準で反映の判断をしていますか?
rokumegu【キ】:必須参加という全社キックオフの前提のもと、「いやいや参加する」という空気感にならないよう、ネガティブな声を優先度高く解消するようにしています。
たとえば「夜の部は時間帯的に参加しづらい」という意見をもらったことがありました。また、お楽しみボックスも届けていますが「パパだけ、ママだけ楽しんでてずるい! とならないように、家族も楽しめるようなお楽しみボックスだと嬉しい」というアイデアをもらったこともあります。検討すべき課題として、運営メンバーと議論をしましたね。
secchin_maru【コ】:そのような声ってどこで集めているんですか?
rokumegu【キ】:今の例でいうと、同期に直接聞いたり、Slackのチャンネルでヒアリングしました。
chisa:「カイゼン内容がカイゼンされたか」はウォッチしていますか?
rokumegu【キ】:カイゼン内容はもちろん、新たな企画や伝えたかったメッセージが伝わっていたかなども含め、「アンケートのフリーコメントにキーワードが入っているか」は重視していますね。
Inota【締】:SmartHRって、社員に向けて一方的に何かを発信するのではなく、意見を拾いリアクションもウォッチしながら、会社と社員の双方でより良い会社づくりと向き合うような文化があるんだと感じます。
僕が入社したタイミングで、SmartHR社の新たなバリューとして「認識のズレを自ら埋めよう」(通称:ズレ埋め)が追加されたんですが、そのときSlackでみんな「ズレ埋め」というemojiを投稿していて瞬く間に普及していったし、経営陣もその効果を実感していたのを覚えています。実際に、今も高頻度で使われていますね。

▲ 人事グループ Inotaさん
イベント運営の「やりがい」は?
chisa:イベントって「とにかく大変!」の一言に尽きると思う一方、やりがいも大きいのではないかと思います。どんなときにやりがいを感じますか?
rokumegu【キ】:開催直前まで「ちゃんとうまくいくかな?」とすごく不安なんですよね。そんな状況で本番を迎えるので、いざ始まってSlackが盛り上がった瞬間はホッとしますね。
一同:わかる〜!!
rokumegu:共感具合がすごい(笑)。とくに印象的だったエピソードとして、「これまでに在籍した会社のキックオフがあんまり楽しくなかったんです。なんなら業務が止まるからキックオフ中は内職をしていました」という経緯のある方から、「SmartHRのキックオフが今までで一番楽しかったです!」と言ってもらえたときはとても大きなやりがいを感じましたね。Inotaさんはどうですか?
Inota【締】:狙いどおりの反応がもらえたときは嬉しいですね! 今まさに向き合っている課題として「他部署のことがあまりわからない」という声があるんですが、その解決への一環で「話しかけやすくなる」を目的とした社員出演のラジオ企画をスタートさせました。すでに数回開催していますが「●●さんの人となりがわかって、話しかけやすくなりました!」という感想がもらえて、とても嬉しかったですね。
riko【コ】:コミュニティとしては「他者の労務担当者との横のつながりが少なかったから、場があること自体が嬉しい」と言われたときや「いつも楽しんでPARK miniに参加しています!」というコメントをもらう瞬間は、すごく喜びを実感します。
secchin_maru:同じくですね。10月に年末調整をテーマにしたPARK miniを2回開催した際、「SmartHRでの年末調整が初めて」というユーザーさんが何社かいらっしゃったんです。その方々から「PARK miniを通じて先輩ユーザーさんとつながれたうえに、ノウハウも聞けて、不安だった初めての年末調整もこれで安心して臨めます!」という声をいただけたときはとても嬉しかったですね。
コミュニティを通じて、プロダクトだけではアプローチできない顧客体験の後押しをできたんだと、コミュニティイベント運営の醍醐味を感じました。

▲ マーケティンググループ secchin_maruさん
おわりに
chisa:皆さん素敵なエピソードをありがとうございます。それでは最後に、一言ずつお願いします!
Inota【締】:これからも締め会を社員の皆さんと一緒につくっていきたいです。一緒にやっていく仲間、募集中です!
riko【コ】:SmartHRはソフトウェアのベンダーであり、ユーザーさんに喜んでいただけるコアとなる接点はプロダクトです。ただ、プロダクトだけでは解決できない課題を、プロダクトとの相乗効果で解決し、さらなる満足を生み出せるのがコミュニティの強みだと感じています。「プロダクトだけでは解決できない課題をユーザーさんとともに向き合いたい」という想いのある人に、コミュニティ運営に携わることをオススメしたいです!
chisa:いい話すぎて鳥肌立ちました。ほら、見てください。
secchin_maru【コ】:ほんとだ、鳥肌たってる。rikoさんのコメントに続くと、僕らはイベント自体をつくりたいというよりは、コミュニティを通じて世の中に必要な人事・労務の情報やコミュニケーションをつくりたいって想いのもと、社会の非合理をハックしていくDNAを持った方々が集まっているというか。
Inota【締】:なんとなく翻訳すると、人事・労務にまつわる知見が共有され横のつながりを持てる『PARK』というコミュニティがあり、そのための一つの取り組みとしてイベントがあって、みんなで社会の非合理をハックするひとつのシステムでありたい、みたいな話ですかね。
secchin_maru【コ】:そう、それ! それが言いたかった。ナイスInotaさん。
rokumegu【キ】:社内イベントは「この会社に入って良かった」「この会社でやっていきたいな」という気持ちを、日常業務以外でみんなで共有しあえる数少ない機会なので、うまくいけば組織に対して大きなプラスの働きかけができると考えています 。
そういう意味でも、Inotaさんの「社員と一緒につくる」という言葉にもすごく共感します。
chisa:「誰かがやってあげる、つくってあげる」ではなく「みんなでやる、みんなでつくる」という主体的な空気感を大切にしていて、それがSmartHRらしいイベント運営の原動力になっているんだと感じました。
皆さんの熱い想いを聞けて、私も継承して「やっていき」という気持ちです! 本日はありがとうございました!
一同:ありがとうございました!

● モデレーター:chisa( @chisa )
● 執筆・編集:ふじじゅん( @fujijun )
● 撮影:たけべ ともこ( @ta_ke_be )
● 画像編集:めらぽん( @merapon )
