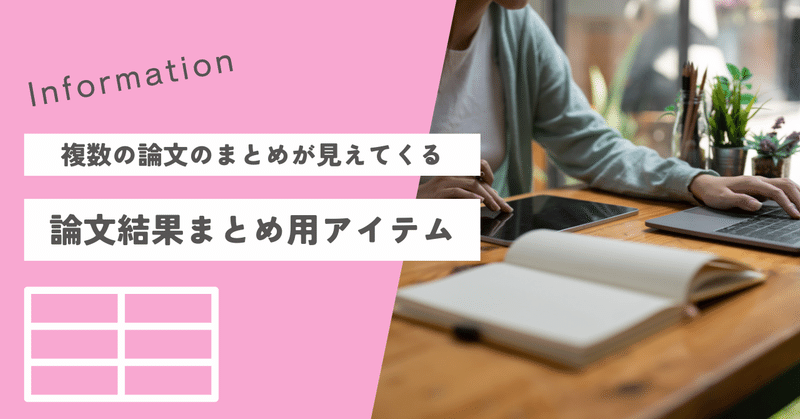
複数の論文結果をまとめるお役立ちアイテムとは?
過去に行われた研究の研究論文(先行研究)をたくさん集めて、その結果を統合して(まとめて)「その研究分野の現状を分析する」のが論文レビューです。研究を始めるときだけでなく、ガイドラインの作成のときにも、日常で活用できる食情報を発信するときにも必要な作業です。そんな「論文レビュー」の大切さと、論文収集のときに使える論文検索サイトや使えるキーワードはこちらでお伝えしましたし
たくさんのヒットした論文の中で読むべきものと読まなくてよさそうなものに分けていくときのコツはこちらで解説しています。
最後に読むべき論文を読み、結果をまとめていくことで論文レビューは完成することになりますが…。読むといっても、ただなんとなく読んでいては、何報も論文を読んでいるうちに、どの論文にどんな情報が書いてあったのか、すぐに忘れてしまいますよね。結果をまとめたいと思っても、どんな情報が得られたのか忘れてしまってはうまくまとめることができません。さて、研究者はどうやっているのか、私のやり方を紹介していきますね。
●かなりの数の論文が集まる
前回のnoteで紹介したように、論文のタイトルと抄録はPubMedという検索サイトで確認できます。この公開情報から読むべき論文は手元に集まったことになります。たとえば私が「たんぱく質とフレイルの関連を検討した研究」を実施したときには、フレイルに関係する論文を食事以外も含めてすべて収集して状況をまとめるように言われ、確か50報くらい集めたような記憶があります。食事以外の要因では、歯の状態や体の炎症の状態とフレイルの関連を検討した研究もありましたし、フレイルがどういう病態を言うのかを説明しただけの、関連の検討以外の論文も含まれていました。この色々ある論文を読み、現状でフレイルの研究はどの程度進んでいてどんな要因と関連があると言われているのか、自分がやりたい「たんぱく質とフレイルの関連の検討」と似たような研究はあるのか、あればどういうことがすでに言われているのか、といった状況を知る必要があります。
●複数の論文をエビデンステーブルに
このような複数の論文を読んで結果をまとめていくときに役に立つのが「エビデンステーブル;evidence table」です。直訳すると「根拠論文の表」ということです。自分が読んだ論文の内容を表にまとめて一覧表を作ることで、作りながら論文の内容が頭に入ってきます。
イメージとしては、論文整理術を紹介したときに、各論文の一覧表を作成するとよいとお伝えしましたよね。
そのとき作った一覧表は、論文のタイトル、著者名、雑誌名、巻ページ番号、PubMedのIDなどの「論文データ」でした。今度のエビデンステーブルの作り方も似ていて、1つの論文ごとに1行で、これらの論文情報をまず書き入れていきます。そしてさらに論文の内容を忘れないようにメモしていく列を作ります。その列に書き入れる項目というのは、たとえば実施した国、対象者の人数と特徴、食事調査の方法、主な結果、解析するときに使った他の因子(交絡因子)など、色々です。
●実際のエビデンステーブル
参考までに、私がたんぱく質とフレイルの研究を行ったときに作成したエビデンステーブルの一部を紹介します。こんな感じでした。

表の一番上の行に、書き込む情報の「項目」があります。左から見ていくとDateは読んだ日、No.は自分が読んだときに整理用に付けたID番号(詳細はこちらのnote参照)、Authorは論文の第一著者名、Yearは論文の公開年、Subjectは研究対象者の詳細(人数や人種、何かの疾患のある特別な人か、有名なコホート研究であればその研究名なども書いてます)、Designは研究の種類の名前、Frailty criteriaはフレイルの判定基準(研究ごとに色々な基準が使われているようだったので、その違いを認識したくて)、FRLSはフレイルのstatus(自分で作った略語、フレイルがその集団の何%かを示した)、Compareはメインの解析をするときにどの群とどの群を比較しているか、Assos.(association(関連))はメインの結果…、という具合です。さらに本物の表は右に続いていて、ほかには交絡因子、除外基準、備考欄などの項目もあります。
図で示されているところはすべて英語で記載されていますが、実際のエビデンステーブルは英語と日本語は入り混じっています。英語のまま抜き出す方が和訳するより速いときには英語のままで書いていましたし、後で結果を統合するときに日本語で書いてあった方がよさそうなときには日本語で書くこともありました。それぞれなんて書いてあるか、たぶん本人でないとわからないような暗号や記号も多いです。それでも自分があとで読んで分かればOK。他の人にお見せするものではないので多少雑でもOK(私の例はまさかこんな場で公開するつもりではありませんでしたので、他の人が読んでも意味が分からないことばかり書いてあると思います)。
このエビデンステーブルを作っていると、各研究がどんなふうに実施されていて、それぞれ結果はどんなことが言われているのか、だんだんと頭に入ってくるのです。
●最初から完成形を目指さない
エビデンステーブルを作り始めるときには、どの項目で一覧表を作るか迷うものです。この項目というのは、最初から決まるものではありません。論文を複数読み進めて作業していくうちに、だんだんと「この項目を抜き出しておいた方がよさそうだな」「これも比較しておきたい内容だな」と気づいて、増えていくものです。増えたらまた、一度読んだ論文をもう一度読み直して、新たに抽出することになった項目を埋めて…ということで手間はかかりますが、最初はそれぞれの論文の内容がわからないのでそうするしかありません。おかげで、どの論文にどんな内容が書いてあるか、重要な論文には何度も目を通すことになるので、繰り返し読むよい機会にはなります。
●そして現状を知る
こうして出来上がったエビデンステーブルを眺めていると、このまとめた分野の研究の現状が見えてきます。たとえば先ほどのフレイルに関する研究をまとめたエビデンステーブルの中で、食事とフレイルの関連を検討した研究だけを集めて眺めてみると、たとえば「欧米の研究ばかりで日本を含むアジア圏の研究はまだない(当時)」とか「関連を検討している栄養素はたんぱく質、ビタミンEやカロテノイドなどの抗酸化ビタミン、地中海式食など」「フレイルの判定には歩く速さや握力などの測定値を使っているものがほとんどだが質問票の回答で判定する方法もある」といった感じです。こうして現状が分かって説明できるようになってくると、自分の研究をどう進めるかが見えてきますし、頭にしっかり入るので他の人にも状況を説明しやすくなります。
●まとめ
複数の論文からその分野の研究内容を統合して現状を知りたいとき、エビデンステーブルが役立ちます。その論文の内容のうち重要なことを、ひとつの研究につき一行で、項目ごとにぬきだしてまとめていくのです。自分の頭に入るように、後で自分が見返したときに分かるように作ればよいので、略語や記号があっても自分だけが分かればだいじょうぶ。そうして作るうちに、各研究で言われていることが頭に入り、全体的に今どういう状況なのか、説明ができるようになってきます。
複数の論文結果をエビデンスとして使って食情報を発信するときにも、この作業が役立ちます。栄養業務に就いている人もぜひ参考にしてくださいね!
【メールマガジン】
信頼できる食情報かを見きわめるための10のポイントをお伝えしています。ぜひご登録ください!
https://hers-m-and-s.com/p/r/sPWrxMBU

すべての100歳が自分で食事を選び食べられる社会へ。
一生で味わう10万回の食事をよりよい食習慣作りの時間にするための
お手伝いをしていきます。
また読みにきてください。
記事がよかったら「スキ」リアクションをお願いします!
励みになります!
【食情報・健康栄養情報を見きわめるためのコツ】
この5つのステップで、信頼できる食情報・健康情報の候補を簡単に抽出できます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
