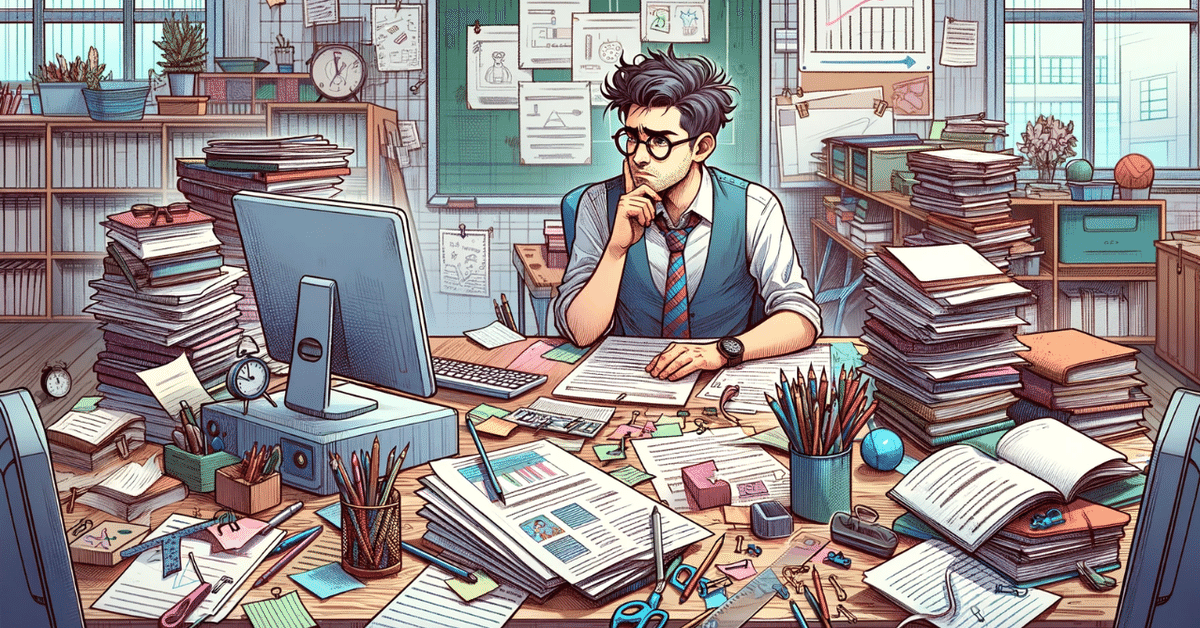
生徒向けの資料のデザインに気を遣う
Google for Education認定トレーナー/コーチの笠原です。
近日中に生徒向けに資料を出す予定があるので、本日はその資料についてあれこれと検討をしています。
どうしても教員の出す資料はデザインが…というケースが多いです。かくいう自分もあまりデザインについて勉強したことがないので、配色などは割と致命的にセンスがないです。
最近はCanvaが普及してきたおかげで、簡単に目を引くデザインを作れるようになったと感じています。
ただ…Canvaのデザインは「Canvaで作りました!」という印象がかなり強い(のと、これだけ全国で利用されているので、デザインがどうしても被るわけです…)ので、頼りきりになるのもよくないなぁと思っています。
だから、本日は少しデザインの勉強をしています。
原則を外さないようにする
自分のデザインの勉強、教科書として利用しているのは以下の一冊です。
町の本屋さんでたまたま手に取って以来、ずっと利用している一冊です。
Amazonのレビューを見ると「当たり前のことしか書いていない」という評価もあるのですが、むしろ自分のような素人にとっては「当たり前のこと」を守るためのガイドラインとして非常に重宝しています。
自分がこの本を買おうと思った理由は、第一章が「いきなり手を動かさない」というタイトルだったからです。
多くの人がプレゼンテーション資料を作るときに、とりあえず、PowerPointを開いて、テンプレートのデザインをセットして……と始めて、作業が進んでいくうちにどんどんと見づらい資料に……。
という様子をよく見ていたので「いきなり手を動かさない」というアドバイスは、非常に信頼できました。
第一章の具体的な内容は要するに「伝える相手のことを考える」「伝える目的を考える」ということなのですが、そのための着眼点や調査のノウハウは「あたりまえ」だからこそ説得力が強くありました。
こういう「原則」を外さないで資料作成に取り組むことを心がけて行くことが大切だといつも注意しながら作業するようにしています。
シンプルにしていくのも手立て
ただ、根本的にデザインを作り込めるような能力を自分は持っていないので、別の方法でも勝負する方法を考えます。
それは、シンプルな方向でデザインやプレゼンを考えていくことです。
そういう観点から非常に役に立っているのが、この本です。
学年集会などで生徒が集まっている中で話すときに、ごちゃごちゃとした資料は悪手だと思っています。
そもそも生徒の場所からは見えないし、集中力が切れやすい状況なので、せっかくのプレゼンの効果が期待できないだろうと思うのです。
学年集会などでのプレゼンを想定するならば、この本で紹介されているシンプルなスライドでシンプルにテンポ良くプレゼンしていくという方法はオンラインでなくても有効だろうと感じています。
少しの工夫をしよう
いずれにしても学校の先生が作る資料は、少しデザイン面で損しているケースが多いです。だからこそ、ちょっとした工夫をしてみるだけで、伝わり方が全然変わるだろうと思います。
「伝わるデザイン」も超有名サイトですが、これも積極的に活用していきたい情報ばかりですね。
無理のない範囲で、少しの工夫をしてみることが大切だろうと感じています。
今回も読んでいただきありがとうございました。シェア、コメント、いいね!をしてくれたら嬉しいです。
連絡先
もし、何かご相談ごとがあれば以下のリンクからお問い合わせください。
問い合わせ
https://note.com/skasahara/n/n7d251ab8d751
Twitter(X)
https://twitter.com/skshr_kokugo
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
