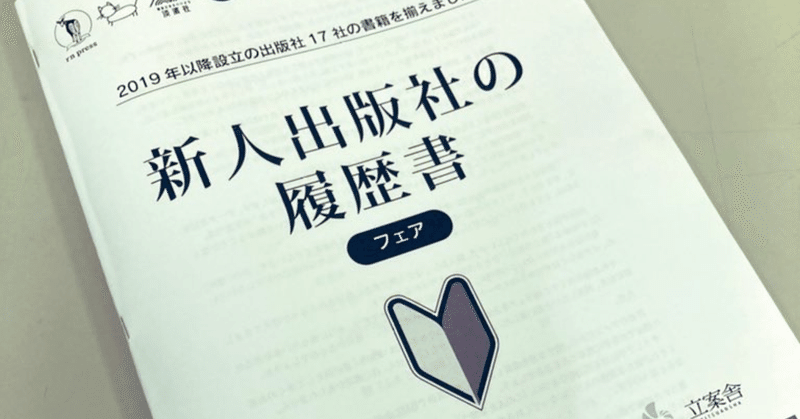
10年目のQ&A。
約1ヶ月前の第166回直木賞・芥川賞発表当日。職場のPCでニュース速報を確認した後、なんの気なしにSNSを開いてみた。受賞作決定から1時間も経っていないのに、すでに多くの書店が特設コーナーの写真をあげていた。
売場面積やスタッフの数、自分が働いているここより規模が小さい店もあるだろう。彼らが急拵えのPOPや看板の下に商品を並べ、店をあげて年に2回の権威ある文学賞を祝おうと駆け回る様子を想像した。おそらくそこには、本を売る以上の「書店員の意志」みたいなものがあるのだろうなと、おそろしく他人事のように思いながら眺めていた。
児童書と新書の売場担当である私は、基本的に文芸書の販促にはタッチしない。受賞作の発注や売場づくりは、上司でもあるベテランの担当社員が行う。
だから他人事なのだ、というのはどう考えても苦しい言い訳で、次々にアップされていく画像をスクロールしながら、その中で奮闘しているはずの彼らを羨ましく思ったりもした。
ー
今の職場で最初に担当したのは文庫と文芸書の売場だった。アルバイトとして入社し、契約社員を経て正社員になったばかりの、書店員3年目の7月。目と鼻の先にあった小さな店舗から異動してわずか1ヶ月足らずで、すぐ大仕事がやってきた。
2015年上半期の第153回直木賞・芥川賞。直木賞は東山彰良『流』、芥川賞は羽田圭介『スクラップ・アンド・ビルド』、そして羽田さんと同時受賞したのが、お笑い芸人ピース又吉直樹の『火花』だった。
発表の瞬間、私は職場ではなく、札幌駅近くの居酒屋で飲んでいた。仕事に関心がなかった訳ではないし、もちろん発表を待つ候補作家の気分を味わいたかった訳でもない。ちょうどその日、本社から【とても偉い人たち】が視察に来ていて、「夜は懇親会だからあなたも参加しなさい」と職場の上司に言われていたのだ。
【とても偉い人たち】も職場の上司も書店員である。今日が何の日か当然分かっているはずだ。普通こんな大事な日に、文芸書担当の社員を飲みに誘うだろうか。そんな考えが頭を掠めはしたが、当時の私に【とても偉い人たち】の誘いを断る勇気はなかった。今もないかもしれない。とにかく、粗相が無いよう注意を払いつつも、どの作品が受賞するのか、また発表後の対応はどうしようか、色んな意味で気が気じゃなかった。
職場から「又吉、芥川賞受賞」の一報が店長にもたらされると、中盤に差しかかっていた懇親会の場は俄然盛り上がった。それもそのはずだった。
芥川賞は直木賞と違い、候補作の時点では未刊であるのが普通だ。上半期の場合、前年11月〜5月の間に雑誌に発表された作品が選考対象となり、受賞後に書籍化されるものがほとんどである。しかし、2015年1月に『文學界』2月号に掲載されたばかりの『火花』は、翌々月の3月にはすでに単行本として発売されていた。『文學界』創刊以来初の重版がかかるほどの話題作だったから、異例の早さで書籍化されたのも当然といえば当然だった。
単行本が発売されて以来ずっと売れまくっている上に、そこに芥川賞という栄誉が乗っかればさらにブーストがかかる。
「あのさ、『火花』が芥川賞を獲りました、って今から店内放送かけさせなさいよ!」
店長のスマホの電話口に向かって【とても偉い人】の1人が叫んだ。もう1人の【とても偉い人】は、電話をかけながらどこかへ消えた。多分、文藝春秋の【とても偉い人】に祝辞を述べに行ったのだろう。
「工藤くん、こういう時はね、今からでも取次会社(問屋)に行って、『火花』よこせー!ってドアをバンバン叩くくらいの気持ちがないといけないよ!」
【店内放送かけさせ偉い人】の言葉に、「なるほど、そういうもんですか」と深くうなずきながら、夜中に顔を真っ赤にした酩酊状態の若者が会社のドアを叩きながら喚く姿を想像した。完全に不審者だ。
それでも書店員3年目にふさわしいくらいには、私は浮かれていた。心の中で「こりゃめちゃくちゃ売れるぜ!やっHooー!」と思ったし、それ以外のことは考えなかった。
実際、お笑い芸人による純文学デビュー作の芥川賞受賞は、作品の売上以上の影響をもたらした。来店客数が目に見えて増えたのだ。『火花』目当ての人がほとんどだったかも知れないが、文芸書以外の書籍の売上も急激に伸びたことには驚いた。
細かい分析なんて当時の私には出来なかった。けれど、今まで読書に興味がなかった人たちの間に「本って、もしかしたらおもしろいのかも」という空気が新たに生まれた、『火花』が「新しい読書の入口」を開いた、そう確信に近いものを感じた。なんの根拠もない分析だったが、私の感覚は正しかったと今でも勝手に思っている。
ー
長く続く出版不況に、ここ2年は感染症の影響も加わって、他業種と同様に書店経営も厳しい状況に置かれている。
自粛ムードで読書需要が伸びるという見方は間違いではなかったと思う。けれど、それが必ずしもリアル書店の売上に直結する訳ではない。家から一歩も出ずともクリックひとつで本が届く時代だ。
ネット書店とリアル書店との大きな違いの一つは、人である書店員が客と向き合って本を売っているか、そうでないかだろう。
多くの小売業が痛感しているはずだが、向き合うべき客が減り売上が下がれば、モチベーションは次第に下がっていく。無観客のスポーツ大会に似ているかも知れない。そしていずれ、その状況が当たり前なんだと思うようになる。仕方ないんだと思うようになる。モチベーションが下がればアイデアは枯渇する。店は魅力を失い、客はさらに離れていく。
書くまでもないことだが、私たちは一人としてそんなことを望んじゃいない。望んでいないのだとすれば、自分で作っちまえば良いのである。たとえ文豪じゃなくても、人にしか生み出せない「新しい読書の入口」を。
5年ほど前、出社後の社員ミーティングで当時の店長が言った。
「ネット書店に勝つ必要なんてない。これからは、ネット書店といかに共存していくか、それをみんなで考えていこう」
思えばこの時の店長のことばを聞いてから今の今まで、書店員とは何かという、ただ一つの問いについて愚直に考え続けている気がする。自分でも驚いた。なんと真面目で、おもしろみのない会社員だろう。
共存とは、別のもの同士が互いを損なわず、折り合いをつけて存在していくことを意味する。意味する、とか書くとことばのプロみたいで間違っていた時恥ずかしすぎるから念のため辞書で調べてみたら大体合っていた。良かった。
別のものなのだから、ネット書店と同じことをしなければと躍起になる必要はない。人にしか出来ないことをやればいい。
『火花』が芥川賞を受賞した後の、店の様子を想像してみる。
入口の一番目立つ場所に、『火花』だけを求めてやって来た多くの人たち。同じ本が山のように積まれた棚から、ほんの少しだけ目を逸らしてみた、かも知れない。その視線は、山の向こう側にある何千何万冊の、膨大な量の本を捉えた、かも知れない。その光景に圧倒され、やがて押し寄せてくる知識と好奇心の大洪水に飲み込まれそうになった、かも知れない。気付いたら、何をしにここへ来たのかと、本来の目的を見失っている自分がいた、かも知れない。
実際には全然違っていたとしても、そんな体験を、これから何度だってしてほしい。書店員が持つ影響力は所詮、著名な作家や、SNSで紹介した本がバズるインフルエンサーに比べれば小さいものだろう。けれど、棚の向こう側に見える驚嘆すべき風景を、売場を通して見せるのは、私たちにしかできない仕事なのだ。
ー
つい最近始まったフェアには、問いに対する私の解答をこの目で確かめてみたいという自分本位な意図も含まれている。
棚の向こう側に未知の世界が広がっているように、たった1冊の本の向こう側にも、幾多の風景を見ることができる。例えば本の奥付に記された、発行所、デザイン、校正、印刷、製本、編集者などなど。作品の中はもちろん、まえがきにもあとがきにも、帯にも表紙の裏にも書き尽くせないつくり手たちの願いや葛藤が、本の向こう側には確かに存在している。
書店にある本をすべて読破するのが無理なように、つくり手の履歴をすべて理解することはできない。
ただ想像することはできる。触れることはできる。数々の出会いと感情の集積が1冊の本を形づくっていることを、感覚的に察知することができる。それに気付いた時、私たちは「新しい読書の入口」に立っているのだと信じたい。
ー
書店員になって10年目に突入した。しかしながら未だに取次会社のドアを叩いたことはない。【とても偉い人たち】の顔が浮かぶ。この調子では一生ああいうポジションにつくことはないだろうな。
別に願ったことはないけれど。
新しいドアをせっせと拵えながら、多くの人たちによってそのドアが叩かれるのを楽しみに待つのが、私の仕事だからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
