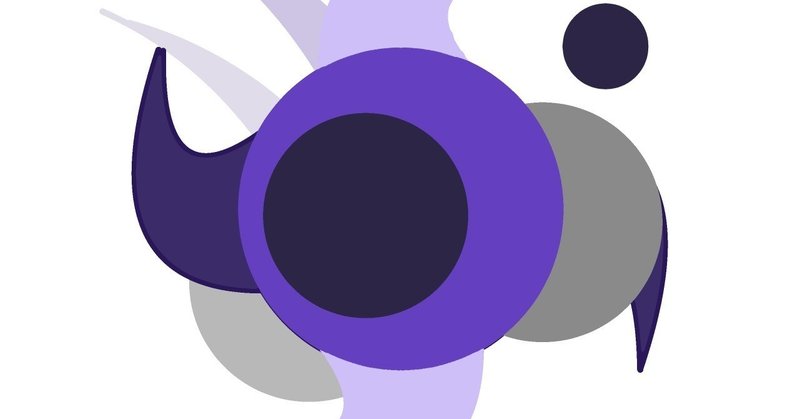
コード理論と多重ファンクション_001
@silagamisto
_20181022
§1. 背景
現代のポピュラー音楽とその周辺の音楽ジャンルにおいて使用されているのがポピュラーコード理論です。以後ポピュラーコード理論のことをコード理論と呼ぶことにします。
コード理論の「理論」とは、「体系的な説明を与えたもの」といった意味合いですから、コード理論とは「コードに対する体系的な説明を与えたもの」だと言っていいでしょう。その中に包括されるのがファンクション理論(≈ 機能和声理論)です。
ファンクション理論の表記には曖昧性があります。これはそこから演繹的に音楽を作るにあたって音楽的多様性を確保するのに必要な曖昧性です。しかし、コード理論全体やその根幹をなすファンクション理論によって様々な分析を進めていくうちに、従来のコード理論では説明不十分;あまりにも曖昧で分析として不十分と感じるコード進行に遭遇するようになってきました。
そこでこのような文章を書き、従来のコード理論よりも広範囲にアプローチできるファンクション表記を考案しました。
§2. この文章のコンセプト
コード理論の根幹をなしているファンクション理論において、大きく分けてトニック(Tonic / 以下Tと表記)、サブドミナント(Subdominant / 以下Sと表記)、ドミナント(Dominant / 以下Dと表記)の3つしかありません。しかし、ドッペルドミナントなど従来のコード理論の機能的にはそのままSだとしても、他のSと比較して明らかにD的な機能を持ったコードもあり、この辺りにいちいち例外的な名前を付けるのでは面倒なので、最初から明確に区分してしまえば楽ではないかというのがこの文章のコンセプトです。
§3. 多重ファンクション表記概要
ファンクション理論はスリーコードとその代理コードから構成されています。これをダイアトニックスケールコードと呼びます。
調性音楽やダイアトニックスケールを倍音的な関係を基軸として導くとすれば、コード; Ra k(a= m ∨ M) (R= Root) (k= tension)のルート音; rが主音に対して第n度音なのか、そしてファンクションがfなのか、また完全5度音を含む3度堆積コード (= Ra k; ¬Rdim k, ¬Raug k)なのか、それだけが重要です。
・ファンクション
まず基軸となるのはスリーコード; (Ⅰ, Ⅴ, Ⅳ) ∨ (Ⅰm, Ⅴ(∨ Ⅴm), Ⅳm)です。前者がメジャー、後者がマイナーとなりますが、どちらにおいてもその根音: r は (ⅰ, ⅴ, ⅳ)ですから、両者においてファンクションの違いはないとするのが簡潔です。ここではまだ従来のファンクションと同様の表記です。
任意のファンクションをF (= Function)を (T∨ D∨ S)とします。
・セカンドファンクション
ドッペルドミナントなどサブドミナントでありながら同時にドミナント的な機能も重ね合わせになっている状態です。それを表現するために、全体のファンクションであるRのあとに小文字でファンクションを記入します。
換言すると、任意のファンクションとその重ね合わせの機能=ファンクションをFf (f= t∨ d∨ s)と表現します。
小文字の部分をセカンドファンクションと呼びます。
例えばトニックであればTt (スリーコード)、Td (中音=ⅲをルートとするコードⅢ7; ¬Rdim k, ¬Raug k)等々。
基本的には転調前に現れることが多くなります。
Key; C→ Key; Fにおいて;CM7(Tt)→(Td)C7→F(Tt)などなど。
・ポテンシャル
さらにスリーコードか代理コードか、その中でもどの位置の機能なのかも表記できるようにします。
任意のその前にコードのポテンシャル(= potential / 位置)を書き、pFf (p= potential= b, d, u, c)と表現します。
中心軸システムから導かれるポテンシャルは4つあり、列挙すると以下のようになります。
位(= 位置/ potential) =p; 任意のポテンシャルのコード
基(= base-potential) =b; スリーコード
下(= low-potential) =l; スリーコードの短3度下の関係の代理コード
上(= high-potential) =h; スリーコードの短3度上の関係の代理コード
対(= contra-potential) =c; スリーコードと減5度の関係の代理コード
・代数ファンクション表記, 代数コード表記
代数ファンクション表記や代数コード表記は今まで使ってきたpFfといった表記のことです。
最後にpFfの後に(∨ 下に)/を書き、コードの種類を以下の小文字で入れると表記の完成です。
代数コード表記におけるkは任意のテンションノートの代数です。
任意のコードはRa kと表されます。また、4度堆積和音はR4と表します。
s= 標準コード= standard chord
pFf/s…… rをルートとするコードRa k (a= m ∨ M); (¬Rdim k, ¬Raug k)
o= 省略コード= omission chord (= パッシングディミニッシュ)
pFf/o…… rをルートとするdimコードRdim k ; (¬Ra k, ¬Raug k)
Fは(R’= r -M3)a kと同じ機能を持ち、基本的にはDとなります。
n= 非機能的コード= non-functional chord= n
pFf/n…… rをルートとする非機能的なコードRa k, R4; (¬Ra k, ¬Rdim k)
§4. 主な多重ファンクション表記
・bポテンシャル;base-potential
bTt/s…… iを基音とするコード; Ⅰa
bDd/s…… ⅴを基音とするコード; Ⅴa
bSs/s…… ⅳを基音とするコード; Ⅳa
・lポテンシャル;low-potential
lTt/s…… ⅵを基音とするコード; Ⅵm, Ⅵ(ピカルディ終止)
lTd/s…… ⅵを基音とするコード; Ⅵ7
lDt/s…… ⅲを基音とするコード; Ⅲm
lDd/s…… ⅲを基音とするコード; Ⅲ7
lSs/s…… ⅱを基音とするコード; Ⅱm
lSd/s…… ⅱを基音とするコード; Ⅱ7(ドッペルドミナント)
・uポジション;up-potential
uTt/s…… ⅲ♭を基音とするコード; Ⅲ♭(¬Ⅲ♭7)
uTd/s…… ⅲ♭を基音とするコード; Ⅲ♭7
uDs/s…… ⅶ♭を基音とするコード; Ⅶ♭t(¬Ⅶ♭7)
uDs/s…… ⅶ♭を基音とするコード; Ⅶ♭(¬Ⅶ♭7)
uDd/s…… ⅶ♭を基音とするコード; Ⅶ♭7
uSs/s…… ⅵ♭を基音とするコード; Ⅵ♭
uSd/s…… ⅱを基音とするコード; Ⅵ♭7
・cコード;contra-potentialコード
cTt/s…… Ⅳ♯を基音とするコード;Ⅳ♯m
cDt/s…… Ⅰ♯を基音とするコード; Ⅰ♯m
cDs/s…… Ⅰ♯を基音とするコード; Ⅰ♯7
cDd/s…… Ⅰ♯を基音とするコード; Ⅰ♯7
cSs/s…… ⅵ♭を基音とするコード; Ⅵ♭
cSd/s…… Ⅶを基音とするコード; Ⅵm
・oコード;dimコード, トニックとしてのⅢm
oコード;omission(= オミッション / 省略)のoがポテンシャルより後に書かれたコードです。Ⅴ7(♭9)を例にあげるとわかりやすいですが、R7(♭9)のルート省略=根音省略は(R’= r +3M)dimになります。換言すると、R'’dimは(R’’’= r -3M)7(♭9)をルート省略したものにほかなりません。
これは古典的なコード理論におけるパッシングディミニッシュに相当します。
ⅴ♯を基音とするコード; Ⅴ♯dim
bDd/o…… ⅶを基音とするコード; Ⅶdim
lDd/o…… ⅴ♯を基音とするコード; Ⅴ♯dim
uDd/o…… ⅱを基音とするコード; Ⅱdim
cDd/o…… ⅳを基音とするコード; Ⅳdim
以上となります。ありがとうございます。
by Silagamisto
@silagamisto
_20181022
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
