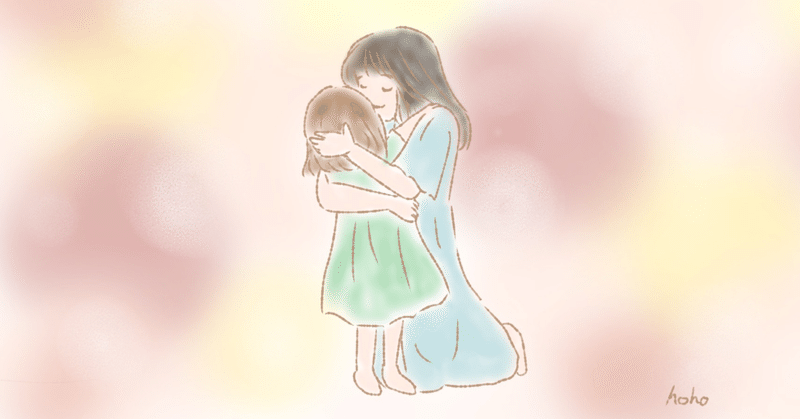
コーチの社会分析 Note【異次元少子化対策の根本ミスとは?】
はい。今日は僕のメンタル系とは別軸。「地方創生ではなく地方創世」というコピーで綴る。そんなソーシャルアントレプレナーでの視点から話をしていきたいと思います。
☆今でも忘れていない学び
その昔、メジロ牧場(現在のレイクヴィラファーム)で場長をされていた武田さんから問いかけられたことがあります。
「私たちが良い競走馬を育むために、もっとも気を付けていることは何だろうか?」
と。当時のメジロ牧場は年間わずか30頭程度の生産をする小規模な牧場でしたが、その中からメジロデュレン、メジロマックイーン、メジロライアン、メジロパーマーといったウマ娘ではおなじみの名馬達が日本競馬の頂点を席巻していました。
そんなメジロ牧場が大事にしていること。僕は「育成ですか?」と答えたのですが、武田場長からは
「惜しい。それもとても大切なんだけど、何よりも大事なことは母馬の状態なんだ」
と伝えて頂き、電撃が走ったような感覚を受けたことを未だに覚えています。母親が健康で幸せだからこそ、良い仔馬が生まれ、育つことが出来る。だから、メジロ牧場では母馬のケアや安心して暮らせる環境にこそ細心かつ最大限の努力を払っていたということです。

☆真の課題は「20代~40代の女性がおかれている状態」にある
というわけで、この国の失策は、まず前提となる課題設定を間違えているところにあります。
子供が生まれないことは「事象」でしかありません。ですので、この事象を解決する為に表面的な手当てだけをしても、根本の病巣が取り除かれることはないわけです。これは国から地方に至るまで、あるいは多くの会社でも見られる「改善というアリバイ」による先送りの病です。
で、政策においてこれらの理解がないのかといえば、そうでもないというところがより大きな問題のようにも感じます。このテーマでは、例えばワークライフバランス社の小室代表が2008年頃から政府の委員にも入り、多くの会議やメディアでもその分析と資料を提案して来られているように、こうした民間有識者のファクトやデータは共有されている筈だからです。
僕自身も以前に渋谷ヒカリエでのお話をお伺いし、深く頷きながら聴かせて頂いたことを覚えています。
☆伊藤忠商事の挑戦
ここで伊藤忠商事のケースを見てみるとしましょう(僕個人も、あるお仕事で管理職の方々への支援で関わり、その在り方からも社風や文化を感じ、投資したくなる会社というリアルの印象を持っています)。
一方で、世間的には商社といえば「ブラック」というイメージの代表格です。実際、2005年当時の伊藤忠商事における出生率は 0.6 と国内平均の半分でしかありませんでした。それが、この20年で1.97と3倍以上になり、国の平均1.3 の150%、東京都の平均1.06 の約2倍近くまで子供のいる家庭が当たり前の会社になってきたわけです。
伊藤忠商事でも2000年度の夫婦共働き9%から2021年度の共働き43%と女性の働き方は大幅に変わっています。そして、女性社員が2人の子供を産み育てる状態を作り上げていてもなお、2010年対比で生産性は5倍という驚異の上昇率を示しています。
より詳細の How to が気になる方は各個お調べ頂くとして、重要なパーツはここです。
【実際、伊藤忠は出生率を引き上げたくて働き方改革に取り組んだのではない。狙いはあくまでも、手塩にかけて育てた女性社員が長く働きやすい職場づくりだった。会社の生産性の改善や成長を追い求める上での取り組みの一つから、副次的な効果として出生率の上昇が起きたということだ】
そう。出生率を政策でKPI(Key Performance Indicator・重要業績評価指標)にしちゃいけない。それが政策の原点として大きな誤りだと感じます。
☆女性の地域外、海外への流出待ったなし
ということで、もはやおわかりかと。
「少子化」を課題にし、成果指標にしてはいけない。
これを課題にするから、そこにばら撒くことで安易に解決しようとする。
政策目的は、この国に生まれた女性のよりよい生き方、暮らし方。
その為のキャリア。ここを国として、地域としてどう育むのか。
これをいつもの「自己責任」逃げではない「実」のあるものにすること。
それは「女性活躍推進法」でやっているというかもしれないが、その結果が伊藤忠商事のように実効性を伴うような具体、結果になっているかといえばそうではないし、日本のかなり大きなエリアで「共働きでも女性が家事100%」という考え方が文化になっている調査結果すらある。僕自身も「女性は子供を生むから採用したくない」とか「出産育児のブランクが出るからゲタをはかせて男子採用」とかいう経営者やHRの言動を耳にしたこともある(つまり、知られてない法より慣習が現実になっている)。
となれば、女性はそんな地域にはいたくないし、そんな国にはいたくない。こうして都市部へ、海外へと渡る日本の女性は確実に増えているし、出生数が過去最低を重ねていくのは、この国で今の女性達が「幸せ」から遠ざかっている結果。そう受け止める真摯さも絶対に必要だ。
☆まずは隗より始めよ・と公務員からやったらと
率先躬行という言葉は心理学的にもど真ん中。なので、実効施策としては、伊藤忠モデルへの挑戦をまず行政機関がやることだと思う。
特に行政組織の採用と育成に関しては予算をかけてでもアップデートしなければいけない局面でもあるし、行政機関が伊藤忠並みに生産性5倍で機能したら、今の世の中が激変するくらいできることはたくさんある。そして、その役割の多くを女性に担ってもらうというのは、方法論として間違っていない・というかむしろ正鵠だとも考える。
法律作って指示命令してる本人が、その法律の趣旨に反してる働き方してるとかは、もはや「誰がその法守るんですか?」の心理になってしまうわけ。
女性が流出する地域、地方、エリア、国が女性の移住定住や人口を増やしたいって話を目標にすること自体が矛盾しておかしいわけ。
なので、僕は忌憚なく行政にも物申しますけど、一方でこうした行政の働き方改革には熱心な賛同者でもあるわけです。それは、誰の目にも見える役所の在り方、働き方が変われば、より早く、より浸透して、国全体に効果があるからなんです。
*というわけで、次回からのコーチング Note は「幸せ」テーマをやろうかなと思います。
ありがとうございます。頂きましたサポートは、この地域の10代、20代への未来投資をしていく一助として使わせて頂きます。良かったら、この街にもいつか遊びに来てください。
