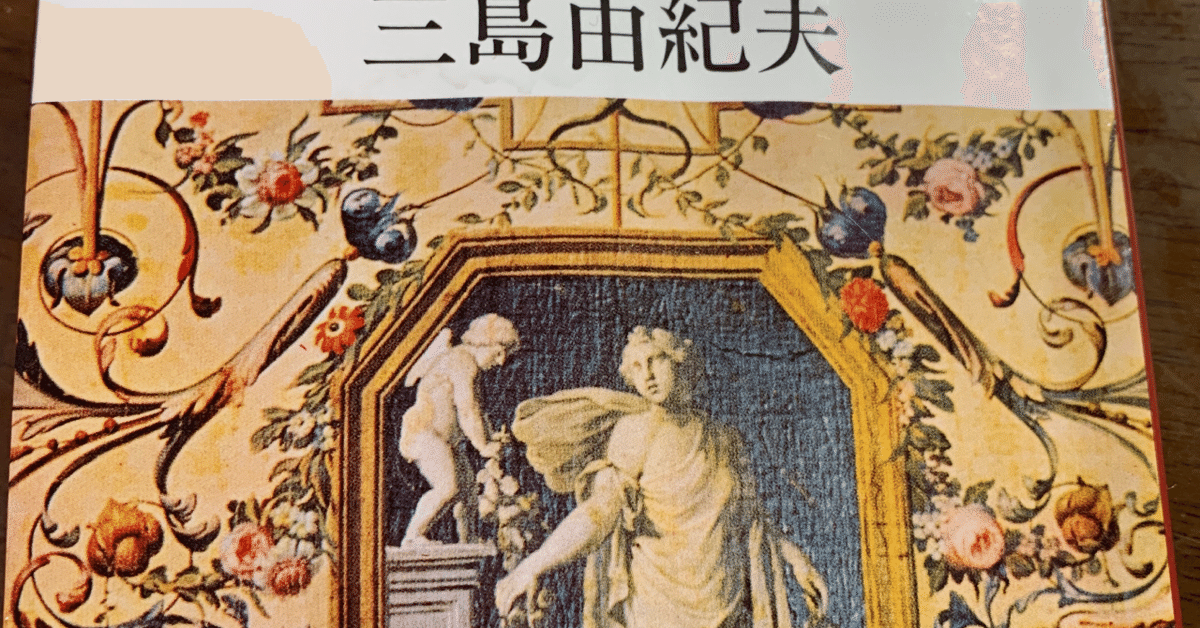
第六回読書会:三島由紀夫『文章読本』レポート
『文章読本』といえば谷崎潤一郎が有名ですが、私は谷崎の『文章読本』を本棚に入れっぱなしでほとんど読み進めることができませんでした。
そんな時たまたま、三島由紀夫の『文章読本』に出会い、パラパラとページをめくっていましたら、日本語に対する情熱、文章に対する純真な心に打たれてしまい、正直、数多ある彼の作品の中で、最も気持ちがほとばしっていると気に入ってしまいました。
とくに第一章に彼の考えがすべてまとまっています。
「文章にも、厳密に言って鑑賞用というものがあるでしょうか。昔はそういうような文章もありました。」「文章技術はもっと職人的な特殊なものとされていました。」「教育が普及して、誰でもいちおう文盲でさえなければ、文が書けるという時代になると、文章のこうした特殊な機能は薄れて、鑑賞用の文章を見る機会は、われわれの周辺には少なくなりました。」
と、にわか知識でねじ伏せてくる素人を一刀両断しているのです。
こうした現状を嘆きながら、本書の目的を、「読む側からの文章読本」に限定することで、「素人文学に対する迷いを覚ますことにもなる」と高らかに宣言しているところが面白く感じました。
もう一つ興奮したところが、読者は「レクトゥール(普通読者)」と「リズール(精読者)」の二種類に分かれるとする、フランスの批評家チボーデが定義したものを採用し、「私はこの『文章読本』を、いままでレクトゥールであったことに満足していた人を、リズールに導きたいと思ってはじめるのであります。」としているところです。
私は読むスピードが遅く、それを克服したいと考えていたのですが、むしろ「精読者」を三島は推奨していて大変心強くなったものです。
これが読書会に取り上げる決め手となったのでした。
三島の思いが詰まった第一章は「あらゆる様式の文章の面白さを認め、あらゆる様式の文章の美しさに敏感でありたいと思います。」として締めくくられています。

第二章以降は、文章、小説、戯曲、評論、翻訳、文章技巧、文章の実際、と続き、そして最終章は質疑応答形式となっています。
この著者からの一方通行でない問答形式をとるところが、三島の読者に対する歩み寄りと優しさすら感じます。
全体を通して、あらゆる文章をどのような視点で鑑賞すれば、より面白くなるかを、例文をふんだんに挙げ、丁寧に論じられています。
圧倒的な知識と深い洞察力によりつつがなく展開され、文章に対する敬愛と、さらには文章を理解しようとする読者への愛情と尊敬の念すら伝わってきます。
センセーショナルな出来事から、彼に偏ったイメージを持っていましたが、大変真面目で純粋な人だったのだと感じました。
第七章の「文章技巧 人物描写―外貌」に記された考察も秀逸です。
小説では人物の外貌が描写されていなくても、読者の想像にしたがって、その想像次第で読者の好みの外貌が描き出されるのを狙っていることに他ならない、と論じています。
その上で、映画スター誕生の仕掛けに言及し、
「もし外貌が大切ならば映画にかなうものはありますまい」「映画を見るとき、われわれは同時に、ある一定のイメージを押しつけられているという感じを否むことはできません。想像力は画面から命令され強制されて、一定の型にはめられてしまい、」「観客は映画そのものよりも俳優によって自分好みを選択して映画館へ行きます。かくして映画スター・システムが生まれるのでありますが、映画のスター・システムとは映画が観客の想像力を殺すことの必然的結果」
という部分に、なるほどと唸りました。
もちろん一概には言い切れませんが、映画スターの成り立ちの真実の一端を突いていると思います。
三島による文章というものの発見は、他にも挙げればキリがないのでここまでにしますが、本書により、文章を紡ぎそれを読んで思いを馳せるという、作家と読者による双方向からの作業は尊く、崇高であることをあらためて気づかされたのでした。
ところで皆さんがこれまでお読みになった文章の中で一番の美女は誰ですか?
私は、ドストエフスキー『白痴』のナスターシャです!
2020年1月18日土曜日開催

【参加者募集】
「週末の夜の読書会」は毎月一回開催しています。
いっしょに文学を語りませんか?参加資格は課題本の読了!
【会場情報】
plateaubooks(プラトーブックス)
〒112-0001 東京都文京区白山5-1-15 ラークヒルズ文京白山2階
都営三田線白山駅 A1出口より徒歩5分
【第6回課題本】
文学は人生を変える!色々な気付きを与えてくれる貴重な玉手箱☆自分の一部に取り入れれば、肉となり骨となり支えてくれるものです。そんな文学という世界をもっと気軽に親しんでもらおうと、読書会を開催しています。ご賛同いただけるようでしたら、ぜひサポートをお願いします!
