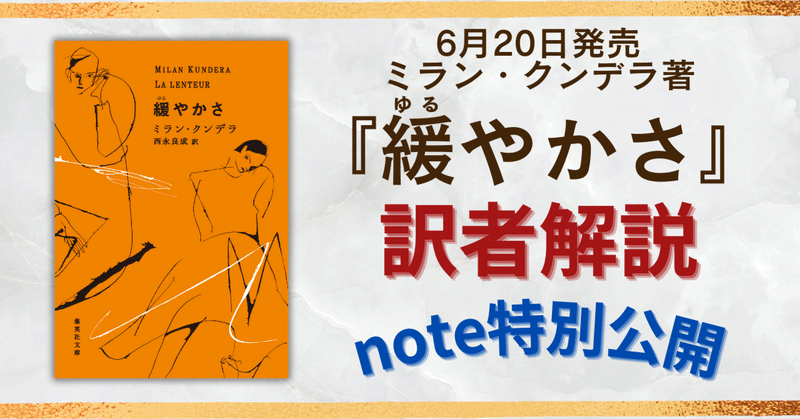
ミラン・クンデラ著『緩やかさ』訳者解説note特別公開
6月20日に集英社文庫より発売されたミラン・クンデラ著『緩やかさ』。
こちらの翻訳をご担当された西永良成先生の訳者解説が届きました。
集英社文庫noteだけで特別公開。
文庫と合わせてぜひお楽しみください!
<訳者解説>
ミラン・クンデラ(1929―2023)の小説『緩やかさ』La lenteurは、1995年1月、パリのガリマール社から出版され、たちまち彼のそれまでの作品と同様ベストセラーとなって、大いに話題になった。著者については、改めて紹介するまでもなく、現在わが国ではその主要作品がすべて日本語で読める。ただ、本作成立の背景については、いくらか解説しておくべきことがあるように思われる。
まず、この作品は著者がはじめてフランス語で書いた小説だということである。1975年、チェコからフランスに亡命したクンデラは、81年にフランス国籍を取得し、以後最期までパリで執筆活動をつづけた。同じ81年に、ディドロの小説『運命論者ジャックとその主人』をフランス語で戯曲化し、86年の評論集『小説の精神』および93年の評論集『裏切られた遺言』も最初からフランス語で書いた。ただ、チェコ時代の小説『冗談』(67年)から、パリに移ったあとの『不滅』(90年)にいたる彼の小説はすべて、原稿はチェコ語で書かれ、そのあと協力者を得て、フランス語版で発表するのが通例だった。しかし、本作の場合はちがう。彼はあえて最初からフランス語でこの小説を書いたのであり、作家としてのこの言語的な選択は、その後もつづけられた。
それにしても、よわい65をすぎ、しかも1989年の〈ビロード革命〉以降祖国での発禁処分が完全に解かれたというのに、いったいなぜ、あえて母語を捨て、元来外国語であったフランス語で書かねばならなかったのか。すでに世界的な名声を得ていた彼が、たとえ従来どおりチェコ語で書いたとしても、だれも奇異に思わず、(とくに、やっと全体主義から解放された彼の祖国では)称賛されこそすれ、非難されることはけっしてなかっただろう。だれにも、なににも強いられたわけではないこの言語的な選択の動機はどこにあったのか。いうまでもなく、これはクンデラ自身の内面の奥深くにかかわる問題であって、他人があれこれ推測してもはじまるまい。
ただ私は、彼が1994年に書いた「解放としての亡命」という文章(「すばる」95年6月号)に読者の注意を惹起しておきたいと思う。ここで彼は、チェコの女流詩人で彼と同じくパリに亡命し、フランス語で文学活動をしているヴェラ・リンハルトヴァーが、〈ビロード革命〉後のプラハでおこなった講演の趣旨に全面的な賛意を表しつつ、「未知の、あらゆる可能性に開かれて」いる「亡命作家の生活の具体的な性格」に注意を払うべきことを強調し、「人権についての紋切り型を反芻しながら、同時に個人をあくまで国民の所有物のごとくみなしつづけている」世界的――むろんこれは、かならずしもチェコ的文脈に固有のことではないのだから――風潮を批判していた。さらに、「作家は唯一の言語の囚人ではないのだ」と、チェコでチェコ人たちに言って憚らなかった彼女の言明を「解放をもたらす偉大な文句」と形容し、大いに共感していた。
この文章を読んだ当時、私はクンデラもやはり、フランス語でみずからの作家生命を全うする決意を固めたのかもしれないと、一種驚きのいりまじった感動を覚え、いまさらのように感嘆の気持ちを抱いたものだったが、じつはすでに、この時期の彼は『緩やかさ』を書きおえようとしていたのだった。書きおえようとしていたというのも、その後私は、そう彼の口から直接きいたからだが、このことはまた、この小説がフランスと同時期にヨーロッパの数カ国語で出版されたという事実によっても確認されるだろう。いずれにしろ、今度の彼の言語的な選択は、強いられた「亡命」を「解放」と「自由」の切り札に転化しようとして、20年近い年月を費やした彼にとって、ある意味では予定され、必然的なものだったといってよい。もしかすると、このような言語的な選択のうちに、「戦争と革命の世紀」と簡単に総括される20世紀の歴史の裏側で、クンデラを含む一部のすぐれた亡命作家たちが文学の自由と新たな可能性の探究のために捧げた、孤独で勇敢な犠牲の異常さをかいま見る思いがする読者もいるかもしれない。
クンデラが作家としての言語だけでなく、小説の題材をも亡命先フランスの社会に求めたことについては、『笑いと忘却の書』(79年)や『存在の耐えられない軽さ』(84年)にもすでに部分的に見られたが、前作『不滅』でははっきりとそうだった。じっさい『不滅』ではそれまで彼に貼りつけられていた「東側の反体制作家」というレッテルを多少なりとも正当化するものと思われた、チェコの歴史、社会、個人の実存は完全に関心のそとに置かれていたのである。フィリップ・ソレルスがこの小説を「フランス小説」と形容したのも無理はない。
ところでクンデラは、西側に亡命したとはいえ、かならずしも西欧社会に「同化」したのではない。彼はつねに西側の、具体的には現代フランスの社会を批判的に見ていたのであって、たとえば『笑いと忘却の書』では「解放」された性とフェミニズムの風俗を、『存在の耐えられない軽さ』では「進歩的左翼」のセンチメンタルな行動などをきわめて懐疑的に描いていた。さらに『不滅』では、高度に発達したマスメディア社会の真の支配者であり、イデー(思想)を体系的に単純なイマージュ(映像)にかえてしまう、イデオローグならぬ「イマゴローグ」たちの軽薄で虚無的な価値観を揶揄しながら、「イデオロギーからイマゴロジーへの、漸進的、全般的、地球的変化」について憂慮していた。そして、このイマゴロジー批判のテーマは、『存在の耐えられない軽さ』や『小説の精神』以来、クンデラが嘆いてやまないもうひとつのテーマ、つまり「なにがなんでも大多数の者に気に入ってもらいたいと望む」あまり、「あらゆる人々の言い分を認め、すすんで先入観に奉仕し」て、「できるだけ紋切り型に順応しよう」とする、今日のいわゆる高度消費資本主義の「キッチュ化社会」批判のテーマの延長であり、展開にほかならないことも明白である。
ここでは立ちいった解説をする余裕はないが、クンデラとは別の道を辿って、別の角度から西欧、フランス社会の「キッチュ化」と「イマゴロジー支配」を予見していた思想家に、自殺したギー・ドゥボールがいる。クンデラの盟友であるソレルスにも強い影響をあたえた彼は1967年以来、極左的なアナーキズムの立場から現代の「スペクタクル社会」を告発・批判しつづけ、一部の事情通たちによって一種教祖的な存在と目されていた。そのドゥボールは、共産主義崩壊後の世界を「集中的スペクタクル社会」(全体主義的官僚主義)と「拡散的スペクタクル社会」(民主主義的資本主義)が以後、単一の地球的な「統合的スペクタクル社会」に融合されてゆくと述べていたが、これはほぼ、共産主義社会と民主主義社会との実存的な断絶という俗説をしりぞけ、あえて「共産主義の経験は現代社会全般へのすぐれた入門だった」と断言したクンデラの述懐と重なりあう。したがって、『不滅』以来5年ぶりに発表されたクンデラの小説『緩やかさ』が、フランス的「スペクタクル社会」を題材に取りあげているのは、ある意味で当然なのである。
この小説に見られるように、「スペクタクル社会」では、たとえば飢餓に苦しむソマリアの子供のイメージと乳幼児商品宣伝用のイメージの区別さえも曖昧になり、どんな衝撃的もしくは感動的な「地球規模の歴史ニュース」もたちまち、別の「地球規模の歴史ニュース」に取って代わられるというのに、逆説的というべきか、それとも虚無的というべきか、メディア社会のスターたち――ドゥボールによれば「外見的な体験の専門家たち」、いくらかドゥボールを思わせる『緩やかさ』の登場人物ポントヴァンによれば「舞踏家たち」――が利己的に個々人のモラルの優劣を競い合う。ここで、そんなフランス的「スペクタクル社会」の代表的なスターのひとりに従うなら、それは現代社会における「スペクタクルが時代の哲学であり、〈歴史〉概念だからだ。スペクタクルはそれ自体ひとつの世界観であり、この世界観はヘーゲル主義を逆転させると言っていいほどだ。なぜなら、この世界観は『理性的なものはすべて現実的であり、現実的なものはすべて理性的である』という有名な文句から、『現実的なものはすべて見えるものであり、見えるものはすべて現実そのものである』という新しいスローガンへの移行を意味するのだからだ」(B-H・レヴィ)という。
しかしそうはいっても、「羞恥は近代、すなわち今日私たちからこっそり遠ざかりつつある個人主義の時代の鍵となる概念のひとつ」であり、作者はあくまで作品の蔭に隠れているべきだと信じるクンデラには、あるいはみずからのかつての自己規定によれば「極端に政治化された世界の罠にはまった快楽主義者」としてのクンデラには、そのような「モラル露出症」的な「スペクタクル社会」の存在は認めても、それに「同化」することなど、とうてい不可能である。そこで彼は「スペクタクル社会」を相対化、つまりユーモアによってパロディー化しつつ、以前におこなった地理的、空間的な「亡命」にくわえて、今度は時代的、時間的な「亡命」をはかろうと夢みる。そして、その亡命先としてラクロ、サドたちの18世紀フランスの快楽主義的な小説世界を、とりわけディドロの小説『運命論者ジャックとその主人』の世界を選んだのは、けっして偶然ではない。なぜならかつて、1968年にチェコがソ連軍に占領されたとき、すなわち彼自身の言葉でいえば「ロシア的な重々しい非合理性が私の国に落ちてきたとき、私は西欧近代の精神を強く呼吸したいという本能的な欲求を覚えた。そのとき私には、『運命論者ジャック』という、あの知性とユーモアと空想の饗宴のなかほど濃密に自己を集中できるところが、他のどこにもないように思えた」という経験があったからだ(戯曲『運命論者ジャックとその主人』序文、1981年)。
そんなわけでクンデラは1970年代初頭に、その10年後に「ディドロへの変奏形式のオマージュ」として発表されることになる同名の戯曲を書き出したのだが、やがて75年に亡命という事態が生じた結果、くしくもこの小説の演劇的「変奏」は、彼が直接フランス語で執筆・発表した最初の作品になった。だが、「物事はたえずその意味を変える」のであって、89年冬の〈ビロード革命〉以後、93年の『裏切られた遺言』の彼はこう書いていた。
「今日の私なら、ディドロは私にとって小説芸術の最初の時代の化身なのであり、私の劇作品は昔の小説家たちに馴染み深く、かつそれと同時に私にとって大切だったいくつかの原則の賞揚だったと言うだろう。その原則とは、(1)幸福にみちた構成の自由、(2)奔放な物語と哲学的な考察のたえざる隣接性、(3)この同じ考察の非=真面目で、皮肉で、パロディー的で、良俗に反する性格である」
このような経緯があったのであれば、彼が「唯一の言語の囚人」であることをやめ、20世紀末の「スペクタクル社会」に背をむけるために、とりあえず『緩やかさ』というディドロ風の小説、ディドロ的小説の「変奏」を書こうとしたのも、けだし当然だったというべきであろう。じっさいここには、知性とユーモアと空想の饗宴があり、構成の自在さ、奔放な物語と哲学的な考察の隣接、非=真面目で、皮肉で、パロディー的で、良俗に反する精神の自由の横溢があることを、すでに読者は確認されているにちがいない。つけくわえておけば、この小説の構成において中心的な役割をあたえられている、18世紀フランスのリベルタンの作家ヴィヴァン・ドゥノンの『明日はない』もやはり著者のかねてからの愛読書であって、そのことは『小説の精神』でも言及されていた。ここにはエピキュリアンとしてのクンデラの慎ましい理想が垣間見られる。
西永良成
※本稿は1995年刊の単行本に収録された「訳者あとがき」を加筆修正したものです。
<文庫版付記>
本書は、1995年10月に集英社から刊行されたミラン・クンデラ『緩やかさ』(La lenteur, Gallimard)を文庫化したものである。この作品の特に注目すべき点は、これまでチェコ語で書かれていた小説が初めて最初からフランス語で執筆されたことである。彼は65歳になって、しかも1989年のビロード革命以後、母語によって祖国で自由に作品を発表できる状況になったというのに、あえてこのような予想外の言語的選択を行なって見せたのである。まるで「作家は唯一の言語の囚人ではない」ことを身を以て示すように。
このような変化はしかし、必ずしも彼を取り巻く歴史的変化のみによって促されたものではない。彼は前作『不滅』によって、だいたい各章が対照的な七部構成の、彼が「ソナタ形式」と呼ぶ小説作法の極限に達したという自覚から、今度は新たなフーガ形式、つまり「より短く、絶えず出現し変奏される主題とモチーフを伴う、分割できない唯一の塊」となるような小説作法への移行を試みたのである。このフーガ形式の作品は以後、『ほんとうの自分』、『無知』、そして遺作『無意味の祝祭』まで継続されることになる。
2024年4月 西永良成
西永良成●にしなが・よしなり
1944年生まれ。東京大学フランス文学科卒。東京外国語大学名誉教授。著書に『評伝アルベール・カミュ』(白水社)、『激情と神秘:ルネ・シャールの詩と思想』(岩波書店)、『小説の思考:ミラン・クンデラの賭け』(平凡社)など。訳書にミラン・クンデラ『笑いと忘却の書』『別れのワルツ』(いずれも集英社文庫)、『邂逅:クンデラ文学・芸術論集』(河出文庫)、ヴィクトール・ユゴー『レ・ミゼラブル』(平凡社)など多数。

『緩やかさ』
↓ご購入はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
