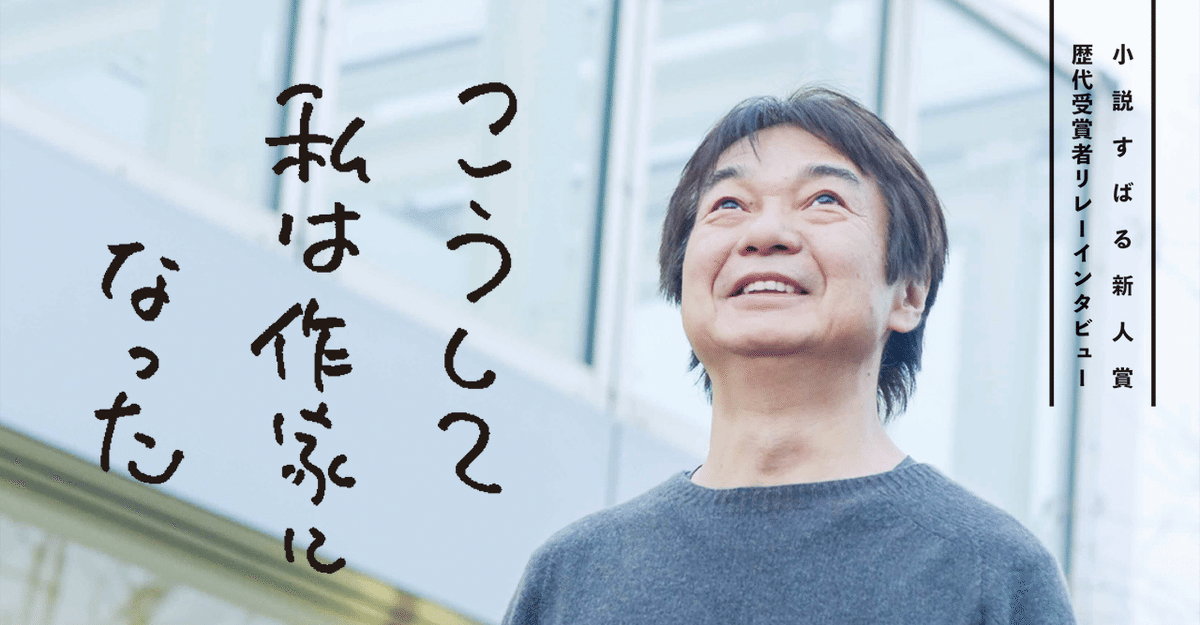
小説すばる新人賞歴代受賞者インタビュー「こうして私は作家になった」 第3回・荻原浩さん
『小説すばる』本誌上でスタートした、歴代の新人賞受賞者によるリレーインタビュー企画。
小説すばる新人賞出身の作家の方々に、創作活動の裏側から新人賞を目指す人へのアドバイスまで、幅広く語ってもらうコーナーです。
佐藤賢一さん、篠田節子さんに引き続き、第3回では荻原浩さんにご登場いただきました!
老若男女にわたる登場人物と、多彩なテーマが魅力的な荻原文学。
その根幹には、プロの小説家として荻原さんが自らに課している高いハードルがありました。
具体的な執筆上の工夫はもちろん、学ぶべきポイント満載です。
デビューまでの道のり
――デビュー当時の話からお伺いできればと思います。小説を書こうと思われたきっかけは何だったんでしょうか?
僕はもともと広告業界でコピーライターとして働いていたんです。35歳で独立してフリーで仕事をしていたんですが、これがわりとうまくいっていて。自由な時間も収入もサラリーマン時代よりずっと多いし、こんなにいい仕事はないと思って満足していました。でもそういう生活ってそうそうずっと楽しいわけじゃなくて。なんだか「一丁あがり」になっちゃった気がして、これでいいのかな、と思うようになったんです。
――当時は年齢的にはおいくつだったんでしょうか。
ちょうど39歳から40歳になる節目のタイミングでした。もう40かと思うと、ますます自分はこのままでいいのかな、と。
ちょうどその頃、仕事についても気になっていることがありまして。コピーライターとして書く広告の文章って、どこまでいっても自分のものじゃないんです。会心のコピーが書けたと思っていても、「これはちょっと好きじゃない」というクライアントのおじさんの一言で全てひっくり返ったりする。そういうのにちょっと倦んでたというか、飽き飽きしていたんですね。
――コピーライターという職業に対しては、昔から憧れがあったのですか?
いや、全然。知りもしませんでした。本当は僕、漫画家になりたかったんです(笑)。周りが就活に奔走しているのを尻目に、会社とか入りたくないなー、そうだ手塚賞に応募しよう! と。ところが下書きを何枚か描いていざペン入れとなると、これが難しくて全くやり方が分からなかった。思い付きだけですぐにできるものじゃないんだと気づきました。そこで、大学で所属していた広告研究会で文章を褒められることが多かったこともあり、やっぱり自分は文章の人間なのかも、と思って。決して文章を書くのが好きというわけではなかったんですけど、ま、コピーライターかなと。
――コピーライターとして働き始めてから、いつか小説を書いてみたいという気持ちはお持ちだったんですか?
それもなかったですね。本を読むのは好きだったんですけど。人様の本を読んでこれはちょっとねー、みたいな批評をする嫌な読者でした。小説を書き始めた理由にさらに一つ付け加えると、こんなことをしていたら俺は一生「自分ならこうするのに」って言ってる嫌なやつになるな、と。それが嫌で自分に「やってみなさい」と言ってみたんです。
――そして初めて書いた『オロロ畑でつかまえて』で小説すばる新人賞を受賞、晴れてデビューされたわけですが、応募作はスムーズに仕上がったのでしょうか?
長年一行や二行のコピーばかり書いていたので、長く書くのがびっくりするくらい難しかったです。「この『てにをは』は大丈夫なんだろうか」とか、いちいち立ち止まって悩んでしまう。最初の数ページをすごい時間をかけて書いた挙句、そこから先が全然進まないんです。「だめだ俺は、自分には向いてないや」とほっぽりだし、「でもやっぱりせっかくだし」と思ってフロッピーを取り出す、その繰り返しでした。そうこうするうちに40歳になっちゃって、なんだかんだで100枚くらいまで書けたんです。そこでようやく、「これ最後までいけるかな、いってみよう!」という気持ちになりました。
――応募先に小説すばる新人賞を選んだ理由は?
ちょうどその頃、目標設定をしようと思って公募ガイドを立ち読みしたんです。ところが当時はミステリの全盛期で、長編のノンジャンルの賞がなかなかない。見た限り、新潮新人賞と小説すばる新人賞、その二つだけだったんです。そこでこれ以上自分を甘やかしちゃいかんと思い、締め切りが近い小説すばる新人賞に狙いを定めました。そこからは結構本気で燃えまして。当時はもう結婚していて子供もいたんですが、「ちょっと1、2か月家庭を放棄させていただきます」と家族に宣言しました。仕事場に泊まり込んで家には帰ったり帰らなかったり、帰っても寝るだけ、という生活を送っていましたね。家族の理解があったのがありがたかったです。今でも頭が上がらない。
――初めから「ユーモア小説でいこう」というお考えはあったんですか?
いこうもなにも、何も分からなかったんですよ。こういうストーリーでこういう話でこういう人がでてきて、っていうのをとりあえず書いてみた。だからユーモア小説とか、そういうことは全く考えていなかったですね。退屈だろうから、ここでちょっとおもしろいことを言わせてみよう、というくらいで。ミステリでもないし殺人も起きないし、ものすごいドラマチックな事件が起きるわけでもないから、何かしないと誰も読んでくれないだろう、と。最終候補になって担当編集の人が会いに来て、「いいですねー、最近こういうユーモア小説みたいのが少ないから」って言われて初めて「あ、これはユーモア小説って言うんだ」と。びっくりしました(笑)。
第10回小説すばる新人賞受賞作
『オロロ畑でつかまえて』
集英社文庫 本体460円+税
デビュー後の日々
――デビュー後はどのような日々を送ったのでしょうか。
最初の頃は小説家になるつもりはなかったんです。「小説も書ける」というのを看板にしてコピーライターを続けていこうと思っていた。事務所に一冊だけ飾って「あ、これ? 実は小説書いたことがありましてね~」みたいな(笑)。でも受賞すると二作目を依頼されるでしょう。そうなってくるとやっぱりもう少し書いてみたいし、やってみようかな、と。
――二作目の執筆については、どうやって進められましたか?
実は、最初から構想が膨らんでいたんです。if歴史物で「もし戦後日本が朝鮮半島のように分断されていたらどうなるか」。政治的な風刺にもできるし、これはおもしろいだろうなと思っていました。毛沢東語録を読んだり、色々調べたりしてしっかり準備していたんです。そんなある日、書店に行ったら、矢作俊彦さんの『あ・じゃ・ぱん!』が刊行されていて。「あ、矢作さん新しいの書いたんだ! 買おう!」と思ってよく見たら、なんとそれが僕が考えていたのと全く同じ題材だった。ここまでかぶるかっていうくらい。ああもうだめだ、書けない、となっていた時に、当時の単行本の編集の人が「オロロ畑の続編でもいいんだよ」と言ってくれた。「あれに続編?」と思う一方で「そうか、その手があったか」と。一作目を書く時にやくざの話にしようか迷っていたんですけど、続編としてそちらをやってみようと書き始めたのが『なかよし小鳩組』です。だから、最初から連作を狙っていたわけではなくて、編集者の甘い言葉に縋りついた結果の二作目ですね。
『なかよし小鳩組』
集英社文庫 本体670円+税
具体的な執筆方法について
――長い作品を書くコツが分かってきたとおっしゃっていましたが、具体的にはどういうことなんでしょう?
分かってきたと言っても本当には分かっていないのかもしれませんが(笑)。最初に躓いたときは、ずっと頭から書くことにこだわっていたんです。もちろんそうするのが普通かもしれないけれど、自分の場合はうまくいかない原因はそこにあるかも、と。そこで「あ、このシーンおもしろそうだから先に書いてみよう」というふうに、バラバラに書いてみたんです。そしてそれを最後につなげる。『なかよし小鳩組』はそういうやり方で書きました。そして実は今も変わらずそのやり方を用いています(笑)。一応頭から書きはしますけど、ちょっと詰まると先へ先へ、と。
――先の場面はぱっと思い浮かぶものなんですか?
こういうお話でこういう時にこんな資料や取材が必要、というメモを最初に書いておくんです。ある程度本気で。そうすると場面の断片が浮かんでくるんですよね。
あと、原稿はすぐに編集者に渡さずに、引き出しの中かどこかにつっこんで醸成させろって言いますけど、そのとおりで、パッて書いてポイッと出すと、自分に酔った感じのままになってしまう。場面の断片なんかも、しばらく経って見てみると、これはちょっと違うかな、となったりもしますね。
――ラストシーンからひらめくことも?
最近はそうでもないですけど、途中まではラストシーンが最初に決まってから全体を書き始めることがほとんどでした。目的地が決まってさえいれば、途中何かあってもそこに行き着けばいいっていう安心感がある。『明日の記憶』なんかもラストシーンが最初に決まっていましたね。『海の見える理髪店』の表題作も、最後の言葉が初めから決まっていた。この言葉で最後締めればなんとかなる、と。そのラストを迎えるためにじっちゃんがぐちゃぐちゃ喋っていくんです(笑)。
『明日の記憶』
光文社文庫 本体619円+税
――荻原さんは短編の名手とも呼ばれますが、短編を書く時に気を付けていることはありますか?
僕は最初長いものが書けなかったくせに、長編に慣れると今度は短編が難しくなりました。あれもこれもと欲張るうちに、短編じゃなくなっちゃうんです。長編は山あり谷ありで、何度もそれを繰り返していくんですけど、短編というのは一つの山に登って下りる感じで、あまり欲張りすぎない方がいい。ワンシーンだけで書けるんです。
最初は原稿の枚数を見て「こんなにたくさん書けない」と思うんですけど、いざ書き始めると、びっくりするくらい足りないと感じるものなんです。話を膨らませるよりも削った方がいいのは確かですね。文章的にも、あれもこれも入れたいというよりは、どれがいらないか? という自問自答が必要かもしれない。「これはなくても意味は通じるよね」っていうところまで考えてみるとよいと思います。でも逆にそこまでいくと「これ、無駄だけどあってもいいよね」っていうのも、特にセリフなんかではよくあって。ルールはないのでその辺は難しいです。無駄な言葉を連ねるっていう個性もあるかもしれないし。
『海の見える理髪店』
集英社文庫 本体580円+税
第155回直木賞受賞作
――セリフはどうやって書かれているんですか?
わりと考えずに書いています。考えすぎると理屈っぽくなってしまうので。偉そうなことを言うと、セリフでは説明しない方がいいんです。セリフはセリフで、そこに情報を詰め込みすぎてはいけない。もっと言うと、地の文でも説明をしすぎない方がいい。一番いいのは何も説明をせず、それでいて「ああ、わかる」ってなる描写。難しいんですけどね。まず第一歩としては、セリフで説明をしすぎないこと。ありますよね、昔のドラマなんかで「げ、お前は○○の□□のなんとかだな!」みたいな(笑)。ああいうのにならないように気を付けた方がいいです。
――たしかに、新人賞の応募作を読むと説明の多さが目につくことがあります。
最初は不安なんですよ。説明しないと分かってもらえないんじゃないかって。だからもう「大丈夫だよ、気にせずに書きなさい」と言いたい(笑)。
――タイトルはどうやってつけるのでしょうか?
最初から決める場合もあるし、最後まで全然決まらない場合もある。タイトルからはいっちゃうこともありますね。『金魚姫』とかは最初から決まっていました。『人魚姫』をもじっただけだから。一方の『オロロ畑でつかまえて』はもともとは全然違うタイトルで、『牛穴村新発売キャンペーン』だったんです。自分でもさすがにないな、と思っていて(笑)。選考委員の先生たちにもタイトルがダメって言われて、コピーライターらしくばーっと代わりの案を考えてファックスで送ったんです。そしたら「『オロロ畑でつかまえて』がおもしろいです」と言われ、「ええ~?!」となりました。デビュー作って必ず著者のプロフィールに入るでしょ。デビュー後何を書いても「あ、オロロ畑ね」となるんです(笑)。どんなハードなものを書いてもオロロ畑。ちょっとまずかったかな、という気がしています。だからデビュー作のタイトルは大事。こだわってつけた方がいいですね(笑)。
登場人物を「放牧」する
――登場人物はどうやって作り上げるんですか?
書いているうちにぼんやりつかめてくるんです。本当はダメなんでしょうけど、どの登場人物も連載の3回目くらいで「あ、こいつはこういう人間なのか」と分かってくる。書きはじめのころは探り探りですね。
――登場人物にモデルはいるんですか?
モデルはいません、というか誰かをモデルにするのが嫌なんです。現実に負けるのが悔しいんですよね。誰とは言わないけど、モデルがいるのはデビュー作くらい。あの時は本当に分からなくて、手探りでやっていたから。でも二作目、三作目からは一切モデルはいないです。自分で考えた方がおもしろいですしね。
――よいキャラクターを作る秘訣はありますか?
とにかく、こういう人、と決めてしまって、著者としての自分はそこには入れないようにしています。登場人物を放牧状態にするというか。最初はちょっと難しいんだけど、そのうちその人のことがだんだん分かってくる。そうしたら、物語を作っている自分の都合ではこういうことを言ってほしいんだけど、この人は言わないだろうなとなったり。あまりに言うことを聞かなくて、思わぬ方向に話がずれていくこともあるんですけど、意外とその方がおもしろかったりもしますよね。自分でちまちまやっていても、想定内のものしか出てこないので。
――扱いにくいキャラクターはいますか?
若い女性かな。彼女らが何をしゃべるか分からなくて。やっぱり自分から遠い立場の人が難しいですね。それを知りたくて書く、みたいなところもあるかもしれません。
最初の頃は当時の担当編集者に「荻原さん、女の人を書くの苦手でしょう」と言われていました。「その通りでございます」と(笑)。たしかに最初の頃は女の人が全然出てこなくて、出てきたとしてもほんのちょっと。「これじゃいかん」と、あえて女の人を主人公にしてみたりしました。居直って書きはじめてみるのは大事かもしれません。
――意外です。荻原さんほど老若男女問わず描き分けている作家さんも少ない気がします。
子どもは通ってきた道なので書きやすいんですけど、女の人はやっぱり難しい。お年寄りもほんとのところはよく分かっていないんです。自分が経験していない未知の世界なので、これで本当にいいのか、紋切り型になっていないか、気を付けていますね。
――登場人物を描く上で特に意識していることはありますか?
これは人にお勧めするべきものなのか分からないんですけど、僕は自分のルールとして、できるだけ視点人物のボキャブラリーで地の文を語るようにしています。語り手がお父さんやお母さんならそれくらいの大人が使う普通の言葉で、子どもの場合はできる限り子どもが使う言葉で描写するようにする。例えば十代の子が哲学的なことをしゃべっていたり、登場人物の後ろに著者が透けてみえるのが、僕はあんまり好きじゃなくて。登場人物を自分の操り人形にはしないように気を付けています。それぞれがちゃんと自分の人格を持った人間になるよう、その人のボキャブラリーで語るようにする。インテリはインテリ、おバカっぽいやつはおバカ、それなりの言葉を使っていく。人によると思うんですけど、少なくとも僕はそうしています。
扱う題材を決める秘訣とは
―ミステリ、ユーモア、ホラーなど、幅広いジャンルにわたって執筆をなさっている荻原さん。新しいテーマに挑戦し続ける背景には何があるのでしょう?
同じジャンルを書き続けていると自分でも飽きてしまうというのが一点。あとレッテルを貼られてしまうと居心地が悪くて。小すば新人賞からデビューすると結構いろんな出版社から声がかかるんですけど、その時受けた注文がだいたい「デビュー作のようなユーモア小説で」というものだったんです。「え!?」と思った。さっきも言ったんですけど、僕自身は決してユーモア小説を書いているつもりはなかったので。「家族小説が得意な人」とか「ハートウォーミングな作品の人」とか言われると、いやいやいや……と。だからほんわかユーモアっぽいものは意図的に遠ざけて、全然違うジャンルを書いてみましたね。僕の場合、これぞという掘り下げるべき大きなテーマがないんです。自分はこのジャンルで、というのがない。だから浅瀬をあちこち一生懸命掘ってみているんです(笑)。
――テーマ自体は何をきっかけに思いつくのですか?
例えば「縄文時代」っていうテーマでいうと、以前自分がクロマニョン人だと思い込んだ少年の話を書いたことがあって。そこでクロマニョン人について調べているときに「いや古代っておもしろいな、誰も書かないのかな」となったんです。取材や調べものをしている中で、違う作品のテーマがでてきたり結びついたりすることはよくありますね。だからやっぱり取材したり調べたりするのって、全て無駄はないと思うんです。もちろんボツになるものは少ない方がいいに決まっているけど、無駄なものはないと思っていた方が日々を健全に送れる(笑)。
――テーマを決めるうえで荻原さんなりの工夫はありますか?
毎回自分でハードルを上げるようにはしています。いや無理だろ、って思うくらいに上げてみる。例えば、何のあてもなく「縄文時代書きます!」って宣言してみるとか。そのあと頭を抱える羽目になるんですけど(笑)。でもそれくらい無理やりハードルを上げた方が、さっきの登場人物の話と同じで、物語が思わぬ方向へ向かっていいものができたりするんですよね。
『二千七百の夏と冬』上・下
双葉文庫 本体648円+税
―子どもの頃から新しいものに対して好奇心が強い方だったんですか?
いや、もともとそんなにチャレンジングな人間ではないです。ただ、ものをつくるという点においては、やってみようと思う気持ちは強いかもしれない。僕、漫画を描いている人に関してはあらゆる人を尊敬しているんです。お世辞ではなく自分には真似できないと思うから。ただ小説家としては、実は誰にも負けたくないと思っている。もちろん小説家の中には「この人はすごい、天才だ」と感じる人もたくさんいるんですけど、自分でもできるかもしれないことだから、それでもやっぱり負けたくない、と常々思っています。
荻原さんから見た「小説すばる新人賞」
――荻原さんにとって小説すばる新人賞は、どのようなイメージですか? やっぱり自分の出身の賞なので、いい立ち位置であり続けてほしいとは思います(笑)。実際にそうだと思いますけどね。継続して活躍している人も多いし、いろんなジャンルを受け入れている。
―新人賞に応募する人たちに向けてアドバイスをお願いします!
さんざん言ってきてなんですが、最初に書く時は別にハードルを上げる必要はなくて、自分の身近な世界を書けばいいと思います。僕なんかは自分を盛り上げるためにハードルを上げているだけなので。例えばなにかおもしろい仕事をしていたら、それを書くだけでもいい。自分では普通だと思っていても、意外と世間は知らないことがあるんです。それだけで一つの題材になったりする。「それしか書けないんじゃないか」と思われてしまう心配もあるかもしれませんが、とりあえずのところは気にしなくていいと思います。
あとは、傾向と対策みたいなことはしない方がいい。「この新人賞は過去の受賞作がこういう方向性だから、同じようなものでいこう」ってやると、絶対逆目が出ると思います。去年と同じだと思われてしまう。だからそういうことはしない、というか気にしない方がいいですね。「自分はこれを書きたいんだ」というテーマをじっくり書けば、読む人も受け入れてくれるはずです。

【プロフィール】
荻原浩(おぎわら・ひろし) ◆ '56年埼玉県生まれ。'97年「オロロ畑でつかまえて」で第10回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。'05年「明日の記憶」で山本周五郎賞を、'14年「二千七百の夏と冬」で山田風太郎賞を、'16年「海の見える理髪店」で直木賞を受賞。「なかよし小鳩組」「さよならバースディ」「千年樹」「花のさくら通り」「ストロベリーライフ」「海馬の尻尾」「極小農園日記」「楽園の真下」など著書多数。最新刊は「人生がそんなにも美しいのなら」。
※小説すばる新人賞についての詳細や応募方法については、以下のページをご覧ください。http://syousetsu-subaru.shueisha.co.jp/award/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?





