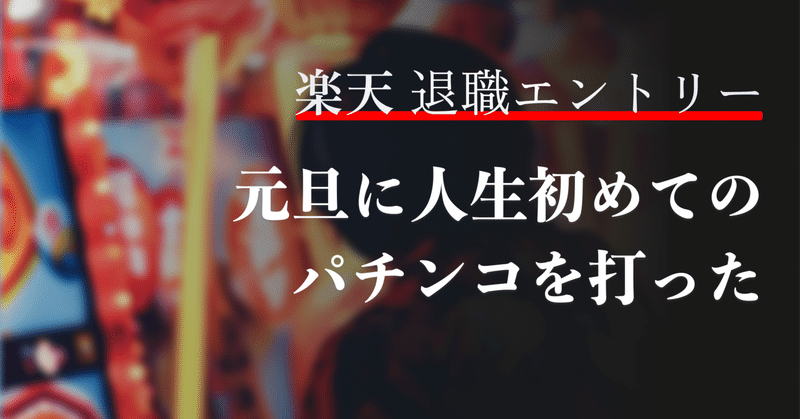
元旦に人生初めてのパチンコを打った【Rakuten 退職エントリー】
202X年の元旦、私は寒さに身を震わせながら、人々が目を細めて見るようなある場所へ向かっていた。しかも、子供がもらったら嬉しいぽち袋に自分のお金を入れて握りしめて。

一見すると、なぜ私がこんな日にこんな場所に来たのか、理解するのは難しいかもしれない。私も先週の自分がこの時の自分を見たら理解できないだろう。
お店の外観は、その日の寒さとは対照的に暖かさを感じさせるような照明で彩られていた。店内に入ると、耳を突くような音と、目を眩ませるような光が私を包み込みんだ。「うるさっ」そうボヤいたのを覚えている。
店内は元旦だからなのか、異様な雰囲気が漂う。タバコの香りもする。
どこに座ればいいかすら分からない私は、人がいる台から1〜2つ開けて座ってみた。
やり方も分からない。私は恐る恐る店員に声をかけ、”初めてのパチンコのやり方”を教えてもらった。私が座っていたのはどうやら、「CRキャプテン翼」の台。ボールを打つたびに、パチンコ台から放たれる光と音が睡眠不足の私に突き刺さったのだった。

私は7年間新卒から勤めた楽天を卒業した。
2023年8月3日時点、私の就職先は決まっていない。
7年間お世話になった楽天を
— しょーてぃー / Experience & Prompt Designer (@shoty_k2) July 2, 2023
6月末で最終出社を迎えました!
新卒からUXデザイナーとしてキャリアをスタートし、UXだけにとどまらず、マーケティングや戦略を含む広範な視点で、社会に“実”を生み出すことを学びました。… pic.twitter.com/xTSieurYsk
私が楽天で学んだことや意識していたことを、いつかの元旦のパチンコの記憶とともに書き連ねる。
楽天で何をしていたのか
楽天の顧客戦略部で「UXデザイナー/UXプランナー」としての働いていた。
顧客戦略部とは?
楽天の巨大なアセットを創造的に活かし日本をもっと楽しくする70以上のサービス、累計発行数3兆ポイントを超える「楽天ポイント」、1億超の楽天会員数などの巨大アセットを有する楽天。そのエコシステム戦略と、アセットを活用したグループ横断のソリューション企画推進を担う
私の主な仕事は、ビジネスとユーザーの要求をバランスさせ、トレードオフにならないようにサービスとユーザー体験を設計することだ。

ビジネス戦略、マーケティング戦略、そしてエクスペリエンス戦略をユーザー体験駆動で統合し、可視化や具体化するという役割を担っていた。
その過程では、ユーザーの現在の心理と行動をモデル化し、外部情報を構造化し、理想的な体験の方向性とコンセプトを描くも少ないくない。
もちろん、コンセプトから具体の体験そしてデザイン要件に落とし込み、デザイナーさんと協力してクリエティブを作っていくことも含まれる。

参考:
何を学び・何を意識していたのか
1.「Structured Chaos」とその中の力
「Structured Chaos」それは濱口秀司氏が提唱する概念で、論理思考と非論理思考の中間にある、最も創造性の高い思考モードのことを指す。それらの中間にある思考モードが最も創造性が高いと説いている。

実際には「ストラクチャード・ケイオス」の状態になることは難しく、論理思考(Structuredモード)と非論理思考(Chaosモード)を交互に行き来することで、結果的に擬似的な「ストラクチャード・ケイオス」の状態になるとされている。
したがって、現実的にクリエイティブなアイデアを生む実践的なテクニックは、「Structured側とChaos側に極端に振り切ることを繰り返すことで、擬似的な”ストラクチャード・ケイオス”の状態を生み出し、創造性を高める」営みだ。
具体的には以下のようなものにあたる…
Structured : logic / number / formula / reliability…
Chaotic : intuition / inspiration / picture / validity..
参照:Structured Chaos
私がいた部署は非常にハイコンテキストな内容から超具体の細かいコミュニケーション文言まで幅広く扱っており、ロジック中心ではあったが、ときに何か混沌とした感性的なところからコンセプトを形作っていくことも少なくなかった。
なので私は、意図的にこれら2つのモードを行き来するために以下の能力を意識して鍛えていた。
抽象化力:複雑な情報や状況を単純化し、本質的なパターンや構造を見つける能力。
構造化力:情報やアイデアを整理し、明確なフレームワークやモデルを作り出す能力。
分解力:大きな問題やプロジェクトを小さな部分に分ける能力。
仮説思考:情報が不完全な状況でも、可能性を探求し、テスト可能な仮説を立てる能力。
変換力:一つの形式の情報を別の形式に変える能力。これはプロジェクト要件をデザイン仕様に変換するなどの作業を含む。逆もまた然り。
直感力:情報が不足している状況でも意思決定を行う能力。
アイデア・クラフト力:アイデアやコンセプトを積極的にすぐに形にする能力。
抽象化については以下の記事でもふれている。
2.大局観と局所観とフレーム
エコシステムとしての効果をどのように最大化するのか?
そこには想像以上にUXデザイン以外の知見と大局観が必要だった。
大局観は全体のビジョンや戦略を理解したり各施策や表現の相対感を可視化などが含まれる。もちろんUXデザイナーとして体験や各個別アウトプットの品質に細部までこだわる局所感はベースとしてもってこそである。
これはいわゆる、「マクロ、ミクロ」、「鳥の目、虫の目」と言われるものに近いだろう。

「ミクロ」にモノを見る人と「マクロ」にモノを見る人がいて、企画やプロデューサー系はマクロが多く、職人的なクリエーターはミクロに偏ることが多いとされる。
部署で求められていたのは、深い職人的プロフェッショナリズムの目を持ちつつ、同時に高い視座・広い視野で見渡し判断するUXデザインであった。
前述した、”ビジネスとユーザーの要求をバランスさせ、トレードオフにならないようにサービスとユーザー体験を設計”するためには、両方の能力が必要であった。これは自分のモノの見方(Frame)やバイアスを常に意識し、破ろうする意識も同時に大切であることに気づいた。
各プロジェクトに必ずUX、マーケ、ビジネスといったスペシャリストメンバーがアサインアサインされる構造だった。
立ち上げもいくつかあったものの、常時にMAU100〜2000万人の案件5〜8件に携わりながらその感覚を実践と共に磨いていったのかもしれない。
3.好奇心とこだわり
好奇心は知的活動の原動力であり、挑戦を続けるためには欠かせない。常に新しい情報をキャッチしてどのように組織に横展開できるのか、所属するUXチームの考え方に適応できるのかなどだ。
ある施策が1%でもコンバージョンが上がると8〜9桁円レベルでインパクトがあることもアルアルだ。大きな戦略進化は重要、小さい改善も舐めてはいけない。
一方で大局観(全体最適的な観点)に偏るとチャレンジしにくいマインドセットなることもあるだろう。
「どうせ小さい歯車の一つだ。自分の考えたことは一部しか反映されない」
と思ったこともあった。

ただ、その中で「好奇心」と「こだわり」を常に絶やさずに、ときにロジックに想いやストーリーをのせ、直感的こだわりを分析・分解・抽象化そしてビジネス言語に変換しモノづくりを行い続けた。
この「好奇心」や「こだわり」に実体験や自身の感性がないと、上っ面だけになってしまうこともあるだろう。
「CRキャプテン翼」の台の前にいる、あの時の私の話に戻そう。打ち始めてから何分がたっただろうか、私は確かにその“確変”の高揚感を味わっていた。
※確変:確率変動の略。大きな意味としては大当たりの確率が変わったゾーン。CRデジパチでは大当たり確率が、現金デジパチでは小デジタル確率が、それぞれアップする機能。
私がパチンコ店に行くことになったきっかけは、楽天でのある案件がきっかけだ。私が当時携わっていた案件のコンセプトについて、偉い方から”パチンコで確変に入ったような高揚感”、”あのペカって光る感じだよね”という発言があった。
動画が見ても頭では分かるが、どうしてハマるのかどの要素がそうさせるのか、どのような相互作用が起きているのか腹落ちしていなかった。
そこで私は、この原体験を自分自身でも味わってみようと思った。今思えばこれは、好奇心だろう。あえて、冬休みを元旦という異様なタイミングで狙ったのも極端にChaosに振ってみようと思ったからだ。
パチンコの興奮を理解するためには、なぜ人々がそれにハマるのかという大局的な視座を持ち抽象化した。冬休みが明け、その興奮をデジタルインターフェースに変換するためには、各部分を分解し、構造化するという局所的な視座を意識しつつ、デザイン要件やプロトタイプに落とし込んでいた。
こんなことがなければ、私は冬の寒空の下でパチンコ店に足を運ぶことはなかったのだろう。
なぜ次の職場を決めずに辞めたのか
端的に言うと時間がなかったからだ。アホなのかもしれない。
実は約半年間、自分のプライベートの時間を95%削り、睡眠時間を削り、”2.AIを活用した試行錯誤”に当ててきた。
当時の生活
仕事(副業不可)・通勤
AIを活用した試行錯誤
家庭
転職活動
1〜3は削れないとなったときに物理的に”4.転職活動”がどうにも入らなかった。
2の流れは不可逆で速すぎた。今もそうだ。
将来を考えて、どこに自分の時間をどこにベットするべきか考えていた。
メーカー勤務の兄にふとそんなことをボヤいたときに、
「数ヶ月無職のまま転職活動しても、次のキャリアには大して響かない」
と言われた。
その時、私は思ったのだ。
「転職活動が目的化せずに、自分の将来を考える時間が純粋にほしい。無職という不安と闘いながら、確変を起こせばいいのか。」
属にいうLLM無職とはすこし違うのかもしれない。
幸いなことに楽天に在籍中にオファーの声もあったものの、
ちゃんと考える時間を持てていない中で、拝受はできなかなった。
プライベートで培ったノウハウを活かした
引き継ぎも行ったので安心してくれ。
これから、どうするのか
これからどうするか言われると正直まだ見えていない。
最近やっていることと言えば…
GPTを使ってアイデアからユーザー仮説を逆解析するサービス(リリース済)
認知バイアスを構造化・可視化して新しい気付きや発見を与えるサービス(開発中)
生成AIを活用した大学・地方自治体の学生向けワークショップ
社会人や企業向けの生成AIの実践講座の実施や登壇
NewsPicks、翔泳社様のProductzineで、Experience&Prompt Designに関する記事執筆
生成AIの活用方法のリアルタイムハンズオンのための「Schoo」生出演
国内最大級のAI活用コミュニティのパートナーメンバーへの就任
UXデザインの民主化(定性調査分析の自動化etc..)
友人の依頼でミュージックビデオを生成AIを活用して作成
ビジネス×マーケティング×デザイン×AI界隈との交流やイベントサポート
ストリートダンスのスクールに通い出した
5kg太ったので、痩せるために必死で奮闘中
…..
ただ、興味がある領域はある
直近の技術の急進的な変化でユーザー価値が大きく変革でき、モノづくりのプロセスも再定義の余地があると考えている。UXデザインのあり方もぐっと進化しているので、新しいフィールドでの体験設計を探索し、次のキャリアに向けてのステップを歩もうと思っている。
#キーワード
・UXデザインの民主化
・人間の認知バイアスの向き合う何か
・物魂電才(意味のイノベーションと相性がよさそう)
※「物魂電才」とは
【シン・ニホン 2023:安宅和人】生成AIで起きた3つの変化/AIを議論しすぎ/世界の2大課題は「地球との共存」と「人口減少」/日本の勝ち筋は「物魂電才」/米中は「電魂物才」
物(もの) : ものづくりの魂、リアルなものへのこだわり
魂(たましい): 日本のものづくりの伝統的な精神、匠の技など
電(でん) : デジタル技術、AI、サイバースペースなど
才(さい) : 技術力、デジタルを活用する才能
サイバースペースは”虚”からは脱しないのだ。
分かりやすくするためにUXデザイナーと書いていたが、その肩書は捨て、「Experience Designer」を名乗っている。その理由についてはこの記事に書いてある。
キャリアポートフォリオ

なんとなく、ある程度規模のある組織で社会に実をつくりながら、副業で実験をし続けるそんなポートフォリオなのかなと思っている。
私のようなスキルセットの人間は、ある程度大きな力学が働く事業のほうが社会貢献できる気もしている。
もしくは、起業するよりも大きなビジョンと原動力を持ち合わせた優秀な経営者の右腕としてのほうがバリューがだせそうだし、私もそのような働き方のほうが腹落ちするような気もする。(分からないけど)
そういえば、初めてのパチンコでは大負けしたわけでもなく、
だいたいイーブンってところだった。
ただ、パチンコはあれっきりやっていない。
まずは何をするべきか考えながら、走りながらキャリア探しをしよう。
あなたのツイート拡散や記事へのいいねが私のキャリアを広げます笑!
退職エントリーを公開しました。学びと経験、どうして先も決めずにやめたのか、そしてこれからどうするのかを綴っています。
— しょーてぃー / Experience & Prompt Designer (@shoty_k2) August 4, 2023
また最近、デザイナーとして「どういう思考トレーニングをしたのか?」と聞かれることが増えたので、その答え7割くらいが載っていると思います。https://t.co/qwIqDv3k87
筆者のプロフィール
LinkedIn、Twitter、noteなどがあります。
連絡はTwitterDM→LinkedInの順番で繋がりやすいです。
いただいたサポートは、記事を書くモチベーションをあげるためのグミの購入に使わせていただきます!
