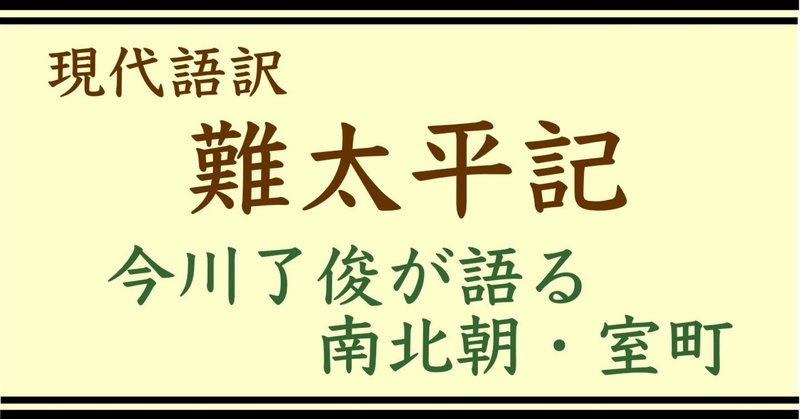
難太平記
はじめに
今川了俊の『難太平記』(応永九年(1402)成立)の現代語訳です。600年以上前に生きていた人の生の声が聞けるのが魅力です。
筆者の今川了俊は南北朝時代後半から室町時代初頭に生きた足利一門の武将です。了俊は応安三年(1370)九州探題に任命されて九州に発向すると、九州の南朝勢力を制圧し、めざましい功績をあげて室町幕府の基礎を築きました。
しかし、応永二年(1395)九州探題を突然解任され、さらに応永六年には応永の乱(大内義弘が起こした反乱)に連座して失脚、その後は没するまでの約二十年間を著作活動に専念することになりました。晩年の不遇は、了俊が九州で独立勢力となることを足利義満が警戒したことが原因の一つだったようです。
この書物には元々はタイトルは無く、『難太平記』という書名は後世に付けられたものです。このような名前が付けられたのは、この書物の前半で、了俊が『太平記』を批判しているためです。その部分には太平記に書きもらされた今川家の武功が記されており、結果的に太平記を補足するものになっています。後半には、了俊自身が体験した南北朝時代末から室町時代初頭の出来事が記されています。
余談ですが、戦国時代に駿河・遠江を領した今川義元は、了俊の兄範氏の末裔に当たる人物です。
なお、各節のタイトルは芝蘭堂が付けたもので、元々の難太平記にはありません。
1.執筆の動機
愚かなる身には、自分の心さえわからないようである。
たとえば、惜しい、欲しい、憎い、いとおしいなどの思いを知らないと言っているのではない。「『このように思う心』とは、どのようなものであるのかを知るべきである」と申しているのである。
また、自分の親や先祖はどのような者で、どのようにして世を過ごしていたのかを知るべきである。人のことはわからないが自分自身について考えると、自分の親より前のことはまったく知らない。故殿(今川範国。了俊の父)が昔語りした時にたまたまおっしゃったことを、今わずかに覚えているだけである。
これから類推するに、私の子どもや孫は、私よりももっと父のたたずまいですら知らないことになろう。
むかし、山名修理大夫時氏という人がいた。これは、明徳の頃に内野の合戦で討たれた陸奥守(山名氏清)の父である。
この人が、子息たちの聞いているところでいつも語ったものである。
「自分の子孫は間違いなく朝敵となるだろう。なぜなら、自分は建武以来、当御代のおかげで世に出ることができたが、元弘以前はただ民百姓のようにして上野の山名というところで暮らしていて、そこから出て来たので、渡世の悲しさも身のほどもわきまえている。また、合戦の難儀も思い知っている。だから、この御代のおかげのかたじけないことも知っているし、世の過ごし方もそれに応じてわきまえていた。しかし、それでさえ、今はややもすれば上をもおろそかに思い、人をもいやしく思うことがある。それでわかったのだが、子供達の代になれば、君の御恩も親の恩も知らず、自分のみを主張して分を過ぎたおこないをするようになるだろうから、我意にまかせて御不審をこうむることになるだろう。」
すると、思ったとおり(山名時氏の子息たちは)御敵となった。
昔の人は、このように世の中の大姿(全体のすがた)をよくわかっていたようである。まことにこの人は、読み書きもできなかったけれど、よくぞ申したものである。
背景の説明
山名一族は南北朝時代の末に11か国の守護となり、「六分の一殿」(日本の六分の一を治める殿)と呼ばれて勢威を振るっていた。それを警戒した足利義満は、山名時氏の死後、応安四年(1371)ごろから山名一族の分裂につけこんで山名氏の勢力削減に乗り出した。
これに危機感を持った山名時氏の子氏清は、明徳二年(1391)、兄の義理、甥の満幸とともに挙兵して幕府に叛旗を翻し、京都に進出した。しかし、大内・畠山・細川ら有力大名の軍勢と内野で戦って破れ、氏清は討たれた(明徳の乱)。了俊が語っているのはこの事件のことである。

平安京の内裏は平安時代の末に火災で焼失したあと再建されず、この付近一帯は荒れ野となって「内野」と呼ばれた。明徳の乱で山名氏清と幕府勢の合戦(内野合戦)が行われたのは、この付近と考えられる。
自分のことを考えると、故殿(今川範国。了俊の父)がいつも仰せになっていたことを聞いて、その頃はそれほど良いこととも思えず、むしろもどかしいようにも思ったが、今思い合わせると一つとして理でないことは無い。
我が身は今老いぼれてしまったので、子どもにも駄々っ子のように思われているが、死んだ後にきっと思い出してわかることであろう。
そのために、父の語られたことをいろいろと書き付けるのである。しかし、間違えて覚えていることが多いだろうから、そのようなことはみな略した。たしかに覚えており、また、証拠の明らかなことだけを申しておこう。
2.足利歴代について
神代にはたった二人の子だけだったというが、その子孫がさまざまに生まれて、その末は、ある者は国王・大臣になり、ある者は民百姓となったという。いやしくて世のために無益な人は田を作ったり人に仕えたりしたため、氏の無い者になった。
今、我らはわずかに父の世のことしか知らず、二三代前の先祖のことはまったく知らないので、やがては我が子孫は必ず氏の無い民同然になってしまうであろう。そこで、今わずかに知っていることを少々書き付けておく。
八幡殿とは、義家朝臣陸奥守鎮守府将軍の御子義国から、義康、義包(義兼)、義氏、泰氏らのことである。泰氏は平石殿と呼ばれた。

その御子は頼氏。治部大輔殿という。
その御子は家時。伊予守と号す。
その御子は貞氏。讃岐入道殿という。大御所(尊氏)と錦小路殿(直義)は、その御子でいらっしゃる。
頼氏は平石殿(足利泰氏)の三男でいらっしゃったが、御当家をお継ぎになった。尾張の人々や渋川などは兄であったが、みな庶子となった。
細川・畠山などは義包(義兼)の下から分かれたようである。義包(義兼)は長け八尺あまりで、力人に勝れた人であった。ほんとうは為朝の子というが、赤子の時から義康が養った。世にはばかって人に言わなかったので、それを知っている人はいない。
(義兼は)頼朝右大将の側近となられたが、なお世にはばかって狂人のふりをされてその代は無為に過ごされたので、「我が子孫には、しばらく霊となって物狂わしいことがあろう」と仰せになったと申し伝えている。
また、義家が御置文で、「我、七代の孫に生まれ替わりて天下を取るべし」と仰せになったのは家時の代に当たり、なおも時が至らないのをお知りになったためか、(家時は)「我が命を縮めて、三代のうちに天下を取らしめたまえ」と八幡大菩薩に祈り申されて、御腹をお切りになった。
子細は、その時の御自筆の御置文に書かれている。まさしく両御所(尊氏と直義)の前で故殿(今川範国)も我らも拝見させていただいた。「今、天下を取ったのは、ただこの発願によるものである」と、両御所も仰せになったことがある。
このように、一代かぎりではない御志で世の主とおなりになったのに、「我らの先祖は当御所(今の将軍)の御先祖の兄の流れである」と、宝篋院殿(足利義詮)に申して系図などをお目にかけた人があった。御意にかなわず、(義詮が)後に人に御物語されたことがあるという。
天下をお取りになった後は、日本国の人でこの御恩の下に無い者はいない。今は、一族たちはことさらへりくだって当然である。
「家によって立身しようとは決して思うな。文道をたしなみ、御代の御助けとなって、その徳によって立身せよ」と、錦小路殿(足利直義)が朝夕仰せになっていた。このことは、石見武衛慈恩寺殿(足利直冬)が宮内大輔と呼ばれていた頃、畠山大蔵少輔直宗、一色宮内少輔直氏や我らに教えてくださったことである。他の人も、多少はうけたまわっているであろう。
3.今川一族について
我らの先祖について述べると、義氏の御子の長氏上総介から吉良と申した。その子満氏の弟の国氏から今川と申すようになった。

貞義上総入道・法名省観と、我らの祖父の基氏とは従父兄弟である。吉良満義右兵衛督と故入道殿心省(今川範国)は、三従兄弟である。
関口、入野、木田などは国氏の子たちで、我らの祖父(基氏)の弟の末である。故殿にとっては、いとこの子たちである。
今川は、基氏だけが相続した。関口は母方が小笠原の出だったので、そちらから所領をゆずられた。入野芸州は三浦大多和の人々が母方で、一部をゆずられて入野というのである。「今川の川端の人々」というのは、この人々のことである。
基氏には御妹がたくさんおわして、みな公家の重縁になり、その子どもは今川の石川ともいい、名児耶ともいう。これは基氏の御養子だったので、故殿にとっては連枝である。建武の頃に御所(足利尊氏)に申し入れられて御一流となった。伊勢の国に蘇我という所があるが、その領家も基氏の妹婿と聞いている。石川三位公といい、父は法師宮の子である。
一色少輔太郎入道(直氏)の父(一色範氏)は山伏であったが基氏が姉婿にしたので、故殿(範国)にとっては伯父で、一色入道(直氏)と故殿はいとこでいらっしゃった。
4.今川庄について
左馬入道(足利義氏)の時から、長氏(吉良長氏)の少年の時の装束料として今川庄を給わったが、「(今川庄は)吉良庄の惣領が進退なすべし」との沙汰があったため、基氏(今川基氏)は(吉良家と)不和になった。

故殿(今川範国)の御代に省観上総入道(吉良貞義)と合体して父子の契約をしたため、違乱はなくなった。了俊(今川貞世)がこれをゆずられて相続した。
東福寺仏海禅師(一峰明一。東福寺十八世住持)は、了俊の師である。それで、東福寺の塔頭の正法院に(今川庄を)永代寄進した。この和尚は我らの先祖が今川を知行し始めた時からの政所であった高木入道という者の伯父でいらっしゃったため、もともと誼があったので、我が七世の父母の菩提のために永代寄進したのである。
しかしながら、もしも子孫の中にこの名字の地を大切に思う者がいたら、公方に申し出て、ここより貢収も多く、確かな私領と替えるがよい。そのままでよければ、塔頭の意にまかせよ。この冊子を証拠とするがよい。
5.足利高氏・直義の誕生
大御所(尊氏)のことを申そうと思っていたのに書き落としたので、改めて申そう。
大御所が御産湯を召された時、山鳩が二羽飛び来たって、ひとつは左の肩先にとまり、もうひとつは柄杓にとまった。

上杉頼重の娘清子は足利貞氏に嫁ぎ、出産のために上杉荘の光福寺の門前にあった上杉氏の別邸に住んで、そこで尊氏を産んだ。光福寺は、後に尊氏が全国に安国寺を設置した際、諸国の安国寺の筆頭と定められた。これが現在の綾部市の安国寺である。のちに上杉氏の別邸は清子の希望によって安国寺に寄進され、常光寺という門外塔頭となっていたが、大正初めに廃寺となって、現在は地元の公会堂になっている。公会堂の脇にあるこの井戸は常光寺で使用されていた井戸で、尊氏の産湯の井と伝えられている。(なお、尊氏は鎌倉で生まれたとする説もある。)
錦の小路殿(直義)の御産湯の時は、山鳩が二羽飛んで来て、柄杓と湯桶の端にとまった。
先代(北条氏)の世にはばかって、その時は披露されなかった。この御代になって、このところ人々もそれを申すようになってきたようである。

本文中に出て来る二羽の山鳩のエピソードは、
鳩が八幡神の使いと考えられていたことによる。
6.足利高氏の上洛
ここから先は
¥ 150
楽しんでいただけて、もしも余裕があったら投げ銭をお願いします。今後の励みになります。
