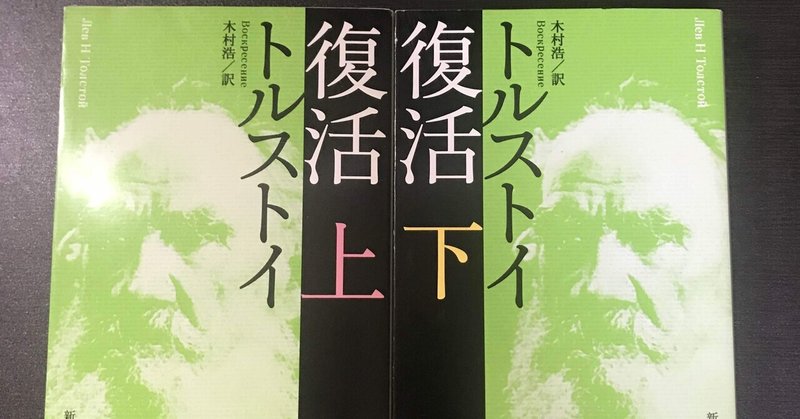
書評:トルストイ『復活』
ロシアの大文豪トルストイが見た人類史的アポリアと、そこに挑むための要件とは?
今回ご紹介するのは、ロシア文学よりトルストイ『復活』。
私はロシア文学好きを自認しているが、トルストイ派かドストエフスキー派と問われたら断然後者であり、正直トルストイはあまり好まないといっても過言ではない。
しかし、今回取り上げる『復活』だけは別で、非常に感銘を受けた忘れ難き作品である。
まずはあらすじから。
----------------
主人公ネフリュードフは、嘗ては高尚に生きる青年であったが、時は彼をむしばみ、やがて軽佻浮薄な人物となり下がったとされる人物。作品登場時の彼はそういう人物であった。
ある時、ネフリュードフはある裁判の陪審員となるが、その裁判に被告として現れたのは、かつて彼が犯した女性、カチューシャであった。
あれほど清廉な乙女だった彼女が、堕落した生活の果てに被告として裁判に立っている。更にあろうことかその裁判では、陪審員のわずかなミスが重大となり、彼女は無実の罪で徒刑を宣告されてしまうのだ。
ネフリュードフはカチューシャの姿に自らの罪科の結果を見ました。そして、忽然として真の自己に目覚め、彼女をも、自身をも救おうと決意する。
裁判の再審、カチューシャの釈放に奔走する中で、様々な囚人、様々な庶民に出会い、その本当の姿を見ることになる。
----------------
この作品は、答えのないような非常に難しい問題に対するトルストイの鋭い筆撃が遺憾なく発揮された、感動的な作品であった。
例えば、ネフリュードフが自身の領地を分割するために訪れた村での民衆の描写は秀逸だ。土地がないということが、これほどまでに庶民の困窮を常態化させるのか。これ1つ取っても深く突き詰めれば、土地の私有という資本主義の外郭をなす権利概念の是非という、人類的な難問にまでメスを入れる裾野の広がりを持つテーマである。
ネフリュードフの思索はやがて、庶民に対しては貴族による土地所有が根源的な悪であること、刑事犯・政治犯に対しては、人が人を裁くということ自体が根源的な悪であるということに行き着くこととなる。そして彼はそれらを解消するために尽力する人生を歩んでいく。
しかしこの作品の優れたところは、一面的な社会批判に止まらない「視座の広さ」にあるだろう。
ネフリュードフの行動に対し貴族が理解を示さないのは言わずもがななのだが、彼が救いたいと願う庶民や犯罪者からも理解されないのだ。
例えば、カチューシャがネフリュードフに浴びせた一言は強烈である。
「あんたはわたしをだしにして、救われようとしているのよ」
ネフリュードフは、確かにそうかもしれない、結局は自分が救われたいだけなのかもしれない、と自問する。
しかしネフリュードフは、己の道が人類的矛盾の解消へとつながる第一歩となると強く強く思い直して、自らを鼓舞し続け、精力的に活動を続けるのだ。批判も全て覚悟の上で。
こうした場面を読む時、我々読者も自分の胸に手を当て、これまで良かれと思ってやってきた数々の行動が偽善だと指摘された時、善行を行う自分に陶酔するためという下心が本音だと指摘された時、果たして弁明できるだろうかと突きつけられよう。
偉業には批判がつきものだと言われるが、自己の昇華のために偉業をだしにしているという批判は最も痛烈なものではないだろうか。そして私が思うに、どんな偉業も絶対にこの点は否定できないと思っている。
人が覚悟するとき、こういう自己矛盾を自ら積極的に認知し、従容として受け入れるのが本当の覚悟ではないだろかと思われる。
答えのない、極めて難しい問題だ。しかしトルストイは、ネフリュードフを通して「善に生きる」姿の生々しい真実を描いたように思う。
因みに、このような善行の動機の清濁というテーマについては、フランス文学のユゴー『レ・ミゼラブル』からも同質のものを感じとった。具体的には、同作の主人公ジャン・ヴァルジャンの善行に対する覚悟にそれを感じ取ることができるのだ。
読了難易度:★★★☆☆(←やや長編のロシア文学なので)
社会の構造的暴力の根幹に迫る度:★★★★☆
トルストイの「正しき生」の骨太感満ち満ち度:★★★★★
トータルオススメ度:★★★★☆
#KING王 #読書#読書感想#読書記録#レビュー#書評#海外文学#ロシア文学#トルストイ#復活#人類史的アポリア#善行と救い#土地の私有#自己矛盾の認知認容
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
