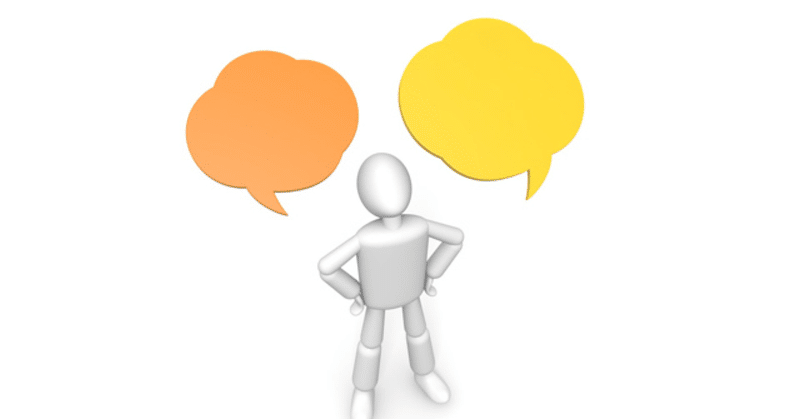2022年9月の記事一覧
人は共通点を見つけると親近感を覚えやすい
それは話の内容だけに留まらない
相手が悲しい顔をして話すなら、同じように悲しむ
相手が怒って話すなら、同じように怒って聞く
困った顔して話すなら、困った顔をして聞く
表情や気持ちを相手に合わせることでも、共通点がつくられる
人との距離を近づけて繋がりを深める方法がある
それはお互いの共通点を見つけること
同じ地元、同じ学校、同じ歳、同じ仕事…
共通の話題がグッと距離を近づける
これは職場で意見が対立したときも有効だ
互いに共通する点は何か?
それは、事業の目的と職場の理念に目を向けることだ
思い通りに行かないとき
人のせいにする人には
「自分では現状を変えられないから、相手に現状を変えてもらいたい」という心理が隠れている
自分が原因だと思う人には
「この状況は自分の力で変えることができる」という心理がある
他人に自分の人生を委ねずに、自分が主導権を握っている
4歳の娘は、機嫌の振り幅がとんでもなく大きい
朝起きた時の最初の一声が、その日の明暗を占う瞬間だ
そんな娘が、必ず機嫌良く陽気に振る舞うときがある
それは夫婦の会話が不穏な空気になったとき
明るく振る舞うことで、場を和ませようとしてるのだろうか
子供の優しさには敵わない
一期一会とは、一生に一度の機会と考えて物事に専念すること
「人との出会いを二度とないものとして大切にしよう」という意味だ
新たな出会いに使われることが多いが、すでに出会ってる人も忘れてはいけない
いつも周りにいる人が、もう二度と会えないかもしれない
そんな一期一会も大切だ
成功するのは一握りの人たちだ
それは少数派になること
普通の人でいたいなら、大勢の中に埋もれてしまう
普通の人が悲観的になるとき、チャンスと捉えて行動する
普通の人が楽観的になるとき、危険を予測して慎重になる
常に普通の人とは逆に考える
成功するには、変な人になるといい
この世の中は需要と供給で成り立っている
需要側にいる人は、「足りない」「ほしい」「得たい」という心の性質がある
供給側にいる人は、「足りている」「与える」「分けてあげる」という性質がある
富を集めるのは、常に供給側にいる人だ
常日頃の心の在り方を、供給マインドに整えたい
人を動かすにはどうしたらいいだろう?
相手の心に響かなければ、動いてはくれない
理屈で叱るより「私は悲しい」「私は傷ついた」
と自分の弱さを見せる方が響く
無理に褒めるより「私は嬉しい」「ありがたい」と喜びと感謝を示す方が響く
人を動かすには、自分の素直な感情を伝えることだ
セルフイメージが高い人は、仕事に喜びを感じやすい
それは幼少期から時間をかけてつくられる
親の言う通りする良い子より、多少やんちゃな子の方が成功したりする
自分の頭で考え、自分で決めて選択することができる子は、人のせいにせずに難局を乗り越えようとする
自己決定力を育もう
「自分のやりたい仕事がわからない」
自分の感情を抑えて行動して来た人
我慢を沢山して来た人
「〜しなければならない」と義務感を重視して生きて来た人
このような人は、本当にやりたいことがわからない
それなら、得意なことから始めてみよう
いつかやりたい仕事に辿り着くだろう
今日は子供の運動会
昨年の運動会が思い出される
子供を抱いて走るリレーで、先頭をスタートしてすぐにコケた
前のめりに転んだから、子供を前に放り投げ、地面に豪快にヘッドスライディング
大恥かいた私に
「あんた昔運動会で転ぶ親見て笑ってたね」と妻の一言
自分に返ってくるんだね
どの国の言語であれ、言葉の成り立ちに深みを感じるものがある
例えば、英語のunderstand
under → 下
stand → 立つ
理解するとは「相手の下に立つ」ということらしい
相手の話が理解できないとき、この言葉を思い出そう
相手を上から見ているのかもしれない