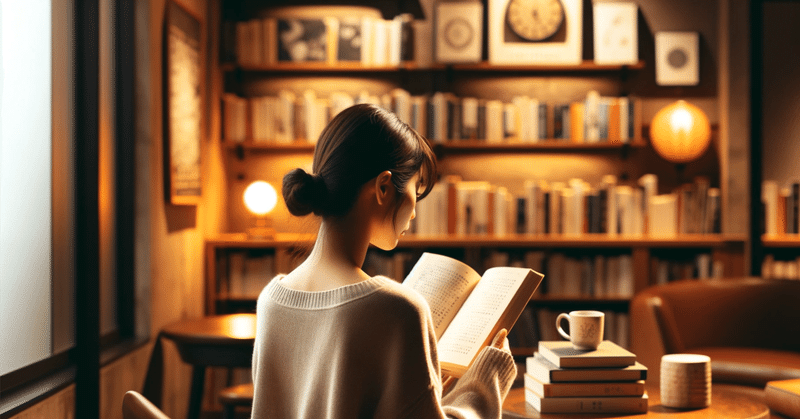
語彙力を高めるための読書
さて、前回は、読書が「時を超える」ことについて書いていきました。
自分が会ったことの無い人、
もはやこの時代にはもう亡くなっている人の思いも受け取ることができる、
それが読書の醍醐味です。
時代が変わっても、
同じように大事なこともある。
時代が変わったからこそ、
もう重要ではなくなっていることもある。
時が流れていく中で、
文字を媒体にして想いを受けとめ、
考えることができるのはまた、
知識に広がりを持たせてくれるものです。
自分の知識を増やし、想像力の翼を広げるためにも、
改めていろんな本を読んでいきたいと思います。
その時代の「当たり前」が反映される『小説』
小説を読んでいても、
小さな「当たり前」の違いに面白さを感じることもあります。
たとえば携帯の無い時代のほうが、
恋人同士にすれ違いが生まれやすいし、
男女平等なんてありえない時代には、
とにかく女性の権利はないわけです。
小説にさえも、その時代の「当たり前」が色濃く反映されています。
感情や出来事を「文字にする」難しさ
さて、今日は前回も少し触れた「文字にすること」について触れていきたいと思います。
文字にするってすごく難しいことだと個人的には思います。
何となく漠然と思っていることも、
実際文字にしてみると、なんか違うなと違和感を感じたりする。
そして文字にしてみると、
自分が言いたかった言葉とちょっと違う言葉になってしまったりする。
しかも、同じ言葉の羅列になる。
だから、言葉にするのは難しい。
文字にするのは難しく感じるわけです。
でも、書物(ここでは「書かれている物」)は、
その困難を超越したところにあります。
「売れている作家さん」の本や、
「とにかく読みやすい作家さん」の本の多くは、
私たちの知っている言語で、
同じ表現の羅列は避け、それでいて美しい日本語が使われている。
これって本当にものすごいことだと思うんですよね。
鑑賞し、評価するのは簡単だけれど、作るのって本当に大変だと思う。
だからこそ、その「生みの苦しみ」を知るためにも、
実際自分で書いてみようか、
なんて思うこともあります(やらないけれど笑)。
読んでいてすてきだなと思う日本語や、
自分ではきっと思い浮かなばないだろうな、
と思う日本語が使われている作品が好き。
そういう意味では、最近もお伝えしましたが、
「蜜蜂と遠雷」の表現は本当に感動しました(語彙力・・)。
”一音一音にぎっしりと哲学や世界観のようなものが詰め込まれ、
なおかつみずみずしい。
それらは固まっているのではなく、常に音の水面下ではマグマのように熱く
流動的な想念が鼓動している。
音楽それ自体が有機体のように「生きて」いる。”
恩田陸「蜜蜂と遠雷」
すごくわかりやすく、すっと入ってくる。
それなのに難しくない。
感じたことのあるような「体験」を文字にしてくれる。
そんなことができるのか~と感心してしまいます。
感情や体験を文字にすることって、簡単なようですごく難しいですよね。
「近頃の若者は~」なんて言われているけれど、
実際大人になってみても
「スゴい!」
「ヤバい!」
で済んでしまうことも多くあります(反省)。
言葉の引き出しを多く持っていれば、
その時その時の感情を、違う場所にしまっておくことができる。
人に伝えるときも、適した表現で届けることができる。
本を読みながら自分の表現力を高めていきたいものです。
ここまで読んでいただいてありがとうございます!
Instagramでは、最近読んだ本の紹介をしています。
興味がある方は是非覗いてみてくださいね↓↓
https://www.instagram.com/enjoy.reading._/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
