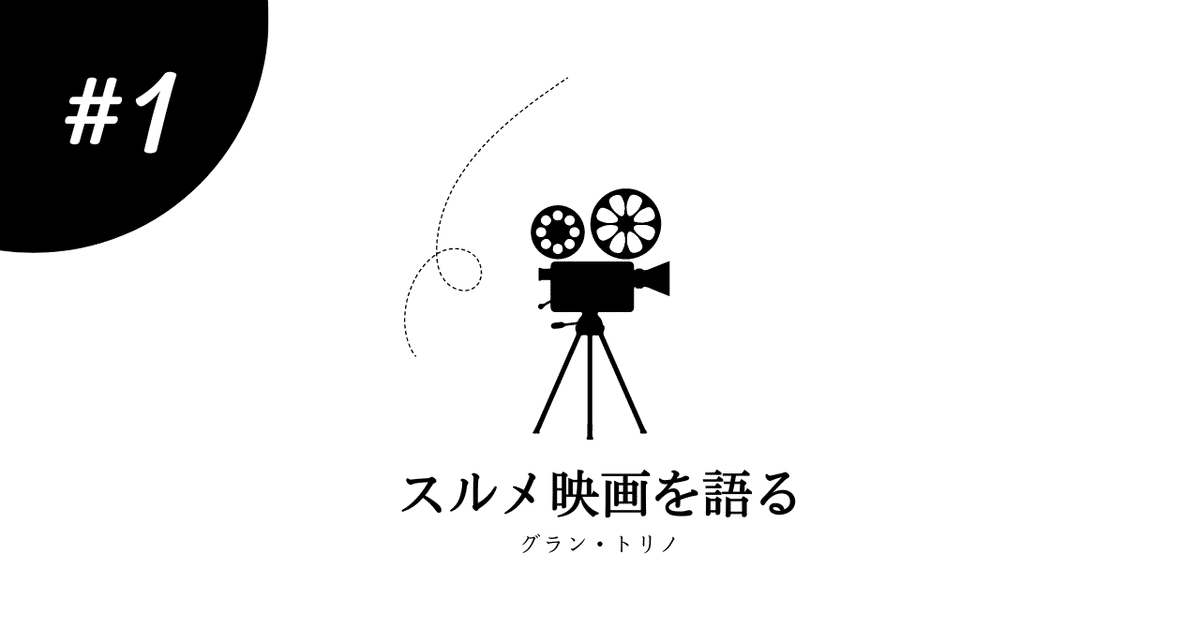
グラン・トリノ(2009)
恥ずかしながらわたしは映画を年に数本くらいしか見ません。ただ、気に入った映画は何年も、何回も繰り返し鑑賞します。このめちゃくちゃ狭いストライクゾーンに入った映画の、いったい何が好きなのかを自分なりに分解してみようじゃないか。という取り組みです。
初回はクリント・イーストウッド監督「グラン・トリノ」(2009年)。
最初に見たのは高校2年生の頃。父がTSUTAYAに行くというので借りてきてくれとお願いした記憶があります。我ながら渋いな。
あらすじ
妻に先立たれ、一人暮らしの頑固な老人ウォルト。学校にも行かず、仕事もなく、自分の進むべき道が分からない少年タオ。 二人は隣同士だが、挨拶を交わすことすらなかった。 ある日、ウォルトが何より大切にしているヴィンテージ・カー<グラン・トリノ>を、タオが盗もうとするまでは――。
主な登場人物
・ウォルト・コワルスキー(クリント・イーストウッド)
長く連れ添った妻に先立たれ、デトロイトに一人住むポーランド系アメリカ人。フォードの自動車工を50年勤め上げ、朝鮮戦争の徴兵経験がある。
・タオ・ロー
モン族の少年。コワルスキーの隣人。
・スー・ロー
タオの姉。
・スパイダー(フォン)
タオとスーのいとこで、モン族のストリートギャングのリーダー。
・ヤノビッチ神父
コワルスキーの教区担当の神父。
二項対立の中にある共通点
グラン・トリノのベースには、ウォルトとタオをはじめとしたロー家の「アメリカ人」と「アジア系移民」という二項対立があります。
彼らは一見全く異なるアイデンティティを持った人たちのように見えますが、注意深く見ていくといくつか共通点があることに気づきます。彼らを対照的に描くことで共通点が浮き彫りになり、そこからステレオタイプ的な分断の陳腐さを考えさせられる。そんな構造の美しさが好きです。
ここでは、ウォルトの持つ背景から、彼らの共通点を仮説立てていきます。
(ちなみにクリント・イーストウッド監督はよく二項対立を仕立ててメッセージ発信している印象があります。またnoteでまとめられるといいな。)
ウォルトのルーツ
まず触れておきたいのが、ウォルトは "WASP" ではないということです。冒頭でカトリック系教会の葬式を描き、タオたち(そして私たち)アジア人から見たら同じ白人のようでも、ウォルト自身も移民のルーツを持っているということが明確に表現されます。途中に出てくる床屋の友人とも「イタ公」「ポーランドじじい」と言い合っています。
WASP(ワスプ、WASPs)とは、ホワイト・アングロ・サクソン・プロテスタントの略称(アクロニム)で、白人のアメリカ人プロテスタント、かつイギリス系の上流階級を指す。WASPエリート集団は、アメリカ合衆国の歴史の大部分において米国の社会・文化および政治を支配し、婚姻・相続及び縁故主義を通じて諸分野を寡占した。
東欧系の人々の多くが「新移民」と呼ばれる19世紀末〜20世紀初頭に一気にアメリカにやってきた層であり、低賃金で都市部の工場労働に就労するケースが多かったそう。その労働力はアメリカの国力増大に欠かせないものだった一方、旧来のWASP的アメリカ文化とは同化せず独自の社会集団を構成していたようです。
憶測ですが、ウォルトは「新移民」の2世くらいの年代なのかなと。
↑ アメリカの歴史はぜひコテンラジオで!
これを聞くとアメリカが舞台の映画の面白さが2割増です(自分比)。
アメリカ人たる通過儀礼
そんなバックグラウンドを持つウォルトですが、映画の中では「アメリカ人」としての自意識を強く持っています。
それは彼自身が生まれ持っているアイデンティティではなく、「アメリカ人としての通過儀礼」を通して意図的に手に入れたものなんじゃないかと考察します。
・フォードの自動車工
ウォルトは半世紀にわたりフォードの自動車組立工として働いたことを誇りに思っています。
フォードは資本主義アメリカの象徴たる企業。熟練工のいない若い国だったアメリカで、いかに安定した品質の自動車を大量生産するか。その解決策こそが、ウォルトが従事したフォードの自動車組立の分業化です。
こうしてフォード社はアメリカの経済大国としての地位を押し上げていきます。
フォードで勤め上げ、グラン・トリノを大事に手入れし、仕事道具である工具を綺麗に保つ彼の姿に「経済大国を作り上げた一員であること」の自負が読み取れます。
・従軍経験
ロー家のルーツであるモン族の「米軍側としてのベトナム戦争参戦」とウォルトの心の奥深くに傷を残した「朝鮮戦争への従軍」には、共通の重みがあるのではないでしょうか。
第一次世界大戦以降はナショナリズムが台頭し、主に"人種"が国民たる強いロジックとなりました。国が掲げる人種が一致しない人たち、簡単に分類できない背景を持つ人たちの苦しみは、これまで多くの負の歴史が物語っています。
たとえば山崎豊子「二つの祖国」では、日系アメリカ人である主人公の弟がパールハーバー後、日本人収容所に隔離されながらも米軍兵として戦うことを志願する場面が描かれています。
従軍経験は、人種や宗教にルーツを持たない者たちが自らを「国民」と主張する誓いであり、権利獲得の機会でもありました。
命令もされず ”自らやった” ということが恐ろしいのだ
劇中、朝鮮戦争で自ら虐殺行為に関わったことを吐露するウォルト。
本当の背景はもちろんわかりませんが、もしかしたらアメリカ人であることの代償が、彼の心の傷なのかもしれません。
まとめ
こうして見ると、グラン・トリノは一見「アメリカ人」と「アジア系移民」という全く異なるルーツを持つ二者間の交流の物語のようで、実はその手で自分たちの居場所をつくろうともがいてきた人たちが出会い共鳴する物語なのかもしれません。
ネイティブ・アメリカン以降、時代ごとに移民が集まり開拓しつづけたアメリカの近代史を考えると、それは当たり前のことのように思えます。
だけど、本人たちが線引きをしていて、それに気づいていない。
「うちの父親は厳格で古い人間だった」
「俺も古い人間だ」
「でも アメリカ人だわ」
『"アメリカ人"とは何か?』
『簡単に分けられないのに、なぜ二分しようとするのか?』
あえて二項対立的に描かれるウォルトとロー家の交流によって立てられる問いに、この映画の深みを感じます。
今後余力があれば、ウォルトやタオの心を深く投影している重要な登場人物「ヤノビッチ神父」と「スパイダー」に注目したnoteも続編として書いてみたいなと。
日本社会でも誰しも個別の背景があるように、日本人が一見「白人」と括ってしまいそうな人々にも個々の背景や社会的なグラデーションがあります。そういった背景をなんとか拾おうとすると、アメリカ映画がより立体的に見えてくる気がします。
そして、そんな社会的背景を全く知らなかった高校生の私にも真っ直ぐに心に届くグラン・トリノのストーリー構成はやっぱり見事。
ぜひ色々な観点で、グラン・トリノを鑑賞してみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
