
ヘルマン・ブロッホ『夢遊の人々』─多重な価値世界に苛まれる現代人─【7410字】
【お気の毒Tips:(Ⅳ)、(Ⅴ)に記事の本旨がまとまっています(目次から飛んで先に読むことを推奨)】
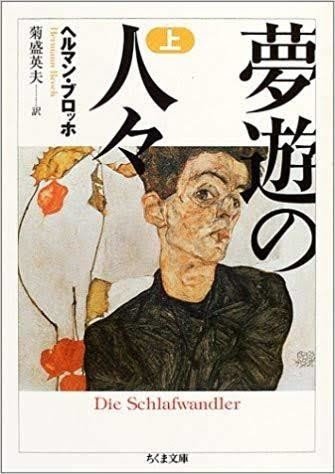
https://www.amazon.co.jp/夢遊の人々-上-ちくま文庫-ヘルマン・ブロッホ/dp/4480420061
『ウェルギリウスの死』を読んで大変な感銘を受けてからというもの、ヘルマン・ブロッホという作家について興味が尽きないなかで本書を手に取ったのだが、率直な感想としては非常に難しい作品だった。というのも、どうやらブロッホが考える長編小説の意義から誘起される難解さのようで、彼は「現代においては長編小説だけが人間の体験可能性をその全体性において描き出しうる唯一の芸術ジャンル」だと見做していたいわゆる「全体小説論者」だったという。すなわち「人間の包括的な生」を書き表すための手段として小説があるとして、その上で「人間なる存在の解剖」を目的としており、小説全体が実験、調査、観察などを通しての人間の研究を目的としたものであることが難解さの原因となっているように思われる。しかし、難解さから言えば普段の私からはほぼ読了不可能な内容であり、本来の自分のレベルを超えた場所に導いてくれるものであったと感じている。
以下では簡単なあらすじ紹介をはじめとし、この小説の構造(形態)への考察、内容解釈を書いていきたい。
Ⅰ)あらすじ
本書は上下巻三部構成となっているため、あらすじを書くにあたって各部ごとに分けて書いていきたい。
ⅰ.第1部 1888年パーゼノウまたはロマン主義
ヨアヒム・フォン・パーゼノウは裕福な地主であり農場主である父親の元に生まれ育ったが、農場の後継としては兄がいたこともありクルムの幼年学校に送り込まれ軍人となった。数年たち陸軍中尉となったヨアヒムは、軍人を辞めて商人となった幼年学校の同窓ベルトラントとの交流を通して自己内の二重の価値を感じ取る。その後決闘により命を落とした兄に代わり実家へ戻ってきて農場を継ぐように求められ、さらには男爵夫妻の一人娘であるエリーザベトとの結婚が仄めかさたことにより、その当時の恋人であった酒場女ルツェーナとエリーザベトの間で気持ちを揺らすこととなる。
ⅱ.第2部 1903年エッシュまたは無政府主義
アウグスト・エッシュは不正の責任を取る形でシュテンベルク商会の会計係を馘首され、離れた地にある船舶会社の会計係として再就職をする。バルタザル・コルンの家を間借りして生活する中、彼から独身の姉エルナとの結婚を求められるが承諾はせずに過ごしていた。ある日サーカスが街にやってきて、ナイフ投げの助手を務めるイロナに見惚れると同時にその危険な犠牲的行為をやめさせるため、自らもサーカスに入り興業を女子レスリングへ転換することを目指す。その後ある程度の成功を見せた女子レスリング事業にて、アメリカ行きの計画を夢想する。
ⅲ.第3部 1918年ユグノオまたは即物主義
この第3部については、構造的な複雑さからあらすじ説明が難しいため、ここでは物語を構成する枠組みに分けて簡単にまとめていきたい。
⑴脱走兵ユグノーは戦火を逃れて行き着いた町で素性を隠し、ヨアヒム少佐の助力を得てエッシュから印刷会社を買い取って事業を展開していく。
⑵将校ヤレツキーは毒ガスの後遺症から片腕を切り落とすことになり、その後はアルコールへ陶酔していく。
⑶塹壕で生きうめの状態で発見されたゲーディッケは奇跡的に息を吹き返し、心身ともにズタボロの状況から徐々に回復し新しい己を形づくる。
⑷ハンナ・ヴェントリングは出征した夫の帰りを待ちながら孤独な生活を続けていく。が、夫が帰郷した家にはもはや違和感を感じるようになる。
⑸哲学博士ベルトラントは救世軍の少女マリーと出会い、彼女と自分の友人たるユダヤ人のヌヒェムを引き合わせていく。
⑹価値の崩壊という哲学的論文として、他の出来事を包括的に考察しながら人間の価値の崩壊を書いていく。
第3部においては⑴を物語上の大筋としつつ、他の語りが同時進行されていきながら互いに交差する場面も交え、最終的に⑹の価値の崩壊という論文としてまとまっていく形になっている。
Ⅱ)物語の人々が属する価値世界─二重世界と逃避─
では次に、各物語において書かれている人物がどのような価値体系に属しているかを詳しく書いていきます。
ⅰ.第1部 ロマン主義への逃避
第1部において主人公として書かれるパーゼノウの属する価値体系としては、まず第一に「制服(軍服)」の価値世界というものがある。これはいわば型にはまった価値であり、常識的な因襲に従った価値体系であると言え、これはロマン主義の世界だ。そして幼年学校の同窓たるベルトラントは因襲を踏み越えた者であり、パーゼノウが所属する因習的価値体系を飛び出し因習に縛られない未知の価値体系に踏み込む道への導き手として悪魔メフィストフェレスのような存在として登場してくる。別の価値世界へ実際に移り住んだ者であるベルトラントと交流しつつ、パーゼノウは酒場娘のルツェーナとの恋愛という非因襲的な未知の世界を夢想する。
地上的なものが絶対的なものに高められる時は、そこにあるのは常にロマン主義であるから、われわれの時代の峻厳で真のロマン主義は、制服崇拝のロマン主義なのである。
『夢遊の人々 (上)』 〈34頁〉
まともな制服は、それを着用している人間を周囲の世界に対してはっきりと区別立てしてくれるからである。制服は、世界と人間とが互いに鋭くかつ明確にぶつかり合い、相互に区別し合う、曖昧模糊とした点を除去すること、それこそが制服の真実の任務だからだ。
『夢遊の人々(上)』 〈35頁〉
以上の引用にあるようにロマン主義(制服)とは、その型に嵌ることで世界に対して自分の立場を明確に主張し、絶対的なものに高めてくれる庇護の価値体系、様式であるのだ。
しかし、ロマン主義者は真の「認識を恐れる」、これは合理的に解決不能な非合理的問題(恋愛)から因襲的結婚への逃避なのである。
ⅱ.第2部 無政府(自由)主義への夢想
第2部の主人公たるエッシュの所属していた価値体系ははじめ会計係として、極度に合理的な数値の世界であったと言える。しかし、彼は自己に言われのない責任でシュテンベルク商会を馘首される。ここにおいて「世界秩序における帳簿ミス」を知覚することとなる。その時点では彼はまだ、ヘンティエンおかみの酒場で無政府主義者であるガイリングの話を聞きつつも懐疑的であり、同時に会計の仕事への不満を漏らす、ここにおいて酒場は合理的な世界秩序の世界と無政府主義との中立地点としての意味合いがあったと思われる。
エッシュは思い返してみた、マルティンは子供の時分からもう跛だったかな。奇形児なんだ、とひとりごとを言い、そして口に出して、「あいつはおれも赤の仲間に入れたがっているのさ。でも入るもんか」(……)「おれの性に合わないんさ。おれはのしあがろうと思っている。のしあがろうとするなら、秩序ってものが大切だからな」
『夢遊の人々 (上)』 〈301頁〉
彼らはすきま風を恐がっており、ドアがぱっと押し開けられると、だれかが入って来て、自分たちから顔をそむけやしないかと恐れる。そんなことをされたら最後、もう罪と贖罪のあいだを公正に判断することができなくなるからだ。そうされた人は二プラス二は四だということを疑い、自分が自分の母の子であって、決して奇形児ではないということを疑る。(……)彼らが営むビジネスの中にこそ、彼らの共同体があるからだ。力がなく、しかも不確かさに充ち、悪意に充ちた共同社会が。
『夢遊の人々 (上)』 〈301頁〉
その後エッシュは社会的な秩序世界への懐疑を深め、サーカスでナイフ投げの的にされる曲芸助手イロナを見て、それを崩壊した社会的秩序下の犠牲者の象徴であると感じ取り、狂った世界秩序外へ逃れる無政府主義の方向へと舵を切ることになる。この無政府主義はあくまで自由主義的なものに留まり、彼はここにある社会的秩序から完全に無縁な場所としてアメリカへと逃れることを望む。
「われわれはアメリカへ行くんだ」(……)「愛は無縁さの中でしか可能ではない。もし愛そうと思うなら、新生活を始め、古いことはいっさい無にしなくてはならないのだ。(……)犠牲は払わなくてはならないのだし、世界に正邪曲直を分ける秩序がやって来て、イロナがナイフの危険から守られ、生きとし生けるものにおしなべて純潔無垢の状態が送り与えられ、どんな人ももはや牢獄で呻吟するようなことがなくなるためには(……)
『夢遊の人々 (上)』 〈497頁〉
だが、エッシュはサーカス団長に売上を持ち逃げされたことによりアメリカ行きを断念し、ヘンティテンおかみと結婚して故郷で大企業の会計士の仕事を見つける。彼の無政府主義(自由主義)への逃避は社会の悪意によって砕かれ、不満を抱えながらもその世界秩序に染まっていくことになる。
ⅲ.第3部 戦禍における夢遊の人々
あらすじにおいて紹介した通り第3部は複数の物語が別々に進行していくため、包括的な状況をはじめ、物語の主軸たるユグノオの属する価値体系を中心として書いていく。
まず前提として、物語は1918年の第一次世界大戦下を舞台として展開していく。その渦中の人々の認識は下記の引用に表れている。
ヤレツキーは笑った、「まともになるためか、世間人の暮らしに舞もどる道を見つけようというセンチメンタルなあがき、身を固め、あっちこっちで交尾してあるくことなんかよしにして結婚すること……だがそんなこと、君だって自分同様信じてなんかいはしないんだ」(……)
「戦争は……決して……終わる……ことなんか……ない……からだ……何度それを言わせようってんだ!」
『夢遊の人々(下)』 〈107頁〉
ここに表れているように、第3部の人々は皆戦争によって一般の暮らしにもどることが困難とされる状況にある。こうした中でユグノオは脱走兵として逃げてきた上でそれを隠し、エッシュから『クルリトール通信』を買い受けて事業を行う。エッシュは戦禍においても自分の商人(即物主義)としての価値体系に所属し続けた稀有な人物といえよう。彼は自らの身を置く価値体系の秩序が回復することを信じ続ける人物として書かれているのだ。
世界は善と悪、借方と貸方、黒と白に分けられており、帳簿上の誤りがおかされるようなことがおきても、そんな誤りは消し去ることができたし、またそれは消し去られるだろう。
『夢遊の人々(下)』 〈107頁〉
このあくまでも職業倫理を貫く姿勢は、下記引用が根拠とされている。
かつての日のごとく進行の庇護に憧れるとしても、人間は自立したもろもろの価値の雑然たる働きの中で途方に暮れてたたずむであろう。そして彼の職業になってしまっている個別的価値に従属する以外に残された道はあるまいし、この価値の機能となる以外に残された道はあるまい──価値の過激な論理性に食い尽くされ、価値のわなに落ちこんだ職業人になる以外に残された道はないのだ。
『夢遊の人々(下)』 〈196頁〉
すなわち職業人としての(自己が所属する)価値世界を、人間は払拭しえないということを根拠としてユグノオは戦禍においても商売を続けようとするのだが、同じ根拠は第3部における他の人々には当てはまるのだろうか?──答えは否である。なぜならば、それらの人々は自らの個別的価値世界に留まる術を奪われた人々であり、価値崩壊によって強制的に所属していた世界から投げ出された人々なのだ。それによって彼らは、生きるために新たな価値世界への順応が要請されることになる。
その手段は様々だ。アルコールへの陶酔、死(零)の地点からの新たな価値の形成、宗教(プロテスタント)への従属、そして順応を望みつつ死にゆく者。すなわちユグノオ以外の人々は自らの従属する価値世界を失った者は、新たな価値世界への所属か、その創造か、もしくは死という道しかないことの象徴として書かれているのだろう。
いずれにせよ重要な事柄は、すべての人々はたとえ所属する価値世界の思考様式を憎悪し、他の価値世界を夢想しつつもそこに所属し続けるほかない存在、もしくは所属する価値世界から投げ出され新たに所属する世界を探す存在、すなわち此処ではない価値世界を夢想し、探し求める『夢遊の人々』であるということだ。
Ⅲ)多重な価値世界で孤独を背負った人々
以上のように、本書『夢遊の人々』に書かれた人々は永遠に自己所属の価値体系を探し求める存在であり、これは絶対的価値体系として存在していた宗教、すなわち「神の庇護」を失った現代人が書かれている。また、彼らは自らが身を置く価値体系であってもそれは逃避や陶酔のための仮の場であり、所属する価値体系と自己には絶対的な隔たりがあり、所属の価値世界/思考様式下おいて真に思考を共有する者は存在しない孤独な存在なのである。
ところでかつては神の似姿であった人間、世界価値の鏡であり、その担い手であった人間は、もはやそのようなものではなくなっている。人間がかつて保護されていた安全さについてなおかすかに知っているにしても、またいかなる上位の理論が彼の正気を狂わせたのかを人間は自問するにしても、また無限なものの恐怖に突き落とされた人間、そうした人間がいかに戦慄するとしても、さらにまた人間がロマン主義と感傷性に満ちていてかつての日のごとく信仰の庇護に憧れるとしても、人間は自立したもろもろの価値の雑然たる働きのなかで途方に暮れてたたずむであろう。
『夢遊の人々(下)』 〈196頁〉
世界は英知的な自我の措定である。というのはプラトン的理念はどこまでも失われはしなかったし、また失われることもないからだ。とはいえこの措定は「ピストルから発射された」ものではなく、ただ依然として価値主体が措定されうるだけである。価値主体は、それはそれで英知的な自我の構造を反映し、そしてそれはそれでその独自な価値措定、その独自な「措定の措定」「措定の措定の措定」といった具合に無限の反復における措定である。
『夢遊の人々(下)』 〈402頁〉
世界は自我の措定でしかないということ、世界の根拠たる価値主体を語ろうとするとき、それを遡った先はまた別の価値主体となる価値があり、これは無限に繰り返されてその根源にたどり着くことは決してない。必ずどこかで措定に行き着き、その措定を主張しはじめた存在、いかなる価値体系的根拠を伴わない自己根源は発見しえない存在なのだ。
Ⅳ)現代人に救いはないのか?─『ウェルギリウスの死』を読みましょう!─
では、宗教的な絶対的価値体系/思考様式を失ってしまった現代人は、一時的な陶酔ができる逃げ場に隠れ、孤独の不安を抱えたまま朽ちてゆくしかないのか? それはわからない。だが、本書では救世主の可能性が示されている。
自らの孤独を自覚し、自分自身の記憶から逃亡する人間の不安は大きい。(……)閉じられた環の末路の軌道を先に立って歩む指導者、この者こそ死せるものがふたたび生けるものとなるために、新たに家を建てるであろう。この者自身死者の群れからよみがえったのであり、時が新たに数えられるように、彼自身の行為のなかでこの時代の不可解な事象を、意味あるものとするであろう救世主なのだ。
『夢遊の人々(下)』 〈547頁〉
ここで示される救世主こそ『ウェルギリウスの死』で書かれているウェルギリウスに他ならず、彼は死に瀕したとき己の精神的営みすべての意義を疑い、自らが家を建てる者になることを諦め犠牲に殉じるために自らの集大成である著作『アエネーイス』を焼こうとする。しかしそうした考えを持ってもなお、彼は決して言葉を紡ぐ試みをやめることはなく、夥しい数の比喩と象徴の言葉の世界を生み出し続け、その行為の中にかすかな光を見出す。それらはここで幾ら言葉を書き連ねてもとても書き表せない。是非とも『ウェルギリウスの死』を読んでいただきたい。
読了が困難な道のりであることも確かに間違いないが、それだけの困難に値する価値としての体験ができる。言葉を超えた光の知覚が表現された一冊だ。
Ⅴ)さいごに─生きるということ─
このように『夢遊の人々』においては救世主の可能性が書かれ、『ウェルギリウスの死』においては救世主の誕生の追体験が実現されている。ただ注意点として、これらの本は人間の究極の到達点として確かに凄まじい力を持ってはいるものの、あくまでそれは光の予感、人を後押ししてくれる力の域を出ることはできない。だからこそ私は何よりも、本書の最後に書かれた言葉を忘れずにいたい。
ロゴスの沈黙のなかでそれはためらいがちにひびくが、それでいてロゴスに担われ、非・実在物の喧騒を圧して高められる。それは人間と民の声であり、慰謝と希望と直接の恐怖の慈悲の声なのだ、「自害してはいけない! われわれはみなまだひとり残らずここにいるのだから!」
『夢遊の人々(下)』 〈549頁〉
いうまでもなくこれは比喩だ。だが、自らの内にこの声を聞いたことがない人間などいないのではなかろうか。これは自らの存在が発する「死を恐れ、生きたいと望む声」であり、ひとつの存在のうちにある自我・価値観・思考様式などあらゆる苦悩の根源でさえ、絶対的に死を望んでいることはないのだと私は思う。自らのうちにあるものが発する声なき声、少なくともこの弱弱しい存在に恩赦を与える権利は常に我々の手の内にあるのではなかろうか。そしてこの恩赦、生の恩寵を自己に与えることこそあらゆる存在の根源に位置付けられた原初の措定ではないか、人間はただ生きることができる場所を探しているだけであり、ただ生きていさえすれば、それ自体が根源的統一を果たしていることになるのではないかと、そんなメッセージが含まれているように私には感じられた。
以上、大変な長文失礼いたしました。全部読んでいただけた方も、そうでない方も、お時間割いていただき本当にありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
