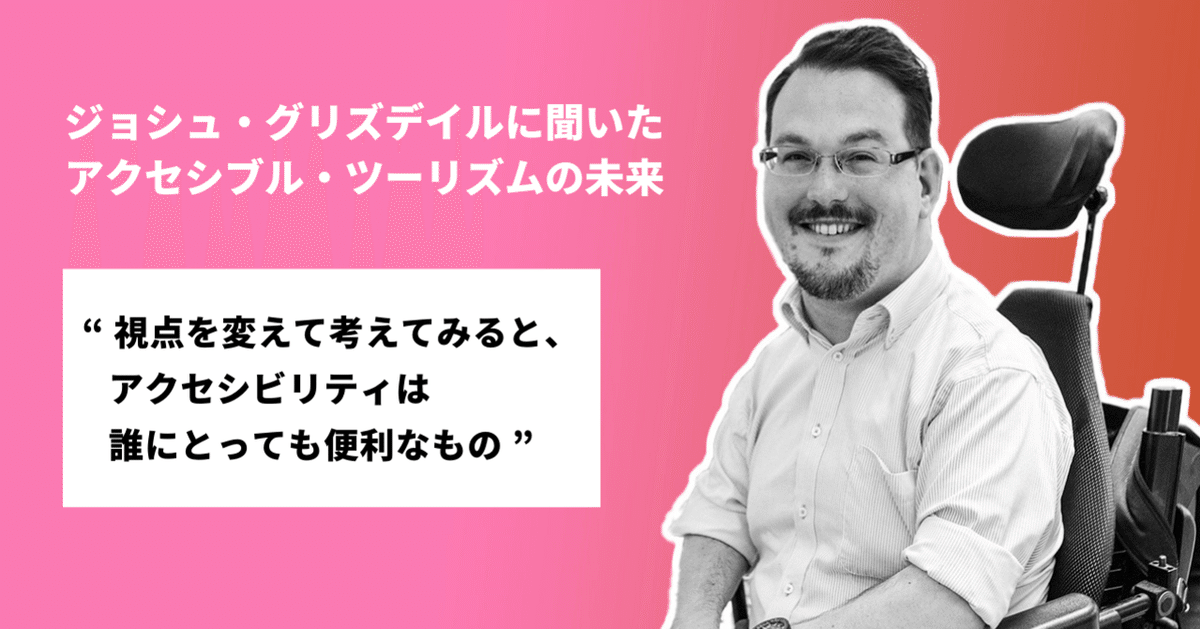
「アクセシビリティは誰にとっても便利なもの」と語るジョシュ・グリズデイルに、日本のアクセシブル・ツーリズムについて聞いた
満員電車。渋谷のスクランブル交差点。狭い路地裏の飲屋街。
多くの訪日観光客が「これこそがJAPANだ!」と言わんばかりに、ワクワクしながらカメラを向ける景色だ。しかし、そんな日本のイメージは、障がいをもつ海外の人々にとっては“不安材料”ともなりうる。
日本がアクセシブルなわけがない — カナダの高校を卒業したばかりの車いすの青年、ジョシュ・グリズデイルもそう思っていたひとりだった。しかし、2000年に初めて日本を訪れたとき、彼は日本が想像以上にアクセシブルな国であることに驚いた。
今回、しいたけクリエイティブが運営するジャパントラベルアワードの審査員に就任したジョシュ・グリズデイル氏(以下、グリズデイル)に、日本での自身の経験や、アクセシブル・ツーリズム実現のために日本ができること、そして日本の観光に対しての想いを語ってもらった。
取材・文:本郷アレクサンドラ(しいたけクリエイティブ)
翻訳・編集:本郷誠哉(しいたけクリエイティブ)

ジョシュ・グリズデイル | Josh Grisdale
カナダ出身。四肢まひ性・脳性小児まひにより、4歳より車いす生活。現在は、高齢者施設でウェブマスターとして勤務するほか、障がいを持つ外国人旅行者のための情報サイト「Accessible Japan」の運営や、国や自治体、企業向けに講演を行うなど広く活躍。2007年より東京在住、2016年に日本国籍を取得。
ー そもそも日本に来たきっかけは何でしたか?
グリズデイル:高校時代に日本語の授業を選択したことがはじまりでした。先生が結構いい加減な人で、毎週金曜日は日本の映画やテレビ番組を見るだけだったんです。でも、それが高校生の自分にとってはとても楽しい授業でした。もし真面目に文法ばかり教える先生だったら、今私は日本にいなかったと思います(笑)。
適当に教えていた先生と聞こえてしまいますが、素晴らしい先生で、日本語はもちろん、ちゃんと日本の文化や歴史についても教えてくれました。そんな先生と出会いのおかげで、日本に興味を持ちはじめました。
高校を卒業した2000年には、父と一緒にはじめて日本を訪れ、その後、2007年には日本に完全移住、2016年には日本国籍を取得しました。
ー まさか自分の授業スタイルがきっかけで生徒が日本国籍まで取得したなんて先生は信じられないでしょうね…。日本に永住しようと思った理由を教えてください。
グリズデイル:私が日本に来たばかりの頃は、観光庁もまだ設立されておらず、日本を旅行するための情報もほぼありませんでした(編集部注:観光庁は2008年に設立)。なので、車いすの自分が日本に旅行するというのは本当に未知の領域でした。
「たとえうまくいかなくても、挑戦したと言えるから」と、両親には新しいことに挑戦するよう常に言われて育ちました。そんな教えの後押しもあり、恐る恐る来日したのですが、いざ日本に着くと良い意味で裏切られました。20年前以上の当時ですら、日本はアクセシブルな国だったのです。

日本に来る前は、映画やテレビで見た日本のイメージしかなく、アクセシブル・ツーリズムに関する情報があまりなかったため、何を期待していいのかわかりませんでした。でも、一度来てみて、日本なら安心して旅ができるという自信がついたので、その後何度も日本を訪れました。
「バリアフリー」の概念が年々広がっていたためか、来るたびに、より遠くへ行けるようになりました。そして、来るたびに日本が私に対して心を開いてくれているように感じたんです。それで、いつか日本に住もうと決心し、2007年からずっと日本で暮らしています。
ー 日本のアクセシブル・ツーリズムは、グリズデイルさんが来日してからどのように変わってきたのでしょうか?
グリズデイル:最も大きな変化は、アクセシビリティに関する法律に多くの改善がなされたことです。例えば、私が日本に移住する数年前に、障がい者の移動に関する最初の法律が制定され、その法律によって、電車の中に車いすの人のためのオープンスペースが設けられました。私が日本に旅行に来ていた頃は、車いすの人をほとんど見かけませんでしたが、今では多くの人がそのスペースを利用しています。
そして2014年、日本は国連の「障害者の権利に関する条約」を批准し、その中では、【障害者の権利を保護する法律を制定しなければならない】と規定されていました。これを受けて、2016年4月に「障害者差別解消法」が施行され、これまでで最も大きな変化がありました。さらに、2011年には「障害者基本法」が改正され、法律の制定に障がい者が関与しなければならないことが明記されたことも極めて重大な変化でした。
ー そんな風に法律が変わっていたとは、恥ずかしながら全く知りませんでした…。法律が変わることによって他にどんな変化があったのでしょうか?
グリズデイル:私自身、政府の複数の委員会に所属しています。委員会の活動は、アクセシビリティに関して政府が行っている法整備のレビューも含まれています。このように当事者が参加する形でアクセシビリティに関する法律が制定され、施行されたことで、社会的な変化も起こり始めました。
インフラが改善されると、障がい者の移動が容易になり、その結果、彼らはコミュニティに参加するようになります。そして、外に出ることで、よりよく見られるようになります。そうすると、新しい議論が生まれ、これまで考えもしなかったことを考えるようになります。障がい者も健常者も関係なく、人々のマインドセットをガラリと変えることができるのです。
ー これは、政治の力が社会にプラスの影響を与えることができる良い例ですね。グリズデイルさんもいずれは政治家に立候補するつもりですか?
グリズデイル:いや、絶対にありません(笑)。でも、投票を通して政府の決定に参加するのは楽しいですよ。私が日本国籍を取得しようと思った理由のひとつです。自分の未来を切り開くために政治に参加したいのです。
ー Accessible Japan(アクセシブルジャパン)をはじめたきっかけについて教えてください。
グリズデイル:先ほどお話したように、私が日本に来たばかりの頃は、アクセシビリティに関する情報があまりありませんでした。なので、自分の言語能力や旅行好きという特性を活かして、その状況を変えたいと思いました。
海外の障がいをもつ人々の多くは、「日本はアクセシブルではない」と決めつけて、旅行先の候補にすらしない人がほとんどです。なぜそういったイメージを持たれているかというと、良くも悪くも、日本に関するセンセーショナルな情報がSNSで多く見られるからです。
満員電車に駅員がさらに人を押し込む動画がわかりやすい例です。もちろん、常にあんなラッシュアワーのような状況ではないですし、日本全国でも東京など本当に一部だけの現象です。しかし、車いすに乗っている人は、あの映像を見て「あんな電車には絶対に乗れない!」と思ってしまうでしょう。インスタ映えすると人気の高い、小さな横丁なども同様です。「狭くて車いすでは通り辛そうだし、お店にも入れない!」って思いますよね。
ー 確かに、あの状況で車いすに乗って電車に乗るのは…。ああいった日本のイメージもあって、アクセシブル・ツーリズムとは結びつかないんですね。
グリズデイル:その通りです。だから、正しい発信が必要です。『Accessible Japan』をはじめた理由のひとつは、「日本への旅行は論外」だと思っている人々に、日本は訪れる価値のある場所だということを伝えるためです。また、日本での旅行を楽しむために必要不可欠な情報を提供したいとも考えました。

旅行を計画しているときってワクワクしますよね。障がい者の方ももちろん同じですが、「ここは自分でも行けるかな?」といった疑問がつきまといます。そして多くの場合、不安がワクワクを上回ってしまい、断念してしまうんです。そこで、必要な情報を提供することで、そのような感情を和らげることができればと思いました。
ー 日本は世界でも有数のバリアフリー先進国であるにもかかわらず、その実力や成果が観光に反映されていないという指摘もあります。例えば、旅行サイトや観光公式サイトで、アクセシビリティに関する情報が掲載されていることはほとんどありません。
グリズデイル:日本ではソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)の推進が遅れています。(障がい者の旅行という観点でいうと)その理由のひとつは、多くの人が「障がいのある人は旅行に行かないだろう」と誤解しているからです。残念なことに、日本ではそれがただの誤解ではなく現実とも言えるのですが。
日本では、市区町村から派遣されたケアアテンダント(介助スタッフ)制度を利用して、身の回りの世話や日常生活の手助けをしてもらうことができますが、ケアアテンダントに旅行に帯同してもらうには特別な許可が必要です。
また、ケアアテンダントを利用できる時間には上限があるので、一緒に旅行に行くとなると、ほとんどの時間を使い切ってしまうことになります。ですから、観光業界の人たちは、障がい者が旅行する姿をあまり見ていません。そして、目にすることがなければ、アクセシブル・ツーリズムという発想は出てこないのではないでしょうか。

しかし、コロナ前の数年間は訪日観光客が大幅に増え、障がい者の方に触れる機会も増えたと思います。先日、仕事で浅草に行ったのですが、3、4時間の間に10人ほどの車いすの方にを見ましたよ。だから観光業界は、アクセシブル・ツーリズムをもっと有効的に活用する必要があります。その有益性が十分に理解されていないので、もったいないと思いますね。
ー パンデミックで観光がストップしている今、これまでの活動を振り返り、いずれ観光客が戻ってくる時のための準備をする良い機会です。アクセシブル・ツーリズムを実現するために、日本が今できることは何だと思われますか?
グリズデイル:そうですね、今は将来に向けて何を準備すべきかを考える本当に良い機会です。当然、国内旅行が先に戻ってくるはずですが、高齢者人口が増えている日本では、多くのシニア層が旅行に出かけるでしょう。そのための準備や情報発信をするには良い時期だと思います。
シニア層の旅行習慣についての調査があったのですが、そこでわかったことは、70歳前後になると、人々の旅行の意思が完全に低下するということです。
主な理由は、「年齢が進むにつれて以前と比べできなくなることが増えるが、家族に負担をかけたくない」という思いです。旅行に行きたくても、人の介助なしで難しい。要するに、アクセシブルではないということが原因です。私たちが手段を提供すれば、もっと多くの人が自由に旅行に行けるようになるでしょう。
ー そう考えるとアクセシブル・ツーリズムは観光業全体に大きなメリットがありますね。グリズデイルさんがこれまで旅行したことのある日本の地域で、身体に障がいのある海外旅行者にお勧めの場所はありますか?
グリズデイル:多くの障がい者にとって、日本での移動は比較的簡単です。しかし、いくつか挙げるとすれば、まずは沖縄です。石垣島では、島と島を結ぶ船がバリアフリーになっていますし、バリアフリーのタクシーもあります。竹富島では水牛車に乗るアクティビティが人気ですが、車いすでも乗ることができます。沖縄の小さな島でもこのようなことを考えているのかと感心しました。
鳥取もお勧めの場所です。鳥取県は日本で最もアクセシブルなタクシーの割合が高いんです。今はわかりませんが、過去には数時間、数千円でタクシーに乗れるというキャンペーンもありました。砂丘では、砂に埋もれない車輪のついた特別な車いすを貸してくれます。
私もまだ行ったことがないのですが、他にも、奄美大島にはバリアフリーのダイビング施設があり、エレベーター付きの特別なボートで車いすで海に入ることができます。山形では、障がい者向けのパラグライダーがあるんですよ。
長崎では軍艦島に行く機会がありました。軍艦島はバリアフリーではありませんが、担架で階段を運んでもらい、見ることができました。あれは夢のようでした。とてもクリエイティブなアプローチでアクセシブルにしていたのが印象的でした。
ー バリアフリーのアクティビティも多いのに驚きました。グリズデイルさんは海外旅行にもよく行かれるそうですが、特にアクセシブルな国と印象を受けた国はありますか?
グリズデイル:シンガポールはすごいですね。もちろん、小さな国だからこそ、インフラ整備に資金を投下できるメリットもありますが、シームレスでとても移動しやすいです。すべてのバスや電車がバリアフリーになっていて、事前に考える必要がありません。
日本では、ほとんどの駅がバリアフリーになっていますが、入り口の場所などを事前に確認しなければならないことがあります。シンガポールでは、すべてとは言わないまでも、ほとんどの観光スポットがアクセシブルでした。
オーストラリアも最高でした。地元のタクシー会社がアプリで車いすタクシーを簡単に予約できるようにしていて、15~20分で来てくれました。日本では通常、車いす対応可の会社を知っている必要がありますし、事前に予約する必要があります。料金も普通のタクシーよりも少し高いこともあります。
ー 日本が海外から取り入れられるもので、まだ十分に普及していないものはありますか?
グリズデイル:タクシーのシステムがそうですね。日本の新しいタクシーについては、多くの人がバリアフリーではないと言っており、賛否両論があります。私のように大きな車いすに乗っている人は、乗るのが大変なんです。また、乗れたとしても、車いすの一部を外さなければならなかったり、横向きにならなければならなかったりと、必ずしも理想的ではありません。また、タクシーの運転手の多くは、車いすのお客さんを拒否します。
日本の電車は交通の便が良いのですが、電車とホームの間に隙間があって、車いすの人が一人で乗るのは難しいことがあります。そこで、駅員さんに頼ってスロープを敷いてもらうことになります。サービスはとても良いのですが、本来はサービスを利用せず、自分で電車に乗るのが理想的ですよね。シンガポールでは、それが実現していました。日本も少しずつそうなってきていますが、完全に実現するにはまだまだ時間がかかりそうです。
もうひとつのポイントは、クリエイティブな発想と柔軟性です。例えばオーストラリアでは、あるレストランでテラス席を予約していたのですが、予想以上に寒かったので室内に移動したかったんです。バリアフリーではなかったので移動できるか心配していたら、携帯用のスロープを設置してくれて、事なきを得ました。
これは、日本でも改善できる点だと思います。多くのレストランには、まだ階段が設置されています。レストランはほとんどが賃貸なので、自由に変更できないことが多いからでしょう。それは変えられない事実かもしれません。
しかし、クリエイティブな発想で改善は十分可能です。Amazonで2万円くらいで売っているスロープを設置すれば解決する問題かもしれないのですから。こういった発想が増えれば増えるほど、アクセシビリティは当たり前で、新しいスタンダードになっていくのだと思います。
ー Amazonで買えちゃうんですね…。2万円でより多くのお客様が幸せになるのであれば安い投資です。では、アクセシブル・ツーリズムから日本はどのような恩恵を受けられるのでしょうか?
グリズデイル:「アクセシビリティへの投資は、ある一定の割合の人々にしかメリットがないのでお金の無駄」と考える人もいます。しかし、視点を変えて考えてみると、アクセシビリティは誰にとっても便利なものです。
私が日本に来たばかりの頃は、エレベーターは障がい者のためのものだと思われていたので、多くの人が利用を控えていましたが、今では多くの人が利用していて、とても助かっています。

例えば、ニュージーランド大使館に行ったとき、私が入れるように入り口の階段部分に簡易スロープを設置してくれました。ちょうどそのとき、後ろから配達員がたくさんの重い荷物を台車に載せてやってきたんです。そこにスロープが設置されていたおかげで、配達員も台車ごと建物内に入ることができました。
もしスロープがなかったら、配達員は1つ1つの荷物を手に持って運ばなければならなかったかもしれません。そして、受け取る側も配達員が荷物を運ぶために往復する間、ずっと待っていなければならなかったかもしれません。
施設に簡単なスロープを設置することは、誰にとってもメリットがあります。余分な出費ではなく、投資なのです。アクセシブル・ツーリズムにも同じことが言えます。インクルーシブで多様性があることは、日本全体の利益につながるはずです。
ー ジャパントラベルアワードに期待することや、日本のアクセシブル・ツーリズムのさらなる向上のために、ご自身の専門知識をどのように活かしていきたいとお考えですか?
グリズデイル:私にとって最も重要なことは、観光事業者がアクセシビリティの重要性に気づくことです。今回の取り組みを通して、今まで考えていなかったことが見えてくるかもしれません。
「車いすの人があの観光スポットには簡単に行けるのかな」「私たちの街には、LGBTQフレンドリーな場所ってあるのかな」と、今回の取り組みを通してはじめて考えることがあれば嬉しいです。
ジャパントラベルアワードの受賞地がその取り組みを評価され、観光客の増加につながることを期待しています。インクルーシブで多様性に富んでいることが、地域や観光事業者にとってメリットがあることを実感してもらうことが大切です。結果として、そのような場所が、他の地域や事業者にとってお手本となれば良いなと願っています。
ー 各デスティネーションを評価する際に、最も重要な要素は何ですか?
グリズデイル:交通手段です。それには2つの要素があります。目的地に行くための交通手段と、目的地での移動手段です。後者は、地方の場合、特に問題とされていますよね。
・そこにたどり着けるか?
・楽しく過ごせるか?
・宿泊できるか?
これらが、私にとって基本的な基準です。ある街に滞在したくても、そこにバリアフリー対応の宿泊施設がなかったために、泣く泣く別の街に移動したこともあります。
また、(地域や観光事業者の)姿勢も私にとっては最も重要な要素の一つです。たとえその場所に課題があり、アクセシブルな場所としての基準を完全に満たしていなくても、変わろうとする気持ちと、改善のための柔軟でクリエイティブな考えを持っていれば、それは評価されるべきですから。
ー まったく同感です!変化の必要性を認識し、それに取り組もうとする姿勢こそが、何よりも魅力的で、本質的な変化のはじまりです。そのきっかけになればと思い、ジャパントラベルアワードをスタートさせましたし、それが実現することを私たちも願っています。グリズデイルさん、取材のご協力どうもありがとうございました!
編集後記:
簡易スロープがAmazonで2万円ほどで買えるというお話が個人的には考えさせられました。本当にすぐにできるアクセシブルな環境づくりですが、これまで一度も考えたことがありませんでした。まずは考える、そこがスタートだと実感しました。
小さなことからでもより多くの人がアクセシビリティについて考えるようになれば社会は変わるのかな、と思いました。(本郷誠哉)
※ 実際にAmazonで「車いす スロープ」で調べてみたら、駅員さんが使っているようなしっかりしたものがたくさん出てきました。Amazon Prime対応も!(明日から使える!!)一例として、下にリンク貼っています。
ジャパントラベルアワードについて
ジャパントラベルアワードは「世界中の人々の心に響く日本」を全国から見つけ出す活動です。自治体や団体における観光やダイバーシティ推進に関する取り組み等をもとに、年に一度、グランプリを含む10のカテゴリーで日本の新しい「感動地」を各業界のエキスパートらが審査・表彰し、世界に向けて発信していきます。
エントリーサイト:https://japantravelawards.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

