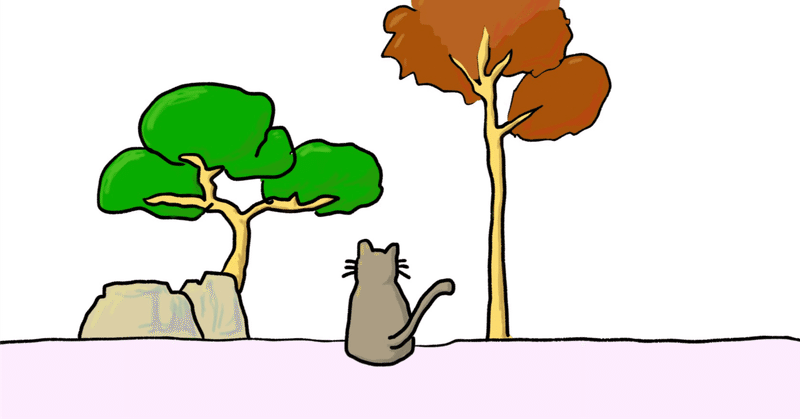
【短編小説】 猫と日記
数週間前から日記を書いてます。でもそれは私の些細な毎日の記録ではなくて観察日記です。同棲中の彼氏が実は猫化しています。もともと極度の猫背ではあったのだけれど、本当に猫になるとは…驚いています。何かのメタファーとかじゃなくて、毛が生えてきて、耳が生えてきて、尻尾が生えてきて、昨日は四足歩行で歩いていました。あくびの代わりにニャーと鳴きました。
今日は夜ご飯にポトフを2人で食べています。これも元々が猫舌だったから食べるのが遅いのに変わりはないけど、最近できた肉球が邪魔でスプーンが使いづらそう。
「この肉球のせいでさ、仕事ができなくなってきてるんだ」
「あーキーボード打ちにくそう」
「コード打ち間違えてエラーばっか出て怒られてばかり」
「在宅勤務だから大丈夫って言ってたけど、やっぱり休職したら」
「そしたら一日中寝てるだけになっちゃって、本当に猫になっちゃうよ」
もう猫になってるよ、その言葉はコップの水と一緒に飲み込みました。症状はどんどんと進行しています。一番気がかりなことを聞いてみました。
「記憶は、まだちゃんとある」
「人間としての、だよね」
彼の目が泳ぎます。すかさず聞いてみました。
「先週末の晩御飯は」
「えっと、いつも通りだったよね。ご飯と、おかず。えっと、ホッケだったっけ」
しどろもどろの答えに、合ってるよと答えました。優しさではありません。これ以上のやりとりがめんどくさく思えてきたからです。本当は先週末は久しぶりの外食に出かけたのです。帽子を被ってマスクをすれば大丈夫と説得して、周りの目を気にする彼のために個室席がある居酒屋を予約して出かけたのです。私だってもうその日にどんな話をしたとか、どんな場面を共有したとか、細部については曖昧なので彼のことを責めるつもりはありません。とりあえず付き合って数年目といった記念日だったのです。
いまさら指輪を渡されました。わざわざ食事に誘ったのは私の方なのに、大仰なしぐさで差し出されたそれになんだか気持ちが冷めてしまったのでした。いままでお金がなかったという言い訳は100歩譲って飲み込むとしても、せめてもっと早く言葉だけでもくれていれば違ったのかもしれないのにと、彼が猫であるとか人間であるとか関係なしに私のなかにはもう思い出だけしか残っていないことを確認してしまったのです。そうして私がプロポーズを断ったことも彼は忘れてしまったのでしょうか。
夕食を終えてクイズ番組を観ながら3種類の味が入ったアソートタイプのピノを食べました。そっと彼の様子を盗み見ます。スプーンよりはピックの方が使いやすそう。そしてアーモンド味ばっかり選んで食べてやがります。少し意地悪がしたくなりました。
「猫にとってチョコもアーモンドも毒なんだよ」
「ニャッ…じゃなくて、えぇ!もっと早く言ってよ」
「なにそれ、もう自分は猫だって認めちゃってるじゃん」
「そんなことはないんだけど」
そう言ってるうちにTVのなかでは案の定クイズ王が優勝して賞金100万円を手にしました。ここぞとばかりに彼にかまをかけてみたのです。
「あの指輪さ、いくらしたの」
彼はハッと目を見開いて慌てふためきました。もふもふになってきてる毛が逆立って尻尾がピンと伸びました。動物は人間よりもずっと感情が表に出て、そんな単純明快さは嫌いではありません。
「思い出した。あの居酒屋で食べた刺し盛り美味しかった。」
「美味しかったね。それで、あの指輪は月給何ヶ月分だった」
「男の意地として絶対言わない」
「じゃあキャットフード何個分かで答えて」
「キャットフードの値段もピンキリだろ」
夜な夜なAmazonで売れ筋のキャットフードを調べてるもんね、そんな言葉を飲み込んだのは流石に優しさです。
「指輪って返金してもらえないの」
だけどその代わりにふと口をついて出た言葉の方がよほど残酷に響きました。彼はそれから俯いて、そんな丸まった背中を見てるといまにも萎んでただの三毛猫になってしまいそうでした。元気だしなよ、も、一緒に過ごした時間は消えないからさ、もどこか抱えている感情とはほど遠い気がしてその言葉が言えなかったのは、やっぱりちょっとだけ私の心のなかにもわだかまっている未練のせいでした。あなたが完全な猫になるまではここにいていいよ。猫になったらうんとあごの下を撫でてあげる。それから陽のよく当たる、猫好きの老夫婦が通っていそうな居心地のいい公園を探して離してあげるよ。そう画策して日記を書き続けているのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
