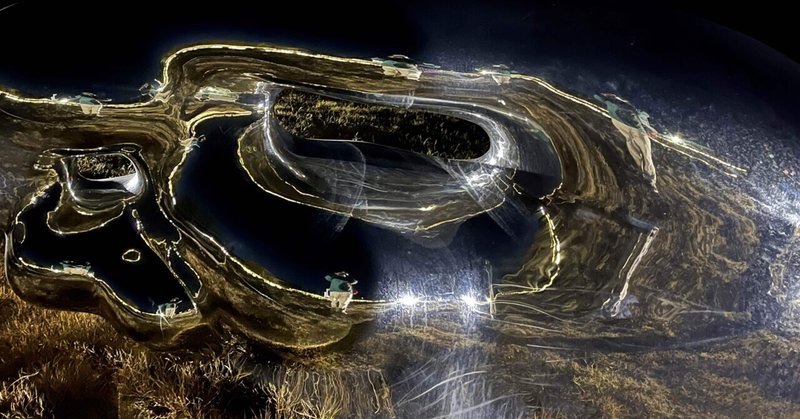
メンタルヘルスとポップカルチャー~生きづらさを逃がすこと
一端の若手精神科医が日々の診療で感じていること、そこから連想したポップカルチャーの話をまじえながら書き残していく文章のシリーズです。
生きづらさの拠り所
街のメンタルクリニックに勤めていると「今日が初めての精神科/心療内科の受診だ」という人をよく診る。特に最近は若い人、特に高校生の来院が多いように思う。理由は様々だがやはり学校にまつわるものが多い。行く気力が起きない、友達との関係性をうまく築けない、人に言われた言葉を気にしてしまう。コミュニケーションにまつわる苦しさは学校生活で直面しやすい。
自分の状態に対して理由を知りたいという方も増えたように思う。話を聞けばADHD(注意欠如・多動症)のチェックリストや発達障害の簡単な診断がSNSやYouTubeで多く出回っているらしい。確かにツイッターで見かけたことがある。自分の"生きづらさ"の原因を暴きたい、そして拠り所を作りたいという気持ちは納得できる。診断がつけば、適切な環境調整が行うこともできるだろう。自分の特性を知ることは生きていくうえで何かと役に立っていく。
一方ではっきりと診断がつかないケースももちろんある。言うなれば個性や考え方のクセとみなされるもの。そしてそれは生まれつきの部分もあるが、環境的・後天的な要因が影響しているケースも多い。じゃれ合いや冗談として「太ってる」と言われ続けたことが結果として摂食障害に繋がるであるとか、学校での陰口がその後も人目を気にしてしまう性格を生むであるとか。当人が気付かぬうちに誰かが誰かに与えている影響は計り知れない。そして同時に、多くの人がひしめき合う社会そのものが目の前に立ちふさがり、暗澹たる気持ちになる。生きるとは、他者に影響を及ぼすということなのだ。
家族の近さ
生まれた時から接する社会の1つである家族が生きづらさの背景になっているとやはり根が深い、と思わざるを得ない。客観的な目線が入ることがなく、親も子も気づかぬうちに双方に影響を与え合う。そんな状態で結ばれていく関係性で出来上がっていく、その人の考え方のクセや思考パターン。家族が故の距離の近さで良かれと思って振る舞ったこと、子が思春期であるタイミングでの感情の掛け違え、生きづらさの要因になることは至る所にある。
Netflix映画「パワー・オブ・ザ・ドッグ」(2021)でベネディクト・カンバーバッチが演じたフィルは家族や新しく家族となる人物を抑圧し、他者に対して支配的に振る舞っていく人物だ。その無自覚な有害性が周囲の人物に影響をもたらす様には眉をひそめてしまうものだが、彼自身が抱えている気持ちもまた嫌悪感だけで排除できないことが映画を観れば分かる。その時代とその境遇。そして生い立ち、育てられ方。誰かだけを断罪することができないことが多いのが家族関係である。映画の中にもその苦しみが描かれていた。
「空白」(2021)はやり場のない怒りや"良かれと思って"の恐ろしさ、そして無関係な人物たちの怖さを描いた映画だが親子関係の描き方も重厚であった。古田新太演じる父親の威圧感は娘を想いやる気持ちも感じ取れはするのだが、その圧迫感はやはり娘の怯えた姿に繋がる。また、劇中で片岡礼子が演じているある人物の母親の言葉も個人的には不穏なように聴こえた。「逃げる」という言葉、そして「責任」という言葉。映画には描かれていない部分に、人とは、家族とはこうあるべきという呪縛が充満している気がした。
根本的に家族ごと何とかしなければならない場合はどこまで踏み込み、治療を行き届かせていくのかについては慎重になる。「お前たちは病気だ」と父親が家族全員に向けて宣告し、家族全員での殺し合いが始まっていく石井聰亙監督の「逆噴射家族」のような展開だけは避けたいと思うが、実際のところ観念的にはこの映画の結末に近い状況になるのが理想なのかもしれない。関係性ごとまっさらにして新しく結び直すこと。しかし全てを壊し尽くすことなく、現実的な対応でこれを成すには時間はかかる。基本的にクリニックに来るのは本人であり、家族全体へのアクセスが難しいことが多い。
誰しもが生きづらさを与える側になり得る、という話は何度でも書き続けなければならないと思う。他者に向けた尖らせた言葉や態度を僅かにでも丸めさせることはできないだろうか。他者の鬱陶しさや扱いづらさに一抹の冷静さをもって接することはできないだろうか。近しい人物に無意識の内に行った振る舞いに攻撃性を見つけ、それを修正することはできないだろうか。
これは常々、自分にも言い聞かせている。近い関係性の中だからこそないがしろになったり、乱雑になってしまう場面があるとすれば、やはり真摯に他人として尊重することが重要だという意識を持ちたい。距離を置いて見るからこそ掬うことができる気持ちや、程よい関係性であるから優しくあれることが絶対にある。それは当然"遠くの誰か"であってもそうであるはずだが。
尊重される世界
"不幸自慢”という言葉がある。生い立ち、境遇、家族関係、恋愛関係、様々な理由で被った不幸を語ることが、自慢として捉えられられてしまうことがあるのだという。心の傷を語ることが誰かにとってはマウントとして聞こえるという事実。考えを巡らすと薄暗い気分になる。勿論それをしたいと思った人に限ったことだが辛い経験を言葉にしたり、自分に起きた出来事を表現に変えることは自由な行為であり、悪く言われていいわけがないはずだ。
「津波ごっこ」という言葉がある。2013年、ceroが「Yellow Megus」をリリースした際のインタビューで2012年のアルバム『My Lost City』を振り返りつつ「あまちゃん」を引用しながら語った箇所で知った言葉だ。東日本大震災の被災地で子どもたちが避難生活をする中で地震や津波をごっこ遊びとして再現し始めたというエピソード。この件に限らず、災害の後に子供たちの間で起こる行動だという。この論考にもあるようにこの行動自体が実際にどういうものかは明確に定義づけられないものだが、辛い出来事を客体化し、楽しむことで恐怖や不安を放出しているというのは一理あるように思える。
親ガチャという言葉で辛さを自虐的に表現するツイートも、毒親にされた仕打ちを書き記した文章も、DVやモラハラについて描いた漫画もそこにケアの意味はあるのだと思う。「津波ごっこ」にも近いような、対象として見つめ、吐き出して、描き、逃がす。そんな行動に思えるのだ。自分の人生に降りかかった災害を受容し、生きづらさに向き合おうとする段階。その入り口の1つ(あくまで、多くあるうちの1つだとは思う)に立つ行動に思えるのだ。
表出させようがさせまいが心的外傷はその人のものとして尊重される世界であって欲しいし、表出したものが”不幸自慢“といった言葉で攻撃されない世界であって欲しい。もしもそれを全肯定できないとしたって、想像力をもって何か言いたい気持ちを薄められないだろうか。あなたにはあなたの痛みがあり怒りがある。ただそれを他者への攻撃の理由にしてはならないはずだ。
心的外傷が更なる心的外傷を引き出し得るのも事実だ。親から子へ。夫婦の間で。生きづらさが循環している事実に直面する時にはその根深さに覚悟が必要である。しかし時に、社会への怨恨や他者への暴力としてではなく、表現として、ポップカルチャーの1つとして形になることだってある。それを尊重し、見守る人が増えることはきっと凄く良いことなんじゃないかと思う。誰しもにとっての生きづらさを逃がす。その1つの糸口になりはしないか。
※何か具体的な答えや解決法を提示する文章ではありません。あくまで思考の過程であり、今伝えたいことの現状報告です。読んでくださってる方とともに考えていきたいことです。この世界に山積みの問題と、僕の診ているメンタルヘルスと、僕を裏切らないポップカルチャーを同じ土壌で。
#映画 #テレビドラマ #メンタルヘルス #コラム #創作大賞2022 #パワーオブザドッグ #空白 #逆噴射家族 #あまちゃん #cero #音楽
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
