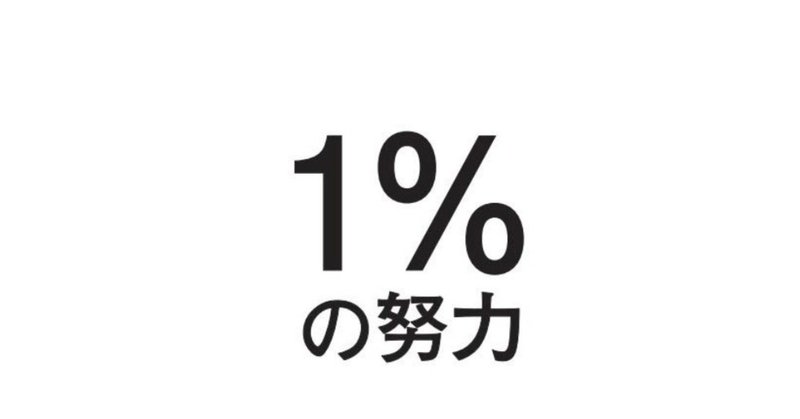
1%の努力 ひろゆき
すごく優しい感じで厳しいことを言っている本でした。最後の方で「僕は弱者の味方」と言っているところも面白いです。
読み終わった時に、なんとも言えない自分の人生に対する勿体無い感が漂った上、周りに面白いことがたくさんあるのに見て見ぬ振りして、他人の顔色を伺うような反応をしている自分がバカらしく感じました。
内容についていくつか個人的に刺さったコメントをピックアップしていきたいと思います。
成功したい人がやるべきこと
・いつだって、発信者は強い
・メインスキル(マクロな経営視点)とサブスキル(ミクロな現場視点)を両方持ち合わせることが強みになる
・実績が必要
自由な人生を歩もうと思ったら、最初に何かしらの実績を残さないと、見向きもされない。これは以前に本の感想を書かせていただいたふろむださんの「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている」でも書かれていました。
特に実力がなくても良いのですが、結局最初の一歩を踏み出せるレベルでないとそこから先に進めないという当たり前の話をしていました。行動している人が世の中の少数派であるという現実があります。
行動するとは?
ひろゆきさんは、事業計画をプレゼンする際には全てのタイプの経営者にアプローチするつもりだったそうです。冷静に考えると、RPGゲームではそのように行動することは多いですよね。特に、子供の時はロジカルに考えるなんで発想がないし、実際できないので手当たり次第に試して前に進んで行きますよね。子供はただ単に進め方がわからないから試しているだけですが、ゲームを楽しんで進めていきます。ところが大人になると、羞恥心からか「小利口」になって“ロジカル”にとか言い始めます。横から見ていると「早く進めろよ」と思うのですが、賢さを出そうとして逆にバカに見える、実に滑稽ですよね。
本書はそれを一蹴している感じがあります。
ポジション
・自分だけができて、他の人が考えないこと
ひろゆきさんはアドバイザーのポジションが自分の能力を最高に発揮できると分析しています。そのため行動を開始する時は、まず状況把握して「自分がどうしたら活躍できるか?」、「他人が何を考えいるのか?」、「どうしたら楽して利益が出るのか?」などの思考を挟むことで、全体をリードするための自分専用の手綱をまず探します。
手綱を探した後は、とにかくアイデアを出し続ける、間違っていてもかまわない。そのアイデアを出し続ける中でその状況や環境のおけるベストソリューションを探すという、量的なアプローチをしているようです。
量的なアプローチと書きましたが、いわゆる実績と頭脳を持った方が全力でアイデアを形にすると個人的には解釈しました。これは鶏と卵ですが、量を出さないと質が上がらない、質が高くないと量が出ないの状態だと思います。能力が低い人ならなおさら量を出し、質を高めるように自己分析をする方向がいいと思います。と言いつつ能力が低い場合、ひろゆきさんを目指すのではなく、あくまで自分のできる範囲で活躍した方が幸せだと思います。そう言った意味でも、目の前の興味ある事柄(仕事、趣味、人、物などなど)に全力で取り組むためにまず自分のポジションを明確にすることを勧められています。
自分ルール
・予測不能のものにだけお金を払う
・「面白い」を採用基準とすることもある
・ホームレス体験をおすすめしている
人それぞれ自分ルールがあると思いますが、ひろゆきさんのルールは少し変わっていて、さらに実行してしまう面白さがあります。予測不能のものだけにお金を払うようにしているらしいです。さらに面白いで人を採用したこともあるらしいです。自分の応用力を常に試しつつ楽しんでいる様に感じます。人は予測不能の事態に陥ると大体混乱して思考や視野が狭くなります。いつも余裕がある方でも危機に直面するとパニックにないりますが、あれはIQが低いという事らしいです。(頭がいいフリして、実は中身のないやつらの特徴がこちら メンタリストDaigo)
ひろゆきさんは予測不能の状態に慣れるために(?)、携帯もお金もない状態で、友人の力を使わずホームレスすることをオススメしています。その体験を通しても案外生きられるなという体感を持ってもらうというアイデアです。
自分がどうしたら楽しいかを分析して、実行する。実にシンプルな思考ですね。
まとめ
自分に対するつまらなさとこれからの行動を変えられる様な期待感を感じる本でした。「自分の未来を切り開きたい」、「自分を変えたい」そんな方におすすめです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
