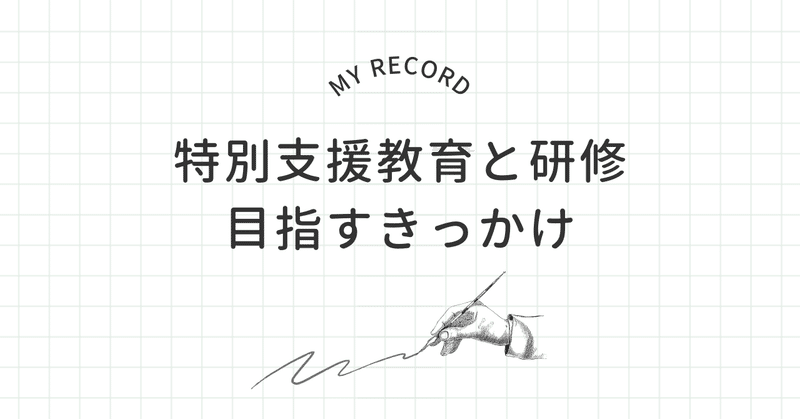
#17 特別支援教育と研修、目指すきっかけ
教員人生を歩む前までの私は、どの校種の教員になるかが定まっていませんでした。
ただ、教員という仕事への意義は感じており、広く社会貢献的な側面を有する仕事に就きたいという考えから、教職課程に進みました。
思い返せば、教員としての出発前から校種への拘りはなく、経験を積む中で少しずつ「何の教育」への焦点が絞られていったものです。
これまでの学び
私自身の特別支援教育への学びを振り返っていくと、
教員として採用される前は、大学で発達障害児支援を一つの専門とし、地域の小中学校の学習支援員として活動、フリースクールやセミナーの受講による学習を行い、
教員としての研究と修養の部分では、自治体が実施する特別支援教育の研修、意見交換会などを通して、基礎知識や実践への知見を深め、
実務的な部分では、日々の職務遂行の中で特別支援教育の職務にあたり、
免許状的な部分では、放送大学、特別支援教育総合研究所の認定通信教育で特別支援教育に関する基礎知識を身に付け、
アカデミック的な部分では現在、大学院で情報通信技術と特別支援教育に関する研究を行っている段階です。
きっかけ
学部1年次に小学校への学習支援員として、通常学校の中で展開されるインクルーシブ的な教育に触れる事ができた経験は、私が通常学校における特別支援教育に携わりたいと考えるようになった一つのきっかけでもあります。
そのような貴重な経験ができたことは教員人生を歩む上で必要不可欠な要素でしたし、同時に自身もまた子どもたちをはじめ、次世代の人たちがそう考えられるような学びを展開する事を目指していきたいと考えます。
またマクロ的には、高等学校における通級の研究推進、特別支援学級在籍者の急増など、ちょうど通常学校における発達障害児支援が盛んに実施されるようになった時期でした。
大学においても、発達障害児支援の実務家教員から指導を受け、特別支援教育の意義を深めることができた事から、「通常学校における特別支援教育」という枠組みを起点として、それに沿った教員となろう、という考えを持つようになってきました。
今思うこと
実務経験を積む中で、通常学校における特別支援教育を考える上で特別支援学校での指導、支援の実際を学び、経験し、より専門性を高める必要性も感じ始めています。
通常学級の立場から、特別支援学級の立場から、また特別支援学校の立場からと、多様な見方や考え方を、より明確に、詳細に、リアルな文脈で語れる事が特別支援教育の専門性を高め、職務への還元に繋がるのだと考えています。
特別支援学校の教員経験のみで特別支援教育を包括的に語ることは難しいと思いますし、逆に通常学級、特別支援学級、又は通級のみでも同様です。
しかし、すべての校種を経験する事(例えば、通常学校でも幼稚園〜高校まで、さらに通級や特別支援学級もあり、同じ特別支援学校でも幼稚部〜高等部まであり、その全ての経験)は現実的に困難であり、隣接校種の繋がりに対する知見を深める必要はありながらも、私自身の守備範囲は中学校を核とした義務教育段階の特別支援教育であると認識しています。
この守備範囲という枠組みを拡張し、少しでも特別支援教育への理解を深めていきたいものです。
どうありたいか
これまでの私の経験から、特別支援教育で目指していきたい姿、携わる目的は
①学習上又は生活上の困難を克服し、自立できるようにすること。また、生徒を取り巻く学びの環境を整え、一人ひとりが主体的に行動でき、安心して過ごしやすい空間を構築する。
②様々な人がつながり、多様な価値に触れ、理解し合い、その一人ひとりが社会の構成者となること。そして、そこには空間的・時間的な制約を超えて行われることも含む。
③教員、保護者をはじめ、生徒を取り巻くすべての人が特別支援教育への理解を深め、生徒への組織的な支援を図り、①・②の姿を実現させられるようにすること。
特別支援コーディネーターや校内委員会の設置、各自治体における就学相談の充実など、特別支援教育の重要性が高まる中ですが、通常学校における特別支援教育には、今もなお高い専門性を持った人材の不足が課題となっています。
①〜③の姿を目指すため、まずは私自身が高い専門性を有し、多様な視点をもつことができるようになる事が必要です。それは学部時代から変わらない軸です。
放送大学大学院への進学もその目的を果たす、過程の一つであり、今後の学びの中で少しでも目標に近づけるよう、実りある学生生活としていきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
