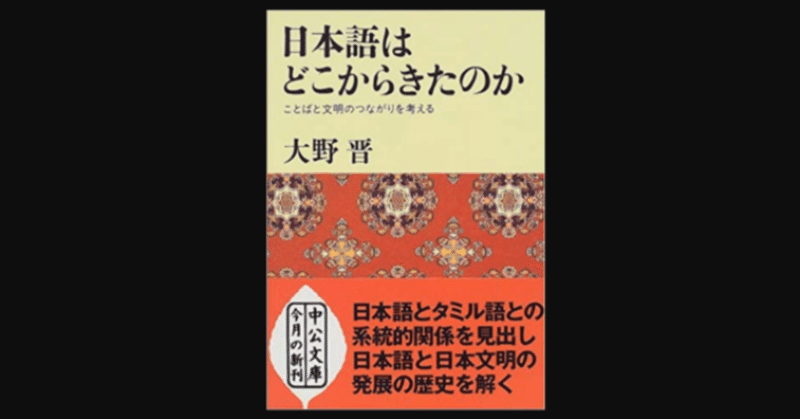
カレーの語源に日本語が深く深く関わるというまさかの説が! 『日本語はどこからきたのか』
ほぼ毎日読書をし、ほぼ毎日「読書ログ」を書いています。414冊目。
カレーは大好きですよね、そのカレーの語源で面白い説がありました。
『大英和辞典』(研究者)を見ると、「Cur-ry」の項に、語源として「Tamil kari sauce』とあります。つまりカレーのもとは、タミル語のkar-iだと書いてあります。(P84)
タミル語のkar-iは「辛い」という意味であり、カレーの語源は「タミルの辛い汁」です。これはカレー界隈では有名な話です。
タミル語は南インドで使われる言葉の一つで、イギリスの占領下で南インドの料理がイギリスに「カレー」として渡り、それが日本に入ってきて「カレーライス」になったというストーリーです。
しかし、本書を読むと違う経路が見えてきます。本書は「日本語はタミル語の系統である」説を唱える本なので、こうなります。
カラ(辛)ということばは、奈良時代にすでに日本で使っています。『万葉集』に「辛塩」ということばがあります。つまり古い古い昔、タミル語と日本語と共通に、カラ(辛)という言葉を使った。
なんだってーー! カレーという言葉の起源はタミル語であり、そのタミル語の系統である日本語の「辛」と同じ言葉だというのです! ガビーン!
さて、
日本語の起源をさぐる研究は盛んに行われており、Wikipediaを見るだけでも、様々な説がある事がわかります。
その中でも異彩を放っているのが、本書がテーマとしているインドのドラヴィダ語族の一つであるタミル語を起源とする説です。
タミル語というのは、南インドやスリランカに済むタミル人が使っている言葉で、地理的に遠すぎるし使っている文字もあまりにも違うので、系統だと言われてもなかなかピンとこない。
言葉を研修する方々もピンときていないようで、Wikipediaのページでは、
インドのドラヴィダ語族、とりわけその1つであるタミル語との関連を提唱する説。
と簡潔な紹介でマイナー説の扱い。
実際、タミル語を起源とする説には批判も多く、著者もその批判にあわせ直接的な系統であるという説は取り下げていたようだ。
じゃぁ、本書は嘘ばかりの読む価値がない本なのか? というとそんなことはなく「日本語はタミル語と同系である」という説を力説する4章以外は非常に読みやすく大変ためになるので、読んでみると面白い。
なにより冒頭の説みたいな話も読んでいると面白い。
それにしても、もしこの節が正しいのなら「カレーが辛い」は「辛い汁が辛い」と言っているようなものだ。面白い。
メコン川のメコンは「川」のことだし、ガンジス川の「ガンジス」も「川」の意味だし、それ全部「川川」だから、みたいなネタと同じノリの話になってしまう。
「それって有意義だねぇ」と言われるような事につかいます。
