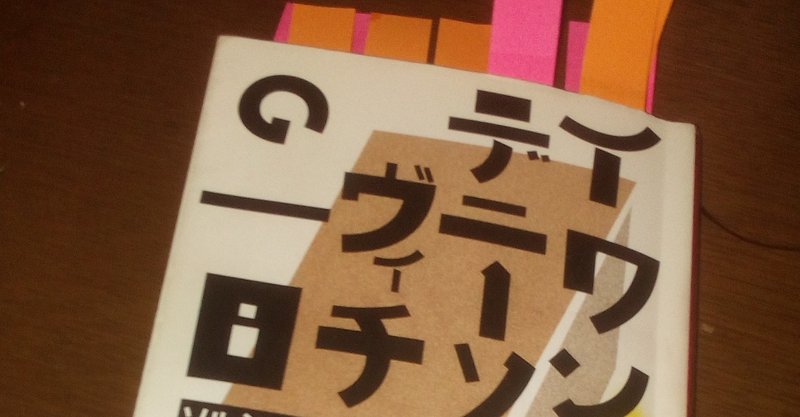
アレクサンドル・ソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』
今日紹介するのは現代ロシアの作家、アレクサンドル・ソルジェニーツィンの作品。この小説はスターリン時代、酷寒の強制収容所――ラーゲル――に、スパイ容疑で十年も収容されているイワン・デニーソヴィチ・シューホフというロシア人の一日を描いている。
この小説は物語を追ってもほとんど意味がない。起きて朝食を食べ、働きに出て、帰ってきて夕食を食べて寝る、という囚人の一日の、そこかしこにちりばめられた細部を楽しむ読み物だ。
それじゃあどの細部を引用しようかという話になるのだが、それがとても迷う。どこかの時間帯の情景も同じ粒度で描かれていて、どこも面白いからだ。
だが、まずはこのシューホフが収容されているラーゲルの過酷さを理解してもらうため、何か所か引用する。まずは酷寒(零下27度)の辛さがにじみ出ている、シューホフが作業現場に行く前の身支度をしてる場面。新潮文庫54ページ
ここラーゲル構外では、刺すような風が吹いているので、シューホフの鍛えぬいた顔でさえ、酷寒にヒリヒリと痛んだ。この分では暖発電の現場へいく間じゅうむかい風が吹いているなと見てとり、シューホフは風除けをかぶることにした。むかい風を防ぐためのボロ切れは、シューホフも他の連中と同様もっていたが、それには二本の長い紐がついていた。囚人たちはこんなボロ切れでもけっこう役に立つと、認めていた。シューホフは顔を目のところまですっかりかくし、二本の紐を耳の下へとおして、うなじのところで結んだ。それから帽子のふちも額にたらした。こうして、もう前の方は目だけしかあいていなかった。ジャケツの腰の部分を細引でしっかりとしめつけた。これで万端ととのったわけだが、ただ手袋が悪いので、もう両の手はかじかんでしまっている。彼は両手をこすったり、バタバタ叩いたりした。もう今すぐにも両手を背中にくまされて、現場まで歩いていかなくてはならないことを知っていたからだ。
すこしは寒さが伝わっただろうか(といって僕も実際に零下27度を体験したことあがあるわけではないのだが)? 酷寒と並んでもう一つ囚人たちを苦しめるのは看守たちやラーゲル所長、さらに監督官だ。常に誰かの監視下にあるのは収容所であるからには当然といえば当然なのだが、僕らの想像を絶する過酷さだ。まずはこの間まで中佐の地位にあった、ブイノフスキイという囚人が監督官のヴァルコヴォイに口答えしてしまう場面の引用から。
囚人たちは作業をするためにラーゲルから出かける前、外に並ばされ身体検査を受けている。50ページ
ブイノフスキイは大声をはりあげた。いや、むりもない。水雷艇とちがって、ラーゲルではまだ三ヵ月しかならないのだから。
「君たちも酷寒(マローズ)のなかで人を裸にする権利は持ってないはずだ! 刑法第九条を知らんのか!……」
なあに、持ってるとも。知っとるとも。なあ、兄弟、知らねえのはお前さんだけだぞ。
「君たちはソビエトの人間じゃない!」と、中佐は追いうちをかけた。「君たちはコム二ストじゃない!」
刑法の条文についてはヴォルコヴォイもまだ我慢していたが、この一言をきくと、百雷が一時におちたような調子で怒鳴りつけた。
「十昼夜の重営倉」
ここで「十昼夜の重営倉」というのが罰だということはわかっても、読者にはその辛さがわからない。それが説明されるのはシューホフたちが作業を終えてラーゲルに戻ってきて寝る前だ。看守がきて中佐を連れていく場面。234ページ
「それじゃ、諸君、いってきます」と、中佐は放心した面持ちで、一〇四班の連中にうなずくと、看守のあとについていった。
その後ろ姿に数人の者が声をかけた。がんばれよ。気をおとすんじゃないぞ。いや、それ以上なにがいえたであろう? 一〇四班の連中は、自分の手で監獄(プール)を建てたのだ。だから、そこがどんなところか知りぬいている。あそこの壁は石、床はセメント張り、ひとつの小窓もない。ペーチカを焚いても、壁の氷を融かして、床に水たまりをつくるだけ。寝床はむきだしの板切れ。もし歯が抜けおちなければ、一日に三百グラムのパン。野菜汁(バランダー)が貰えるのは三日目、六日目、九日目の三日だけ。
これが十昼夜! この独房に十昼夜、重営倉で最後までぶちこまれていれば、もう死ぬまで健康は回復しないという。結核のとりことなって、病院を抜けだすことはできないのだ。
また、十五昼夜、重営倉でぶちこまれていれば――もう冷たい大地に眠るばかり。
こんな過酷な状況を描けばどうしてもドストエフスキーの小説みたいに暗い感じになりそうなものなのに、そんなことには全くならない。むしろチェーホフの小説を読んでいる感じに近い。それは、こんな厳しい環境下にあっても囚人たちが楽しみを見つけて、たくましく生きている様が生き生きと語られるからだろう。楽しみは大きく二つだ。煙草と食事。いい場面はいくつもあるが、その中から一か所だけシューホフが煙草をツェーザリという囚人からもらう情景を引用する。43ページ
同じ班のツェーザリがタバコを喫っているのに目ざとく気づいた。しかも喫っているのはパイプではなくて、巻タバコだ。つまり、一服おごってもらえるやつだ。しかし、シューホフはいきなりたかろうとはしなかった。ツェーザリのすぐ横に突立って、なかば顔をそむけて、じっとあらぬ方を眺めていた。彼はまるでケロリとした顔つきで、あらぬ方を眺めていたが、ツェーザリが一服吸いこむごとに(ツェーザリは物思いにふけっていて、たまにしか吸いこまなかった)、赤く円をえがいた灰のふちがのびていって、それだけタバコが短くなり、パイプの先に迫っていくのを見逃さなかった。
そこへまた山犬のフェチュコーフが忍びよってきて、ツェーザリの真正面に突立って、じっと相手の口もとをのぞきこみ、眼をギラギラさせた。
シューホフには一かけらのタバコもなかった。きょうは晩まで手にはいる見込みもなかった――だから彼は全身を期待におののかせていた。今の彼には巻タバコの吸いさしのほうが、自由そのものよりも望ましいものにさえ思われた。それでもなお彼には気位というものがあったので、フェチュコーフのように相手の口もとをのぞきこんだりはできなかった。
ツェーザリの体には、ありとあらゆる民族の血がまじっていた。ギリシャ人でもなければ、ユダヤ人でもない、さりとてジプシーでもない。いや、とにかく、はっきりしないのだ。まだ若い。映画の監督だった。もっとも第一作も撮りおえぬうちに、ぶちこまれてしまったのだ。黒々とした濃い口ひげをたくわえている。ここへきても剃りおとさないのは、身分証明書の写真がそうなっているからだ。
「ツェーザリ・マルコヴィチ!」と、フェチュコーフの奴はこらえきれなくなって、猫撫で声でいった。「一服喫わして下さいよ!」
と、その顔は激しい渇望で醜くゆがんだ。
……ツェーザリは黒い瞳の上になかばかぶさっていた瞼を心もちあけて、フェチュコーフを見やった。彼がパイプを前より愛用するようになったのは、喫っているときにぜひ一服やらせてくれと、横どりされたくないためだった。タバコが惜しいのではなくて、思考が中断されるのが残念だったのだ。彼がタバコを喫うのは心の中に力強い思考をよびさまし、それによって何かを発見したいためであった。ところが、彼が巻タバコに火をつけたとたん、何人かの目の色に『最後まで喫わんでくれよ!』という表情が浮かぶのだった。
……ツェーザリはシューホフを振りかえって、話しかけた。
「どうぞ、イワン・デニーソヴィチ!」
そういって、親指で琥珀の短いパイプから火のついている吸いさしを、よじるようにして抜きとった。
シューホフははッとして(そのくせ、彼はツェーザリのほうからすすめてくれるのを期待していたのだが)、素早く片手で恭々しく吸いさしをつまむと、今度は用心ぶかく落とさぬようにもう一方の手を下から受けとめる形にした。彼はツェーザリがパイプのまま喫わせたがらなかったといって、腹をたてたりなどしなかった(人の口にはきれいなものもあれば、汚らしいものもあるからだ)。それに、鍛えにきたえた彼の指は火の先をじかに持っても火傷しなかった。いちばん肝心なことは、彼が山犬のフェチュコーフをだしぬいて、今や唇が火で焼けるまで、思う存分けむりを吸いこめるということだった。ふーッ! けむりは飢えた体ぜんたいにひろがり、爪先にも、頭の中にまでじーんとしみとおった。
思ったよりも長くなった。ツェーザリのタバコをめぐって、シューホフとフェチュコーフが争う姿が生き生きと描かれている。こんな感じでこの小説は主人公のシューホフを中心として、小狡くて怠惰、でも愛さずにはいられない男たちの日常がユーモラスに語られる。その群像劇をうきうきと読み進めているともう終わりという感じ。
でもこの本は一度読み終えてもう開かないというタイプのものではない。すぐまた最初から読みたくなる。そして実際に読み始めると、今度はシューホフを取り巻く状況(上で引用した「十昼夜の重営倉」の過酷さなど)がばっちりわかっているので、もっと面白くなっている。
こういう風に繰り返し読めるのは、解釈が読者に委ねられている、というか、語り手の思想を押しつけるようなところがないからだろう。生き生きとした現実がそのまま本に閉じ込められているというか、これは柴崎さんの小説の記事でも書いたけど、小説が始まる前からシューホフたちは向こう側の世界で生きていて、終わった後もずっと生き続ける感じがすごくする。そして本を読むことで自分も一囚人の立場にたってシューホフたちの暮らしを疑似的に体験する感じがする。
もちろん柴崎さんの小説の場合には実際に暮らしている社会の状況が近いから、小説内のどこかに自分がいる感じすらして、そのことで最初っから登場人物のことをまるっきり理解できないということはあまりない(もちろん近くにいても相容れない、理解しあえない、というか丸っきり何を考えているのかわからない、ということはあるわけで、最新作の『待ち遠しい』ではそこを描いている)。
一方でソルジェニーツィンの小説世界は自分とはもう全然関係のない世界なわけだ。当然柴崎さんの小説世界のような近さは感じない。感じないんだけど、やっぱりすごく親密な感じがする。シューホフからしたらお前と仲良くなった覚えはない! って感じだろうけど。全然立場が違う人、環境が違うところに住んでいる人に共感することができるのが、やっぱり小説なんだよなあと思う。という、月並みなこと(でも本当だと思う)を書いて、今日は終わりにします。
ではまた!
よかったらサポートお願いしやす!
