
9 フラーから考える建築家の倫理 光嶋裕介
「建築家は家屋の海原の中にたとえば聖堂をつくる。ヨコのひろがりの内に、タテの力が働く場をつくり出そうとする」(『ヨコとタテの建築論』慶應大学出版会、2023、p.128)とは、建築史家の青井哲人の言葉である。
青井はまた、「新しい制作のきっかけは、いつも所与の豊穣な世界にある。素材もそこから集められ、集まったものが交雑する。ところがそこに世界からの超越が兆す。接続しない自律はありえない。ヨコのないタテはありない」(同上、p.34)とも述べている。
ヨコに展開するのは、白岩さんが第7回で書いた黒人奴隷の逃亡のためにつくられた「地下鉄道」のように、得てして「見えない」ものである。強度ある思想こそ、ヨコに展開する最たるものだ。
ヒトラーが「バウハウス」という新進気鋭の造形学校を閉鎖に追い込み、教育を妨害したのも、ナチスの思想と相容れないものを排除するためである。そのバウハウスを創立し、近代的な建築である《デッサウの校舎》の設計も手がけた建築家のヴァルター・グロピウスはバウハウス閉鎖後アメリカに渡り、ハーバード大学に招かれて教鞭をとった。バウハウス最後の校長を務めたミース・ファン・デル・ローエも、マサチューセッツ工科大学に迎えられている。この2人が果たしたアメリカ建築教育への貢献は大きい。

アメリカが打ち出した科学技術に基づく建築の国際様式としての「モダニズム」
ヨーロッパ発の新しい思想「モダニズム」がアメリカにおいて一気に覚醒したのは1932年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された〈近代建築:国際展(Modern Architecture : International Exhibition)〉がきっかけといえる。
この伝説的な展覧会を建築史家のヘンリー=ラッセル・ヒッチコックと共に企画したのは、第6回でも紹介したフィリップ・ジョンソンである。フランスのル・コルビュジエはもちろんのこと、ドイルのミースやグロピウスら、ヨーロッパで活躍するモダニズムの先駆者たちによる建築が広く紹介された。ジョンソンたちが旗振り役となり、白くて幾何学的な美しいモダニズム建築をこれからの建築様式として発信するのは、ここ自由の国アメリカであることを、世界に強く印象づけたのである。
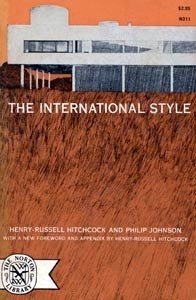
この展覧会成功の一因は、「モダニズム」を建築様式の確固たるスタイルとしてというよりも、概念、もしくは時代精神らしきものとして打ち出したことである。その結果、「モダニズム」は解釈の可能性を広く保ったまま、当時の社会と共鳴していった。
ヨーロッパに比べて圧倒的に歴史の浅いアメリカは、経済大国へと成長しながらも、文化的コンプレックスを抱えていた。世界にアピールする建築文化を発信することで、そうしたコンプレックスを払拭したかったのだろう。
重要だったのは、歴史的様式が持つ装飾性を排除することではなく、むしろ白くて新しいものとしてのモダニズムを「技術(technology)」に基づくものと位置づけた点である。先進的なヨーロッパの建築家たちの力を借りながらも、アメリカ人による自前の建築思想を展開するためには、「技術」という普遍的な拠り所が必要だったのである。
こうして「科学に裏打ちされた技術」という普遍性を中心に据えた「インターナショナル・スタイル(国際様式)」は、国境を超えて発展していくことになる。
バックミンスター・フラーの思想
そんなモダニズム思想の主戦場は、都市であった。
モダニズムの発展可能性は、建設技術によってこそ支えられていたし、発展と進化を続けるものとしてのテクノロジーに、モダニズムは希望の光を見ていたのである。
1920年代の繁栄が、資本主義という欲望の現れとして摩天楼の風景を創造したことは、すでに述べた通りである。装飾のないシンプルなガラスの表層の裏には、建設技術への決定的な信頼があった。
このアメリカのモダニズムの思想における中心人物のひとりが、「バッキー」の愛称で親しまれた数学者・思想家・建築家のリチャード・バックミンスター・フラーである。彼は、圧倒的な視野の広さをもって世界を包括的に捉えた天才であるが、ここでは「天才」とラベリングして思考停止状態に陥ってしまうのではなく、むしろフラーに寄り添って考えてみたい。

フラーは1929年、安価で環境効率のいい工場量産化住宅《ダイマキシオン・ハウス》をデザインして、アメリカ建築界に登場した。「ダイマキシオン」とは、「ダイナミック(動的)」と「マキシマム(最大)」、「テンション(張力)」という3つの言葉を合体させたフラーの造語である。
フォード社が工場で高度に品質管理されたベルトコンベアによってT型フォード車を大量生産したように、住宅においても現場で職人がつくるのではなく、工場で組み立て(プレファブリケーション)、現地まで運ぶというアイディアを考案し、アメリカの住宅難に一石を投じたのである。ほかにも、持ち運べるバスユニットや、アルミなどで軽くつくった《ダイマキシオン・カー》まで考えたが、住宅の工場量産化が定着することはなかった。
フラーは「より少ないものでより多くのことをなす」ための技術として、数学・物理・哲学を自由に横断・駆使し、建築と結びつけて考え続けた。その結果、人間が安全に住まうための「シェルター」という考え方を《ジオデシック・ドーム》に結実させた。
フラーは主著『宇宙船地球号 操縦マニュアル』(原著1968、芹沢高志訳、ちくま学芸文庫、2000)を通して、地球を「宇宙船地球号」と呼び、地球が閉じたエコ・システムを成立させながら宇宙空間を飛び続けられている核心に迫ろうとしている。
宇宙船地球号に関してはとりわけ重要なことがある。それは取扱説明書がついていないということだ。(中略)私たちは自分たちの最高の能力、つまり知性を使わざるをえなくなった
この美しい地球を持続可能なものにするためには、最小限のエネルギーで効率を最大限まで上げる必要がある。そのために、自然との関係性を探究する知性が不可欠だというのである。
その思想の実践として完成したのが、1967年モントリオール万国博覧会のアメリカ館のドーム(冒頭の写真)である。ドームこそ建築の合理的な形態と考えたフラーは、トラス構造を用い、最小限の部材でドームを実現することに成功した。
理念上、最小限の表面積で、最大限のヴォリュームを確保する幾何学はドームであり、その形が極めて合理的であることはわかる。しかし、四角い家具が配置できないなど、実際に使いこなすには難点が多いのも確かだ。その一方で、先日アメリカ・ラスベガスに巨大な球体に映像を写し込む大型アリーナ施設《Sphere》が完成して話題を呼んでいるのを見ると、やはりフラーの夢には未だに多くの人を魅了する力があるのだと感じずにはいられない。
「宇宙船地球号」のためのフラーの建築
さて、MoMAでの〈近代建築:国際展〉によって「インターナショナル・スタイル」としてのモダニズムがますます世界へと浸透していった1930年代、若きフラーは初期活動の一端として、「SSA(Structural Study Association)」という建築家グループを結成している。
印牧岳彦の『SSA:緊急事態下の建築ユートピア』(鹿島出版会、2023)によると、「産業化の進展にともなう空間的・時間的自由の拡大というこの傾向は、建築、都市のスケールを超え、理想社会(=ユートピア)を目標とした絶え間ない発展として捉えることになる」(p.197)という認識から、フラーは建築が「環境制御」になりうると考えていたという。資本主義社会で欲望のままに生きていては、地球という宇宙船は持続しないと直観していたフラーは、自然のなかにある原理を理解し、自らの環境をつくろうとしたのである。
つまり、いわゆる「インターナショナル・スタイル」とは異なるモダニズムのあり方としてSSAの唱えた「環境制御」という考え方があり、それは「『人間活動』と『物質』の双方にわたる力の相互作用を制御し、それを『生産的な使用へと向けた流れのパターン』へと組織化することを意味し、その目的は、それ自体ひとつの『環境的な力』である『人体』に『生命力の増大』、あるいは『新陳代謝における浪費の除去』をもたらすことにあった」(同上、p.331)というのだ。
フラーが建築家の枠に留まらないのは、彼が世界のあり方をどこまでも真摯に考え続けた人物だからだ。「宇宙船地球号」は有限であり、資本主義のもとで無尽蔵に搾取していては、沈没してしまう。この恐れに基づき自身の哲学を探究し続けたがゆえに、彼の思想はヨコに展開する力をもったのである。
フラーの思想は、展開可能性に満ちている。ヘリコプターで持ち運べるほど軽量化したドームやシェルターが、戦いに加担する軍事産業において重宝されたのは、皮肉なことだったが。
引き継がれるフラーの思想
1968年、『ホール・アース・カタログ(Whole Earth Catalog)』を創刊したスチュアート・ブランドもまた、フラーの思想をヨコに広げたひとりである。
地球の外側からの視点を持てば、自分たちの住む地球のことがよくわかる。宇宙から見た地球の写真をNASAから手に入れて、創刊号の表紙にしたのは、そうしたメッセージを示すためだったろう。また「カタログ」と表することで、地球は自らの手を動かして「つくる」ことが可能であることも示唆した。
ブランドは、この雑誌の廃刊後に著した『地球の論点』(原題「Whole Earth Discipline(2009)」、仙名紀訳、英治出版株式会社、2011)のなかで以下のように回想し、環境問題をはじめ、都市化や原子力、あるいは遺伝子についてまで科学的な議論を展開している。
私は40年前に雑誌『ホール・アース・カタログ』を立ち上げたが、その巻頭にこう書いた。「私たちは神のごとく、ものごとをうまく処理することが望まれる」——ずいぶんと、のどかな時代だった。新たな状況には、新たなモットーが必要だ——「私たちは神のように振る舞わなければならず、しかも巧みにやり遂げなければならない」。『ホール・アース・カタログ』は、各人の力を呼び覚ました。本書は、もっと前向きの力を結集することを狙っている
自らを編集者ではなく「環境運動家」であると宣言し、テクノロジーをベースに地球のことを考え続けたブランドは、次のような結論で本を締め括っている。
エコロジーのバランスはきわめて大切だ。センチメンタルな感情で語るべきものではなく、科学の力を借りなければならない。自然というインフラの状況は、これまで成り行きに任されっぱなしだった。これからは、エンジニアの力を借りて、修復していかなければならない。
「自然」と「人間」は不可分だ。私たちは互いに、手を携えていかなければならない。
単なる雑誌という枠を超えて一大ムーブメントとなった『ホール・アース・カタログ』が、60年代後半のヒッピー文化と共鳴したことは、忘れてはならない。のちにApple社を設立したスティーブ・ジョブスやマイクロソフト社をつくったビル・ゲイツらも大きな影響を受けている。
ジョブスがスタンフォード大学の卒業式辞で語ったあの有名なフレーズ「Stay hungry, Stay foolish(ハングリーであれ、愚かであれ)」も、元を辿れば、ブランドが『ホール・アース・カタログ』の最終号の巻末に掲載したバッキーの言葉なのである。飽くなき探究を続けたフラーの思想は、モダニズムと並走しながら多方面へと展開したのである。
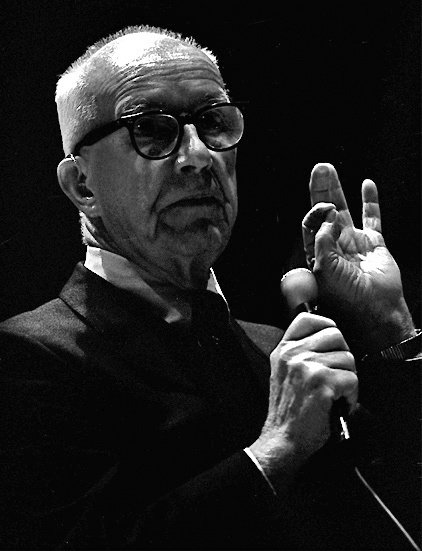
建築家の倫理をどこに置くのか
ここで、改めて「バックミンスター・フラー」について考えてみたいのは、彼は建築家として一体誰のために建築をつくっていたのか、ということである。何が彼を突き動かして、あれほどの強度をもつ思想ができあがったのだろうか。
唐突に聞こえるかもしれないが、これは建築家の倫理について考えることと等しい。いささかナイーヴなことを言わせてもらうと、世界を見渡せば人間はいまだに争い、分断のなかで戦争をしている。白岩さんのいう「非人間化」を止めることができずにいる。戦争は人間の命はもちろん、地球をも破壊する。環境の持続可能性を大いに損なう行為である。
宗教や価値観の対立から圧倒的な暴力によるテロや戦争を繰り返す主体である国家とは何か。そもそも人間が生きるとは何か。そうした根元から考えていくと、フラーは地球の大地の上で幸せに生きるためのものとして、建築を思考していたのだと思う。
「宇宙船地球号」を適切に操縦するためには、自然から学び、そこにある法則を自ら実践する必要がある。利己的なものを満たすより、未来の子どもたちのために美しい地球を持続させること、地球をより良い場所にしようとする利他的な気持ちがフラーの活動のベースにあったように思えてならない。こうした利他性は、マックス・ウェーバーが分析したプロテスタンティズムの倫理のひとつ「できる限り稼ぎ、できる限り蓄え(節約し)、できる限り与えよ」(ジョン・ウェスレー)に通じるものがある。古き良きアメリカには、こうした禁欲的なプロテスタント精神が根付いていたのではないだろうか。
一方で、建築家とは、他者からの要請という「依頼」があって初めて仕事が成立する職業である。自らの思想とまったく相容れない依頼があった場合、はっきり「NO」と言うべきなのだろうか。潤沢な予算と報酬を目の前にしたとき、思想の異なる共感不可能な建物でも、設計を引き受けるべきなのか。
私は建築家として「他者への想像力」をもって、誠意ある対話のなかから魅力ある建築を一緒につくりたいと思っている。集団でのものづくりである建築は、そうした複数の世界を実現する力があるはずだ。つまり、仕事欲しさに依頼主の言いなりになったり、おもねったりするのではなく、依頼主が建築に見ている夢や、そこで過ごす人たちのここちよさ、設計者としての理想の空間など、すべてを総合的に満たす、「みんなのための建築」という寛容なあり方を実現したい。
フラーと同時代の建築家のグロピウスは、73歳のとき(1956年)の講演で、資本主義に邁進する社会への危機感を以下のように述べている。
科学時代の始まりと機械の発達とともに、古い社会の形式が崩壊したのです。文明の道具がわれわれ人間よりも大きくなりました。道徳的な力でリードしてゆく代りに、近代人はただ機械的に質でなく量にたより、また新しい信念を築く代りにただ実用的な目的だけに奉仕するという考えを発展させました。
新しい文化がふたたび人間生活の夢と驚き、喜びと幻想を、新しい魔術的な美しさで表現できるように、われわれの引き裂かれた世界を統一する基盤を見出すことが必要となってくるでありましょう
そして最も大切なこととして、「美をつくりだすこと美を愛することは、大きな幸福をもたらして人間を豊かにするばかりでなく、道徳的な力をもたらしてくれる」(pp.12-13)と語っている。この「道徳的な力」こそ、グロピウスの建築家の倫理なのだろう。
先に述べた「他者への想像力」も、グロピウスが美の中に見た「道徳的な力」を感じるためのものであり、決して人間だけに向けるものではないと私は思っている。むしろ、言葉を持たない自然といかに心を通わせて、建築に命を吹き込むことができるかを考えたい。
フラーが宇宙的な視点から地球のための建築を思考したように、グロピウスが「多様のなかの統一」を目指したように、もし「みんなのための建築」をつくることができたら、それもまた人間にとってのより豊かな世界への回路になるはずだ。そうした可能性を信じられる社会をつくるべく、これからも寛容な姿勢で、あらゆる他者と粘り強く対話を重ねていきたい。
〈プロフィール〉
光嶋裕介(こうしま・ゆうすけ)
1979年、アメリカ・ニュージャージー州生まれ。建築家。一級建築士。博士(建築学)。早稲田大学理工学部建築学科卒業。2004年同大学院修了。ドイツの建築設計事務所で働いたのち2008年に帰国、独立。神戸大学特命准教授。建築作品に内田樹氏の自宅兼道場《凱風館》、《旅人庵》、《森の生活》、《桃沢野外活動センター》など。著書に『ここちよさの建築』(NHK出版 学びのきほん)、『これからの建築―スケッチしながら考えた』『つくるをひらく』(ミシマ社)、『建築という対話 僕はこうして家をつくる』(ちくまプリまー新書)、『増補 みんなの家。―建築家一年生の初仕事と今になって思うこと』(ちくま文庫)など。
◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!
◉光嶋さんと青木さんがその出会いからを話す対談が収録されている、こちらの本もぜひどうぞ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
