
【第6回】ニッポンの世界史:アメリカ映画とソ連映画から見る「アジア」観
「世界史」には決まりきった構成があると思っていませんか?
そんなことはありません。その構成は、長い歴史の中でくりかえし定義されなおし、いまなお変身の途上にあります。世界史の描き方には、日本人が世界や歴史を見るときに突き当たる「困難」が色濃く反映されている。そして、日本における「世界史」は、教科書を中心とする”公式”世界史と、それに対抗する”非公式”世界史のせめぎ合いのなかで再定義されてきた——このような視点から、「ニッポンの世界史」をよみとく文脈を明らかにし、世界史の描き方の現在地を探る特集です。
ところで、敗戦後の日本人は、アートやエンタメを通して、どのような世界観を育てていたのでしょうか?
「学問や政治の動向はさておき」としたいところですが、そうも言ってはいられません。
戦後の世界は、1946年のチャーチル英・元首相の「鉄のカーテン」演説、1947年のトルーマン米大統領による「封じ込め政策」、1948年のソ連によるベルリン封鎖を皮切りに、アメリカ陣営とソ連陣営に真っ二つに分かれて睨み合う「冷戦」の時代に突入。
戦後直後の混乱、復興にむけた動きのすすむ中、科目世界史の誕生した1949年は、東西ドイツが成立し、中華人民共和国が建国され、NATO(北大西洋条約機構)ができるという、激動の時代でもありました。
こうした政治的な動向は、いうまでもなくカルチャーの世界にも影響を与えます。
戦後日本に対して、アメリカとソ連が、それぞれのアートやエンターテイメントを売り込もうと躍起になったのです。
アメリカ映画の描いた世界
そもそも日本人は戦前から欧米文化に慣れ親しんできました。
戦後になっていきなり外国映画を観るようになったわけではありません。1903年に浅草電気館で映画が放映されるようになると、全国に上映館が広がり、ヨーロッパ映画が流行。当初、映画はどちらかというと品の悪いものとみなされていました。
ところが第一次世界大戦でヨーロッパ映画の供給がストップすると、代わってアメリカ映画が、知識人や教養ある富裕な階級を中心にも人気を博するようになります(藤木秀朗『増殖するペルソナ──映画スターダムと日本近代』名古屋大学出版会)。
一方、アメリカのスラップスティック的な映画も、大衆的な人気を得ます。アクションの要素の多い活劇はまだ幼かったのちの映画評論家・淀川長治(1909〜98)にとっての原体験でもありました(淀川長治『淀川長治自伝』上、中央公論社、1988)。
その後、太平洋戦争が始まると、当然のことながらアメリカ映画は規制を受けます。
そして迎えた敗戦。GHQ/SCAPの占領政策に映画を通して協力したのは、大戦末期にハリウッドの映画会社が共同で組織でした「アメリカ映画輸出協会(MPEA)」のコンテンツを、セントラル・モーション・ピクチャー・エクスチェンジ(セントラル社)でした(以下、北村洋・笹川慶子「日本におけるアメリカ映画の受容」、『JunCture : 超域的日本文化研究 』9 132-146頁、2018)。
セントラル社はまずは文化人に対して啓蒙をこころみます。
詩人の春山行夫、文学者の本多顕彰、ジャーナリストの中野五郎、文筆家の林芙美子、政治学者の堀真琴などといった同協会のメンバーは、メイヤーの意を汲んで講演を行ったり、新聞を発行したり、ラジオ番組に出演したり、特別上映会に参加したりした。こうした文化人たちは、自身の映画論を「局外批評」として誹謗するきらいのあるプロの映画批評家に挑み、ハリウッドの政治的、社会的、文化的な重要性を強調しつつ、セントラル社の作品を「民主主義」や「人道主義(ヒューマニズム)」といったアメリカ的と見なされた価値観をよりよく理解するための啓蒙の道具として扱った。
その上で、文化人ではなく、大衆の側に寄り添った映画批評の動きも、先ほど挙げた淀川長治らによって始まります。淀川はセントラル社の元社員で、戦中に戦時統制による雑誌の統合整理で休刊していた『映画之友』の編集長に抜擢され、「あくまで「ミイチャン、ハアチャン」と蔑視されがちな一般観客 の立場から一緒に「教養」を獲得することを信条としてい」た映画人です(上掲、141ページ)。
こうしたテコ入れにより、ハリウッド映画の興行収入は、1950年代にかけて急増し、短期間で邦画をしのぐほどとなりました。
その後、1952年の占領終了を前に、同1月1日にセントラル社は活動を停止し、アメリカの映画会社は競い合って新作を輸出します。
当時のハリウッドでは豪華絢爛な大作化の流れが起きていました。特に歴史に題材をとった作品は大作傾向が強く、なかでも日本でヒットしたのは、以下のような作品です(カッコ内は日本公開年)。
『ジュリアス・シーザー』(1953)
『クォ・ヴァディス』(1953)
『風と共に去りぬ』(1953)
『ローマの休日』(1954)
『王様と私』(1956)
『戦場にかける橋』(1957)
『十戒』(1958年)
『ヴァイキング』(1959)
『ミイラの幽霊』(1959)
『ソロモンとシバの女王』(1959)
とりわけ、『ベン・ハー』(1960)は興行的に大きな成功を収めます。
ソ連映画の描いた世界
アメリカ映画の商業的成功に対し、おもに知識人を中心に「自主上映」という形で受容されたのがソ連映画です。
もともと日本の映画人にも、ソ連映画の芸術性は知られていました。しかし、内務省の検閲却下によって上映禁止であったため、戦前の日本ではほとんど上映がされなかった。そのため、セルゲイ・エイゼンシュタインの『戦艦ポチョムキン』自体の上映なきまま、「モンタージュ理論」が先行して輸入されるという状況が生まれていました。
ようやく戦後に上映が可能となるわけですが、商業的な上映ではなく、自主上映という形がほとんど。
なかでも、セルゲイ・エイゼンシュタインの『イワン雷帝』が注目を集めました。1928年にモスクワ公演をおこなった2代目市川左團次との交流から、歌舞伎の「見得を切る」演出がとりいれられていることで知られ、1944年に制作されていた第1部が1948年に放映されています。
同じくエイゼンシュタインの『戦艦ポチョムキン』が自主上映されたのは 1959年のことで、商業的な興行はもっと遅れて1967年のことです(小川佐和子「二重の神話化 : 日本における『戦艦ポチョムキン』上映史」、『人文學報』116、85-106、2021)。
ソ連の映画は国営化されており、社会主義の思想に即した芸術のあり方である「社会主義リアリズム」に従ったものでなければ、制作・上映が許可されませんでした。
スターリンは映画を社会主義理念の普及にとって最も重要なものとみなしており、『イワン雷帝』第1部も彼の絶賛した作品の一つです。のちに制作された第2部は、独裁者の暗部を描くものとして改作が命じられ、失意のうちにエイゼンシュタインは1948年に没し、ようやくそのままの形で公開されたのは「スターリン批判」(1956年)以後の58年のことでした。
このようにアメリカ映画と比較して、ソヴィエト映画の受容は限定的なものにとどまりました。
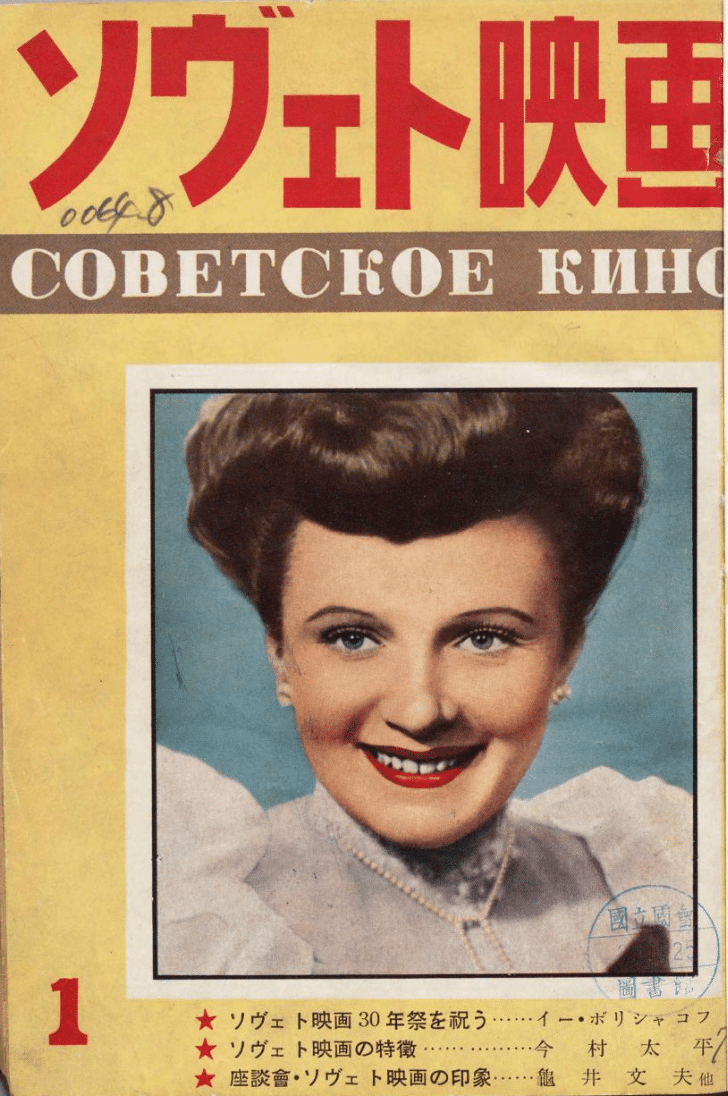
映画のうつした「アジア」観
これらのほかに、知識人を中心にヨーロッパ映画に対する再評価や、1960年代以降の日本映画の主に地方の労働者の間でのシェア拡大の動きも重要ですが、戦後の日本人にとっての世界は、やはりアメリカ映画を媒介に形作られていた部分が大きいはずです。
しばしば指摘されるように、ハリウッド根底には、アジア人を「白人=アメリカ人」とは正反対の属性をもった「よくわからない存在」として描く傾向があります。
近代以降西洋世界が他者を表象する、そのような手つきを「オリエンタリズム」と名付けたのは、パレスチナ生まれの批評家エドワード・サイード「オリエンタリズム」でした。
西洋にとっての「他者」は1950年代には露骨に「アジア」や「アフリカ」「未開の文明」だったわけですし、1960〜80年代になるとスパイもの中で「ソ連」、1990年〜2000年代以降は「中東のアラブ人」「テロリスト」、現代ではおそらく「AI」が、「よくわからない存在」へと代入されます。
たとえば『十戒』のなかでは、ファラオは野蛮で、荒々しく、激情的なキャラクターで描かれます。その対となるのが、西洋文明へとつながっていく理知的なユダヤ人ということになる。

その点では、ソヴィエト映画も変わりません。たとえば『イワン雷帝』では、即位後早々に、近隣のイスラム国家であるカザン=ハン国を攻め込みます。
そのきっかけとなったのは、たどたどしいロシア語で対決姿勢を示す、民族衣装をまとったカザンの使者でした。

明治以来、ヨーロッパに入り、アジアを抜け出すという「脱亜入欧」を掲げて近代化を進めていった日本にとって、こうしたコンテンツをどのような立場から眺めるかという問題は、非常に複雑です。
ついこの間まで、日本はアジアの盟主、少なくとも東アジアの盟主を自任し、欧米世界と対決していたのですから。
ただし今や、第一次世界大戦以来、そして特に第二次世界大戦後の世界は、明治以降日本が目標としてきた西ヨーロッパ諸国(イギリスやフランス)は、たいへんな損害を受けている。
それに比べると、アメリカもソ連は、それぞれヨーロッパを越え出て、新しい価値観を生み出そうとしていた、比較的歴史の浅い新興国家でありました。
しかし両者の描く世界像において、アジアは「遅れたもの」として描かれる。それら「アジア」のイメージを、当時の日本人が自分たちのものとして受け入れたいと思ったわけないことは、想像に難くありません。
戦端をひらいてつまづいた日本が、戦後の新しいアイデンティティを獲得するには、占領軍を率いるアメリカに入る(=入米)べきか、それともそれに抗してソ連に入る(=入ソ)べきか。
1950年代にかけて、現実的にとりうる選択肢はアメリカ陣営以外にはなくなるわけですが、いずれにせよどちらの選択肢をとったとしても、日本のアジアに対する認識は「脱亜」へと傾いていきました。
言い換えれば、日本人の認識から、かつて委任統治していたパラオやマーシャルなどの南洋諸島、植民地統治していた台湾や朝鮮の存在、占領していた東南アジア各地、日中戦争の戦地である中国大陸のイメージが抜け落ちていくこととなる。
日本があって、それとは別ものとしてアジアがある、その外にはヨーロッパがある。あるいは、日本があって、アジアを飛ばして、その外にヨーロッパがある。それ以外は「空白地域」——。
さまざまな形が考えられますが、こうした「アジアの欠如」こそが、その後の「ニッポンの世界史」にも少なからぬ影響を与えていくことになります。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
