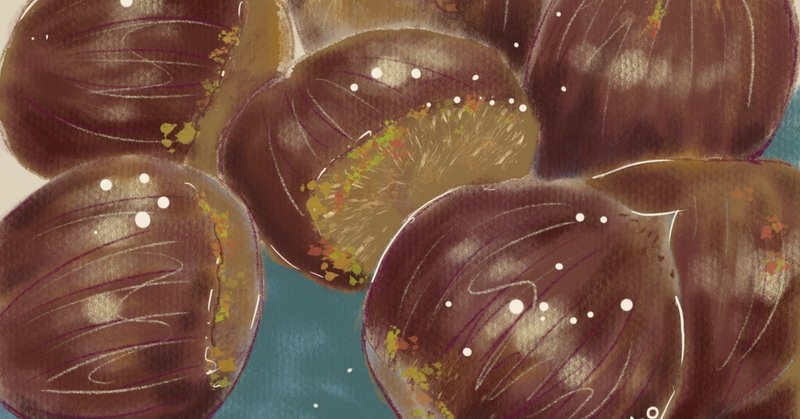
子どもと大人とスマホ【今日学んだこと】10/6/2020
今日学んだことを綴っています。
図書館で出会った雑誌から
近所に図書館があることの幸せ。
毎日でも行きたい。
館内をブラブラ歩いて、自分の目に飛び込んで来るものを今か今か、とドキドキしている時の幸福感。
「自分の目に飛び込んで来るもの」とは、今興味をもっているもの。意識的か、無意識か、どちらでも。
とにかくその時の自分にピッタリなものを、図書館の神様が教えてくれる。ような感覚を楽しんでいます。
今日「お?」と思い、手に取った本は「かぞくのじかん 2020秋 VOL.53」。そして目についたのは、特集の
「子どもとデジタル ちゃんと怖がって、ちゃんと使う」
まさに昨晩娘とスマホの話をしたところ。さすが図書館の神様、今日もステキな情報をありがとう。
まだ我が家では子ども(中学生)にスマホを持たせていません。家の近くからスクールバスが送り迎えをしてくれるし、塾など夜にひとりで外出することもなく、必要なしという判断です。(家の中では自由に使えるタブレットを渡しているので、実際不自由はない様子。)
世の中、スマホの利用者がどんどん低年齢化していますが、お父さんお母さんたちはこういうところに気をつけるべき、という最新の情報がたくさんありました。
それらは本を見てもらうとして、わたしが共感したのは
スマホを使いこなして興味のある分野へと進んだ子もいるし、ネットゲームで詐欺を働いて補導された子もいます。要は使い方次第です。
まさにその通り!と思います。
「包丁を子どもにいつから持たせるかを考えるのと同じように、スマホの使い方が危なっかしければ、親が子にしっかり関わることが必要です。」
かぞくのじかん 2020秋 VOL.53
タブレット利用は目に悪くないか?Youtubeは見せてもいいのか?害はないか?LINEは?SNSは?といった問題は、子育て中の親の間では常に話題になりますね。
とくにまだ小さい子。(もう中学生くらいになると、話題にもならないほど浸透してる。)
便利なツールは今の世の中溢れかえっています。でもそれを、危ないから、子供にはまだ早い、害が多い……など全く触れさせないのはもったいない気がします。
息子は2歳から専用のタブレットで動画やアプリを見ています。5歳の今では、パスワードを入れたり、自分の声で検索をしたり。動画で足し算引き算なども覚えてしまいました。
フィルタリングなど子ども用の環境を整えてやること、時間管理やタブレットと目の距離など、親がやるべき事をやれば、このようなツールは怖くない、と思います。
また、子どもたちがオトナになる頃はもっともっと進んだ社会。ツールに操られるのではなく、そのツールを使いこなし、さらには新しいツールを創り出すのが当たり前になる日がきっときます。というか、もうそういう時代か。
私はもう、ついていけないけど。
子どもたち、ルールを守って大いに楽しんだらいい。そのルールづくりが問題ですよね。子どもにも分かりやすいルール。
親の目の届くうちに、親の声が耳に入るうちに、お互いがきちんとそのツールの便利な使い方に慣れ親しんでおけば、いきなり何でも出来てしまう好奇心いっぱいの小さなオトナがそれを手にするよりは、トラブルになる確率も多少は減らせるのでは、と昔友達が言っていました。
記事では「玄関ドアの法則」が紹介されていました。
ネットに投稿する情報は、家の玄関ドアの外側に貼りだせるものだけ。それ以上の内容は投稿しない。(情報リテラシー専門家 小木曽 健さん)
これが理解出来ないかもと思ったら、スマホを持たせるのは早い、とのこと。
息子はまだSNSなどの存在には気がついていませんが、娘はスマホじゃなくても家の中のタブレットで外と繋がっています。玄関ドアの法則。分かりやすいから伝えておこう。
そうは言っても
どんなにうまくやろうとオトナがルールやら環境やら整えても、結局は子どもの能力、好奇心には勝てないのかな。とも思います。いたちごっこ。
オトナだってついついスマホいじってしまうのですから。便利だし。楽しいし。コメント見たいし。仕事もほとんどスマホでできてしまうし。
オトナも子どもも一緒。一緒にその便利さと怖さを学べたらいいね。
今日はこれにて。おしまい、おしまい。
サポート頂けたら嬉しいです!自分の世界をどんどん広げ、シェアしていきたいです。コツコツ階段を登り続け、人生を楽しみ尽くします。
