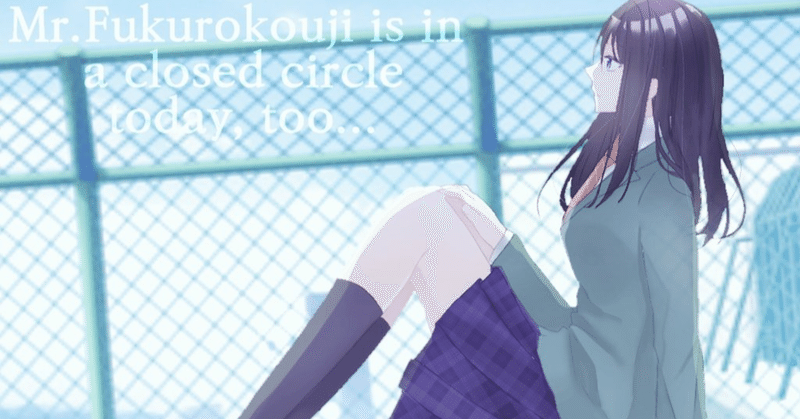
真相は財布の中にはない 【袋小路くんは今日もクローズドサークルにいる 外伝1】
とある日の放課後、赤い夕陽が傾きかかっている頃のことである。
僕と時任さんは、掃除を終えたばかりの部室で、西日を顔の側面に受けながら、小さなテーブルの上に乗った古い財布を見下ろしていた。いや、財布というには少々小振りなので、小銭入れと表現した方が適切かもしれない。
「どうしましょうか」
「いやほんと、どうしましょうね……」
どうして僕らが小銭入れひとつで唸っているのかと言うと、少し時間を遡る。
*
突然だが、クローズドサークルというものをご存じであろうか。
そう、ミステリーでよく見るあれである。絶海の孤島だったり雪山の山荘であったり失踪する列車であったりするあれのことだ。
外と連絡が取れない閉鎖環境で起こる連続殺人事件と言われれば一部のミステリ好きは沸き立つようであるが、僕――袋小路鍵人はそういったクローズドサークルを意図せずに作ってしまう呪いにかかっていた。……そう、呪いである。事件現場に居合わせてしまうと、事件の真相を理解するまではそこから出られないどころか、外部との連絡はとれなくなるわ散々な環境を作ってしまう呪いである。控えめに言って大迷惑な呪いだ。
名探偵と呼ばれた曾祖母のせいで発動したその呪いは、息子である祖父、孫である父、と脈々と受け継がれてきたらしい。同じ呪いにかかっている父に話を聞いた時は、現代日本で呪いとか(笑)などと思ったものだが、実際に体験してみれば笑ってなどいられなくなる。
そう、僕はつい数週間前に強制的にクローズドサークルになった――してしまったと言いたくない――図書室で、殺されかけた友人が手遅れになる前に事件を解決しなければならないという、地獄のようなリアルタイムアタックに挑む羽目になったのだ。
名探偵あるところに事件ありと言うが――僕なんかは「名探偵が諸悪の根源じゃん」なんて思っていたけれども、むしろ僕のほうが名探偵などよりよほど歩く災厄である。人を呪わば穴二つと言うが、僕の呪いの場合、下手をすれば数十人から数百人を巻き込む可能性もあるため、もはや墓穴は二つじゃ到底足りない。曾祖母は早急に解呪して子孫である僕らに謝罪会見を行ってほしい。どうして息子たちひいては子孫たちを呪ったんですか。事件解決ができなかったのは自分の問題ではないのですか。
……とまあそんなことを死者が実際に聞き入れてくれるはずもなく、僕は、図書室の事件に居合わせ、事件を解決まで導いてくれたクラスメイトの女の子――時任朝乃の協力のもと、呪いを解く鍵を探すことになった。
その第一歩が、僕らの活動の拠点となる、「オカルト研究部」の部室を新たに設けるにあたってあてがわれた部屋の掃除だったというわけだが――掃除の最中、時任さんがぽつりとこぼしたのである。
「わたし、ずっと考えていたんですが……クローズドサークルは『どこまで』発動するものなんでしょうか」
「どこまで?」
「呪いの発動条件は、ふくろうさんが『事件現場にいる』ということでしょう。その事件とは、どこまでが適用されるものなのかと、疑問に思いまして」
たとえば、と彼女はハタキを動かしながら言う。
「盗みとか、詐欺とか。他にも、軽犯罪と言われるものも呪いで言う『事件』の対象なのか、ということです。そういった現場にふくろうさんがいれば、すぐさまそこが閉鎖環境になるのでしょうか」
「恐ろしいこと言うな……」
「ですが可能性はあるでしょう」
それはそうだ。……と、いうか。
「その話の答えに関して、心当たりがあるよ」
「なんと」
僕の言葉を受け、時任さんが目を丸くする。
僕自身も今の時任さんの疑問を聞くまで忘れていたことだったが、思えば父から聞かされた話の中にこんなものもあったのだ。
「父がまだ学生だった頃、久々に会った従妹の人と出かけたらしいんだけどさ。その時、二人で寄ったコンビニで万引き騒ぎがあったんだって」
「万引き騒ぎ。なんだか話が見えてきましたね」
「早い早い」
「万引き犯が誰にも気づかれずに逃げようとした時、扉が開かなかったんですね? それで、万引き犯がアタフタしている間に犯行が発覚。その場に居合わせたお父様が真相、つまり万引き犯を理解したためにクローズドサークルが解除され、扉が開くようになり、開かなかった扉の件は気のせいとして有耶無耶になった」
「早い早い早い早い」
導入で全てを理解しすぎではなかろうか。
いやまったくもってその通りであったらしいが。
父はたしか、この話を『おもしろい経験』として語っていたような気がするけれども、よくよく考えればこれはクローズドサークルの呪いの事例であるように思える。父は呪いの発動に気が付いていなかったのだろうか。それとも、本当に扉の故障だったのか。
真相は全てコンビニの中にあったはずなのだが――電話が繋がるかどうかを確認すればわかったはずだ――父は確認していないようであったので、本当のところはもうわからないのである。
「なんであれ、殺人や殺人未遂というような、大きな――というと語弊があるかもしれませんが、一般的に想像できる重大な事件でなくとも、呪いが発動してしまう可能性はあるわけですね」
「意図せず僕の災厄度が上がった気がするな……」
しかし、一度気にし出したら、本当にどこまで呪いが発動するのかが気になってきてしまう。軽犯罪でもクローズドサークルができてしまうかもしれないのだとしたら、一体どこまでが『事件』に入るのだろう。
「あら?」
棚のホコリを落としていた時任さんが、不意に声を零す。なんだろうと振り向けば、彼女はその手に何かを手にしていた。近づいて手元を覗き見ると、それは使い古された財布のようだった。いや、年季が入っているだけで、使い古されたというわけではないのかもしれない。
「誰のもの、でしょうか」
「こんなにホコリをかぶってるんだから、多分かなり昔のものだよな。しかもここ、長く部室として使われてなかったはずだし」
オカルト研究部は部活という名目ではあるものの、正式には同好会の扱いだ。
同じく同好会扱いのクラブと部室を二分して、半分のスペースを使っているのだが――僕らにあてがわれたスペースは長らくどこの部活も同好会も使っていなかった場所だったはず。つまり、出てきた財布は恐らく、かなり昔の先輩のものであるということになる。
「名前は……書いてありませんね」
「まあ高校生にもなって小銭入れに名前を書いてる人もそういないだろうけど」
「名前入りの財布を持っている人はいるかもしれませんが、このくらいの小さなお財布ですと、確かに……」
何代か前の先輩のものなのか、はたまた顧問だった先生のものなのか。
返そうにも、返す相手に皆目見当がつかない。職員室にいる先生に預けるのがいいのかもしれないが、正直なところ、先生に預けたところで持ち主に戻るとは思えない。ここで長年ホコリをかぶっていたのなら、恐らく持ち主もなくしたことに気付いていないか、気づいていても放置しているかのどちらかだろう。
僕らは顔を見合わせた。
それから財布を見下ろした。
――そうして話は冒頭に戻るのである。
「少し、考えてしまったんですが」
時任さんが、小銭入れの中身を指でかき混ぜながら呟いた。中の小銭がぶつかり合って、チャリチャリと軽い金属音がする。やはり、仲には数百円ほど入っているのだろう。ちらりと見た限り、百円玉と十円玉がいくらかあったような気がする。
「これをわたしがネコババしたとして」
「待って」
「この場はクローズドサークルになったりするんでしょうか」
「僕の声もしかして聞こえてない?」
いきなり何を言い出すのか彼女は。
こちらの言葉を完全に黙殺して続けられた言葉に、唖然とする。
……いや、たしかにネコババも犯罪は犯罪だ。僕は法律には詳しくはないので正確にはわからないが、着服だとか、遺失物横領だとか、窃盗だとか、そのあたりの罪が適用されてしまうはず――この金額と状況で立件できるかは別として。
「どう思いますかふくろうさん」
「どうって」
「迂遠な言い方では伝わりませんか」
「伝えて欲しくない気がする……」
「試してみましょう」
「伝えて欲しくないって言ったよな?」
僕と彼女は短い付き合いだが、わかることもある。時任さんは時折、意味不明なところで手段を選ばないことがあるのだ。そして、すぐに耳を閉店させる。常に聴覚は営業していてほしい。『聞く耳』に日曜日は必要ない。
「……でも正直なところ、思っていたんじゃないですか?」
時任さんは内緒話でもするかのように、そっと声をひそめた。
「『ネコババしてもバレないなら先生に素直に届けるのもなんだかなぁ……』」
「わああ」
確かに、考えなかったといえば嘘になる。
が、仮にも時任さんのような『名探偵』のする思考回路ではないのではなかろうか。
……いや、かの名探偵シャーロック・ホームズも狂言で火事だと叫んでみたり、ハッタリをきかせてみたり、もろもろグレーなことをしていたようだから、必要とあらば名探偵であってもやることはやるのかもしれないが。
それはそれとしてネコババは『必要』か? 強制クローズドサークルの呪いの発動条件を見極めるために必要なことだ、ということか?
「どうでしょう」
悪魔が囁く。
「このお金でアイスを買いにいきませんか」
「ぐうう……」
確かに、掃除も疲れたし、小腹が空いたしで、甘いものでも食べたいと考えていたところだったけれども。
「大丈夫ですよ。誰も見てませんよ」
確かに、誰も見ていないし知らないだろうけれども。
……まあでも実際、呪いの発動条件を見極めることは、今後の人生にも必要なこと、であるようにも思える。何せ、強制的にその場を鎖してしてしまう呪いなのだ。なんでもかんでも場をクローズドサークルにしてしまっていては、僕はそのうち誰かに消されてしまうのではないか。いや、まったく冗談ではなく。
それに何より、駄目だ。
既に口の中がアイスになってしまっている――。
「……わかった。実験してみよう」
「!」
苦渋の決断であった。
いやしかしこれは実験であってまったくもって私欲などではないのだ。断じてネコババでは――ネコババかもしれないが、あくまで世のため人のためなのだ。
そうして僕は小銭入れを掴むと、意を決して、閉まったままの部室の扉に手をかけた。
――結論からいえば、部室の扉が不自然に開かなくなることも、スマホが圏外になることも、窓が開かなくなることもなかった。
僕は時任さんと並んで学校からすぐ近くのコンビニに行き、アイスを買って、そこでふとあることに気がついた。
「なあ時任さん」
「はい、なんでしょう」
「そもそも、これ、意味なくないか実験として」
何せ、犯人は僕なのだ。正確に言うなら、僕ら、か。
クローズドサークルの解除の条件は、僕が『事件の真相を理解すること』。犯人が自分たちなら真相の理解もへったくれもない。たとえクローズドサークルができていたとしても同時に解除されていることになる。ということは、呪いが発動されたかどうか確認できない。
「……ふむ」
そう言うと。
時任さんは棒のチョコアイスを舐めながら、薄く微笑んだ。
「――確かにそうですね。気づきませんでした」
*
その後。
僕は結局、時任さんの言もあり――僕も良心の呵責に耐えられなかった――使った金額と同じ金額を小銭入れに戻し、担任の笠原先生に届けた。笠原先生は笑顔で「あら、ありがとう」と言って、それから目を見張った。「これ、昔わたしが落としたと思ってた――」
なんと、小銭入れは、この学校が母校である先生のものだったらしい。先生に指摘されてよーくよく見てみれば、財布の奥の奥、剥がれかけた名前シールがあった。どうしてそこに貼ったのだろうか。
とまれ、謎の小銭入れの真相は、結局財布の中にあったというわけだが――先生は笑って、せっかくだからこれで好きな物買いなさい、とそれを僕らにくれた。使わないから寄越したという感がないでもなかったが。
……時任さんは、どこまで知っていたのだろう。
思えば、聡明で観察力も卓抜している彼女が、実験が無意味だったと気づいていなかったとは考えにくい。名前シールのこともである。あえて黙っていたのだとしたら、一体それにどんな意味があったのだろうか。
結局、クローズドサークルが『どこまで』発動するのか、それは明らかでないままだし、彼女が何を思っていたのかもわからないままだ。気づいていたのかもしれないし、気づいていなかったのかもしれない。人のお金でアイスを食べたかったのかもしれないし、ネコババをすると言った時の僕の反応を見たかっただけなのかもしれない。
なんであれ、全ての真相は、彼女の心の中にしかないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
