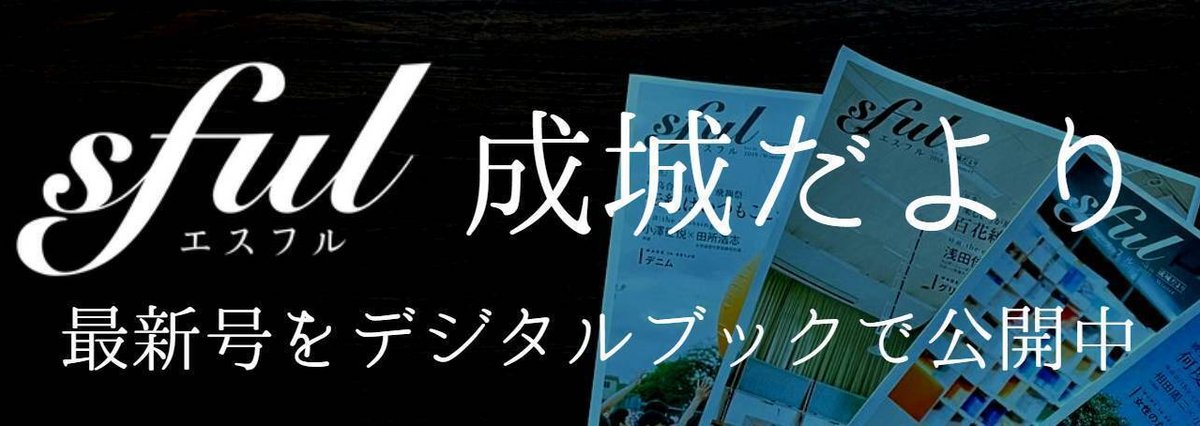本に出会い、人とつながる”ワザあり”な図書室
『sful-成城だより』vol.17(2022年発行)の「ワザあり!in Seijo Gakuen」では、成城学園中学校高等学校校舎の図書室を紹介しました。とはいえ、誌面で紹介できたのはごくごく一部に過ぎません。 取材チーム一同が「ずっとここにいたい!」と夢中になった図書室の魅力について、司書教諭の嵜口康子先生にじっくりと伺いました。
昼休みは漫画コーナーでリラックス
成城学園中学校高等学校には、7万5500冊もの蔵書を誇る図書室があります。温かみのある木製の書架が並ぶ図書室は天井が高く、棚と棚の間のスペースも広々として開放感を感じます。
柔らかい日の光が差し込むグラウンドに面した大きな窓辺は、居心地が良く、それでいて集中できる自習エリアです。このほかにも、大きなテーブルが置かれ、グループワークを目的とした自由に会話できるスペース、一歩入ればおしゃべり禁止の自習室など、全部で114席の自習スペースが用意されています。
「図書館に入ってすぐ右手にあるのがグループワークの部屋で、窓辺の自習エリア、自習室、一番奥の書斎エリアと、奥に行くほど静かに集中できるような導線になっています。自習室は中学の「読書」の授業にも使われるなど、目的にあった使い方ができるようになっています」(嵜口先生)
「静かに読書や勉強をするだけではなく、気軽に気分転換できる場所にもしたかった」と嵜口先生が話すように、「食後の一休み」「リラックスしたい」という目的でやってくる生徒も多いようです。そんな生徒たちに人気なのが、窓際にある学習漫画コーナー。人気漫画の英語版、歴史や文学が学べる漫画など、楽しみながら学べるラインナップが揃っています。

中学生と高校生が交流する場にも
2016年に中高一貫校舎ができるまでは中学と高校それぞれの校舎に図書室がありましたが、新校舎では中1から高3までが同じ図書室を利用しています。「中学生がちょっと背伸びして高校生向けの本を読むこともあれば、高校生が『懐かしい』といって中学生向けの本を読むこともあります。そうやって幅広く本に触れられるのが、図書室の良さですね」と、嵜口先生は話します。
異学年交流ということでは、嵜口先生からとても印象深いエピソードを伺いました。
たくさんの生徒が自習していた試験前のある日、貸出カウンター前の長テーブルで中学生に数学を教えている高校生が目にとまりました。勉強を終えた中学生が帰った後、嵜口先生が高校生に「自分もテスト前で大変なのにえらいね。知り合いなの?」と声をかけたところ、「全然知らない子だけど、たまたま隣の席だったので教えてあげていた」と答えたというのです。
「成城学園は幼稚園から大学まであるので、違う学年でも知り合いがいることは珍しくありません。彼らもてっきり知り合いなのかと思ったのですが、偶然図書室で席が隣だっただけだと聞いて、こういう形で中学生と高校生が交流できるのはとても素敵なことだなと思いました」(嵜口先生)
実はこの図書室には、生徒同士だけでなく、先生と生徒、先生同士が交流を深めるようなシカケがあります。図書室の中央には階段があり、その階段を上るとすぐに職員室となっています。つまり、図書室で自習していて疑問点があれば、生徒はすぐに職員室にいる先生に質問や相談ができるのです。そんな生徒たちのために職員室周辺にはカウンターテーブルや相談コーナーがあります。また、図書室の中には、貴重な教材が収蔵され研究活動に使える教員専用部屋も設置されています。

たくさんの素敵な本と出会ってほしい
勉強したり、リラックスしたり、異学年交流をしたり――。図書室を利用する生徒の目的はさまざまですが、嵜口先生の願いは、やはり「いい本と出会ってほしい」だそうです。
コロナ禍で休校になり、図書室が閉鎖されていたときは「毎日のように図書室に通っていた子たちはどうしているだろうと考えると胸が詰まりました」と話す嵜口先生。
休校が明けてすぐに、スマホやタブレットで電子書籍を読める電子図書館の導入を決めました。
この試みは好評で、図書室が利用できるようになっても一定数の生徒は電子図書館を活用しています。電子図書館を導入してわかったことですが、人に相談しにくい悩み事があったり、勉強につまずいたりしたときに、人を介さずに読みたい本を読めるというメリットが大きかったようです。しかも、紙の本のように人前で広げずにスマホで読めるということも、思春期の生徒たちに受け入れられた点でした。
電子書籍でも紙の本でも、選書は司書教諭にとってもっとも大切な仕事のひとつ。「多くの生徒が興味を持ってくれそうな本を選ぶようにしている」と話す嵜口先生は、話題の本の情報収集のため、週末はほとんど書店巡りをしているそうです。そのようにして話題作のチェックを欠かさない一方で、長年読み継がれてきた文学作品にも親しんでほしいといいます。
「読み応えのある名著を読んだ生徒から『難しかったけれど面白かった』という感想を聞くと、うれしくなります。簡単な本はいつでも誰でも読めますが、10代の一番のびしろのある世代にこそ、成長するような本をじっくり読んでほしいですね」(嵜口先生)

本好きはもちろん、どんな生徒も豊かな時間が過ごせる図書室。時間を忘れて本を読みふける生徒もいれば、集中して勉強する生徒もいる。床に座り込んで楽しそうに漫画を読む生徒もいる。ここには思い思いに過ごせる自由な時間が流れているようでした。
文=sful取材チーム 写真=佐藤克秋
本記事の無断転載・複写を禁じます。