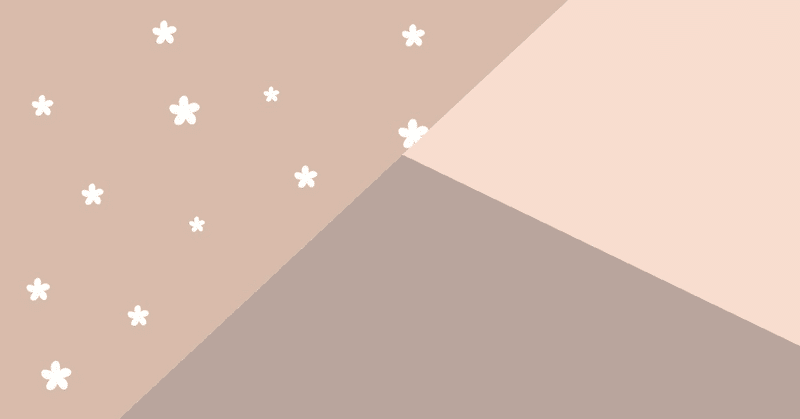
【創作小説】小部屋 (透編)
昔行きつけだったバー『フラニー』にて詩史と企てたパリ旅行を、透が一人で決行したのは1年程前のことである。そこで偶然訪れた個展で出会ったのが、画家である深雪だ。
「絵なんてどこでも描けるわ」
パリには飽きてきたところだったの、と深雪はさぞ当たり前であるかのように、透の住む東京の部屋へ引っ越してきた。何でも、別れた恋人に会いに行く為に訪れたパリを気に入り、そのまま長々とパリ暮らしを続けていただけのことであったらしい。
あれ程焦がれていた詩史とは、すっかり疎遠になっている。浅野がついに弁護士を雇うなどと透を脅したからだ。当然透に勝ち目などなく、詩史の側から離れるという選択に迫られるほかなかった。
詩史と距離を置いて冷静になった頃、母を思い浮かべたことがある。母は自分をどう見ていたのだろうか。旦那のいる親友と逢瀬を繰り返す息子のことを。
「透、もう寝ない?明日も仕事でしょ」
お風呂上がりの深雪が言う。彼女は今日、透の婚約者になったばかりだ。そうだね、と空返事だけして透はまた記憶に引きずり込まれる。東京にいる限り、詩史が透の中に作った小さな部屋は遠ざかることはあれど、消えることはない。こうやって愛する人の隣にいてもなお、時々透の心は無意識に小部屋へと逃げてしまう。
「女はバカな方がいいよなあ。」
いつだか耕二は言っていたけれど、透はそれが正しいのか分からない。結局詩史は知っていたけれど。二人の愛に永遠などない事も、一緒に生きるという言葉が幼稚な逃避であった事も。そんなことを知る由もなく、心のどこかで彼女がいつかは自分のもとへ来てくれるのだと信じて疑わなかった。浅はかだ、今になっては笑ってしまうほどに。もはや詩史という部屋なんてものは端から幻想でしかなかったのだろうか…。
気持ちが悪いわ、と詩史ならきっとそう言うだろうと透は思う。詩史なら、寝る前にアイスクリームを食べることを嫌っただろうと。ましてや深雪はベッドに腰掛けているし、マグカップの中のバニラアイスには少量のブランデーがかかっている。
透は遠くをぼうっと見つめながら、何もかもがすっかり変わってしまったとまた思いに耽る。26で結婚する透も、3年前に結婚して既に娘が2人いる耕二も、浅野の不倫によって離婚を果たした詩史も。
世界は自分を中心に構成されていると透は考えられるようになった。時間軸が詩史ではなくなってしまった。その喪失感を断ち切るのには随分と時間を要したものだ。
しかし、深雪からの愛を愚かにも信じてみたいと思う。深雪とこれから一生連れ添ってゆくのだ。これが最上の幸せだと透は騙されたまま死にたいとすら思う。
笑い声が絶えず流れるテレビを見つめながらゆっくりとアイスを口に運ぶ深雪の頬に唇を寄せる。きっとこれからも彼女とゆっくりと流れる日々を送る。そして彼女を、日々を、もっと愛せるはずだ。
あまりにも当たり前に深雪が側にいるので、詩史にあんなにも執着していた事を面白いとすら思うこともある。
「めちゃくちゃだ」
透が呟くと、深雪は手元のマグカップを見つめながら笑った。
「確かにね、溶けたアイスは汚いわ」
※この作品は、私が敬愛しております江國香織先生の小説「東京タワー」の二次作品です。
サポートいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
