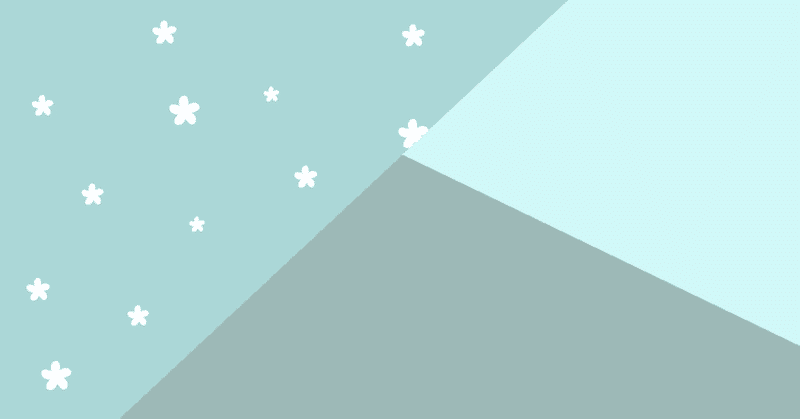
【短編小説】Cats and Dogs
猫と犬が降る、というホストマザーの発した意味不明な言葉に思わず「猫と犬が降る…」とおうむ返しをした。2年前、ホームステイをしていたアメリカでのことだった。あの日見た大雨を今でも時々思い出す。日本語で言うところの、バケツをひっくり返したような大雨を意味するらしい。───寧ろバスタブをひっくり返しても足りないと思ったが。
とにかく、あの日はそんな大雨だった。
夜、ホストマザーはスーパーマーケットまで買い出しに行くのが億劫になったのか、今夜はレフトオーバー(残り物)パーティをしましょう、と提案した。冷凍庫から出したピザとタコスのシェルをオーブンでローストする。ジップロックに保存していたタコミートを取り出し温める。そして冷蔵庫に残っていたロメインレタスとトマトを刻みタコス用にして、トマトの残りをスープに仕立てた。幸いなことにキャビネットにひと瓶だけサルサソースのストックがあったことまで覚えている。レフトオーバーと言いつつも、それらは立派な食事へと変化を遂げたのである。
食卓にて”It’s raining cats and dogs!” と私が覚えたての英語を話すと、ホストマザーはとびきり嬉しそうに笑った。あなたもすっかりアメリカンね、と。あの夜の私は、ほんとうに自由の国の人間だった。
今日も雨の中を歩いている。傘なんかじゃ気休めにしかならない大雨の中を、わざわざ左肩を濡らしてまで彼とふたりで傘を差して。右手は傘、左手は荷物で手が塞がってしまっている。だから解けた靴紐を結び直せない。日毎に彼に落ちてゆく痛みにも抗えない。せめて今だけでも雨の冷たさで麻痺させられたならよかったのに。ニュースの予報では明日までにこの雨が止むのだという。もしもその通りになったら、いつだか放課後にやけくそで行ったインチキ占い師の「お付き合いできるでしょう」も叶うと信じてみようかと心の中で賭けてみる。
彼の家に入った瞬間、今日は待てない、と彼は言って私をドアに押し付けてキスをした。
傘立てに入れてすらもらえなかった傘。乱雑に置かれた荷物。スーパーの袋がくしゃりと音を立てて崩れた。2割引で買ったソーセージを早く冷蔵庫に入れなきゃとか、一番下に入れた卵が割れてないといいな、とか蕩けそうな脳みそでなんとか考えてみる。これ以上彼を好きになりたくない私の、ささやかで無意味な抵抗。本当は彼以外のことの全てがどうでも良くなっているくらい、手遅れなのに。
私に触れる彼の手だけが濡れていて冷たかった。たぶん、私に対する気持ちくらい。
結局いつも通り行為はベッドで済まされた。一切の無駄のないそれが終わると、彼はすぐさまクローゼットからTシャツを二枚取り出してそのうち一枚を私に投げた。バンド名がプリントされたそれを着る。元々背が高いのにオーバーサイズを好む彼の服は、私が着るとまるでワンピースだ。最近彼がハマっているというゲームの起動音が鳴る。ゲーム機を手に持っているであろう彼を視界に入れないように、わざとガチャガチャ音を立ててバッグから化粧落としを取り出した。
「お風呂、借りるね」
どうぞー、と言う彼の声を背中に受けながら脱衣所に入る。ドアの向こう側から激しい銃声音と下品な英語が聞こえる。うるさいなあと思いながら、Tシャツを脱ぎ捨てた。くしゃくしゃになったTシャツの英文字。直訳すると「冷たい雨」。それがなんだか無性に遣る瀬無くて、溜め込んできた悲しさが溢れてしまう。どうせ彼には聞こえない嗚咽を、それでもどうにかかき消したくて、急いでシャワーを出した。
出てきたのは冷たい水で、涙はいよいよ止まらなくなった。
他人の家の風呂場を長々と使うのはなんだか憚られたけれど、これくらいの仕返しなら許されるだろうとバスタブにお湯を溜めることにした。窓のブラインドを少しだけ開けてみると、雨脚はちっとも弱まっていなかった。
「猫と犬、降ってるなあ…」
ちっとも自由じゃない私は、彼が唯一置いているレモンの入浴剤は入れないことにした。甘くないならいっそ何も感じない方がマシだから。
もしも私がもう会わないと言ったら、彼は引き止めたりはしないだろう。それどころか、あっさり私の代替を見つけるところまで容易に想像がつく。セフレという言葉よりも軽薄に思える関係なのに、私の好きが足枷になって私はこの地獄から一歩も動けないでいる。虚しさをセックスで埋めて、セックスで埋められる虚しさにまた虚しくなる負のループ。
シワの少しついたTシャツを着て部屋に戻ると、彼はいつの間に作っていたらしいスープを器に注いでいるところだった。
「なんか作ったけど食う?」
「料理できるとか初耳なんだけど」
「テキトーだよ。食うでいいよな」
食べる、と言う頃には目の前にスープカップが置かれていた。前に雑貨屋で見かけた器。これペアで売ってるやつじゃなかったっけ。スープに丸々入ったソーセージは安物で皮はちっとも弾けなかったし、コンソメだけで味をつけたのか物足りない味がした。彼はスープにブラックペッパーを少しかけてくれたけど、私はパセリの方が好きだ。
だけどこのスープの存在が、彼から受け取ってきた少ないモノや言葉の中で一番温かい。体温以外に彼から温かみを感じることができたのだと思うと、やっと彼に対して優しい気持ちになれた。
これが私なりの許しであって、諦めであって、穏やかながらに確かな決別への覚悟へと変わった。
スープを啜る二人。沈黙。
雨足が強くなるのがはっきと聞こえる。
「It’s raining cats and dogs, isn’t it?」
「えっと、ドッグ?キャット?」
「あのね、土砂降りのこと、直訳すると猫と犬が降るって言うんだよ」
「とんでもない言い方すんだな」
もうすぐ日付が変わる。雨は降り止む気配を見せない。
「私さ」
うん、と彼が聞き返す。
「こういう風にならずにあんたのこと普通に好きでいられたらよかった」
唐突に言った言葉に彼はさして驚かず、むしろその返事で私をひどく動揺させた。
「俺も、そう思ってた」
じゃあ何故こんなにも拗れてしまったの。
「私、もうあなたに会うのやめるよ」
これを言えるようになるまで本当に長かった。だけど丁寧に拾ってつけてしまった足枷を外せるのは、自分ひとりなのだ。
「悪かったよ、今まで」
彼がどの行為に対して謝っているのか分からなかった。それでも彼に罪の意識があったということは、私を傷つけてきた行動が故意だったと捉えることもできる。
「なんか一線を超えておいて大事にするなんて言えなかった。そのくせ手放すのが惜しかった」
ショユウブツみたいな、と彼は申し訳なさそうに言った。
残酷な追い討ちだ。
「私ね、自由に戻るの」
「戻って、タコスとかピザとかお腹いっぱい食べるだけで笑いたいの」
何言ってんだ、と言う彼を遮って私は言った。
「あんたに振り回される自分が嫌だったの、私ちゃんと自由だったのに。残り物で幸せになれたのに。」
「意味分かんねえ、もう帰れよ」
私は荷物ごと玄関に放り出されてしまった。Tシャツは冷たい雨によって間もなくびしょ濡れになった。
雨に濡れながら大事に抱えてきたものの重さを考える。いつかの放課後の占い師の言葉も。
どちらも、今になってはもう意味をなさない。
───24時3分。
“It’s raining cats and dogs!”
Meaning: Something that you say when it is raining heavily.
( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/it-s-raining-cats-and-dogs )
サポートいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
