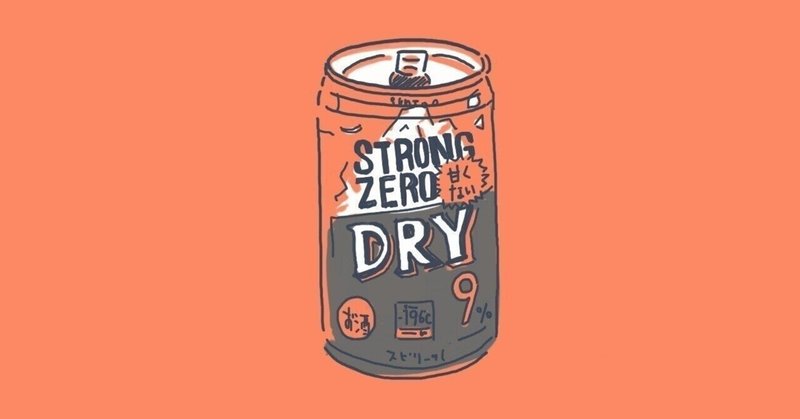
ストロングゼロを飲んで世界と戦う?
最近、職場がごたごたしているさとくらです。
僕の所属する部署の誰かが異動になるんだとか、ならないんだとか、あーだこーだ。
異動するなら、僕なのではないか、うんぬんかんぬん。
ちょっと面白そうなので、異動したい僕。
歯の矯正がズレて、うわの空な同期。
最近ようやく離婚が決まった先輩。
最近、結婚した後輩の女性。
話題はなぜか、名字が変わることについて進んでいき、同期の女の子が「名字変えたくないんだよね」と言い始める。
「男の方が名字を変えても良いよね。むしろ僕は名字を変えたい」と言う、僕。
「じゃあ、さとくら君が名乗りたい名字ってなに?」
質問されたのは僕なのに、答える暇のない大喜利が始まる。
結論は「十六夜(いざよい)」。
十六夜太郎(仮)と僕は今後名乗る訳だ。
中二病ど真ん中って感じで逆に良いのでは?
ということで将来、僕は十六夜という女性と結婚し、彼女の姓を名乗りたいと思う。
ところで、十六夜って名字はあるんですかね?
調べていないんですが、日本も広いですし、どこかにはいますよね?
さて、今回のエッセイは2019年1月30日にカクヨムで書いたものです。ちなみに、缶チューハイのストロングゼロは個人的には舌には合わず、ハマりませんでした。
●●●
文芸誌を毎月買っている僕ですが、中身をすべて読んでいる訳ではありません。
基本的には気になったものを拾い読みをする程度です。けれど、ふと時間が経って、本棚にある文藝誌を手に取って読む、ということをよくします。
今回、手に取って読み始めて止まらなくなったのは、新潮2019.1の金原ひとみ「ストロングゼロ」でした。
金原ひとみは翻訳家の金原瑞人の娘で、芥川賞を綿矢りさと共に受賞した人です。芥川賞を受賞した「蛇とピアス」は映画化もされて話題になりましたが、作品群の中での傑作は「AMEBIC(アミービック)」だと思っています。
あくまで個人的にですけれど。
そんなことを言いつつ、僕は金原ひとみの熱心な読者ではありません。ただ、僕の世代(もしくは僕より少し上の世代)で小説、文学を書こうと思ったり、興味を持った人は洩れなく綿矢りさと金原ひとみに注目していたように思います。
ちなみに芥川賞と同時に直木賞も受賞が発表されます。金原ひとみと綿矢りさが芥川賞を受賞して脚光を浴びる中、直木賞を取ったのは京極夏彦と江國佳織でした。文学好きからすれば、この二人の受賞は十分な事件です。が、注目を受けたのは綿矢、金原コンビでした。
その結果という訳ではないでしょうが、受賞後の数年間、綿矢、金原はコンスタントに作品を発表できませんでした。京極、江國は変わらぬスピードで自身の作品のクオリティを上げていきました。
注目されることが必ずしも作家にとって幸福なことではないのだと思います。もちろん、注目度が売り上げに繋がるのですから、完全に度外視する訳にはいかないでしょうけど。
さて、話がズレましたが新潮に掲載された「ストロングゼロ」です。
ストロングゼロは甘くない上に、アルコール度数が高いため、簡単に酔える缶チューハイとして2018年に人気になりました。その中でストロングゼロ文学なるものも流行りました。
名作の文章の中にストロングゼロが出てきてオチみたいにする、という流行で、現在はそれほど見かけなくなりました。
そんな流行を踏まえて金原ひとみが「ストロングゼロ」を書いたのかどうか、僕には分からないのですが、ストロングゼロがアル中の意味として使われていることは明白でした。
「ストロングゼロ」の主人公は出版社に勤めている女性で、一緒に住んでいる男性がいます。
彼との生活が一年経った頃に「俺おかしくなったのかな」と言って、部屋に引きこもってしまいます。病院に行っても変わらず、毎日ベッドの上で眠り続ける彼を前に、主人公の女性は以下のように考えます。
私の好きな彼は失われた。でも私の好きでない彼もまた彼で、そういうのは好きじゃないの、それだったらいらないの、と振るほどには私は強くなく、彼は彼だからどんな彼でも大丈夫と言えるほどにも私は強くない。
結果、主人公は現実から逃避するようにコンビニでストロングゼロを飲みはじめ、仕事中にも飲まなければ自分を保てなくなっていきます。
あらゆるものが以前通りのように振る舞えなくなっていく女性の日常はリアルで、それの行き着くラストは在り来たりですが、上手いと膝を叩くオチでもありました。
そんなストロングゼロを読んでいる間、僕の頭に過った作品がありました。こちらは2017.4文學界に掲載された第47回九州芸術祭文学賞最優秀作の尾形牛馬「酒のかなたへ」です。
アルコール依存症で四回目の入院中であり、今回こそ酒をやめようと思っている男が主人公です。物語の後半で主人公に向けて酒をの飲め、という男が現れます。彼は八回の入院していました。
彼は言います。
「なあ、古釘君、人間にとって死がすべて、死こそがすべてなんだ。もし人間に意味があるとなら、その生に意味があるとじゃなくてその死にこそ意味があるとだよ。アル中はな、それに気づいた人間なんだよ。アル中は死の世界からの使者なんだ。だから、古釘君、このウィスキーを飲め」
酒は現実という意味(死)からの逃避であると同時に、戦う手段なのかも知れません。
少なくとも金原ひとみの「ストロングゼロ」の主人公は恋人が失われていく(死んでいく)現実に耐えきれずに、ストロングゼロを飲みます。
逃げているように見えて、日常を送り続ける姿には惨めにも戦っている誠実さが浮き彫りになっていきます。
アル中の人間が立派だとは口が裂けても言えません。
僕が実家に居た頃、父は毎日のように酒を飲んでいました。時々、飲み過ぎて暴れたり、電話先の相手に喧嘩を売り始めたりしました。
ほとんどアル中の領域に父は足を突っ込んでいたように思います。僕はそういう父を見て、軽蔑しながら、どこか目が離せられないものを感じ続けていました。
それが歳を重ねて、僕が今お酒を飲んでいる理由なのかも知れません。が、そろそろ控える時期に差し掛かっているようにも思います。
単純に飲んだ次の日がしんどい、という超現実的な理由で。
サポートいただけたら、夢かな?と思うくらい嬉しいです。
