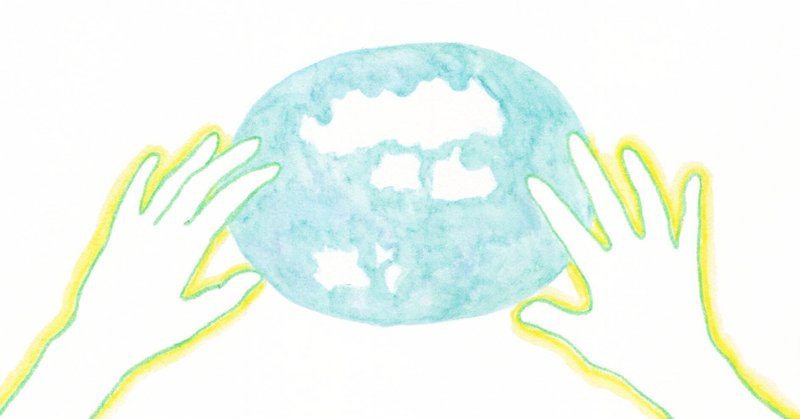
〈ファンタジー小説〉空のあたり1
昼休、会社を抜け出したぼくは、喫茶店に着く。そこで出された飲み物は、「空のかけら」と交換できた。それを手に入れる条件を満たしていないぼくは、代わりに奇妙なしごとをこなす。裏技で、空のかけらを得たぼくは、やがて知り合った女の子と、お店の裏メニューを発見する。それを飲むと、ここに逃げて来た理由を、思い出した。空のかけらを使い果たしたぼくは、最後のしごとをし、家に帰った。
1. 救出
用水路に足を取られないように、ぼくは必死に歩いた。何かに追われているように、ぼくは感じた。けれどそれは、幻だった。自分でも、半分気づいているのだった。それでもぼくは、あくせく働き、今、こうして休憩中に逃げ出して、用水路に足を取られないように、懸命に歩いている。
そろそろゆっくり歩いても、良いころだろう。
にゃあと猫の声がする。三毛猫の声だと思ったが、その根拠はどこにもない。と、空から何かが降ってきた。そのとたん、目の前が、まっ茶色になった。
カラスがカァとないた。
とてもゆうふくな声だ。きっとゆうふくなカラスで、小さなモグラとも仲が良いのだろう。こんなことを聞いてきた。
「あなたのおだんごは何色?」
「みどりです」
ぼくは、抹茶を想像して答えた。
「それは、茶色じゃなくって?」
「いいえ」
まっ茶色と、抹茶色はちがう。
「そんなことより、ここはどこですか?」
さっきからぼくは茶色い紙に包まれていた。捨てられたガムのように。
「チガウヨ」
いきなりカラスは心を読んだ。そうだ。さっきの抹茶だって、ぼくの心の中のことだったのに。
ここはとくべつなばしょ。
「じゃあ、この扱いは、なんなんですか。ひどいじゃないですか」
「それは、自分の色。自分で、ぬった色」
そうだった。ぼくはさっき、茶色いクレヨンで、メモ用紙をぬりつぶしていた。そしてたまらなくなって、会社を抜け出したのだ。
お昼休みは、あと十五分。早く戻らねば。机の上の、茶色にぬりつぶされたメモがみつかる前に。
「その前に、洗濯に行ってきます」と、ぼくは言った。
Tシャツには、もう茶色がしみこんでいた。取れるだろうか。十五分で。
「取れないね。がまんなさい」
そんなこと、カラスに言われたくなかった。
「じゃあ、いいですよ。ちがうのに替えるから」
そう言って、ズボンのポケットにあるはずの替えのTシャツを、ぼくは取り出した。
「ホウ」とカラスは、ため息をついた。
でも、Tシャツは、くしゃくしゃで、ゴワゴワだった。それに、茶色い包み紙に包まれた状態では、何もできないことが分かった。
「あの、ここから出してください。着替えるから」
「そんなの私には、できっこなーい」
バサバサと羽の音がして、カラスは行ってしまった。
「どうすればいいんだよう」
すると、心の中から声がきこえた。それは、心からの声だった。
手をのばしなさい。
ぼくは、ぎっと手をのばした。
そこにあるのは、空間だった。
何もつかめない。誰も、その手をつかんでくれない。そう思った時、バリっと音がして、ぼくを包んでいた紙がやぶけた。そこには、まあるい目が、のぞきこんでいた。
「ダァイジョウブですかぁ?」
その人は、手をひざにおき、少し前かがみになって、ぼくをのぞきこんでいた。ぼくは当然の質問をぶつけた。
「あのう、ここはどこですか」
「森じゃないことは、たしかです」
「じゃあ、海ですか?」
けれど、その質問が、とても意外だったらしく、その人は、もっと目を丸くして、こう答えた。
「それに近いかもしれません」
「なんだか、潮の香りがした気がしたから」
その人は、ぼくの手をひっぱってくれた。思ったよりザラザラの手だな、と思った瞬間、相手は真逆の感想を持ったみたいで、こう言った。
「あなたの手は、海みたいですね」
そんなにうるおっているだろうか、と思いながら、「そうですか」とだけ、ぼくは言った。
見回してみると、そこはカウンターのある、喫茶店のような所だった。壁には、三角形の旗がたくさん連なり、ぶら下がっていた。いつかおばあちゃんと行った、海沿いのレストラン。そこで食べたマカロニグラタンの味を、ぼくは思い出した。
カランコロンという音がして、誰かが入って来た。
「いつもの」と言って、その人は、カウンターの窓際の席に座った。
「はいよ」
丸い目の人は、厨房の中へ入って行った。この人は、きっと、このお店のマスターなのだ。
ぼくも、そっと席に座った。
お金は、あっただろうか。ポケットの中を探ると、小銭入れが入っていた。
「すみません、同じものをお願いします」
「はいよ」
マスターは、厨房に入って行った。 ぼくは、ほっとした。
しばらくして出てきたのは、水色の瓶と、グラスだった。水色の瓶は、もう蓋が開いていた。
窓から遠い席に座っていたのに、瓶は日の光に当たったように、キラリと光った。
ぼくは、まず瓶に手を付けずに、窓際に座っているお客さんを観察した。その人は、瓶からグラスに飲み物を注ぎ、それをぐびっと飲み込んだ。
ぼくも真似をして、瓶を傾けた。無色透明な液体が、グラスに入って来た。鼻を近づけてみると、一度も嗅いだことのない香りがした。これってなんていうんだっけ。と、ぼくは頭をめぐらせた。けれど、結局なにも見つけられずに、ふりだしに戻ってきた。
わからなかったので、もういいや、と思い、えいっと、それを飲み込むと、口にほころびができたように、笑みがこぼれた。これは、おいしいサインだ。脳が、おいしいと言っている。だからぼくは、ほほえんだのだ。そう思ったが、それがどんな味なのか、ぼくには、とんと分からなかった。甘いのか辛いのか、すっぱいのかさえ分からなかった。
もっと、自由に
どこかで、声が聞こえた。それは、小鳥のような声だった。ぼくはびっくりして、マスターの方を見た。
「どうしましたか?」とマスターは言った。やっぱり、違う声だ。
ぼくはため息をついた。ぼくはびっくりするために、ここに来たんじゃない。じゃあ、何のために来たのだっけか。と、考え始めて、ぼくは、すぐに迷いはじめた。
ゴールのないゴールが、空に浮かんでいて、ぼくは飛べなくて、永遠に手の届かないゴールを、道の真ん中から見上げている。そんな気持ちになった。
そんな風にぼくが迷っている間に、窓際のお客さんは、あっというまに飲み物を飲み終えていた。そして立ち上がると、マスターに何かを渡した。ぼくはそれに目を凝らした。てっきりお金だと思ったのに、それはまるで違った。
それは、空だった。さっきぼくが見上げていた、けっして手の届かない空を、小さくちぎったものだった。
「ごちそうさま」と、お客さんは言った。
え? これがお金なの?
ぼくは焦った。
「あ、あの、それ、持ってないんですけど」
正直にぼくは言った。
「それは困りましたねぇ」
マスターは、全然困ってなさそうな顔でそう言った。
「なんだ、ぼっちゃん、無銭飲食かい」
お客さんが、ガラガラの声で言った。
「え、そんなつもりは。だって、普通のお金なら持ってるんです!」
ぼくは小銭入れから、お金を取り出した。けれどマスターはそれをチラッと見て、「こちらは、お使いいただけませんね」と、さらりと言った。
ぼくは全身がこわばっていくのを感じた。このままだとぼくは、無銭飲食というものをしてしまうみたいだ。
「どうしたら良いですか。ぼく、皿洗いでも、なんでもしますから」
すると、マスターが、優しく言った。
「では、それをください」
マスターが指さしたのは、ぼくの首だった。
首を切って渡せとまでは言わないだろうけれど、さすがにちょっと怖かった。
ぼくは、そっと首を触った。そこには感じたことのない、冷たい感触があった。いつのまにか、ぼくの首には、見覚えのないネックレスがかかっていた。
「なんだこれ」
それは、真珠よりも小さな、黒っぽい粒が連なってできていて、カタツムリの殻みたいな飾りが、一つ、ついていた。
「こんなの、いくらでもあげますよ」
そう言ってそのネックレスをはずそうとしたが、全然取れない。それは、イボみたいに首に張り付いていた。
「あれ、これ、取れないな」
首をかきながら、ぼくは言った。
「それは、あることをしないと取れません」と、マスターは言った。
「なんですか」
なにか、悪い事でもさせられるのじゃないか。そんな恐怖が、頭によぎった。
「それは、ひまです」
マスターのその返事を聞いた時、一気に、肩の力が抜けた。
「ひま?」
首をかくのも忘れて、ぼくは言った。
「はい。誰かが過ごすはずだった、ひまという時間を、あなたが代わりに過ごしてあげるのです」
「え、そんなの、良いんですか?」
「ひまな時間が嫌いな人って、結構いるんですよ」
そういうものなのだろうか。にわかには信じられなかったが、まずは、言われたとおりにやってみることにした。
「では、こちらにどうぞ」
マスターは、ぼくを連れて短い廊下を渡り、一つの部屋に案内した。
「あ、靴は脱いでくださいね」
そう言われたので、ぼくは入り口で靴を脱いで、そのクリーム色の部屋に入った。
中には何もない。と思ってよく見たら、透明な棒が二本と、箱が一つ、置いてあった。
「こちらでお過ごしください。気を付けなければならないことは、ひまな状態を保つということです。それだけです」
マスターは、パタンと扉を閉めて、部屋を出て行った。静かな部屋に、ぼくは一人きりになった。
ぼくは、そのクリーム色の部屋に腰を下ろした。何をして過ごしていたら良いんだろう。とりあえず、気持ちよさそうな絨毯だったので、仰向けに横になった。頭がふかっと、絨毯に埋まった。今、ぼくはとても眠かった。そうだった。とっくに十五分は過ぎてしまっている。でも、もういいや。
どうぞ、このまま。
また、小鳥の声が聞こえた。ぼくは、この声をもっと聴いていたかった。世界に終わりがくるまで、ずっと。
夢の世界に近づくにつれ、ぼくはだんだん寒くなってきた。ぼくはどうして、こんな寒い所にいるのだろう。夢の中ならもっと、暖かくても良いはずなのに。だって寒い所は嫌だから。
それでもぼくがこうして生きていられるのは、まだ体の中に、わずかな体温が残っているからだった。
となりを甕が通り過ぎて行った。亀ではない。甕なのだ。甕は、重たい体を斜めにしながら、うんしょ、うんしょ、と歩いていた。中には、梅干しが入っているのか、しその香りがただよってくる。ぼくは梅干しが特別好きなわけじゃない。だけど、おばあちゃんが漬けてくれた梅干しだけは、甘くて大好きだった。それは、しそで巻いた梅干しだった。だけどおばあちゃんが死んでから、ぼくは梅干し自体を、ずっと食べていなかった。そのことに、今、初めて気づいたのだった。
「あのう、すみません。ちょっとその梅干しを、一つ分けてもらえませんか」
「なんで?」と甕は返して来た。
「あ、ごめんなさい。もう、しばらく食べてないものだから。なんだか久しぶりに食べたくなったんです」
やっぱり、初対面でいきなり梅干しをもらうなんて、失礼なことなんだ。と、ぼくは思った。
「はい」と言って、甕は頭をかたむけて、ぼくに甕の中味を見せてくれた。
「え、くれるの?」そう言って甕の中をのぞき込むと、たくさんの梅干しが、目に飛び込んで来た。そしてその中に、一つだけ、光っている梅干しがあった。
それは、ぼくの好きな、しそ巻きの梅干しだった。
「あ、これ、これいいですか?」と、ぼくは興奮して言った。
「いいよ」
「うわーい」
ぼくはその梅干しをつまんで、口にいれようとした。
その瞬間だった。
「はい。楽しんじゃってますねー」という声がして、ぼくはクリーム色の部屋で目を覚ました。目の前に、マスターの顔があった。
「あなた、夢を楽しんでましたね。今」
「あ、はい。確かに」
ぼくは、ねぼけまなこのまま答えた。
「私は言いました。ひまな状態を保つと。だけどあなた、楽しんでましたね。それは、ひまな時間とは、言えません」
夢の中で楽しむこともだめなんだ。
「すみません」
「それでは、ひまな時間を、お過ごしください」
そう言って、マスターはまた、扉をパタンと閉めて出て行った。
あーあ、おばあちゃんの梅干し、食べたかったなぁ。せめて夢の中だけでも。
ぼくはまた寝っころがった。天井に、照明は一つもついていない。けれど、部屋全体がふうわりと明るい。どうしてだろう。部屋全体が光っているのだろうか。
そんなことを思っていると、また眠気が襲って来た。けれど、また眠ってしまったら、楽しい夢を見てしまうかもしれない。ぼくは、楽しい夢を見ないように、左手を体の下に敷いた。これでもう、楽しい夢を見ないだろう。
目の前に、大きなメリーゴーラウンドが置かれていた。これを見たら誰だって、「あ、楽しんでしまう」と思うだろう。だけどぼくは安心した。ぼくにとってメリーゴーラウンドは、楽しい乗り物ではないからだ。ぼくは、そこから逃げ出した。
馬の背に乗って、上下しながら回転するという乗り物を、ぼくは、どうしても受け入れられなかった。人からは見られるし、酔いそうだし、馬から落ちそうだし、なぜ、お金を払ってまで、そんなことをしなければならないのか、分からなかった。だから、生まれてから一度も、乗ったことがない。それだったらのんびりと、ソフトクリームを食べていた方が良い。
ぼくはソフトクリーム屋を探した。目の前に、いかにもソフトクリームを売っていそうなお店があった。
「すみません。ソフトクリームありますか」
「ソフトクリームはないんですけど、ハードクリームならあります」と、店員さんは言った。
「ハードクリーム?」「はい」
すぐに店員さんは言った。
「じゃあ、それを一つください」
とにかくぼくは、すぐに食べたかった。
店員さんがコーンを持って、慎重に巻いてくれた。
「はい。二百五十円です」
ここでは、普通のお金も使えるみたいだ。良かったと思いながら、ぼくはポケットから、小銭を取り出した。
「いただきまーす」
ガキンと音がして、ぼくの歯が欠けた。
「痛……」
さっきコーンに巻かれていくときにはあんなにソフトだったのに、今や、鋼のように固くなっていた。
「なんですか、これ」
「ハードクリームです」
店員さんは、ニッコリして言った。
ぼくはまた、目を覚ました。
「おいしかったですか?」マスターが、横にいた。
「歯が欠けました」
ぼくは自分の前歯を触ってみた。けれど、どこも欠けていない。ただ、左手がしびれているだけだった。
「危なかったですね。もう少しで、楽しむところでしたね。じゃあ、それをください」
「それ? あぁ、これですね。もう取れるんですか?」
「はい」
ぼくは、首に手を回した。マスターの言った通り、しゅーっと首をなでると、ぽろぽろとネックレスの粒が取れた。マスターは、紙を広げて待っていた。その紙の上に、ぼくは全部の粒を乗せた。最後にカタツムリの殻みたいなのも乗せると、「あ、これはいいです」とマスターに返されてしまった。ぼくは、それをポケットに入れた。
「ありがとうございます」
カウンターに戻ると、マスターは、それを空き瓶の中に大切にしまった。
「どうしてそんなものが欲しいんですか?」と、ぼくは聞いた。なんとなく、あの粒は自分の一部みたいな気がしていたから、少し気味が悪かった。
「これには、あなたが感じた、忙しさや緊張感、疲労感などが、吸い込まれています」
「そんなの余計に、欲しいと思いませんよ」
「そんなことないんですよ」と、マスターは、ほほえんだ。
ともかく、これで晴れて無銭飲食をせずに、この店を出られる。
窓の外は、もう暗くなっていた。
「ぼくもう、帰らなくちゃあ」
そう言ったとたん、「帰りたいですか」と、いきなり真剣な声でマスターが聞いてきたので、ぼくは、ちょっとびっくりした。
「あ、はい。でも、ぼく帰り道が分からないんです」
だってここに来た時も、包み紙に包まれていたのだから。
「それなら、おんぶしてもらってください」と、マスターはにっこりとして言った。
「え? おんぶ? 誰に?」
「この方です」
ぼくは、カウンターの端の席に、さっきとは違うお客さんがいるのに気づいた。その人はスキンヘッドで、静かに座って、透明な飲み物を飲んでいた。
「お客さん、すみませんけども、帰るついでに、このお客さんを送っていってもらえませんか」と、マスターは頼んだ。
その人は「いいよ」とだけ言って、透明な飲み物をぐびっと飲み干した。
「あ、お代はけっこうですから」と、マスターは言った。きっと、ぼくを送ってくれるせいだ。
「すみません」と、ぼくは言った。
お店を出ると、そこは空中だった。風がびょうと吹いて、ぼくの前髪を飛ばした。そこで初めて、ぼくはこのお店が、とても高い所にあるのだということが分かった。
二本の太い柱の上に、このお店は建っていて、錆びた鉄の階段が、ずっとまっすぐ下までつづいていた。
ぼくは、この高さは、少し怖かった。でも、カンカンカンと音を立て、階段を下りて行くリズムは、少し、心地良かった。
「ありがとうございましたー」
マスターの声が、後ろで聞こえた。外は真っ暗で、風は冷たかった。
ようやく地面にたどりつくと、スキンヘッドの人が背中を向けて、しゃがんでいてくれた。ぼくはまた「すみません」と言って、その人におぶさった。その人は立ち上がると、すいすいと歩き出した。
メリーゴーラウンドに乗るのも、ためらうぼくが、今、知らない人の背中に乗って、揺られている。なんだか不思議な気持ちだった。
そして、少し恥ずかしかった。
帰り道、誰にも会わなかったのが、救いだった。
