寄るべない二人



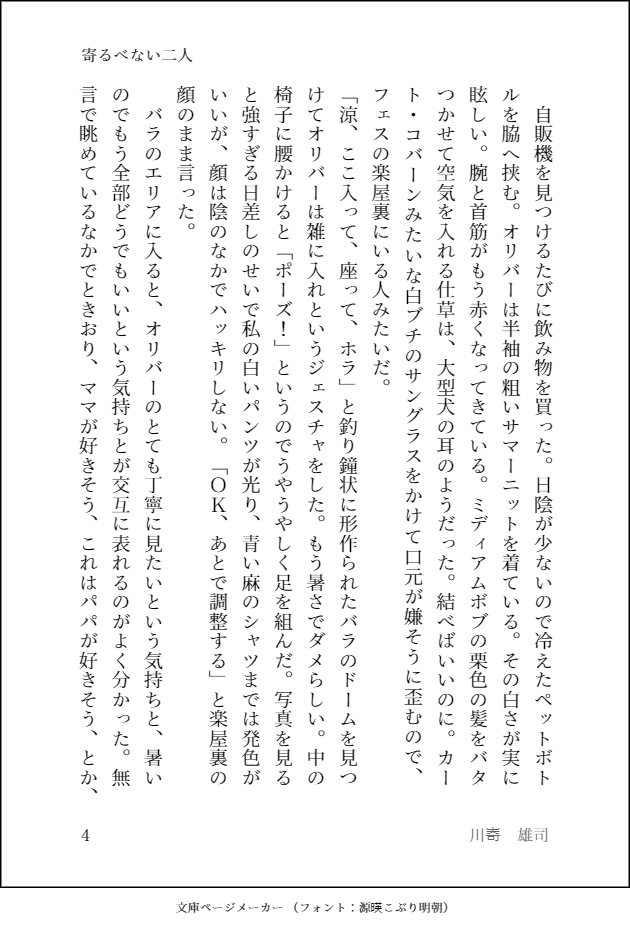



バスは苦手で、特に後ろの方へ座るとエンジンの振動で酔ってしまう。まんなかのドアより手前の、足元に段差のある座席がすきだ。棒のように突っぱって出た膝小僧をさすりながら窓外を眺める。後ろに座ったオリバーが耳元でささやいてくる。
「バラがたくさんあるんだ。すごい数なんだよ。品種も多いし、珍しいのもある。今日はバラ日和でよかったよ。暑いから蕎麦も美味しいだろうね。ね、蕎麦。食べようね」
似たようなことをここ数日ずっと言っているので、適当な返事で済ませた。
私も植物園は好きだけど、深大寺は訪れたことがなかった。
小石川には、数年に一度しか咲かない花が咲いたというときに行った。巨大な食虫花で、俗称を死体花という。うだるような暑さの八月の日で、特設のテントの下に咲いている花は、特別拝観で引きずり出された仏像みたいだった。下の方で膨らみが四角に切り抜かれていて、そこから虫を溶かす場所を覗くことが出来た。そのためにこんなことをするのか、と思いながら覗いた。虫はいなかった。俗称のせいか、どうか、すごい腐臭のイメージを持っていたけど暑すぎてわからなかった。ゴミの処理熱で熱帯を維持している夢の島の独特な匂いを思い出した。蒸した空気の密度の匂い。そこへは冬に行ったのだった。それが正解だろう。死体花の前でしゃがみ込んでいたら、八月はそれだけで熱帯なのだと思い知った。小石川はよう子と行った。夢の島はあきなちゃんと行った。オリバーはまだいなかった。
バスの揺れに耐え抜いて、降りるとき、食虫花の小窓から逃げることができた虫もいただろうかと考えた。振動から逃げて出た外は暑く、日差しのするどさにぶたれた。
参拝して境内を歩いていると、貼ってある札のひとつに目がいった。
「オリバー! 見て、ね、これ何? 明らかに悪魔だよね? え、何これかっこいい」
「うわ、本当だ、すごいフォルムだな」
「モチーフ何なの、バッタ?」
「バッタ? バッタではないんじゃないかな……」
「え、でもこの触角とかさ、なにかしら昆虫じゃない?」
「まあ、たしかに、しかし顔つきが悪いヤツだか、良いヤツだか、分かんなくなってくるね」
二枚一組という厄除けのステッカーをオリバーは両親とおばあちゃんに買った。私は自分にひとつと、来週退職する職場のおばちゃんに買った。
植物園に入ると「うわあ、広い」と言い続ける私を置いてオリバーはすたすたと行ってしまう。追いついたと思うとパッと視界がひらけてまたひとつ広くなった。洋風の庭だな、と言うとずいぶん笑われた。
オリバーのお母さんはイギリスの人で、向こうの親戚のなかでもおじさんがガーデニングに凝っているらしい。イギリスの地理にはまるで疎いので、いつ聞いても頭の中で全部「ロンドン」になってしまう。間違えるたびに訂正をされるけど結局「ロンドンではないロンドン」として覚えてしまう。そのおじさんは池も手作りしたらしい。オリバーは小さいころ、悪ふざけでそのおじさんに池へ落とされたことを今でも恨んでいる。「でもその庭のバラは本当にきれいなんだよね」
自販機を見つけるたびに飲み物を買った。日陰が少ないので冷えたペットボトルを脇へ挟む。オリバーは半袖の粗いサマーニットを着ている。その白さが実に眩しい。腕と首筋がもう赤くなってきている。ミディアムボブの栗色の髪をバタつかせて空気を入れる仕草は、大型犬の耳のようだった。結べばいいのに。カート・コバーンみたいな白ブチのサングラスをかけて口元が嫌そうに歪むので、フェスの楽屋裏にいる人みたいだ。
「涼、ここ入って、座って、ホラ」と釣り鐘状に形作られたバラのドームを見つけてオリバーは雑に入れというジェスチャをした。もう暑さでダメらしい。中の椅子に腰かけると「ポーズ!」というのでうやうやしく足を組んだ。写真を見ると強すぎる日差しのせいで私の白いパンツが光り、青い麻のシャツまでは発色がいいが、顔は陰のなかでハッキリしない。「OK、あとで調整する」と楽屋裏の顔のまま言った。
バラのエリアに入ると、オリバーのとても丁寧に見たいという気持ちと、暑いのでもう全部どうでもいいという気持ちとが交互に表れるのがよく分かった。無言で眺めているなかでときおり、ママが好きそう、これはパパが好きそう、とか、おばあちゃんは家にこういうのあると喜ぶ、とかぶっきらぼうに言う。家族に対する愛情が溢れていてかわいらしかった。これは涼に似てる、と言って指さしたバラは肉厚の白い花弁が大ぶりにひらいていて、茎に向かって集まる中でそれぞれの花弁が重なって透けるのか淡いピンクが見える。私はどちらかといえば浅黒いし、顔つきもくっきりしているのでどこが似ているのか分からないが、嬉しかった。バラに似ていると言われるのは初めて。
バラの数は本当に多い。建物も多い。その中がまた広い。さすがに疲れて日陰に腰掛けていると、鐘が鳴った。気がつけば二時間が過ぎていた。お伽噺のような音色で鳴り響くので、ずいぶん遠くまで旅してきたように感じる。
蕎麦屋は何軒もあった。どこへ入ればいいのかとぐるぐる見ていたが、門から店の入り口までちょっとした庭のあるところに決めて、縁側の席に座った。赤い敷物が苔むした庭の緑によく合っている。オリバーは盛り蕎麦、私はとろろそばにした。お茶を飲みながら庭を眺めていると、懐かしい気分がしてくる。店の構えのせいだけでなく、オリバーと居る心地よさのせいだろう。日陰で休むことが出来た余裕もある。最後に蕎麦を食べたのはいつだったろうか。
「うちのじいちゃんお蕎麦好きでさ、昔よく食べたな。粘り気のあるものは体にいいんだって言って、いつもとろろにしてたそういえば。ワカメとかさ、納豆とかさ、もうなんでも、粘り気が大事なんだって。オリバー納豆好きだよね、そのまま食べ続けた方がいいみたいよ」
「うん、そうする。あとは何? オクラとか?」
「そうそう、オクラも。あとバナナは腐り始めが一番だって」
「それも粘り気の中に入るの?」
「いや、どうだろ。ついでに思い出しただけ。思い出しついでで全然違う話だけど、この前母親から聞いた話、じいちゃんとばあちゃんの馴れ初め聞いたんだよ」
「へえ、面白そう」
「二人とも北海道出身なのね。ばあちゃん八人姉妹の四人目でさ」
「八人姉妹はすごいね」
「すごいよね。それで畑仕事して、下の子の面倒見たりなんだりで暮らしてたんだって。でそのときミシン売りしてたじいちゃんと出会って結婚して、若いうちにポンと二人で東京に出てきたんだって。それでそんな知ってる人の誰もいないところにたった二人で急に行くことになって、恐くなかったのかって母親が聞いたら、畑仕事するよりよほどマシだってすごい顔して言ってたって」
「そんなに畑仕事嫌だったんだ」
「そう。誰にもそれは言わずになんか夢と希望を振りまいて出てきたらしいけど、ただ畑が嫌だっただけだって。でもいくら畑が嫌でもさ、それなりに惚れてないと無理じゃん? 一緒にいる人がよほど安心できる人でなきゃさすがに不安じゃない? じいちゃんの何がそんなによかったのかも聞いたら、馬に乗ってる姿がシュッとして格好良かったんだって。オリバーも馬乗れる? かっこいいだろうな」
「あー、乗ったことはあるよ」
「本当? 見てみたいな。それでそのまま、誰も知ってる人のいないところに二人でポンと、行くのもいいよね」
馬に乗って現れたオリバーを想像しながら、私は何が嫌なんだろうかと思った。バスの揺れも、夏の暑さも、ばあちゃんの畑ほどのものだろうか。オリバーはワサビの量を間違えてひどい顔をしている。私は笑いながら、蕎麦湯を待っている。
「生きろ。そなたは美しい」
