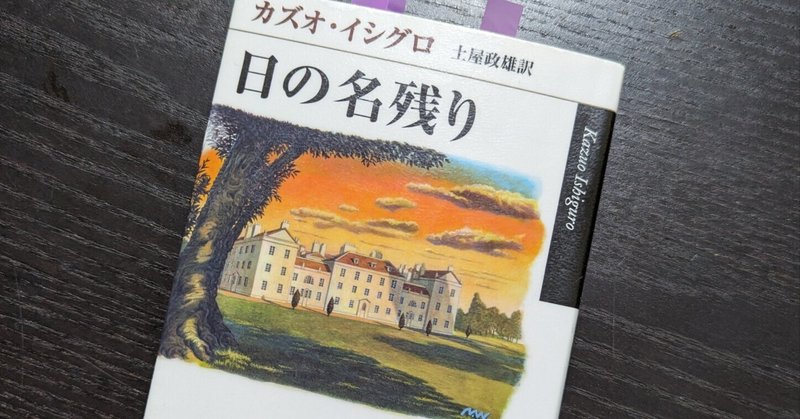
カズオ・イシグロ 日の名残り 弁護士の品格についての一考察
イギリスで最も権威ある文学賞と言われるブッカー賞を受賞した、カズオ・イシグロの「日の名残り」。本書をつらぬくテーマを一言で表すとすれば「品格」でしょう。
そんな本書を読めば、おのずと、自分の職業における「品格」というものを考察せざるを得ません。
ソーシャルメディアの発展とともに、セルフブランディングの名のもとに、自らを大きく見せさえすれば良い、というような風潮が氾濫する昨今において、改めて「品格」について考察し、自らを省みる機会を持つことは大変重要ではないでしょうか。
この記事では、「日の名残り」を私なりに考察しつつ、翻って、「弁護士の品格」というものについて考えていきたいと思います。
「日の名残り」
第二次大戦後の新たな価値観と古き良き貴族的・伝統的価値観とが混ざり合う1956年のイギリス。熟練の執事であるスティーブンスは、アメリカ人の新たな雇用主であるファラディ氏の勧めで、小旅行に出かけることになります。
戦前、スティーブンスは、ダーリントン卿に仕える執事として、その屋敷「ダーリントン・ホール」を一手にとりしきっていましたが、ダーリントン卿の死後、その広大な屋敷の引き取り手がいなかったところ、アメリカ人の富豪ファラディ氏が買い取ったのでした。
執事という仕事に人生を賭けてきたスティーブンスは、ダーリントン・ホールを離れて長期の休みなどとったこともありませんでしたので、旅行にでもでかけてみてはというファラディ氏の勧めを最初は断ろうとします。
しかし、このとき、ダーリントン卿の死後、ベテランの召使たちが次々と退職してしまっていたため、ダーリントン・ホールは慢性的な人手不足にありました。
スティーブンスは、数十年前に結婚を機に退職した女中頭ミス・ケントンからの手紙を受け取り、彼女に屋敷に戻ってきてもらうために彼女に会いに行くとの名目で、旅行に出かけます。
その道中、過去(1920〜30年代頃)の回想と現在(1956年)とを行き来するかたちで、物語が進行します。
この小説は、スティーブンスの一人称で語られるのですが、このスティーブンスがいわゆる信頼できない語り手であることが、読み進めるうちに明らかになっていきます。
おおまかに、次の二点において、仕掛けがほどこされています。
⑴スティーブンスが敬愛してやまず、その人格を最大限に賛美するダーリントン卿が、実はナチス・ドイツの協力者として世間から認知される人物であり、戦後、多くの非難を浴び、おそらく自死による非業の死を遂げたこと
⑵スティーブンスがあくまで仕事のために会いに行くと読者に向けて語るミス・ケントンに、スティーブンスはかつて恋心を抱いていたようであり(もちろんスティーブンスはそれを認めようとしません)、ミス・ケントンもスティーブンスのことを心にくからず思っていたようであること
そして、この二点についてのスティーブンスの振る舞いの根底にあるものが、スティーブンスの考える「執事の品格」というものなのです。
⑴について、スティーブンスは、どうやらダーリントン卿がナチス・ドイツと接近することを快く思っていなかったようですが、政治について知識・知見のない小市民が、貴族が行う政治に口出しするなど慎むべきとの考えや、執事たるもの主人の決定に異を唱えるなどもってのほかというような、いずれもスティーブンスが「品格」の発露と位置付ける見解により、ダーリントン卿に意見することはしませんでした。
そして、スティーブンスは、大変な人格者として尊敬し、自身の生涯を賭けて仕えようと心に決めていたダーリントン卿が、ナチス協力者の汚名を着ることになってしまったことを悔いつつも、自分はそうするより他なかったのだと諦念を語ります。
⑵についても、スティーブンスは、自身のミス・ケントンへの淡い恋心、また、ミス・ケントンのスティーブンスへの想い(どこまで美化されたものかはもはやわからないわけですが)に無理やり蓋をし、仕事に没頭することが「執事の品格」だと考えていたわけです。
しかし、歳を重ね、生涯の主人であったはずのダーリントン卿が死に、家族もいない自分自身を省みると、ミス・ケントンと生きることもできたことを後悔せざるを得ないのでした・・・・
ラストシーン、スティーブンスは夕陽に向かって涙を流します。
それは、生涯の主人・ダーリントン卿を失ったことへの涙、ミス・ケントンとの人生を選ばなかった悔恨の涙、そして、失われゆく英国の伝統への惜別の涙なのです。
しかし、涙を流した後、スティーブンスは以下のように述べて前を向きます。
「あのときああすれば人生の方向が変わっていたとかもしれないーそう思うことはありましょう。しかし、それをいつまで思い悩んでいても意味のないことです。私どものような人間は、何か真に価値あるもののために微力を尽くそうと願い、それを試みるだけで十分であるような気がいたします。そのような試みに人生の多くを犠牲にする覚悟があり、その覚悟を実践したとすれば、結果はどうであれ、そのこと自体が自らに誇りと満足を覚えて良い十分ない理由となりましょう。」
そして、スティーブンスは、新たな主人であるファラディ氏に誠心誠意仕えるべく、苦手なアメリカ的ジョークを学ぼうと心に決めるのでした。
「品格」とは
「品格の有無を決定するものは、自らの職業的あり方を貫き、それに耐える能力だと言えるのではありますまいか。並の執事は、ほんの少し挑発されただけで職業的あり方を投げ捨て、個人的なあり方に逃げ込みます。そのような人にとって、執事であることはパントマイムを演じているのと変わりません。ちょっと動揺する。ちょっとつまずく。すると、たちまちうわべがはがれ落ち、中の演技者がむき出しになるのです。偉大な執事が偉大であるゆえんは、自らの職業的あり方に常住し、最後の最後までそこに踏みとどまれることでしょう。外部の出来事にはーそれがどれほど意外でも、恐ろしくても、腹立たしくてもー動じません。偉大な執事は、紳士がスーツを着るように執事職を身にまといます。公衆の面前でそれを脱ぎ捨てるような真似は、たとえごろつき相手でも、どんな苦境に陥ったときでも、絶対にいたしません。それを脱ぐのは、みずから脱ごうと思ったとき以外にはなく、それは自分が完全に一人だけのときにかぎられます。まさに『品格』の問題なのです。」
スティーブンスは、「品格」についてこのように述べ、執事であった自分の父もまた、この「品格」を体現する人物であったと述べます。
優れた執事であったスティーブンスの父は、老後、「ダーリントン・ホール」の雇人として働いていましたが、仕事中に倒れ、そのまま息をひきとります。その折、「ダーリントン・ホール」では、ダーリントン卿主催の重要な会議が行われており、スティーブンスは、仕事を優先し、死に際に父のそばにいることをしませんでした。父を尊敬すればこそ、私事を仕事に優先しない姿勢を貫き、父もそれを望んだはずだというのです(浅田次郎「鉄道員(ぽっぽや)顔負けの使命感です・・・)。
そして、このような常に仕事を優先させる姿勢は、ミス・ケントンとの間でも同じく貫かれます。
スティーブンスとミス・ケントンは、仕事の打ち合わせと称し、夜毎、ミス・ケントンの部屋でココアを飲みながら雑談する、という習慣を持つようになります。その中で、スティーブンスは、ミス・ケントンから、求婚を受けていることや、結婚を迷っていることなどを打ち明けられますが、素知らぬふりで返し、ミス・ケントンは結局、結婚して屋敷を去ります。
スティーブンスはミス・ケントンに想いを寄せているはずなのですが、恋愛感情は御法度とばかりに事務的な態度を取り続けるのです。
父やミス・ケントンとの関係で「執事の品格」にこだわったスティーブンスですが、主人であるダーリントン卿との関係でも、もちろん「執事の品格」に従って振る舞います。
親ナチス、親ヒトラーに傾斜するダーリントン卿に、スティーブンスも疑問を抱いていないわけではありませんでした。しかし、スティーブンスは、以下のような考えのもと、ダーリントン卿への意見具申を控えるのでした。
執事の任務は、ご主人様によいサービスを提供することであって、国家の大問題に首を突っ込むことではありません。この基本を忘れてはなりますまい。国家の大問題は、常に私どもの理解を超えたところにあります。大問題を理解できない私どもが、それでもこの世に自分の足跡を残そうとしたらどうすればよいか・・・・? 自分の領分に属する事柄に全力を集中することです。文明の将来をその双肩に担っておられる偉大な紳士淑女に、全力でご奉仕することこそ、その答えかと存じます。
このような、「品格」に裏打ちされた振る舞いの結果が、ミス・ケントンとの別離、また、ダーリントン卿の汚名となってしまうわけですが、他方で、本書が、「品格」の重要性までも否定しようとするものでないことは明らかです。
スティーブンスの説く「品格」は、失われゆく伝統的英国的価値観としてむしろ好意的かつノスタルジックに捉えられ、さらに、本書のラストでは、スティーブンスが、新時代にアップデートされた「品格」のあり方を模索し始めたことが示唆されているように読めます。
弁護士の「品格」
小説というものを読んだ際、やはり、自分ごととして引き直して考えてみることが重要だと思っています。
自分ならそのシチュエーションでどう行動しただろう、とか、自分ならそのうような行動ができただろうか、などと考えることで、「ああ面白かった」だけで終わらせず、小説を読むのに使った時間や得た感動をフルに、人生・仕事に活かせるのではないかと。
そのような観点から、本書は、読者各自の職業の「品格」というものについて思いを致す、絶好の機会を与えてくれるものだと思います。
かつて、私が1年ほどお世話になった事務所のボスは、散髪の予約の際にも、ランチの予約の際にも「弁護士の〇〇です」と名乗っていました。
当時は、それを聞いて、弁護士であることがアイデンティティで、弁護士だということでしか自分自身を定義づけられないというのはなんとも悲しいものだとも思っていました。
しかし、本書を読んだ今では、そのような在り方こそ、まさにスティーブンスが説く「スーツを着るように」弁護士という職業を身にまとい、決して人前でそれを脱がないという「弁護士の品格」の体現だったように思われて仕方がありません。
さて、弁護士にとって、「品格」とはなんでしょう。
スティーブンスいわく、
品格の有無を決定するものは、自らの職業的あり方を貫き、それに耐える能力
だといいます。
ここで、弁護士の使命は、基本的人権を擁護し、社会的正義を実現すること(弁護士法1条1項)であるとされています。
そうすると、弁護士の「職業的あり方」とは、「基本的人権を擁護し、社会的正義の実現を目指すこと」と考えられます。
あくまでこのような、「基本的人権を擁護し、社会的正義の実現を目指す」姿勢を貫き、それに耐える能力を持つことが、「弁護士の品格」だと言えるのかもしれません。
ダーリントン卿が、英国貴族としての使命感から国際平和のためにドイツとイギリスの架け橋になろうとしたように、弁護士は、その職業的使命のため、基本的人権の擁護と社会的正義の実現のために闘わねばならず、そうあり続ける姿勢こそが「品格」の源泉だということになりましょう。
しかし、現代において、このような、弁護士法制定当初の理想を追求できている弁護士がどれほどいるでしょう。
「基本的人権の擁護」、「社会的正義の実現」と言われると、異論はあるかもしれませんが、およそビジネス的な仕事とは一線を画すようなイメージを持ちます。
ビジネス的な価値観というものは、「品格」とはおよそ相容れないように思われます。ビジネスとは、金銭的・経済的な対価を得るために行うものであって、高尚な使命感を基礎とする「品格」とは異なるものです。
スティーブンスなら、ビジネス=アメリカ的、品格=ヨーロッパ(イギリス)的、と整理するでしょう。
弁護士数の増加による業界の競争激化、事務所規模の大型化、インハウスローヤーの増加など、弁護士業界も急速に変化してきています。
そのような時代にあって、弁護士の仕事も急速にビジネス化が進んでいるように思われます。
もはや事務所経営のことや売上のことを考えることもなく事件を追えた、職人気質の旧来の弁護士像というものが失われて久しいように思われるのです。
SNSの時代は自己アピールの時代です。
(検証不能なので)言ったもんがち、とばかりにSNSでマッチョな自分を喧伝するばかりの弁護士も増えています。
果てしない自己アピール、セルフブランディング。スティーブンスが見たら眉をひそめるでしょう。
要は、グローバル化とともにアメリカ的・ビジネス的価値観に支配され、そこからは逃れられないのが現代を生きる我々なわけですが、そんな時代だからこそ、求められる弁護士の姿を体現し、「品格」を保つべく努力を続けることも重要なのではないでしょうか。
とはいえ、「品格」を尊ぶスティーブンスは、古き良き時代を懐かしむばかりで、決して時代のメインストリーム・本流にはなり得ないこともまた、頭に置いておかなければなりません。
つまり、「品格」は、それだけでは旧時代の遺物と成り果ててしまう定めにあり、生き残りをかけたアップデートが必要でもあるのです。
こうして書いていますと夏目漱石の「坊っちゃん」を思い出します。
人間性において優れており、「品格」を有しているはずの「坊っちゃん」と「山嵐」は敗れて(精神的には負けてはいないにせよ)学校を去り、「赤シャツ」と「野だいこ」は学校を牛耳り続けます。
ここでも、古き良き時代の体現者は、悪貨が良貨を駆逐するがごとく、わきへ追いやられるのです。
結局のところ、「品格」派は、欲望をむき出しに振る舞う「ビジネス」派に敗北するわけなのですが、そうであれば、何のために「品格」を持たなければならないのでしょう。
月並みな結論にはなりますが、これはバランス感覚の問題なのではないかと思われます。
つまり、「品格」すなわち伝統的な職業的価値観を保ちつつ、時代に沿ったビジネス的感覚も取り入れていく、というのが、現代人の目指すべき在り方なのではないでしょうか。
常にビジネスのことしか頭にない、という人間は中身がないように見えます。他方で、「品格」に拘泥しすぎると、時代に取り残されます。
この中庸とはどのようなものか。現代的職業人は、これを考え続けなければならないのかもしれません。
このことを意識しつつ、最終的には、「何か真に価値あるもの」=基本的人権の擁護+社会的正義の実現「のために微力を尽くそうと願い、それを試みるだけで」いち弁護士の人生としては、「十分」なのではありますまいか。
滋賀 草津 弁護士|ミカン法律事務所|企業法務 建築・不動産 行政事件 法人破産から離婚 相続 交通事故 労働事件まで (mikanlaw.jp)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
