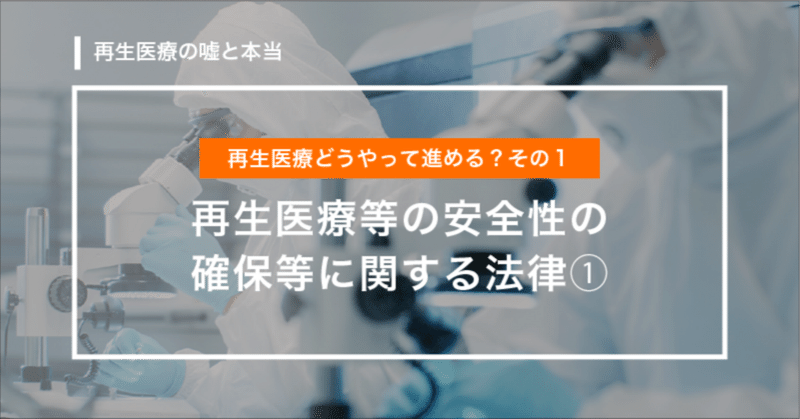
【第3回】再生医療どうやって進める?その1「再生医療等の安全性の確保等に関する法律①」
この法律が出来たのが平成25年。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下、再生医療等安全性確保法 参照:厚生労働省ホームページ)」により、従来、医師の裁量権の範囲として規制がなかった細胞加工物を用いた自由診療に、事前規制の網がかぶせられることとなった。
てな定義から始まって、また、再生医療等安全性確保法では、臨床研究として実施される再生医療についても規制されることとなったんだけど。
ただ、二重規制を避けるため、他の法律で既に規制を受けているものについては適用除外となっている。具体的には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法 参照:厚生労働省ホームページ)」において規制される再生医療等製品及び再生医療等製品となることが見込まれる加工細胞等の治験、並びに、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律及び同法施行規則で規制されるものについても、再生医療等安全性確保法の適用除外となっているんだけど。
また、再生医療等安全性確保法で規制するものは細胞加工物のうち、薬機法上の再生医療等製品を除いた特定細胞加工物のみであり、プラスミドベクター、ウイルスベクターのような遺伝子治療は適用対象外となっており、遺伝子治療の臨床研究は臨床研究法(参照:厚生労働省ホームページ)により規制される。遺伝子治療の自由診療については規制する法律は存在していないことが課題となっているし、他のあたかも再生医療の製品が法律外で自費診療として、安全性も確認されてないまま医師が医療として提供しているケースも多いのが現実で…なんとかならないかなぁてな、感じの話が今回のテーマでした。
あら?再生医療を進めるには…の今回の題が説明されてない。。。
次回こそは進めます。
よって
第3回の世界に誇れる「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」についてもう少し詳しく話そうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
