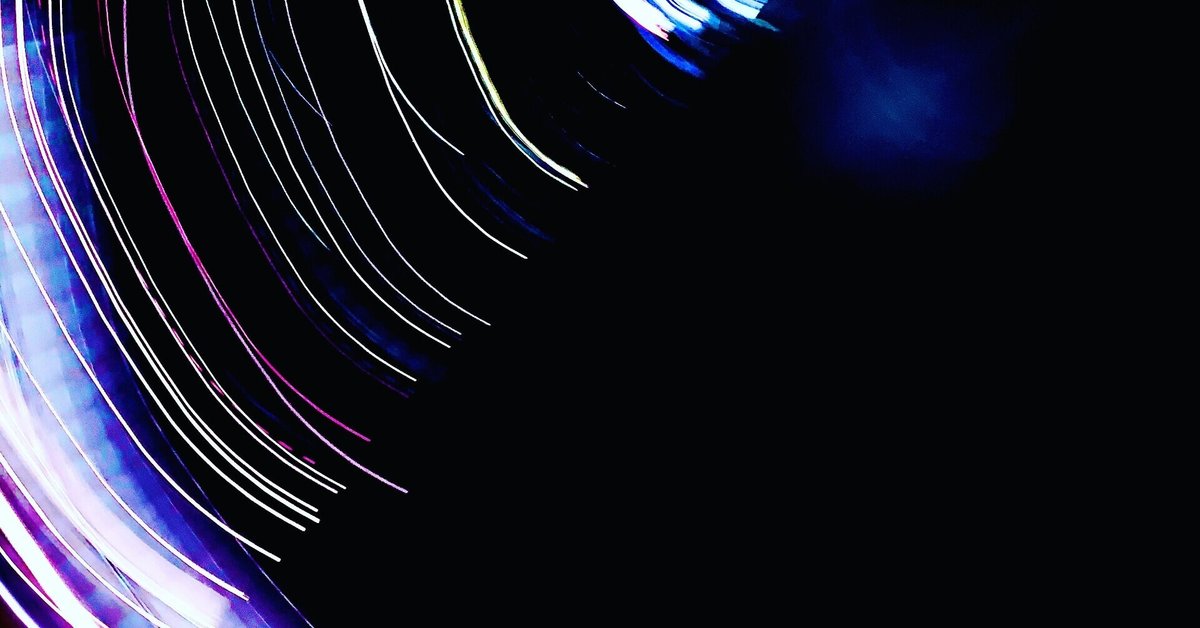
45分の授業の中に静と動を
◆前回、授業中に立ち歩くことは本当にダメなのか?という話を少し入れました。補足します。授業妨害にあたる行為は指導します。優先することは、まず安全、次にみんなの学ぶ権利の保証です。他者の学びを害することはあってはならないと考えます。ではどうするのという話。
◆よく、キレて教室を飛び出してしまうケースが取りざたされています。どこへ行ったか分からないと危険だから隣の空き教室でクールダウン、或いは水道で水の飲んで落ち着けるようにする。キレるということは限界を超えたということ。これは、集中がキレる時も同様の原理で気分転換が必要です。調べ学習を45分間ぶっ続けでやるような授業があるとすれば、それは拷問でしょう。少なくとも私は放課後のデスクワークで45分間誰とも会話せずに離席せずに黙々と仕事を遂行できる自信はありません。子どもも同じです。
◆ちょっとしたアクション、「動」の時間を挟んであげること。私は「静」的な時間になりそうな授業のときには意図的に「動」の時間を設定します。例えば、社会の歴史学習では、自由進度学習を取り入れているので(自由進度学習については機会があれば後日記事を作ります)自分で課題を設定したらその後は黙々と調べる時間になります。最初は、意気揚々と調べ、ノートにまとめていくのですがずっとやってるとどんなに頑張り屋さんの子でも作業能率が低下します。よく言いますよね、人間の集中力は15分間程度だと。そこで、「みんな疲れたよね、よし『どろぼうタイム』にしよう。」そう指示を出すと一斉に子ども達が立ち上がり、ウロウロし始めます。「何調べてんの?」「へぇ、そうなんだ!」「そこ、よく分からなかったんだよね」互いに途中までの調べてまとめたノートを覗き合います。覗き見て、盗めそうなものはいただく(泥棒する)これが『どろぼうタイム』です。これは、学芸大学附属世田谷小学校の沼田先生の『ルパンタイム』の実践です。
◆友達と対話する、友達の学びを知る、そうやればいいんだと気付く、といった学びのメリットが多々あります。が、それ以上に「気分転換」、ここにねらいがあります。5分の『どろぼうタイム』で子ども達の集中はリセットされます。友達からの刺激を受け、むしろ意欲は高まります。「自分もこうしてみよう」「あとちょっと頑張ってみよう」自分でエンジンをかけ直し、残りの時間にスパートをかける。立ち歩いていいことを全員に保証する。別に友達が何やってるかなんて見に行かなくていい、じっとすることが苦手な子にとって堂々と発散できる時間を授業の中に創出する。
◆それ以外の方法では、授業形態の工夫。机を動かす。これも動的なものです。起立して音読する。役割演技する。黒板の前に行って説明する。みんなの前で手本をしてもらう。何なら水分補給したっていい。ちょっとしたアクションを多くの先生方は授業中にやっていると思います。「静」的な授業のときこそ、「動」的な時間をちょっと入れる、という話でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
