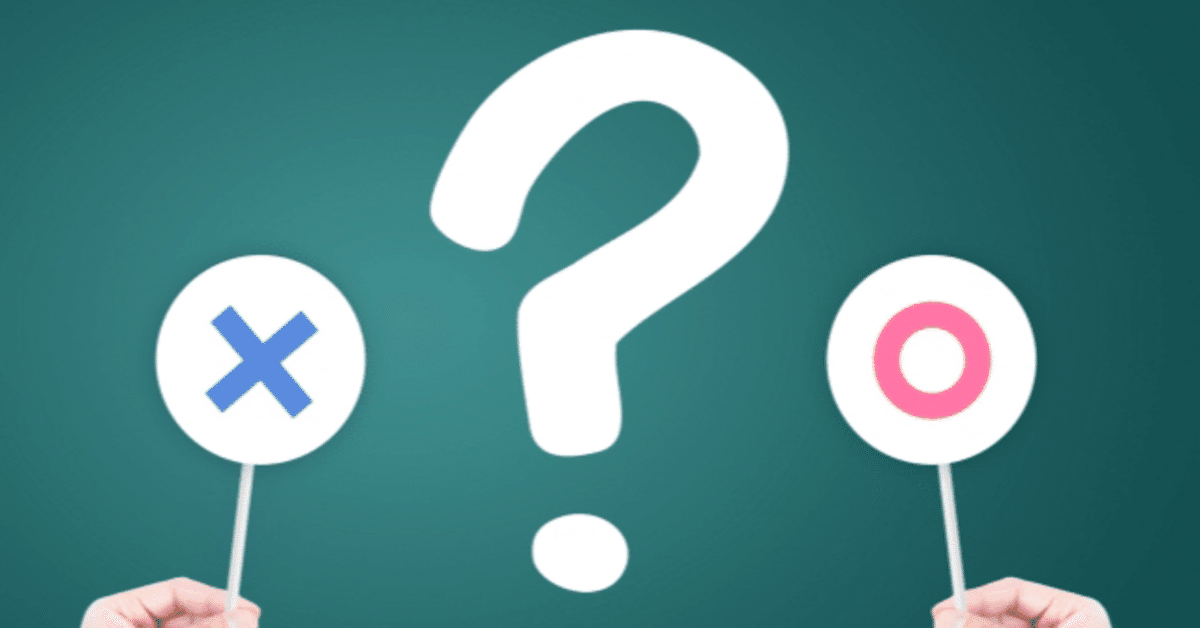
「正解」を見つけるためには「指標」が大事 -いいパスとは?-
いいパスとはどんなパスか?
「正しいパス」を教えられて、その通りにしようと頑張るというのが普通かもしれませんが、それは「正しいパス」があらかじめ決められているということになります。しかし、実際に必要なのは「ゲームに勝利するためのスキル」であり、そのやり方がそのチームにとって本当に正解なのか?勝利に結びつくのか?ということが重要です。「理想のパス」については従来の日本のやり方に疑問が投げかけられているところですが、「勝利に結びつくのか?」というところから始めてそのチームにとっての「正解」を探していくしかないのではないかと考えています。
それぞれのチームにとっての「正解」を探すには「勝つために何を最大化しようとするのか」が明確になっていなければなりません。「何を最大化するか」というのは例えば攻撃でいえば、
・レシーブからアタックまでの時間を短縮してできるだけ早く切り返す(「時間の短さ」を最大にする)ために、パスやトスをできるだけ直線的で低くて速いものにする
または
・「最高打点で攻撃できるアタッカーの数」を最大にするために、全てのアタッカーが開いて十分な助走をすることができるように、それに必要な時間を確保するためにパスを高くする
という選択肢があります。ここではどちらがより合理的か?の説明は省きますが、後者を前提として話を進めていきます。
富山大学男子チームのエピソード
私が外部コーチをしている富山大学男子チームでは、これまで「高いパスで余裕を作って全員が攻撃参加できるようにしよう」ということは共有してきたはずなのですが、「とにかく高くあげればいい」という選手がいたり、自分がパスして入りやすい(つもりの)直線的なパスを入れたがる選手がいたり、チームにとっての正解のパスのイメージが共有できているとは決して言えない状況でした。
チームにとって「どんなパスがいいパスか?」というイメージはとても重要なのですが、選手にその質問をすると「腕の面をセッターに向けて」などという「いいパスをするために『やるべきこと(コツ)』」みたいな答が返ってきたりして、なかなか質問が成立しないことも多く、「いいパスが満たすべき条件は?」という言い方をしてもなかなか伝わりませんでした。しかし、今回そこに光が見えたので、その理由を考えてみたいと思います。
「最高打点で攻撃できるアタッカーの数」を最大にするためにパスをどのくらい高くすればいいのか?
2024春季北陸三県の大学リーグで、富山大学男子は、初日の5セットマッチ2試合をストレートで勝利しましたが、良かったのは「チームにとっての理想のパス」のイメージがクリアになったかも?ということでした。
具体的には「OPの選手がラリー中に開いて十分な助走をする余裕のあるパスがいいパス」という基準設定ができたということです。
このOPの選手は春からMB→OPに変わったのですが、高さもパワーも十分で、ラリー中に開く余裕がある時は決定率が高く、チームの大きな得点源になっていました。しかし、助走に開く余裕がない時はほとんど決まらず逆にミスになることも多いという状況で、「パスが余裕を作ったかどうか」で成否が決まると言ってもいいくらいでした。
そこで、「OPの選手が余裕を持って開いて助走できるように、パスで時間を作ろう」という指示が上手くはまったというわけです。「OPの選手が余裕を持って開いて助走できるパスがいいパス」という基準がとても分かりやすい、目に見えて良否の判断がしやすい「指標」としてうまく機能したのだと思います。
うまく機能した要因
うまくいった要因としては、このOPの選手が高い能力を持っていたこと、かつ「しっかり開いてしっかり助走する」ということをサボらずいつも全力でやろうとしていたことが大きかったと考えられます。もし「しっかり開く」ということをやらない時があったら、助走を短くすることで間に合ってしまうことになったり、単に切り返しをサボって「間に合わない」状況になったりして、パスの成否が結果に結びつかなくなります。つまり、パスが「条件を満たしているかどうか?」が分からなくなるわけです。
「開く余裕がない状態」に慣れている選手の場合、「十分に助走せずに切り返す」ことを頑張ろうとするので、パスで余裕を作ってもそれを活かせないことが普通です。十分な助走とジャンプから自分の能力を最大限に発揮することを知らない選手は多く、そこから変えない限り「余裕を持って開いて助走できるパス」という条件は設定できなくなります。今回のOPの選手もミドルでプレーしていたときはあまり助走していなかったかもしれませんが、ポジションを変わったことで「やるべきこと」を最初から意識できたのかもしれません。
パスの意識が高まって、他の選手たちも攻撃参加の意識が高くなり、とてもいい展開のゲームができたと思いますが、こういうアプローチの成功体験は貴重ですね。
いいパスが「満たすべき条件」は何か?をクリアにして、それを自分たちで探索して「チームの正解」を見つける、そういうアプローチが当たり前になれば本当に面白いと思います。そのためには「探索条件」が分かりやすいことが重要なのですが、今回のようにいろいろなことが揃うことは滅多にないかもしれません。コーチングスタッフとして「分かりやすい探索条件」を探し、必要な要因を揃えることに努めていきたいと思います。
以下に関係のありそうな記事をピックアップしました。
ご意見をいただければ幸いです。

バレーボールに関する記事を執筆しています。バレーボーラーにとって有益な情報を提供することをコンセプトにしています。
