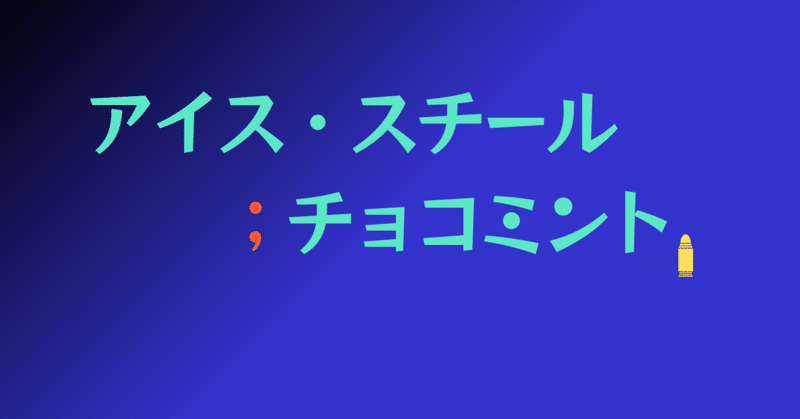
[連載小説]アイス・スチール;チョコミント 一章 5話 ハードカバーは役に立つ
5話 ハードカバーは役に立つ
一太は、怜佳と高須賀未央の出迎えをディオゴに申し出た。
しかし一任されたのは佐藤アインスレーだった。ディオゴにいまだ認めてもらえない苛立ちがわいたと同時に、やはりと納得するところもあった。
アイスのことは、物心ついた頃から知っていた。
ディオゴの手下の中には、いかにもな強面や、厳つい男たちがいくらでもいる。それらをおさえて、近所のスーパーで見かける主婦と同じに見える人が、ボスの右腕であることが信じられなかった。
佐藤アインスレーの略名〝アイス〟は、本業の「アイスマン》」からくるものでもある。
それを知る者は、そのままの意味とともに尊称、あるいは蔑称として使っていた。仕事を完遂するときも、いつものとらえどころのない笑みをうかべたまま片付けている「冷静な人間」に違いないと。
アイスは否定も肯定もしなかった。
一太は、その答えを知っている。
幼かった頃、母はときどき一太をつれて<ABP倉庫>を訪れることがあった。
いま思えば、本妻を意識して張り合っていたのだと思う。怜佳のほうは怒るでも嫉妬するでもなく、知人を迎え入れるように接していたから、暖簾に腕押し状態だったが。
そこで会ったアイスは、一太には文字どおり「甘いおばさん」だった。
母がディオゴと話をしているあいだ、アイスが外に連れ出してくれることがよくあった。行き先は、甘いものが食べられる喫茶店。アイスクリームの専門店が新しくできると、そこにも連れていってくれた。
一太がアイスクリームをなめている隣で、アイスはいつもコーヒーを飲んでいた。
アイスクリーム屋にきているのにコーヒーを飲んでいるアイスが、子どもの目には不思議だった。
「いつもおんなじのばっか頼んで、よっぽど好きなんだね」
お気に入りになった、ひとつのメニューばかり食べている一太と同様、アイスもまた何度も同じことを言って笑っていた。
いつも笑みをうかべている人であったが、嗤っている場面を見たことは一度としてない。母親がディオゴと話すあいだ、倉庫の隅にあったバットで遊んでいたときのことは、今でもはっきり覚えている。
たまたま足元近くにあらわれた小さな蜘蛛に、一太は悲鳴をあげてしまった。
「ぼうず、どうした?」
近くで荷物のチェックをしていた男ふたりが、すぐ駆け寄ってきてくれた。しかし、原因が蜘蛛とわかった途端、揶揄の声をあげた。
「キャー、ぼくって虫がダメなの!」
「ぼうず、蜘蛛ぐらいで悲鳴あげてるとタマが腐り落ち——」
「誰なの? 蜘蛛を虫とか言ってるおバカは」
下品な嗤い声を遮ったのは、倉庫に入ってきたアイスだった。
「苦手なものいきなり見たら悲鳴ぐらいあげるでしょ。思い出しなよ。ナカノだって悲鳴こそ上げなかったけど、ゲロ吐いたりしたことあったじゃない」
「な……いい加減なこと言わないでくださいよ!」
「なんだそれ? サトーさん、こいつ何見たんです?」
「始末の現場の掃除に連れて行ったとき、死体見た途端にやらかした」
「あのときは初めてで……」
「うん、慣れないうちは仕方ない——ではすまされないけど、先に対処法おしえとかなかった、あたしも手抜かりだった。でもって、イケモトのほうは——」
「わ、わかりました! ぼうず、悪かった」
よほど明かされたくないことがあるのか、子どもの一太に拝むポーズで謝った。
「一太、お母さんが呼んでる。いこう」
アイスについて歩きながら、一太は早口で言った。
「別に怖かったんじゃないよ? 急に出てきたから……」
「うん、びっくりしたんだよね」
本当は蜘蛛が大きらいだった。正直にいうと怖い。
このことを母親に話すと、馬鹿にされた。だからナカノやイケモトの反応も当然に思え、アイスにも隠そうとしたのだが、
「あたしが怖いのは蝶々。胴体だけ、ぷっくりした感じがブキミでさあ」
訊いてもいないのに、アイスは自分から話した。
「大人のくせにそんなこと言って、おかしいとか言われない?」
「大人になったっても怖いものは怖いよ。理屈じゃ説明できない。ちょっと座ろっか」
会社の外階段に腰を落とした。お母さんが呼んでるんじゃなかったの?
「蝶々みても平気になりたいと思って、写真見たり、触ってみようと頑張ってみたことあるんだ」
「でも、さっき怖いって」
「そう。やってみたけど全然ダメだったんだよ。変わんない」
他人事みたいに笑った。
「原因がわかんなくて、理屈抜きでダメならもう、どうしようもないじゃない? もういいやって思ったら、以前ほどビクビクしなくなった」
「開き直るっていうやつ?」
「むずかしい言葉知ってるねえ。で、あたしなりの答えはね、怖いって思うのは、自分を守ろうとしてる証拠でしょ? なら、怖いって気持ちを無理に抑え込まなくたっていい。どうして怖いのかとか、自分の怖いをよく知って、付き合っていくのもありっていうのが、あたしの蝶々対策」
「おれも蜘蛛ダメなまんまなのかな」
「怖いって人によっていろいろだよね。カエルとかハチとかアリが怖いっていう人もいるし、どれぐらい駄目なのかも。
だから一太の怖いは、一太がいちばんよくわかってる。たぶん、一太でしか答えが出せない。あたしがやった以外に方法があるかもしれないから、一太も考えてやってみて。いいのがあったら、あたしにも教えてね。蝶々対策に使ってみるから」
「わかった。やってみる」
「答えが出たところでアイスクリーム食べにいこうか」
「でも、お母さんが待ってるって」
「言ったっけ? お母さんの話が終わってたら、今度はお母さんに待ってもらえばいいよ。一太ばっかり待つんじゃ不公平だ」
アイスが腰を上げた。やわらかな笑みをみせるアイスを見上げながら、一太も立ちあがった。
一太の記憶のなかには、この笑みがずっとある。<ABP倉庫>の一員になってから見るようになった笑みとは違う、特別な笑みだ。
これのせいで、アイスだけは理解してくれると過度な期待を抱くようになっていたのか……。
怜佳と高須賀未央の件に、一太が援護に加わることすらも拒んだアイスに失望した。ディオゴの指示があったとしても、アイスならとりなして一太を加えることもできたはずだった。
ディオゴのプライベートに関わる案件は、かなり近しい間柄にある〝ファム〟でないと許されない。この件に関わることは一太にとって、ディオゴとの真の親子関係への入り口となる。天涯孤独の身の上のアイスなら、理解してくれると思っていたのだが……。
苛立ちが徐々に強くなった。怜佳と高須賀未央の情報をまとめ、ディオゴに上げたのは一太だ。どうせなら最後までやって、成果をつかみたくもあった。
一太は数人の部下を伴い、独断で動いた。アイスと実行力を競り合う機会にもなる。
<オーシロ運送>に遅れて着き、子どもを連れたアイスの姿を見つけたときは遅きに失したと思ったが、怜佳の姿が見えないことで別の展開がみえてきた。
爆発火災が起きているなか、アイスが怜佳を置き去りにするとは考えずらい……
アイスが指示どおりに子どもを連れ帰るのかの確認は部下に任せ、一太はひとり<オーシロ運送>のそばに残った。
そうして、怜佳の策略とアイスの変心を嗅ぎ当てることになる。
***
<オーシロ運送>の社屋はさして広くない。二谷が現れたドアをくぐると休憩室があり、その奥に駐車場に出るドアがある。外への出入りは、休憩室からも可能なつくりになっていた。
事務所に通じるドアから外に出るまで、直線ならおよそ六歩ぐらい。そのたった六歩の距離が、すんなり通れなかった。
休憩室に入るドアを開けてすぐ、アイスはコンバットナイフの出迎えをうけた。
相手の方が身長が高い。斜め下に突き出されたナイフの流れに逆らわず、ハードカバーで押さえ込むように叩き落とす。
刹那で返したハードカバーの背表紙を、敵の喉へめりこませた。
間髪入れず、腹に横蹴り。二番手でくる男にむけて倒れ込ませて出鼻をくじく。
休憩室は狭く、動けるスペースが限られる。中央におかれたテーブルとパイプ椅子を、残るふたりに挟まれないように利用した。
ミオも俊敏だった。動くアイスの背中に遅れることなく反応する。アイスは敵を背中側に回り込ませないことに全力を傾けた。
狭いスペースで入り乱れて銃が使えない。倒れた仲間を飛び越した二人目の黒シャツ男もナイフを振り下ろしてきた。
アイスはハードカバーを右から左手へ。
利き手をあけながら、ブレードをすり抜けつつ、右掌底で黒シャツの顎にジャブ。そのまま右手を黒シャツの首にかける。
左手のハードカバーをテーブルに立てる。
その天(本の上側)の部分にむけて、引きつけた黒シャツの首を叩きつけた。
ハードカバー本が、下方向からの斬れないギロチンになる。首にかけていたアイスの右手のひらにまで、首に与えたダメージが伝わった。
「離して!」
黒シャツを片付けている間に、バズカットにラインを入れた男が、ミオの腕をつかんで強引に連れて出ようとしていた。
アイスは最短距離で移動する。
テーブル上をすべって反対側に着地。バズカットが事務所のドアノブにかけようとしていた手を、ハードカバーを縦にして殴りつけた。
悲鳴に続けたFワードとともに、バズカットがミオを盾にする。アイスへと突き飛ばしてきた。
アイスは前につんのめるミオの身体を受けとめながら反転、バズカットからミオを遠ざける。
その隙でバズカットのナイフが襲ってきた。
左ボディへと突き出されたブレードを捌こうとして、パイプ椅子に阻まれた。
どうにか急所だけは外した。
突き出されたバズカットの右腕を左脇に挟みこんで固定。
そのまま頭突きを繰り出す。
相手より低いアイスの身長は、かならずしも不利になるものではない。額の高さがナチュラルにバズカットの鼻の下にマッチし、頭突きが人中に入った。
同時に、左脇を捻じ上げるように締める。
ゴギッという鈍く低い音。男の肘を破壊した。
頭突きはアイスの額も切っていた。歯にぶつかった薄い皮膚が破られたが、額の出血はたいしたことではない。流れる血を拭わないまま、ミオの手をとる。
「あたしの側にいれば大丈夫」
強張った女の子の身体をひっぱり、ドアの外にやっと出た。
手首をつかまれたミオは、反射的に抗った。
違う。アイスだ。外に逃げるのだ。
アイスに右肘を折られた男の悲鳴が耳から離れなかった。
悲鳴なんて映画やドラマの音声でしか聞いたことがない。名役者の演技とは別次元の生々しさに、頭の中まで総毛立った。
休憩室の床に倒れている男たちに蹴つまずきそうになりながら、ドアの外へとむかう。
膝が震える。足元がたよりない。ほとんどアイスに引きずられるようにして駐車場に出た。
アイスが手をはなした。
途端に不安になった。ひとりぼっちで味方が誰もいない孤立感におそわれる。
突如とした起こった衝突音に肩をはねあげた。
アイスが積み上げてあったパレットを崩したのだ。崩れた木材製品が、重力に引き込まれるままアスファルトに衝突する。騒々しい音を立てて、空気をふるわせた。
怜佳は外に出たら合図しろと言っていた。そして、
——二〇秒以内になるべく離れて
何をするつもりなのか。このまま怜佳をおいていっていいのか。答えを出すまえからアイスに引っ張られて走り出した。
「もうちょっと走って! ここを離れないと危ない」
そんなに動き回ったわけでもないのに、息が切れて胸が苦しい。ミオは平坦な路面でつまずいた。
路面に倒れ込むより先に、アイスに抱きとめられた。さして大きくない身体のどこにこんな力があるのか。半分引きずられながら移動を再開したとき、背後で爆発音を聞いた。
ミオは驚かなかった。
頭が空っぽになったせいだ。爆発音に頭の中まで吹き飛ばされたようだった。
空っぽの頭は、危険から逃げる命令も出せない。なのに無事でいる。
硬直したミオの身体をアイスが抱き抱えて移動していた。路上駐車のワンボックスの影に伏せている。爆風で飛んでくる破片を避けた。
しばらくしてから頭を起こしたミオの目に、炎と猛烈な煙を噴き出す<オーシロ運送>がうつった。
ぼんやりしていた頭がはっきりしてくる。目の前で起きている惨事の意味をつかんだ。
「……怜佳さん! 二谷さんを助けなきゃ!」
立ちあがろうとして、力づくで押しとどめられた。
「素人が装備もなしでどうやって? 有毒ガスが出てることもある。生身で入るのは自殺行為だよ」
アイスの声は腹が立つほど落ち着いていた。
「消防を——」
「これだけの音がしたんだから誰かがもう通報してる。追っ手はさっき見ただけとは限らない。いまのうちに急いで」
怜佳は助からないと言われたようだった。
「けど、もしかしたらの数パーセントが起きてるかもしれないでしょ⁉︎ ここでその可能性を捨てたら、あとで後悔する」
「怜佳さんが生きてると思うなら、なおさら自分の安全を最優先にして。もしも、あんたが他の人間のいいようにされたら、怜佳さんが命懸けで逃がしてくれた意味がなくなる」
ミオは、いやだとも、わかったとも言えなかった。
背を押されるまま、黙って走り出した。周囲を警戒しながら走るアイスについていく。
しかし五〇メートルも行かないうちに、アイスの歩調が乱れ、足が止まった。
膝に手をついたアイスの顔色が白い。体格で大きく負けている三人を相手に戦ったのだから、ダメージがあってもおかしくはなかった。
「もしかして怪我したの⁉︎」
「いや大丈夫。ただもう、ごらんのとおりの歳だからさ」
さきほどまでの緊張感を霧散させ、へらりと笑う。
「隠れられる場所までちゃんと連れてくから、心配しないで」
目に入りそうになっていた額の血を乱暴にぬぐうと、再び足早に歩き出した。
ミオに妙案は思いつかない。けれど、いつまでたっても周囲の大人に言われるままでいいのかとも思う。
優しくて仕事もできる母、彩乃のことは好きだし、尊敬もしていた。父ともめているのは、うっすらわかっていたが、いずれはこれからのことを相談してくれると思っていた。
ふたりで決めたのなら離婚したってかまわない。彩乃についていくつもりでいた。
なのにミオを置き去りにして〝事故死〟してしまった。
ミオは納得できなかった。夫妻が遭った不幸として処理をした警察にではない。性急な答えで解決させた彩乃に、怒りすら覚えていた。
怜佳にしてもそうだ。助けてくれることに感謝しかない。
ただ、母の親友だからというだけで、後見人を引き受けるものだろうか。後見人になれば、夫ディオゴが遺産を狙ってくることを怜佳なら予測できたはずだ。怜佳は彩乃からの遺産を守るというが、ディオゴが絡んでくるのでは本末転倒な気がした。
彩乃も怜佳も、ミオを助けようとしてくれるのだが、どこかしっくりしないズレた感じがある。
アイスのこととなると、もっと収まりが悪かった。仲間を裏切ってまでミオを助けるメリットなんてあるのか。
彩乃のオフィスを売ってできたお金が、アイスの報酬とつり合っているというなら、それでもいい。
引っかかるのは、差し迫った場面でもうかべている笑み。それがアイスの底知れなさを感じさせ、味方になってくれたと素直に喜べない。
怜佳がえらんだサポート役だが、この人と一緒にいて安心していていいのか……
胸がざわつくまま、ミオはアイスについて歩く。
アイスには確信があった。
怜佳は我が身を犠牲にしたのではない。あの荒っぽい仕掛けは、紙の上で何度も計算して確信をえた爆破火災計画で、勝算があるからこそ実行した。
それにしても、ここまでやるとは思い切りがよすぎる。依頼主としては厭なタイプになるかもしれなかった。予測範囲外の行動で、どんなトラブルが飛び出してくるかわかったものではない。
ともあれ別の問題があった。
左脇腹に、生温く濡れた感触がある。休憩室が狭く、バズカットのナイフを捌ききれなかった。ミオがいる手前、確かめていないが、十中八九、出血がとまっていない。治療が必要だった。
迎えうった三人は、いずれも知らない顔ばかりだった。この首謀者が怜佳の言うとおり一太だとしたら、ディオゴの指示を守る体裁のために、メンバーを外注でそろえた。
そうまでして一太が成果を求めるのは、ディオゴに認めてもらいたい……などと考えてしまうあたり、ずいぶんウェットになったものだ。
自分にあきれ、眉間に峡谷を刻みそうになるが、強引に笑みの形にかえた。
深刻な顔をしても事態がよくなるわけではない。表情筋からリラックスさせて、思考も柔軟に働けるようにする。
体格もパワーも平均しかないアイスが<ABP倉庫>の裏仕事をこなせるのは、あるものを最大限にいかす方法を探り続けた結果だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

